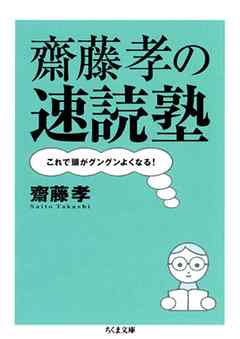あらすじ
速読の究極の目的は、理解力を高め、頭をよくすることだ! 二割読書法、キーワード探し、呼吸法から本の選び方、読む時間の作り方まで、著者実践の秘訣を大公開。「脳が活性化し、理解力が高まる!」夢の読書法。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
速読の究極の目的は、理解力を高め、頭を良くすること、そして自分の言葉として出せなければならない!との意見には大賛成。右ページだけ読んで左ページは穴埋めする読書法はまだしも、二割読書法には衝撃を受けた。キーワード探し、呼吸法から、本の選び方、読む時間の作り方、自分のものとして出せるレベルにまで到達できる方法論まで著者実践の秘訣を大公開してくれている。水道橋博士のあとがきも必見。
Posted by ブクログ
今まではいろいろなサイトから調べた速読術を駆使して速読を行ってきました。速読術の本ではどのような手法が書かれているのかが気になり、この本を読んでみました。
以下、この本から得たことを書いていきます。
タイトルの通りですが、読書の目的とその手法について書いてあります。
### 読書の目的
- 本の要約ができるレベルに終わらず新たな価値を付与してオリジナルのアイデアや提案、見方が出すこと(=理解力Aになる)
- バランスの取れた価値判断能力が養われる。価値観の偏食を直してくれる。
- 本から新しい概念を得る。そしてその概念を駆使できるようになる。
### 速読の方法
- 2割読書法:2割りを読んで8割りを理解する
- 読む2割りをおさえるために、テーマを外さないようにする。
- テーマは、タイトル、帯、目次から推測する
- 引用ベスト3(キーワード/文章/段落などから人に本の内容を伝える前提で、3つは選ぶように読む)
さらに自分の意見を加えられるようになるには
- 著者のテーマに違和感や共感を持ったところをポイントにし、どんな天に違和感を持ったか共感を持ったかを明らかにしながら読む。
Posted by ブクログ
ためになることがたくさん。
・Aレベルの理解力とは、単に内容を理解するだけでなく、新たな価値を付与して、オリジナルのアイデアや提案、見方を出せること
・本を読み、新しい概念を獲得し、概念を駆使してコミュニケーションをとるようにする
・本を読むことは視点移動である。著者側・登場人物側に移動し、新しい概念を吸収する。自分の考え方とは異なる考え方を受け入れる、素直さを忘れない。
Posted by ブクログ
本をたくさん速く読むことが目的ではなく、新たな概念や気づきを得るのがゴール。
読書により、先入観や凝り固まった自分の考えに固執しないための知性を養うことが大切。
1冊の本に固執せず、その著者やテーマに関係する本を横断的に読み、背景にある系譜を芋づる式に紐解いて行くと、多面的に理解が広がる。
速読は、目的ではなく、結果にしか過ぎない。
本に対する正しい向き合い方や読書の意義がわかったときに、自然に見に付いているものである
Posted by ブクログ
読書の方法について書かれています。
私は性格上、本は1ページ目から順に、飛ばさずに読む、そうでなければなんとなく気持ち悪い。のですが、ではそうやって読んだ本がどれほど記憶に残っているかというと……。
本を読むというのが、「最初から最後まで文章を追っていく」ということではなく、「その本に書かれた要点や重要な部分を記憶して活かす」ということであるなら、斎藤氏の提案する読書法は理に適っていそうだなと思いました。
Posted by ブクログ
限られた時間の中で、大量の文章中の概念を、「自分の言葉として使えるよう吸収する」という目的に特化させた本の読み潰し方。速読法には怪しいものも多いが、本書の方法は知的に誠実な速読法だ。
大事なのは書物の中の何を拾い何を捨てるかということ。具体的には、書籍中の8割は捨てる覚悟で、2割のエッセンスだけを抜き出し、出力できるよう要約にして他は捨てる。捨てた分だけ代わりに読む冊数を増やし、大量の概念を吸収することで、特定の文脈での理解の基盤を作る。基盤ができた分野の理解は更に早くなり、関連書一冊にかける時間は短くなり、以下ひたすら加速していく。
前半に読書の目的は何かについての考察があり、著者は本書でのゴールを「本を引用し、その中の概念、発想を自らの考える道具にする」ところに置く。後半にはそのゴールへ向かって、具体的に大量の書物の概念を吸収していく単発のノウハウが連ねられている。
ただ漫然と読むのではなく、いつどのくらいの時間の中で、何のためにその本を読むのか。限られた時間の中で生きる我々は、常にそのことを自らに問い続けなければならない。そう教えてくれる本である。