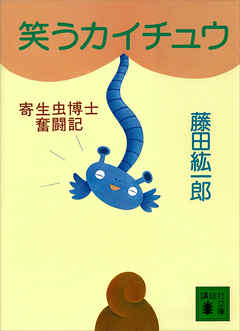あらすじ
花粉症やアレルギーは寄生虫で防ぐ!? ダイエットにカイチュウがお役立ち? かわいいペットの虫退治など、身近な体験を人と寄生虫との共生から易しく説き明かす。善玉カイチュウからグルメが危ない激痛アニサキスまで、隠された体内ドラマを面白おかしく綴った大ベストセラー・医学エッセイ。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
カイチュウ博士藤田紘一郎先生の寄生虫本。
先に読んだ「目黒寄生虫館物語」と一緒に、娘の夏休み課題対策として。
両冊とも、寄生虫研究者たちは変わり者で優しく、「人間でも動物でも大便を集めて調べるの大好き!!」な人たちだという感じだった(笑)
こちらの笑うカイチュウでは、まずは昨今の日本における寄生虫研究の縮小化を憂いている。
日本は清潔になったし、寄生虫の研究も一段落でこれ以上の必要はないんじゃないかということ。
そういえば私が子供の頃やっていたギョウチュウ検査も今はない。
しかし実際には次々に新しい寄生虫たちが発見されたり、新たな病気を運んだりしている。
最近話題のトキソプラズマ、アニサキスなどは実際に死者も出たり問題となっている。
また、化石生物の寄生虫を調べることにより生命の進化が分かるなど、多角的な研究も行える。
研究とはその分野だけでなく、他の分野に繋がり合っていくのだから、寄生虫分野も新たに進んで新たな研究成果が知りたいですね。
Posted by ブクログ
[うにょにょ]「気持ち悪い」、「怖い」、「非衛生的」......そんな言葉をいの一番に思い浮かべてしまう寄生虫。そんな寄生虫に人生を費やすと決めた著者による、入門書にして現状を正しく理解してもらうことに努めた啓蒙の書。とはいえ、決してお固いものではなく、エッセイ調の文体になっていることもあり、一般の読者にこそ手が取りやすい一冊になっています。著者は、家族に寄生虫を研究すると告げた際にポカンとされたという藤田紘一郎。
一度は日本で激減した寄生虫が、有機栽培の野菜やペット文化の普及で再び増加しているという指摘にまず驚き。ただ、ことさらにその脅威の側面を取り上げるのではなく、寄生虫のライフサイクルの中で人間がやっていいこととやってはいけないことを丁寧に説明してくれているところに、研究者の寄生虫に対するバランスの取れた目線が感じられました。ちなみにグロテスクな挿絵などは(少なくとも電子書籍版には)入っていませんでしたのでご安心を。
興味深いのは、人間と寄生虫との関係が一概に善悪で片付けられるものではなく、ときに「まぁそれぐらいなら」というように持ちつ持たれつの依存の関係を認めているところ。本書で示されるように、ときに片方の命がもう片方により取られることがあることも考えれば、灰色決着とも言えるそのバランスの取り方は、自然がそれこそ自然と馴れ合った、または牽制し合った結果生まれた一つの決着の仕方なのかもしれないなと不思議な感慨にとらわれました。
〜寄生虫と宿主は長い深化の歴史のなかで、互いに進化、適応し、adaptation toleranceの状態にいたったものと理解される〜
こういう知らない分野の話は本当に面白い☆5つ
Posted by ブクログ
13/101。
寄生虫ってそんな生き物なのか!という驚き。
昔猫を飼ってたから、トキソプラズマの話は興味深かった。
妊婦さんは猫に近づけない方がいいんだね。あたしはもう感染してるような気がするなあ。
正直寄生虫に関する知識なんて全くなくて、ダニかノミみたいなもの?って思ってた。全然違った。
たぶん、本物を見たら相当気持ち悪い見た目なんだろうし、筆者のやってることも結構常軌を逸してるんだけど、それをコミカルに書いてるのがすごい。
でも食後に読んだらさすがに気持ち悪くなった。笑
Posted by ブクログ
以前お付き合いしていた人に
「誕生日のプレゼントに何が欲しい?」
と聞かれ、答えたのがこの本(笑)
とにかく文章が面白いし勉強にもなる一冊。
オススメです☆
Posted by ブクログ
寄生虫のエッセイ。
怖いもの見たさに(?)最初に読んだ本。
とても読みやすく、このほかにもたくさん出版されているのでつい読みたくなってしまいます。
「抗菌グッズ」や「潔癖」の危険性を教えてくれます。
Posted by ブクログ
SSさんのお勧めで読んだのですが、確かにこれは面白い本です。
海外赴任者の奥さんが、お尻から出てきたカイチュウを掴んで気絶する話。寄生虫学者が、朝早く地方のホテルを抜け出し、犬・猫の糞集めをやってて警察官に不審がられる話。なにせ、寄生虫のことゆえに下ネタが多いのは仕方ないけど、笑わせてくれます。
一方で、不思議な寄生虫の生態や感染経路を判りやすく解説してくれています。生野菜・刺身・踊り食い・ペットなどからの感染経路の紹介や、寄生虫の中でも怖いもの・さほど問題にすべきでないもの(例えばある寄生虫は皮膚直下を走り回るので爬行疹という発疹が出来る。しかし、1週間もすると死ぬので実害は起こらない)などがあることを教えてくれます。
ただ、これを読んじゃうと、しばらく生ものは食べたくなくなると言う欠点もありますが。(苦笑)
ところで、おなかにカイチュウを飼うと原因となる抗体の発生が抑えられ、花粉症にならない。その上、ダイエット効果(虫が栄養を吸っちゃうので)もあると言うのですが、どなたかお試しになりませんか(笑)。
Posted by ブクログ
寄生虫学、感染免疫学、熱帯医学の専門医による、寄生虫に関するエッセイ集。1994年に発刊されてベストセラーとなり、1999年に文庫化された。
日本におけるカイチュウ感染率は、戦争直後70%以上あったものが、公衆衛生に関する徹底した取り組みにより、わずか20数年間で0.2%以下に低下した。しかし、その後、有機栽培野菜の流行、様々な種類のペットを飼う人の増加、グルメや健康を意識した食の広がり等により、この世界でも最も清潔と言える日本において、寄生虫病が再び増加しているのだと言う。具体的な原因は、アライグマやサルのペットとしての輸入、ドジョウの踊り食い、ヘビの生血のワイン割り、ナメクジの丸飲み、ジビエ料理、様々な生魚等々。
寄生虫というのはその名の通り、宿主に寄生することによってのみ生きられる生物であり、上記のような生活様式や嗜好の変化により本来の宿主ではない人間の体内に入った場合には、ときとして健康に大きな影響を与えるものの、本来宿主に寄生している限りは基本的に悪さをしないものである。また、寄生虫感染はアトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー性疾患の発症を抑制する効果があり、日本人のアレルギー症の急増は寄生虫感染率の低下が一因とも言われている。
著者が本書の出版に当たって「ずいぶん気を使った」というように、寄生虫というテーマは確かに万人に抵抗なく受け入れられるテーマではないと思うものの、本書の提示するメッセージは深い。それは、何より人間が自らの都合で自然との共存・共栄関係を変えようとすることへの警鐘である。
(2015年9月了)
Posted by ブクログ
「私は猫になりたかった(西江雅之著)」以来、学者の書いたもので面白いものに出会ってなかったが、これは面白かった。
最初の話が「カイチュウの卵とじ」。タイトルで度肝を抜かれる。
「寄生虫がアレルギー反応を抑える」という話は、医学界に一石を投じるものだと思うし、「セックスの氾濫が男性を衰えさせる」というのは現代の日本に対して警鐘を鳴らすものだろう。
「住民をいたずらに不安に陥れてもいけないが、恐ろしい病気にかかるという不安も伝えなければならない」と、寄生虫による病気について語った部分は原発事故の自治体の対応を連想させる。
「最近の医学の進歩で、多くの薬を使うようになったことが、人の免疫能を低下せてている」という記述も印象に残った。
一読に値すると思う。
Posted by ブクログ
イタズラに恐怖心をあおるつもりはないですが、
あなたは寄生虫に寄生されてはいませんか。(笑
ひじょーに面白い。
ここで、作者の危惧していることが、
あぁ日本だなと思うことなので抜粋したい。
日本では寄生虫学が衰退していってるそうだ。
なぜか?
それは日本にはほとんど寄生虫による症状がなくなってきているからだ、
存在しない病気の勉強なんていらないんじゃないって単純な理由。
こんなことでいいのか?
確かに日本ではないかもしれないが、
世界で、これほど感染している症状もないのに。
ってね。
「世界に目を向けると半数の25億人がなんらかの寄生虫を保有し、三分の一が寄生虫病になやまされている。マラリアには3.5%一億七千七百万人。フィラリアには5%二億五千万人」
これほど寄生虫による患者がいるにもかかわらず、
日本の医学部では日本にはそんな患者いないから勉強しないというのです。
これだけ物も人も世界を駆け回るようになっている時代。
寄生虫研究は日本ではなくなっていいのでしょうか。
こんな日本にすんでいるのは怖いと思いませんか。
日本は、遅れている。
進んでいるものと遅れているものがあるのを理解しなくてはいけない。
なんでも進んでいるわけでもないし
なんでも遅れているわけでもない。
おまけ、平田オリザさんの解説も面白い。
人は一人では生きて行けず、誰かに寄生しているものだ、
と思えば、優しくなれるよね。
って思うね。
Posted by ブクログ
我が日本からほとんど姿を消した?と思われている寄生虫について,楽しげな語り口で述べる.昨今の海外旅行やグルメのブームによって,寄生虫のリスクは実は再燃しているのだという,たいへん重要な事実を指摘する.この本から,具体的な知識や対処法も多少は得ることができるが,心当たりがあったら迷わず医者に行くのがよい.
Posted by ブクログ
アレルギーの話をしていたらこの本を紹介していただきました!色々な寄生虫の話が読めて面白かったです。なによりも著者の寄生虫に寄せる「愛」とか、色々な患者さんの実話とかがたくさんあって。。寄生虫は身近にたくさんいるけれど、それにかかってなくなる人はごくごく少数である。筆者も指摘していることだけれど、日本人は何かと大げさにしすぎなんだと思う。公園などの砂場に放置されたイヌや猫のフンから寄生虫に感染したと言えば、砂場で遊ぶなと言ったりする。ほんとに感染する確立は極少数だというのに。。寄生虫についてちゃんと正しい知識を身につけて対応していきたいと思った。
Posted by ブクログ
教授であり医者でもある藤田紘一郎先生が書いた本。感染免疫学・寄生虫学で多数書籍を出しているが、とりあえずこの本は話半分で読む必要がある。それが出来るならとても面白い。寄生虫の笑える話やアフリカのトンデモ事情までエンターテイメントを提供してくれる。ただここに書かれている情報を素直に信じてしまう人は回れ右した方が良い書籍。あくまでエンタメ。
Posted by ブクログ
大学の医学部には「寄生虫学」という分野があるものの、寄生虫被害自体が減少したため学問としての存続危機を迎えている、と記されたのが1999年の本書出版当時のこと。あれから四半世紀、現状どうなっているのか気になるところではある。
実は、1999年当時でも既に花粉症やアトピー性皮膚炎などの疾患者増加が見られ、人の体内から寄生虫がきれいサッパリいなくなったのが原因ではないかと考えられていた。清潔好き潔癖症日本人が逆に生物としての抵抗力を阻害していたのは文明の皮肉である。
ちなみに個人的体験だが、田舎育ちの小学生時代、大便中にお尻からサナダムシが出て来たことがあって引っ張りだそうとするも、滑って失敗。その後、虫下し薬を飲んで駆虫した記憶がある。私が今もなお花粉症でもアトピーにも悩まないのは、もしかしてアレの残滓のおかげかもしれない。
そして1999年当時は、海外種ペットの輸入拡大や無農薬野菜、ジビエ料理、滋養強壮を狙った生血や生肉などから、今までなかった寄生虫感染が見られるようになった。(だからといって、花粉症やアトピー体質症が減少したのでもないようだが)
本書では、筆者が見聞した様々な寄生虫の悪巧みを解説。
結論から言えば、寄生虫感染を防ぐには生肉など非加熱食は避ける、淡水魚類の刺身等もアニサキスの宝庫なので気をつける、素性の知れない輸入食品は買わない、ペットとのキスも止めるなどの自衛策はあるものの、(命がけの)美食家やペット愛好家達には大きなお世話かもしれない。
本書には思わずオエッとなるシーンがかなりある。それでも、筆者の明るいユーモアのおかげで陰湿な読み物になっていないのがベストセラーの要因となっている。
Posted by ブクログ
寄生虫を研究する博士、藤田先生によるエッセイ。
20年前の本ですが、「寄生虫とは何か」をその生態や人間との関わり、今後の研究次第では癌やアレルギーの治療にも役立つかも、なんてことまで書かれていて非常に興味深い話ばかりです。
現時点での寄生虫研究がどこまで進んでいるのか知りたくなってきます。
藤田先生の寄生虫への偏愛ぶりに少し影響されたのかもしれません。
Posted by ブクログ
寄生虫が体内にいると花粉症にならないかもしれないし、太らないかもしれない。でも、お尻からうどんみたいなのがでてきたらビビるよね。体にいても 良い寄生虫と悪い寄生虫がいるから要注意。
Posted by ブクログ
学者さんの書くエッセイは笑いどころが面白い。でも食事前にはオススメしない。頭のいいオッサン(失礼)が二人してウ○コ拾いながらキャーキャー興奮してると思うと和むなあ…。
Posted by ブクログ
愛って突き抜けるものなんだなぁ。
虫の名前は漢字のほうがよかった。し、写真や図もあればよかったが、倦厭されないようにと分かりづらいようにしたらしいけども、名前は漢字のほうが分かりやすい。
現代に生まれてよかった!こういうの読むと自分も知らない間に感染してんじゃないのかって怖くなる。
けれども大変面白かった。
Posted by ブクログ
笑いました。まさか、寄生虫を、こんなに、愛着をもって語れるかたがいようとは、、!!けっこう大事なことを、それとなく教えてくれる良い本だと、思います。