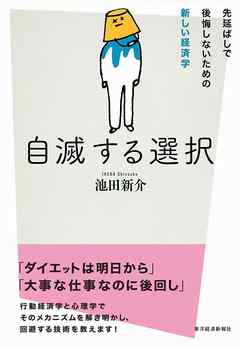あらすじ
「ダイエットは明日から」「仕事をつい先延ばし」――
後悔するのをわかっていて目の前の快楽になびいてしまう、人間の本能とも言える選択のクセのメカニズムが、行動経済学と心理学によって解き明かされます。
「夏休みの宿題を後回しにする人は、喫煙・ギャンブル・飲酒の習慣があり、借金があって太っている確率が高い!」といった驚きの分析結果などを示しながら、ダメな自分を賢く誘導する方法や、喫煙・肥満・多重債務などの社会問題を解決する手立ても示します。
「自滅する選択」のメカニズムを説き明かし、改善策と対応策を考えだすための一冊です。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
夏休みの宿題を後回しにする人は、喫煙・ギャンブル・飲酒の習慣があり、借金があって太っている確率が高い!ということを学術的に分析するという身もふたもないが、それ故に、僕のように今後悔い改めていきたいと思っている人には良書となることを確信する。
最後に、きちんと処方箋も記載されているのご安心を。
本書のいうように、人間は、目の前の快楽になびいて合理的で賢明な選択をとることが困難である。計画者である理想の自分(天使)は、実行者である怠惰な自分(悪魔)によって、いともたやすく敗北を喫する。
それにはちゃんと理由がある。主に、経済学の概念である「現在バイアス」と「双曲割引」を用いて分析していく。好きだとか嫌いだとか、信じるとか信じないとか、そんな吹けば飛ぶような感情論ではなく、有意な統計データを地道にとって、言葉とロジックでそれを説明してくれている。
言葉とロジックで原因・理由が分かれば対応もできる。
ところで、本書の結論として、リバタリアン・パターナリズムに行きついてしまうのはやむなしといったところか。
人は遺伝子を選べない。選べない以上、生まれもって、現代社会に著しく不利な性質をもって生まれる人は一定の割合で生じる。僕は子どもを授かった関係でその手の本を読んだが、出産を含めて人の営為をゼロリスクにすることなど不可能なことが多いのである。これをあくまで自己責任とするか、本書のいうようにデフォルトの段階で手を差し伸べて事態を改善していくか、難しい問題だ。
Posted by ブクログ
先日読んだ「予想どおりに不合理」に続いて、
行動経済学をもう少し深めたく読みました。
こちらは日本の著者なので、読みやすさを期待してました。
が、しかしこちらの方が読みにくいという恐ろしいことに。
しかも別に日本のカルチャーはあんまり関係なかったし。
とは言え、内容としては面白かったです。
肥満、ギャンブル、借金などをサンプル分析から
そういった性向を持った人である確率が高いとして、
そういう人がなぜそういう行動をとるのか、
という点を明らかにしてくれます。
惜しむらくはわかりづらい。
ただ、最終的にリバタリアンパターナリズムという
考え方が提示されるあたりはワクワクして読めました。
任意的選択を与える際に、先にバイアスをかけることで、
正しいと思われる選択に導く、ということを
為政者などが行うというものですが、
これは今後の社会にとっては、大事だろうなぁと思います。
ただ、その為政者に理性があることが大前提ですし、
あまりにやりすぎるのは少し怖いのですが。
そんな本でした。
Posted by ブクログ
先延ばしで後悔しないために。。。
行動経済学の本はだいぶ多くなってきましたが、
自滅選択をキーワードに展開される興味深き本。
「自滅する選択」を、自分で選んでいるのに自分の利益に
反してしまう矛盾した行動と定義し(P.2)、心理学、脳科学
などを含めて、説明してくれる行動経済学の教科書的な内容。
肥満と借金、たばことギャンブルの相関を導き出し、それに対抗
する「自制」する手立てを示していく。
そして、経済学だけじゃなく、「XXな自分」をなんとかする材料と
しても有効かと。
Posted by ブクログ
目の前の利益は大きく見える。=ビルの手前に木がある場合、遠ければビルのほうが大きく見えるが近づくと、木のほうが大きく見える。=利益の実現まで時間がある場合は、健康という長期的利益のほうがケーキという短期的利益より大きく感じるが、目前だと、ケーキを選択してしまう。
長期的利益の後回しと短期的利益の前倒し=夏休みの宿題
「賢明」な人は、将来の緩い自分を見越して(目前になると短期的利益を優先する自分を見越して)、現時点で長期的利益を放棄するコストを大きく評価するので、断行できる。=テレビをやめられないことがわかっているので最初からスイッチを入れない。
現在の減税によって、手元の流動性が増すとより消費性向が高まる。その結果、リカードの中立命題が成立しない。
太宰治=津島家のコミットメント 出奔(しゅっぽん)=逃げて姿をくらますこと
今日食べるか明日食べるか、の選択では双曲割引のせいで、今日食べる、が勝つ。そうでなく、今日食べると明日以降も食べる、ことになることを認識した上で、ずっと食べる、のかずっと我慢する、のかを選択することが重要。
マイルールを設定する。マイルールは明確である必要がある。マイルールは正当化と例外化、によって破られる可能性がある。
マイルールがコミットメントとして機能すると、強迫観念にまで発展する可能性がある。そのため、わざとルールを意図的に破ってリセットする。
吝嗇(りんしょく)=ケチ、と読ませることもある。意味はケチ。
計画期間を短く決める=月いくら、よりも週いくら、とする。ずっと食べない、飲まない、ではなく3日、あるいは一週間、という期間のみ設定する。
敵が弱いうちに叩く=食欲が増大する前に少しずつ食べる
自制問題を伴う選択は、認知能力が必要な他の作業を同時に行わない。=テレビを見ながら食べない。
オプトイン方式(入会の自由)ではなく、オプトアウト(退会の自由)方式にする。
メニューの最初にあるものが選ばれやすい。レジのヨコの商品が買われやすい。
Posted by ブクログ
【先延ばししない為に必要なことは?】
ダイエットをするために、1年間毎朝ランニングをしようと思った人の中で、本当に達成できた人はどれ程いるだろうか?きっと多くの人が、目の前の利益に誘惑され、1年後に待ち構えている、将来の痩せている自分を捨てているのではないだろうか。そんな、計画をしても先延ばし、若しくは中断して後悔したことのある人向けに書かれた本である。
本書では、行動経済学を元に先延ばしにしてしまうメカニズムを分析し、原因を追求している。そして最終的には、どうすれば計画通りにモノゴトを達成出来るのかを説いている。
行動経済学自体は、数式が複雑で理解が難しいが、それを理解しなくても大丈夫。そのあたりは、「ふ〜ん」程度で流し読みし、先延ばしにしない方法を学べば良い。
受験勉強や就職活動、資格試験、仕事など、あらゆる場面で必要になる「計画する」ということ。そこに潜む罠とそれをいかにして乗り越えるかを教えてくれる本である。
Posted by ブクログ
時間割引率の話や行動経済学…今やもっとわかりやすい本はあるのだから、わざわざ読まなくても…と思ってしまいました。タイトル、サブタイトルのイメージと違い、ちょっと難しかった。大学で使う教科書っぽいと思ったら著者は阪大教授で、行動経済学学会会長でした。
翻訳本だと同じような内容でもエピソードがたくさん出てきて読みやすいんだけどなあ。
ソデに書かれていたフレーズ
夏休みの宿題を後回しにする人は、喫煙、ギャンブル、飲酒の習慣があり、借金があって太っている確率が高い。
ひええ…
Posted by ブクログ
難しい本でした。計算式が多くて理系の人にはオススメです。
その中でもオススメは。
人気の携帯電話を予約購入する場合を考えてください。
その入荷予定が2ヶ月後であった時、入荷がさらに1ヶ月遅れて
3ヶ月後になる場合には値引きを要求したいところです。
その要求する値引き額を「遅れのディスカウント」と言います。
これに対して3ヶ月後に入荷予定だったのを一ヶ月早める場合に
余分に支払っても良いと思う金額を「早めのプレミアム」
と言います。
ここで7ドル分のレコード商品券の受け取りを考えてみましょう。
レコード商品券の受け取りが1週間後から
4週間後に遅れる場合に感じる価値の減少は平均で1ドル8セントで、
4週間後から1週間後に早めるために払っても良いと考える額は
25セントに過ぎなかったそうです。
これを見ると人間は損することに敏感なのがわかります。
同じ100円でも、道端で拾った100円と支払う100円では気持ちが違う
ということ。人間というはわがままな生き物ですね。
Posted by ブクログ
行動経済学の専門家による「大事なことでも後回しにする傾向」について解き明かした本。裏表紙にある「夏休みの宿題を後回しにする人は、喫煙・ギャンブル・飲酒の習慣があって太っている確率が高い」という命題を、本1冊で証明している。理論的ではあるが、きわめて狭い範囲のことだけを取り扱っており、あまり興味がわかなかった。
「私たちの消費水準は実際には、たまたま景気がよく所得水準が高いときには高く、不景気で所得水準の低いときには低い(平準化(スムージング)の傾向が生かされない)」p141
「(映画「スーパーサイズミー」)実験 ①1日3回マクドナルドの商品を食べる、②1日の歩行距離をアメリカ人の平均である2500歩以内に抑える、③「スーパーサイズ」を店員から勧められたら、勧められるまま食べる、といった過酷なルールに従う。実験終了の30日後、体重は、84.1kgから95.2kgに増加、肝臓には深刻な炎症が見られ、躁鬱傾向まで現れた」p215
「(本書の結論)自分のルーズさに無自覚な人ほど自滅選択の傾向が強い」p269
Posted by ブクログ
"経済学の世界で、経済の実態や今後の予測に基づく経済政策を提案する過程で、消費者がどのような行動をとるかを定義づけてシミュレーションするようだ。
その際、人間は合理的かつ効率的な消費行動を常にすることが前提で、語られてきたことが多かった。
しかし、実在する個人個人の消費行動は合理的ではなく自滅するような行動を取ったりする。
双曲割引という専門用語が登場し、その説明をしているのが本書。
私は理解ができなかったので、時間を空けて行動経済学に関する本を読みたいと考えている。"
Posted by ブクログ
双曲割引の下では、時間が経つにつれて選択に適用される忍耐強さが弱くなる結果、長期的観点から計画していたことに矛盾を生じて実行できなくなってしまう点
それを防ぐにら、明日の自分に過度の自信をおいて選択しないこと、つまり将来の緩い自分を織り込んだ賢明な選択を行う
Posted by ブクログ
①自滅する選択とは?
・自分で選んでいるのに自分の利益に反してしまう矛盾した行動
②先延ばししない方法は?
・ルール化する
・長期的利益の後回し、短期的利益の前倒しが人間の心理
・計画期間を短く刻む(3日、1週間、2週間)
③気づき
・太っている人ほど、負債傾向、低貯蓄
・多曲割引は、遠い将来より、近い将来の方が割引率が高くなる傾向のこと
・小額なほど、金利が高くても気にならない
・近いものほど割引率が高い
Posted by ブクログ
経済学以前に『自滅する選択』というあおりに気になって電子書籍にて購入。目先のことだけでなく将来を見据えて行動していくことが必要である、と。利益と損失とはなにか、少しずつでも改善していくことが必要である、まあ急き過ぎてはいけませんよっておはなし。
Posted by ブクログ
読むのに時間がかかった。直近の利益の方が大きく見えてしまうので、長期的な利益が台無しになってしまうことがあるという内容。ダイエットは明日から、給料日はご馳走、宿題の締め切りはギリギリなど。普通にあると思えることが、実は合理的で効率的な選択ではない。
マイルールの設定や初期設定の変更でそれらは補正可能。意思を貫くには「これからもずっと続けるのか、ずっと反故にするのか」という選択が有効。
Posted by ブクログ
目先の利益に囚われる人間のバイアスについての説明がされておりわかりやすい。
同じような内容を何度も書いており、量の割に内容は薄く感じた。
Posted by ブクログ
人間の将来価値や将来損失の現在価値把握は、伝統的な経済学が想定している指数割引ではなく、近い将来は高い割引率で、遠い将来は低い割引率で割り引く双曲割引であると考えることによって、目先の誘惑に抵抗できない人の行動を説明できる、ということを詳しく説明している。
これに対応して自分の行動を自制するメソッドとしてのコミットメントについても説明している。
Posted by ブクログ
行動経済学について記載した本であり、おもしろいが、数学的要素を省いて文章で伝えようとするためにかえってわかりにくくなっている感がある。章ごとに箇条書きのまとめを行うなど、もう少し情報の整理をして頂けるとよりわかりやすくなると思う。
・負債や喫煙、ギャンブルなどをする人には共通点があり、みんな双曲的な意思決定をしている。将来より目の前のことを優先している。
・選択を改善する三つの方法
①意志力や認知力を使わずに長期的な選択が確保できるよう、コミットメントの手法を用いる。
②計画期間を短く刻んで行動計画を立てる。たとえば小遣いなど一か月ごとではなく、1週間ごとにするなど。
③認知判断できる状況をつくる。たとえば食べ物であれば、お腹がすく前に選んでおくなど。
・定期的な締切があった方が成績はあがる。
・個人として自制を行うには、まず定額貯金か何かに取り組み自らをテストして、自覚することが必要、。これが外部から与えられたものだと意味がなくなってしまう。
その後、コミットメントを使う。法的なこと、他の人に行って約束してしまう事など。他には期間を短くくぎって実行するなど。
・人の行動をかえるデザインとしては、上記を利用し、期間を短くする、401kのようにデフォルトを変えてしまうなど。
Posted by ブクログ
この本ではなぜ先延ばしして後悔するのかをテーマに行動経済学を説明する。つまり、あくまで行動経済学の本である。それを忘れて一般書やビジネス書のように読むと「?」がついてしまうので、注意が必要だろう。
メモ)
▽概要
・「単純」な人と「賢明」な人に分けた場合。
単純な人は我慢できずに林檎が熟す前に食べる。
だが賢明な人は将来の自分が我慢できないために
青い林檎の状態で食べる状態も起きてしまう
・「賢明」な人は将来の自分を正しく悲観している人
▽対策
・自分たちの中では天使と悪魔が存在する。
悪魔の「明日から」というささやきは「明日からずっと」と同意語
・誰にでもわかる明確なルールをつくる。曖昧にすると悪魔は例外ルールをつくってしまう
・コミットメント(制約)が厳しすぎると教義的になり損失を生み出す可能性がある。時々ゆるめることも必要
・私たちは経験でしか自分の意志力の強さは計れない
・計画期間は短く刻んで行動計画をたてる
・実績が出来たルールは習慣化出来る。強化できる
▽ナレッジ
・将来の自分を縛り付けるための手段がコミットメント
・将来よりも現在にウエイトを置くことを現在指向性
どれだけ置くかを時間割引率という概念で説明
・洗濯の意思表示をしないことをデフォルトという。選び手を誘導する
・人は快感や苦痛も習慣化してしまう。習慣化すると得られる刺激も少なくなる
・物理的な時計ではなく心理的な時計を持っており時間の進み方が違う
将来の時間の進み方は早く、今は遅い
・限界消費性志向は流動性が高いものほど高い(例:現金)
・会員などの自動登録は脱会の自由が認められていることが必要
・金額が大きいほど時間割引率は低い
・待つという行為には心理的コストが発生する
・物事を先延ばしする人は重大と思われる仕事を自分からみつける、つくりだす
Posted by ブクログ
経済学、数学の基礎がない自分には難しすぎる内容だった。
気軽に読める本ではないので注意。
読み込めばおもしろいとは思う。
肥満、借金、ギャンブル、喫煙・・・目先の快楽に目がくらんで、将来にそなえられない人々は、行動の選択が似通ってくるそうな。
今まで出会った人の中でも、いるいる!と思ってしまった。