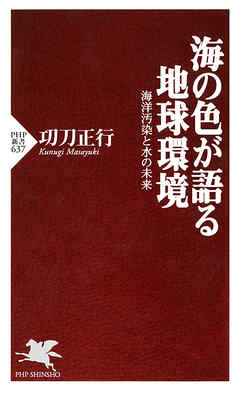あらすじ
真っ青に澄んだエーゲ海は死んでいる! 逆に、日本沿岸のような茶色がかった海こそ生き物の宝庫なのだ。水の「色」を見れば、その環境が手に取るように分かる。では、「真っ黒なインド洋」「銀色のラプラタ川」「真っ赤に染まった相模湾」「ブルーにしか見えない南極の氷山」からは何が読み取れるのか? そもそも水の色はなぜこれほどバリエーション豊かなのか?水の時代と言われる二十一世紀現在、水の惑星において使える水が絶対的に少なくなってきているという状況に直面している。過度のインフラ整備により緻密な自然のシステムは確実に支障をきたし、垂れ流してきた有害化学物質は、一億倍に濃縮されてあなたの食卓に…。本書では、十数年もの間、観測船に乗り込み調査した著者が、海洋汚染の実態を報告。色鮮やかな写真と共に地球の未来を考える。水なしでは生きられない我々が、この星の七割を占める海を知らずに環境は語れない!
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
伊豆諸島や沖縄などに行けば、海の青さに間違いなく感動する。ダイビングをするようになって、海の中も見ることができてからは、なおさらその感動の深くなっていたように思っていた。しかし、あまりに青い海は、その海に珊瑚や藻類やプランクトンなどの生物が少ない証拠だという、よく考えれば分かっていたはずのことを本書はもう一度教え、考えさせてくれる。
第一章では著者が見た世界各地の海の色と、それらがどうしてそのような色をしているか、生物、そしてその栄養であり、海洋汚染の原因にもなる有機物、と海との関係が詳しく解説される。大学の専門課程でCOD(Chemical oxygen demand)について、散々勉強させられたことを久々に思い出した。
第二章は、著者が貨物船や客船に乗って世界中の海水を調査したことが書かれている。前半は旅行記のような雰囲気もあって、ほほえましく楽しく読めるが、調査の結果、世界中のどの海域の海水からも農薬が検出された、というおぞましい事実について、著者は強烈に警鐘を鳴らしている。
第三章以降、水の話になり、地球上をいかに水が循環し、生物、もちろん人間にとってどのように利用されているか、さまざまな観点から説かれている。
タイトルの通り、海の色から地球のこと、我々の命のことを考えさせられる。
Posted by ブクログ
海がきれい(例えばエーゲ海など)なのは、生物がいないから。プランクトンや魚類がいる海はいろいろな色をもっている。
そうはいってもきれいな海も見てみたい。本書で示されたコズメル島(メキシコ)にはいってみたいと感じた。海と空との切れ目がわからなく、船が空中を走っているような感じであった。
日本の下水普及率は70%であるが、窒素およびリンまで処理ができる高度処理下水施設の普及率は13%程度。これが北欧ではほぼ100%、欧米諸国では30~50%が高度処理。日本はまだ。
写真も多く一読の価値あり。
Posted by ブクログ
軽い気持ちで読み始めたら、けっこう専門的な用語が、さりげなく頻出する。そこで、実はけっこう難しい内容も織り込まれているんだなぁと気がつく。
世界各地を航行する船(調査に協力してくれるこうした船を篤志観測船というとか)に乗り込み、地球規模で海洋汚染の解明に取り組んでいる筆者が、様々な海を例に、赤い海、黒い海、紺碧の海など、海の色の仕組みと汚染の関係を紹介。
エメラルドグリーンや真っ青に澄んだ海が、実は生物が少なくミネラルも不足しているという事実。
化学記号が出てくるたびに、(私の場合)ちょっとついていけなくなってしまうが、あらためて「水」が人の生活と非常に密接な関係にあり、かつ、かけがえのない大切な資源であることを再認識させられる。