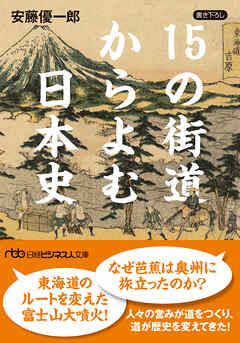あらすじ
「なぜ芭蕉は奥州に旅立ったのか?」
「多くの大名が東海道より中山道を好んだ理由は?」
日本史を紐解いていくと、道、つまり街道を舞台に歴史が生まれる場面に幾度となく遭遇する。そして、歴史が街道を作ることも少なくない。
例えば、東海道は江戸と京都を結ぶ街道という印象が強いが、それは江戸に幕府が開かれてからのイメージに過ぎない。それまで、東海道は幕府が置かれた鎌倉と京都を結ぶ街道としての印象が強かった。しかし、徳川家康が江戸に幕府を置くことで、東海道は江戸と京都を結ぶ街道に変身する。また、我々がイメージする東海道の難所と言えば箱根峠だが、実は箱根峠を越えるルートは、もともとは東海道の本道ではなかった。本道は、足柄峠を越えるルートである足柄路だったのだ。江戸市中にも大量の火山灰が降ったという宝永の富士山の大噴火が本道を箱根路に変更させたことで、地域が変貌していく。
「一度、廃れた熊野古道」
「実は4つあった日光街道」
「将軍の緊急事態を想定していた甲州街道」――
本書は、定評ある歴史研究者が、全国の街道と我々になじみの深い歴史とを重ね合わせ、様々なエピソードと新たな発見ともに綴る歴史ノンフィクションである。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
今でこそ○○街道などと整備された道路だけど、現在に至るまでは様々な歴史があったと感じることができる一冊。
参勤交代の時代や遡り鎌倉幕府の頃の熊野古道など、時代やその風景も色々楽しく読めました。
街道が栄えたこともその使われ方も成る程と思えた。
Posted by ブクログ
古来から人物の往来が街道を栄えさせ、その逆もまた然り。武士、皇族や貴族、商人や庶民など、様々な人々が行き交い、その歴史を見つめて来た全国各地の街道。
その成立の由来と、歴史的価値や大きなイベントなど、各街道毎に独自の視点から触れられていて読みやすい。個人的には江戸時代に整備が進んだ五街道(東海道、中山道など)よりも、伊勢参宮街道や西国街道など、マイナーな道にまつわるエピソードの方が興味深い。
ネタバレ覚悟で取り上げると。。
◯京都の七口(伏見口など)
京(都)はその成立から防御を重要視していて、京都と諸国を結ぶ主要街道の七つの出入り口は、激しい戦闘の部隊となって来た。血生臭い権力闘争の歴史を物語る証人である。
◯伊勢参宮街道
お伊勢参りの熱狂は、参宮街道沿いの「御師(おんし)」=(プロモーター)による、参拝者集団への手厚いおもてなしが、各地に口コミで伝わり広まっていった。
◯熊野古道
平安期に上皇や貴族による「熊野詣」で整備され繁栄を極めた熊野古道だが、峻険で静寂なこの道を歩く事が仏門修道に繋がり、心の平安をもたらす。現世利益を願い、陽気に練り歩くお伊勢参りとの対比が興味深い。
◯西国街道
江戸時代、西日本の大名の参勤交代には、当初は主に瀬戸内の海路が利用されたが、海路の危険さや瀬戸内の気象条件、何より各藩の財政難が海路より陸路を選択させ、江戸期後半の繁栄に繋がっていった。
◯四国お遍路道
江戸期に大ブームになった四国八十八霊場巡りは、ある一人の修行僧が発刊し、版を重ねた「ガイドブック」の力に依る所が大きい。「地球の歩き方」ならぬ「四国霊場の歩き方」、旅心を掻き立てるものは今も昔も変わらない。
ざっとこんなエピソードがありました。
個人的にはここに取り上げられた参拝道、とくに熊野古道や四国八十八霊場、歩ける身体の内に実際に踏破してみたいです。
Posted by ブクログ
日経ビジネス人文庫の歴史シリーズ。
このシリーズで新刊が出ると、ついつい読みたくなってしまいます。様々な角度から歴史を見直すきっかけをくれるシリーズですので、毎回楽しみにしています。
今回のテーマは「街道」、道です。
いわゆる五街道だけでなく、いろいろな街道をテーマにしていますので、なかなかマニアックです。
「街道はそんな歴史のドラマを生んだだけではない。逆に歴史が街道を生み出したこともあった」と冒頭に述べているように、街道は、一時代だけのものでは決してなく、長い歴史の中で生まれてきたものであり、様々な歴史の場面で異なる顔を見せていたのだとすると、改めて歴史の奥深さを感じることができる一冊です。
<目次>
1 松尾芭蕉は奥州街道で見た名所旧跡に何を思ったのか
2 日光街道は四つあった
3 鎌倉街道は常に「いざ鎌倉」への道だった
4 富士山の噴火で東海道のルートは変更された
5 参勤交代では東海道よりも人気があった中山道
6 甲州街道最大の宿場内藤新宿はなぜ復活したのか
7 なぜ上杉謙信は北国街道を整備したのか
8 街道輸送の主力だった馬が街道名になった中馬街道
9 京都への道(京の七口)は明治維新の狼煙が上がった道でもあった
10 伊勢参宮街道からやってきたお伊勢参りはどんなもてなしを受けたのか
11 上皇や貴族は熊野古道をどのように旅したのか
12 なぜ西国街道は五街道にまさるとも劣らず賑わったのか
13 お遍路道はどのようにして生まれたのか
14 オランダ商館長一行は長崎街道で何を見たのか
15 武士の旅日記に国内の主要街道はどう書かれていたのか