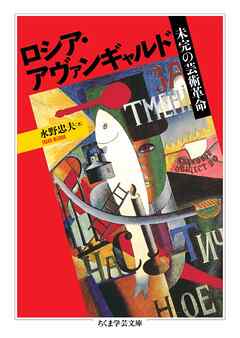あらすじ
既存の価値観に対する攻撃とともに、ロシアでは20世紀初頭に産み落とされた前衛芸術。1917年の社会主義革命に先行したその活動は、芸術革命に呼応するものとして政治革命に同調し、昂揚する民衆のエネルギーに支えられて、芸術運動を展開してゆく。これがロシア・アヴァンギャルドと呼ばれる運動である。しかしそれはやがて、スターリン体制から「形式主義」として批判され、芸術の論理によらず粛清され抹殺されてゆく。マヤコフスキー、マレーヴィチ、メイエルホリドなど、激しい時代を生きた芸術家たちの活動に光をあて、その再評価の嚆矢となった20世紀美術史の名著。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ロシア・アヴァンギャルドを絵画/美術のみならず、文学、演劇(逆に演劇のほうが比重が大きい)の観点から、更に切っても切れないロシア革命、その後の政治的動きと絡めて解説した本。
ロシア・アヴァンギャルドと一言で言っても、芸術史的には、美術ではスプレマティズムとかロシア構成主義とか立体未来派とか、文学的にはフォルマリズムとかがお互いに影響を与え合い(他の主義への批判も含めて)、それが純粋に芸術的な論争だけでなく、政治的な(反革命的だとかプロレタリアに寄り添っていないだとか)もからめた芸術論争であった。斯程にロシア・アヴァンギャルドは政治と切っても切り離せない関連であることがわかる。
そして最後には社会主義的リアリズムの前におしなべて芸術がひれ伏しロシア・アヴァンギャルドが潰えていく様が描き出される。
芸術が政治に絡むと、兎角濁ったものと見勝ちになるが、そこを見ずしてロシア・アヴァンギャルドという潮流を知ることはできない、ということを学ばせてくれる本。
Posted by ブクログ
古い権威の打破と新しい芸術の創造、よほどの古典礼賛者や体制順応派でもない限り、この手のことをぶち上げない、若くて才能あるアーティストなんていないはずである。ロシア・アヴァンギャルドの特異性はこうした芸術革命と政治上の共産主義革命が一致してしまったことにある。しかも、共産主義の理想や革命が幻滅で汚されてすり減る前の、ピカピカの革命と。 戦乱に巻き込まれて荒廃し、何もないモスクワのカフェで、にもかかわらず意気軒昂に怪気炎を上げまくるアヴァンギャルドたちのエピソードが伝える高揚感のすさまじさよ。しかも、この無名とまでは言わないが、少なくとも当時の第一人者ではなかった、口ばかり達者な若造たちが、革命政府の文化政策をほとんど丸投げされることになるのだ。後に革命の大儀なるものがどれほど地に墜ちようと、この輝きには目が眩んでしまう。最後は悲劇に終ることが分かっていても、ではなく、永遠に続くわけがないよなあ、こんなもの。
あと、解説でも振れられていたけれど、アヴァンギャルドたちの出身地としてウクライナやグルジア(ジョージア)などとあると反応してしまう。確かに彼らの起こしたムーブメントを「ロシア・アヴァンギャルド」と一括りにしてしまうことは、プーチンの汎=ロシア(スラヴ)主義にあいまいな是を与えることになるのかも知れない。じゃあ、となるとソヴィエトならいいのかとも思うが、ふとそもそもなんで「ソヴィエト・アヴァンギャルド」じゃなかったのかとも思う。この辺、ちんけな政治性がまつわりついてなければいいが。ほら、日本ではほとんど見かけないけど、欧米系の知識人で本来ソヴィエトと言うべきところでも、頑なに「ロシア」と言い張る人いるでしょう。あれなんなのかなと思うのだけれど。
Posted by ブクログ
バーリンの『ロシアインテリゲンツィアの誕生』を読んで、19世紀のロシア思想に浸ったまま、抜け出したくない気持ちから本書を手に取った。
本書は、ロシア革命期〜ソ連のスターリンによる粛清までの間の、「ロシア・アヴァンギャルド」と呼ばれる、芸術運動を取り上げる。
その言及する範囲は、絵画や詩にとどまらず、舞台演劇やその衣装、音楽まで幅広い。
当時の数多くの芸術家について言及されており、筆者の知識と理解の深度に圧倒される。
初版は1985年。
まだソ連が地図に存在していた時のことだ。
ロシア革命は政治革命であるが、過去を否定し乗り越える芸術の革命の試みは、それよりも早く、かつヨーロッパ全体で始まっていた。
当時のロシアは文明の後進国であったが、20世紀ヨーロッパで抽象画を生み出したとされる3人の画家のうち、2人がロシア人だというのは興味深い。
しかし時代の進行に伴い、革命は日常へ、斬新さは陳腐へと変容。
日常生活よりも革命精神を重んじる詩人・マヤコフスキイの訴えは、社会の変革期における芸術家のイメージそのものだ。
市民の無関心と世俗欲、政府による統制と、国際社会の力と政治のプレッシャーが、革命をその目指すものから遠ざけた。
当時のロシアの空気を感じる。
登場人物は多いが、最終的にはマヤコフスキイと舞台監督のメイエルホリド2人に焦点が当たる。
革命の形式化に絶望し拳銃自殺を図ったマヤコフスキイと、信念を貫き処刑されたメイエルホリドが、アヴァンギャルドの終焉ということになる。
一方、政治革命と芸術革命の関連で主要な人物として記されているのは、かのスターリンのライバルでもあった、トロツキーである。
彼は、革命時の軍事会議議長という軍のトップであると同時に、「人は政治のみによって生きるにあらず」と述べ、メイエルホリドの舞台で即興の演説を行うなど、アヴァンギャルド芸術を理解していたことがうかがえる。
一方で、その態度が異端と見なされて粛清を招くことにもなっただろう。
或いは、スターリンがその強権によって成し遂げたソ連の近代化と、その結果としてのナチス・ドイツへの勝利は、トロツキーではなし得なかったのではないか、ということも想像された。
いずれにしても、トロツキーの自伝も既に本棚にあり、読むのがますます楽しみだ。
スターリンの伝記から、当時のロシアの政治世界には比較的馴染みがあったが、芸術分野は初めてで、本書からの学びが多かった。
解説の中で、80年代のゴルバチョフによるペレストロイカと91年のソ連崩壊により、政府により隠されていた資料が明るみに出てロシア・アヴァンギャルドへの認識が高まったこと、2000年代に入ってからも東京でロシア関連の展覧会が定期的に行われていたことを知った。
西武百貨店のコミュニティカレッジやパルコ出版が、ロシア・アヴァンギャルドを取り上げていたことも興味深い。
東京でロシア・アヴァンギャルドに関する展覧会が最後に開催されたのは、2013年のようだ。
2014年以降に起こったことを考えれば、それ以後の日本国内での展覧会が困難であったことは、国際社会での立ち位置を考慮すれば致し方ないのかもしれない。
スポーツも芸術も、政治に支配される。
だからこそ、本書のちくま文庫による再版には感謝と敬意しかない。
ショスタコーヴィチの交響曲をまた聴きに行きたい。