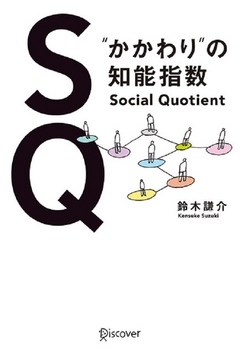あらすじ
「IQ(知能指数)」「EQ(こころの知能指数)」から
「SQ(かかわりの知能指数)」の時代へ!
●なぜ、若者たちはお金より人の役に立つ仕事を望むのか?
●なぜ、女性たちは高級外車よりエコカーを“カッコいい”と思うのか?
●なぜ、父親たちは郊外のマイホームより職場の近くに住むことを望むのか?
TBSラジオ「文化系トークラジオLife」、NHK「青春リアル」でメインパーソナリティを務め、
若年層の圧倒的支持を集める気鋭の社会学者が10,000人の社会調査データを基に描きだす、
21世紀、日本人の「新しい幸せのかたち」。
◎ ◎ ◎
少子高齢化、地方の過疎問題、無縁社会など、課題山積のわが国において、これからの社会を考える鍵となるのは「“身近な他者”とのかかわり」である、と著者は説く。
そして本書では「SQ」というキーワードを提唱する。SQとは、「身近な他者への手助けによって、人がどのくらい幸せになるかを表す指数」。
震災後、「絆」という言葉が注目され、また、「袖振り合うも多生の縁」ともいわれるように日本では古来より大事とされてきた人間関係が、
高度経済成長期、ポスト黄金時代を経て、今後どのように変容していくのか―――
「SQが高い人は幸福な人である」
「SQが“いざというときに頼れる人”をつくる」
「クールビズが普及しないのはSQが低いから?」
「SQで考える新しい居住・通勤のかたち」
「SQ的コミュニケーションが地域社会を再編する」
などなど、具体的かつ刺激的な処方箋まで提示しつつ、さまざまなデータや社会事象をあげながら考察していく、提言の書。
特別付録:あなたのSQタイプを診断できる「SQチェックシート」つき。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
面白かった。第二章の、ポスト黄金時代の説明にすごく納得できた。第三章の、つくられた地域のまつりが、地元にもあるが、20年やってると根付いた感がある。SQは結構たかかった。貧乏だからかなぁ
Posted by ブクログ
「かかわり」を通じてコミュニティのありかた、これからの価値観を考えていく本。
「モノを作ったり消費したりすることによる幸福感はいまの若者にとって魅力的じゃなくなったよ、その代わりに人とのかかわりを基にした幸福感が魅力的にとられているし、そっちのほうが持続可能だよ!」といったところか(大雑把に要約)。
俺自身がまさにそういう感じで、画一化された消費物より、人間関係から生まれる一回限りのもののほうが好きですね。
お金で簡単に買えるものにそこまで魅力感じないし、それよりも考え方とかをおたがい共有して何かするほうが楽しいし。
ただ、自分の周囲を見ているとあながち昭和型の価値観も健在なのかな?と感じることも多いかも。旅行といえばドライブ!って人も少なくないし、記号的にブランド物を消費する人も多いし。
ただ、個人的にここ数年は伝統とか重んじる組織との関わりが強かったし、そのせいってのもあるのかな。
俺自身、「居場所づくり」を当面のテーマと考えているし、こういう考えを起点にして具体的な計画を練っていきたいです。
Posted by ブクログ
ソーシャルキャピタルかと思って読みましたら、ちょっと違うかった。けど概念は似ているなと思います。
人と人との関わりについてをIQならぬSQを用いて表現しており、SQが高い人は他人への貢献度や次世代思考などが高い人という風に表現されています。そもそも、これが考えだされたのは、今の時代背景は高度経済成長時代の考え方をそのまま引きずったままズルズル来てしまった日本社会をどうにかできないか、という思いも感じられます。なぜ黒のスーツで就職活動しなければならないのか、エコといってるけど、エコバッグをたくさん持っていたらエコじゃないのでは?などなど結構面白い概念。
Posted by ブクログ
今SQ(Social Quotient)の考え方が必要なのか、時代と人々の価値観の変遷を通して論じたのちに、どんな社会づくりやまちづくりが今後必要なのかということについて述べている。
最初は個人がどうやって能力を高めるかみたいな話なのかなと勝手に思っていましたが、「かかわりの知能指数」というだけあって、人との協力や家族との関係、コミュニティとの関係などと絡めていたので、とても面白かったと思います。
実は地元が名指しされていたのですが、あんまりその通りのまちづくりはできてないなぁと悲しくなったりもしました。市役所の誰かがこの本を読んでくれることを願いつつ、自分にできることから始めていきたいと思います。
Posted by ブクログ
これまでの普通は普通ではない、を理解するにはいい本。論説を鵜呑みにするわけではないけど、いろんなことが腑に落ちたのは確か。
社会情勢も絡んでて賞味期限は短い本でもあるので、気になる人はイマ読むべき
Posted by ブクログ
モノやお金がある程度行き渡った社会では他者への貢献が幸せを生み出す。
こうした幸福感を生み出す他者への貢献とはいったいどのようなものなのか?
について
SQ(SocialQuontient)というtermをコアに丁寧にわかりやすく書かれています。
特に第2章「曲がり角にきたゆたかな社会」では、戦後〜高度成長時代〜ポスト黄金時代の社会の価値観の変遷が簡潔にまとめられています。
自分が生きる時代とはどういうものなのかベースとなる知識であり、学生時代にこういう本が読みたかった。
3章、4章ではSQをキーにしてコミュニティモデルや未来像について書かれるとともに、
社会学の基本思想なんかを踏まえながら見知らぬ他人との協力の大事さなんかが語られています。
震災後人との関わりについて何か思うことのある方にオススメ。
Posted by ブクログ
かかわりの知能指数とは、幸福度を高める他者とのかかわり力のこと。
他人の手助けをすることを幸せの基準とすること。
人は誰かと協力しないと生きてゆけません。縁を大事にすること。
適切な範囲内でできる範囲で手助けすることが一番。
お金で幸せを買う時代はおわり、人との付き合いで幸福感を得る。
高齢者と若者が出会う場としての中規模地方都市の活性化を目指す。
Posted by ブクログ
SQとはSoceial Quotientの略で、幸福度を高めるような他者(=社会)へのかかわりの力を表す指標のこと。知能指数を表すIQのような概念らしい。
9.11以降、世界的に消費社会からSQ型の社会へと移行する動きがある中で、3.11以降、日本においてもその傾向が顕在化してきている。ただ、日本はSQ型の社会構造がまだ整備されておらず、人々の根底にある価値観も追いついていない。そのミスマッチから様々な社会問題が起きていて、このままだと10年後取り返しのつかないことになるからSQがどうして必要なのかを説明します。というのが、この本の雑な概要。
高度成長期からバブル崩壊までの社会構造の変遷を少しクドいほど丁寧に説明しており、このあたりは社会学を学んでいる人には退屈かもしれない。でも、この変遷を過不足なく拾っているからこそ、「SQ、大事だよね」の説得力が増すのであり、最終章での著者の(衝撃の?)告白にも迷いなく頷けるのだろう。
「いい学校」「いい会社」の階級上昇が約束されていたり、モノや消費活動によってアイデンティティの構築が可能だったりした「黄金時代」が崩壊したにもかかわらず、今の日本社会の制度や多くの日本人の価値観が、旧来の「黄金時代」から抜け出せていない。という指摘は、教育や広告に関わる中でひしひしと感じていること。インフラの整備だけでなく、コンテクストの構築にまで言及しているところは、身の引き締まる話でもある。
付録のSQ診断のようなコーナーのイラストが超ステレオタイプ(アニヲタとかセレブ)なのが気になる(俯瞰的なわかりやすさは大事だが、定型からあぶれてしまった人たちまでをカバーするのがSQ型社会が目指すべき到達点ではないの?SQを広める本がステレオタイプのイメージ訴求に追従するのは、浸透しやすい一方で、かつてのエコやロハスのように消費されてしまう危険性もある)が、ぼんやりと抱えていた「SQ的なものって大事だよね」の背景の部分を丁寧にまとめてくれているので、考えるきっかけとして多くの恩恵を受けた一冊。
Posted by ブクログ
著者がいう。SQ(Social Quoitent)が自分に全然ないことに驚嘆。
この本は、日本の人材層の変化をわかりやすく丁寧に紐解きながら。
そして、今後の日本に必要なSQ社会的人物の渇望が書かれた良書だと思います。
グローバルな知識をもち、ローカルに行動できるコーディネート力を身に着けたい。
Posted by ブクログ
まさにまさに今読むべき本のひとつ。社会貢献というほんの少し前のトレンドではなく、生きやすい社会をつくって行くための様々なアイデアや示唆がある良書。いまだに高度経済成長時代のシステムという亡霊が蔓延するこの時代に対しての具体的な提言がとても興味深かった。街づくりや行政の人など多くの人に読んで欲しい。
Posted by ブクログ
身近な他者への適切な範囲での手助けが、人々の幸福度を高める。社会的なかかわりの力を表す指数「SQ(Social Quotient)」が高い人の幸福度は高い。SQ的な行動や、SQ的な社会づくりのあり方を説く。
Posted by ブクログ
高度経済成長期の価値観から脱却し、幸福度を高める生き方を、SQを使って分析し、活用していくことを提案している本。
どのような価値観を持ち、行動をとっている人が、幸福感を感じることが多いのか、ということをデータをもとに分析している。
過去の仕事観や家族観の形成理由や、それらの価値観が現在では当然のものとして受け入れられない理由等、歴史的な理由も解説されているので、それらを読むのもいいかも。
ちょっと気になるのは、「SQ的な社会でSQ値の高い人間として生きていくというのは、自分には無理のような気がします。」と、SQ的社会の難しさを自ら認めてしまっていること。
「SQ的な手立てとは別の手立てが必要」と書いてあるので、次回は手立ての議論がされることを楽しみにしたい。
Posted by ブクログ
人々の幸福とはなにか。
東日本大震災では、多くの方々が、一度も見たこともない人々に
支援を行っていました。
彼らは、自分たちから積極的に行っており、それが、彼らの幸福にもつながっている
つまり、人々を助け合うことで、幸福を得られるといった考えが、これからの日本社会において非常に重要であることを述べている。
著書では、現在起きている社会的事象を、この考え方に照らし合わせて、
述べている。
経済学、社会学やコミュニティ形成に興味のある私にとって、
大変興味深い本でした。
今後の社会の変化がどのように起こっていくのか、という事に
興味のある方は、読んでみてもいいかもしれません
Posted by ブクログ
良書。また読む。共感する箇所がありました。いまやってるソーシャル・リクルーティング(茶会人訪問)やソーシャル・コマース(内緒)のウェブ開発で(結果的に)「SQを高める設計」をしてることが確認できました。「SQ」という概念はもちろんこの本を読むまで知りませんでしたが、近いことは考えてたなあと。
Posted by ブクログ
IQ,EQからSQ(Social Quotient:かかわり知能指数)の時代へというキャッチコピーに惹かれて読んでみた。震災後1万人の調査から「他人に関わって相手のためになることをしたいと思っている人は幸せな人が多い」、そして「他人に関わろうとする態度は、それがないと不幸になるわけでないが、幸福度が増す要因になる」ことを明らかにした。さらにそこには適切な範囲(自己犠牲的な奉仕より、自分のできる範囲で協力など)があることも指摘している。そして献・広・心・次というキーワードからSQ度という指標を提案している。SQ度というのはマーケティング的かなという気もするが調査結果及び指摘は納得感あるもであった。
著者は76年生まれでTBSラジオ「文化系トークラジオ Life」、NHK「青春リアル」などにパーソナリティーをしている。同年代ということもあり、特に「life」はweb上でアーカイブを聴いたりして、共感することが多かった。それだけに期待が大きかったのであるが、万人向けを目指したのが、「まあそうだよね」というところで終わってしまい残念。もちろん「まあそうだよね」を数値的に示すのはたいへんなのであるが。
今後は、もっと現状を突破するような言論を期待したい(そうなると本は売れないかもしれないが)。
Posted by ブクログ
丁寧でよかった。持続的に持ち続けることができる関りを有する人はより幸福である可能性が高い、という統計に基づいて、これから来るであろう人口減少、消費減少の社会に対しての提言まで、ソフトで読みやすかった。
一番よかったのは、黄金世代、団塊の世代ののちに来る現代までの世代の幸福に関する特徴と推移の考察が分かりやすくて、ちょっと別ノートにでも書きだしたい気分。学者たちが次の世代のために必要なアイディアを提言し続けることの大切さを、なんとなく感じられた。
17.4.20
Posted by ブクログ
タイトルに対して読者が期待する内容と乖離が生じる可能性が高いと感じた。戦後からの社会学的な分析は非常に参考になったが、SQという新しい概念への言及などが非常に乏しい。
Posted by ブクログ
p.48図「献・広・心・次」の度合いを(再)確認してみよう。
p.48の図で示された近すぎないか遠すぎないかの度合いをチェックすることで、いまの自分の傾向を知るだけでなく、過去の自分と比べた変化を確認できた。
学生のころはやはり自己犠牲に走りすぎていたり、地球規模の普遍的価値を求めたりしがちだった。よくある若者らしい理想主義や潔癖主義だったし、自分と世界の間に社会が失われたセカイ系の感覚にも近い。端的に意識高い系だったともいえる。
それから数年のらりくらりと生きてきて、学生の頃と考え方がまったく変わっていない自分にすこし危機感を感じていたのだが、この図を通して、今はそこそこバランスのとれた距離感を意識できている、ということで少しは人間的に成長したのかなと及第点をあげてやろうと思えた次第。
・電源のコンセントをリビング中心に据える提案
・ソフトカー+電動カートの電気シェア
などには心惹かれた。
(集住介護シェアハウスとかもできないかなー。新聞奨学生みたいにちょこっとずつ介護に貢献しながら生活できるみたいな。)
Posted by ブクログ
日本人の絆意識は震災を機に深まったと言われているが、あたかもそれが一般化され、検証されないまま「幸せ=他者への手助け」という普遍構造のごとくまかり通っている感に疑問を感じる。レベッカ・ソルニットは著書「災害ユートピア」の中で、大災害の中に奇妙な共同体が生まれる理由について、平常時の様々な構図が崩壊することによって大多数が兄弟の番人になろうとし、同じ目的意識、連帯感の中に一種の喜びをもたらすからと分析している。つまり「かかわりへの喜びは」ある意味特需的ともいえ、決して普遍の意識とは言い切れない。ただ、そうは言っても、著者自身がかわり度に対してSQというレベル分けしている以上、その前提は大して問題ではないのかもしれない。「100万人に1人の天才よりも100人に1人のそこでしかできないことができる才能」という言葉には納得させられた。
Posted by ブクログ
これからの社会を生きていく一つの指標として、SQという概念を提示、それを説明、それがもたらす理想、について。
なんていうかね、わかるんだけどね、なんかちょっとしんどそう、って思えてしまうダメな私。
Posted by ブクログ
SQの話というよりは、これまでの日本で起きた家族や他人との関わり方の変遷についての解説が詳しく述べられていました。
それだけでも、結構ためになるというか、今の社会がどう成り立っているかを理解できるだけで有意義な本だと思います。
いわゆる、IQやEQのような、個人レベルの話にとどまらず、
社会全体の仕組みづくりのような、広い視野の話が含まれていて、とても勉強になりました。
Posted by ブクログ
No.471
かつては社会のために何かしようとしても一人では困難、でも今は違う。できる範囲で、行動を起こせばよい。その範囲が大きく拡大している。
Posted by ブクログ
仕事には、お金よりもやりがいを求める若者
高級外車よりエコカーをかっこいいと感じる女性
等、これまでのベースにあった価値観が変化している現在の社会。
この本では、幸せというのは「周りの人に対して何ができたか」に依存するだろう、という仮説のもと、それを様々なデータから検証しています。
社会に対するかかわり度を「SQ」と定義し、アンケートに答えていくことで自分の傾向が分かるというのも面白かったです。
何となく、最近感じていたことを言葉にしてくれた本だったように感じています。
Posted by ブクログ
メガトレンドがどうなっているのか。
人口学はやはり馬鹿にできないほどのインパクトをもっていますね
その流れの中で、各世代が何を価値をおき、生きてきたのか。生きていくのか。参考になりました。
要は、自分たちの生きてきた価値観や常識が、世代ごとに異なり、それを理解し、活かしていかないといけないな、と。もっと、勉強したくなりました。
Posted by ブクログ
SQとは、身近な他人への手助けによって人がどのくらい幸せになるかを表す指数。
私自身、ブログを持ったり、意外と地元志向だったり親しい人や馴染みのある土地は離れずらいと思っています。
なんとなく意識する「絆」について、多角的に理解が深まる、今まさに興味深い内容でした。
Posted by ブクログ
タイトルや表紙は自己啓発本だけど、内容は社会学。
日本の戦後の歴史を辿りながら、ポスト消費社会について考察し、提言している。
「経済成長時代」という1階の上に築かれた「2階としての消費時代」。
しかし、1階部分が崩壊したにも関わらず、2階だけがアンバランスなまま存在し続けていた。
いや、もう既に崩落していて、その残骸が「無縁社会」かもしれない。
けれど、「無縁社会」はあくまで「過去の残骸」であって、消費社会を生きた世代の問題である。
今の若い世代が作っている社会はもっと「繋がって」いる。
その繋がりを、世代を超えて広く社会に活かし、身近な助け合いをしようという提言が、本書である。
例えば、ソーシャルな場としてのショッピングセンターや、コンセントを壁面ではなく中央に配置したリビングによってバラバラにならない家庭、偶然すれ違った個人個人が電力を譲り合う電気自動車などの提言が盛り込まれている。
<「何を買ったか」ではなくて、何をしたか、何を伝えたか、何を手渡したか、そうしたことでその人の価値が測られる時代です。>
この一文に、本書の全てが凝縮されていると思う。
Posted by ブクログ
SQ「Social Quotient」とはかかわりの知能指数のこと。
日本でも震以降、社会貢献の機運が高まっているように見えますが、これは
世界的な潮流のようで、むしろ震災を機に表に出たというのが著者の主張である。
戦後日本の歴史を振り返りつつ、家族の概念がどのように変化したのか、今後どう変化していくのか、ヒントを示している。
今後は、本著ではあるべき論だけなので、地域をコーディネートする人材をどう育成するか、商業施設間を結ぶ物流・人流をどうするか、という具体論が展開されると言いかと思います。
Posted by ブクログ
今までの鈴木氏著作のなかでいっちばん読み易かったです。こんなに解り易く書いてもらっていいんだろうかと本当に不安になる…蛇足ですが最近どの著者のどの本もそうで、ありがたいんだけどなんか、いいのかなって思ってドキドキする…
提示されていることは新しいアイディアというより、いま波として起きつつあるものを明確に描き出して下さった感じで、ほんとに、この感覚/価値観がもっともっと広がれば良いなと思いました。
SQ値はベラボウに高かったですが、だから幸せかと言われると良くわかりません。たぶん、SQ値の高さは相互関係があってこそ活かされるのではないかなーと思いました。