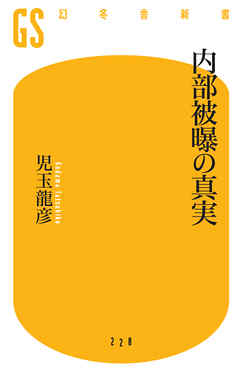あらすじ
「私は満身の怒りを表明します」「7万人が自宅を離れてさまよっているときに、国会は一体、何をやっているのですか」――内部被曝研究の第一人者が、科学者の使命を懸けて政府の対応を厳しく批判。大きな感動を呼んだ国会でのスピーチを全文採録。さらに電子書籍版では、放射線被曝を原因とする子どもの甲状腺がんでは、遺伝子のある部分に特徴的な変異が見られるという、きわめて重要な最新研究成果を紹介。科学的証明には時間がかかるとされていた、放射線による子どもの健康被害の問題に、衝撃的な一石を投じる必読の増補版である。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
原発事故の一番の問題は放出された放射性物質の総量が莫大で必ず濃縮が起こり、高線量のスポットができること。対策は食物は全数検査と、地域は学校などを優先して、高濃度スポットを測定して、除染する。わかりやすく書いてあるのでおすすめです。
Posted by ブクログ
BIO Tech 2012では、IT創薬に関する講演会の司会をやっていらっしゃいました。政治力学ではなく、医療科学の視点から、ごく当たり前の話を語った本です。
Posted by ブクログ
素人でも非常に分かりやすく読みやすい。
内容などは他の方にまかせるが、
東日本大震災では悲しく、絶望の思いもしたが、
日本には児玉先生のように、正義感に満ち溢れた
立派な人がいると知り、それは気持ちの上でも救いのように思える。
先生の人間性に感動する。
Posted by ブクログ
国や東電を批判している有名どころの科学者や医者の本を何冊か読んだけど、この本はそれらの人たちと少し違った趣がある。
”人が汚したものなら、人がきれいにできないわけがない。そのために全力を尽くすのがわれわれ科学者の責任である”p.136
「今日本が持っている科学技術の力を結集して除染につとめ、日本の国土を元に戻そう!」という強い気迫が伝わってきて、読んでいるこちらも前向きになれる。
まだ読んでいない人には、ぜひおすすめしたい。日本にこんなに熱く、立派な科学者がいるんだ!
Posted by ブクログ
確かに、数年・数十年経ってから明るみに出てくる真実ってのは枚挙に暇が無いし、不幸にもそれは、デメリットである場合が多いと思う。だからこそ、その可能性に対しては謙虚でなければならないと思うし、軽んじるようなことがあってはならないと思う。一方で、大きくないリスクにあまりにも拘泥し過ぎて、大勢を見失うようなことがあっても、それはそれでいけないと思うし。要するに、なかなかこれが答えっていう風に片付けるのが難しい問題に関しては、中庸の姿勢で、朝令暮改もアリで、真摯に向き合っていくしかないのですね、結局のところ。
Posted by ブクログ
少し荒っぽい所もあるが、もっと知られても良い内容が含まれているように思う。不完全な形であっても、こういった第一線で働く人の声を広く知らせることも出版の大切な役割だと感じた。
食品などの放射線測定には、厚生労働省が標準としてきたゲルマニウムカウンターより、高性能で容易に検査出来る測定器があること、
検査体制の遅れも、法整備が追いついていないため、設備を持っている部署が動くに動けないこと、
除染についても、イタイイタイ病の時、20年かけて行った経験があるのに、その時の経験が反映されていないこと、など。
Posted by ブクログ
ざっと流し読み。一躍反原発のヒーローになった児玉教授だが、除染に関してはその中でも意見が分かれるところである。果たして本当に除染は可能なのか。なにしろまだ分からない事が多い事態なので、政府が総力を挙げて取り組むべきなのだが、増税やら再稼動やらに一生懸命でまったく当てにならない。科学者個人の良心に頼るしかないのが悲しい。
Posted by ブクログ
専門家とは、
・危険なことがあったら、これは本当に危険だから、苦労があっても何でもやっていこう国民に伝える。危険を危険だとはっきり言うのが専門家。折り合いをつけることではない。
・歴史と世界を知り、本当の危機が顕在化する前にそれを防ぐ知恵を教える人でなければならない。
・専門家には想定外があってはならない。想定されたリスクを瀬に、正しく伝えなくてはいけない。
との言葉にただ納得。
そしてまた、そのことを思うと、本当の専門家は日本では重用されていないのだと改めて思いました。
Posted by ブクログ
ごめんなさい、今頃読みました。。。
国会発言が7月末、それから5ヶ月経過して変わったことと云えば、
計画なき除染(移染)が大々的に事業化されてしまったくらいですか?
しかも、危惧されていた『利権がらみの公共事業化』に近い形で。
警鐘を鳴らしてくれる人がいるありがたさと、
それを実現しない(「できない」ではなく「しない」)官僚・政治屋に
絶望しかけている今日この頃です。
【収録内容】
第一部 7・27衆議院厚生労働委員会・全発言
1 私は国に満身の怒りを表明します
2 子どもと妊婦を被曝から守れ――質疑応答
第二部 疑問と批判に答える
第三部 チェルノブイリ原発事故から甲状腺がんの発症を学ぶ
――エビデンス探索20年の歴史と教訓
第四部 "チェルノブイリ膀胱炎"
――長期のセシウム137低線量被曝の危険性
おわりに 私はなぜ国会に行ったか
付録 国会配布資料
Posted by ブクログ
人が汚したものを人がきれいにできないわけがない。
○総量が多い場合、平均濃度ではなく濃縮が問題
→モニタリングの重要性
○子供を守ること
○緊急避難的除染と恒久的除染を分けて考える
○避難と補償の問題は分けて考える
○アイソトープセンター、東レ、クリタ、竹中工務店、千代田テクノル、アトックス…知見を活かす
○セシウム137
○科学者と政治家の違い(本質論をすべき)
○ベクレルからシーベルトを推定する議論の難しさ
Posted by ブクログ
TV報道で、国会で怒っている児玉先生の様子が報道されていました。
ああ、こうやって本気で怒っている人が国会に出れるんだと、その時なぜかほっとしたのを覚えています。
児玉先生のような方がこれだけ被爆の危険性を訴えているのに、
なぜ、政府、東電、大手マスコミは、その危険性を過小評価した報道しかしないのか?全く疑問です。
自分で責任がとれないから?責任を問われるのが怖いから?
これから5年先、10年先、次々と被爆被害が明らかになった場合、現状とは比べ物にならないほどの批判にさらされ、責任を問われるはず。
その時はどうするんだろう。
A級戦犯が今でも生きているように、本当の犯罪者は生き残り、トカゲの尻尾切りのように、さして悪くない人間が象徴的に裁かれて終わりなんでしょうか。
Posted by ブクログ
科学者、専門家としての良心や使命感が(やや感情的な文言も目立つが)読み取れ、その面では腑におちる内容。
ただ、福島事故を、放射線予防医学の観点のみから語るのは、問題のごく一面しか見ることにならない、ということを、このような本の読者は認識する必要があると思う。エネルギー問題、科学進歩の正邪、不確実性に対する認識の限界に前向きにチャレンジすべきなのかどうか、経済や人々の豊かな暮らしについてどう考えるのか、これらはすべて相互に関係している。一分野の専門家の意見だけで、今回の事故に対して「どういう方針で解決すべきか」を語るのは、無謀であることに注意しなければならない。
また、健康や生命に関わる情報は、個人にとって本質的に切実な問題であるだけに、「がん」という言葉がいっぱい登場する一般向け書物は、人々に不安を植え付けるおそれがあるだろう。医学者の書く一般向け著述には、そういう可能性がありえるのだが、出版社は読者の不安を利用して販売効果を上げたいと考えるのが普通だ。
児玉氏の主張は、氏の専門家としての実績から言えば、おそらく特にバイアスもなくナイーブな科学的良心に基づくものと見てよいと思う。しかし、本書を出版した、幻冬舎には、上記のような下心がなかったとは言えないのではないか。
Posted by ブクログ
東京大学アイソトープ総合センター長の児玉龍彦氏(著者)が,7月27日の衆議院厚生労働委員会に呼ばれて発言した内容をメインに収めた新書です。
私も福島原発の事故以来,「問題は内部被曝を如何に防ぐかだ」とブログなどに書いてきました。本書は,専門家の立場から,その内部被曝について警鐘を鳴らし,「はやく現在の測定方法や法律などをすぐに変えて,対処すべきだ」と,訴えています。
「人が汚したものを人がきれいにできないわけがない」という熱い思いが伝わってきます。
時々専門用語も出て来ますが,その都度,脚注がありますので大丈夫でしょう。
Posted by ブクログ
東大先端科学技術研究センター教授、アイソトープ総合センター長による著作。衆議院厚生労働委員会に参考人として出席し、一躍に有名になった。東大教授=御用学者のようなイメージを持っている人がいるかもしれないが、これまでの限られたデータや、南相馬で自身(のグループ)が除染作業を行った時のデータから、科学的に考え、説明しようとする姿勢は好感が持てる。放射性物質が平均的に低い濃度でも、様々な臓器で濃縮することにより被害が起こる可能性を指摘している。原発事故関係の本では読むべきものの一つと思われる。
Posted by ブクログ
衆議院厚生労働委員会の発言で、国民を感動させた児玉龍彦氏の著作である。委員会の発言内容と説明用資料はもちろん収録されているが、それ以外にもチェルノブイリにおける甲状腺がんや膀胱炎にかんする調査結果が含まれている。
放射能被曝に閾値があるのかという問題については、この本を読む限りでは少量でも害があることが理解できる。遺伝子の一部が傷つくことにより、将来がんが発生しやすくなることがチェルノブイリの甲状腺癌の研究からわかってきた。
福島ではヨウ素による被害はそれほどひどくなさそうであるが、セシウム137による汚染が長期にわたって発生した場合どのような被害が引き起こされるか想像できない。特に、内部被曝を抑えることが重要で、そのためには食品検査を効率的に行う体制の確立と除染が重要だ。
Posted by ブクログ
大反響だった東大児玉先生の国会スピーチ。悪魔の証明というか、どのくらいなら安全とか、そういうことじゃないんだ!という強い怒り。Webにも動画や書き起こしがあるが、冷静に文章で読み直すと改めて科学者としての責任感の高さを感じる。
Posted by ブクログ
内部被曝のことを報道で目にする機会が少なくなったし、見たとしても集団検査で検出されなかった、という話が多い。ではもう大丈夫なのか。ホールボディカウンターで総計を見るのではわからない、核種ごとの違い、蓄積される部位の違いなどの話が、その後の検査にどう反映されているのかも、僕は知らない。
安易なエビデンスはいけない、多数の例があってもエビデンスにはならない、という言葉が突き刺さった。チェルノブイリでさえ20年かかったのだと。ではまだ何もわからない、と怯えるだけでいいのか。怯えすぎかなあ、という印象がないわけではない。除染の基準はハード過ぎるかもしれない。でも、「直ちに影響はない」を、今こそ追求しないといけないのかもしれない。
とにかく、局所的な何かだけでものを語ってはいけないのだ、ということがよく伝わる本。
Posted by ブクログ
国会の参考人発言で注目された方である。その発言内容を中心にまとめた本である。チェルノブイリの甲状腺癌の因果関係が証明されたのが20年かかっている。今後はセシウムによる膀胱癌への影響が注目されるとのこと。内部被曝については時間がたたないと分からないことがあり、その場でのエビデンスに縛られすぎると間違った結論にもなる。事実を踏まえて経過を見る態度が必要と臨床的な姿勢。専門家が「想定外」を連発するのは無責任と潔い。この本も事故後に一気に増刷されたがその後は増刷されず、世間の興味が薄れたのか。ただここで述べられていることは今も生きる。
Posted by ブクログ
国会での発言が話題になった児玉龍彦さんの本。
国会での発言内容やチェルノブイリでの放射能の影響の事例など書かれている。
原発事故の影響で実際に癌などが増えるのは、放射能飛散後10~30年たってから。
放射線で最初に遺伝子を修復する機能が破壊され、次の変異で発症するため。
福島原発の影響が本当に出てくるのは、これから先の事なんだなぁ…。
Posted by ブクログ
医師である著者が内部被曝の危険性を訴える本。
東日本大震災以降に、内部被曝がいかに軽視されてきたかが分かる。
子供や妊婦といった日本の将来のために、
国を挙げての早急な除染の必要生を痛感した。
著者曰く、「専門家とは、歴史と世界を知り、知恵を授ける人」であり、
想定外があってはならないとのこと。
その専門家が意見を気軽に言える場、専門家と現場との協働する場が、
今の日本には必要であろう。
政府や企業のことだけを盲信する訳にはいかない。
Posted by ブクログ
・内部被爆の一番大きな問題はがんであり、がんは放射線がDNAの切断を行うため。DNAというのは2本の鎖からなる二重らせんのため二重のときは非常に安定しているが、細胞分裂するときは二十らせんはほどけて1本ずつになってそれぞれが2倍に増えて鎖が4本になる。この鎖が1本になる過程のところが切れやすく危険。
→妊婦の胎児、幼い子供などの成長期の増殖の盛んな細胞に対して危険性を持つ。
・甲状腺の場合は汚染された牛乳などをたくさん飲むと最初にRET遺伝子がやられるが、1回やられただけでは発ガンせず増殖するのみ。その後もう1個がやられるとがんになる。
・学会の主流と政府は何を誤ったかというと、現行法の「高い線量の少量の汚染」を考え、濃度を元に「さしあたり健康に問題ない」としてきた。しかし、システム論から見ると線量が問題で、「低い濃度でも汚染が膨大になおこると、特定の場所や食品に濃縮がおこり、健康に害をもたらす」
Posted by ブクログ
いっとき、国会答弁がYouTubeに流れていたことがきっかけで買った本。
遠方の地でえらそうなことを言っている人よりはるかに心にずしんとくる内容。
ちなみに、通販生活2012春号にも登場している。
Posted by ブクログ
本からの抜粋。
『現行法の「高い線量の少量の汚染」を考え、濃度をもとに、「さしあたり健康に問題ない」としてきた。しかし、システム論から見ると総量が問題で、「低い濃度でも汚染が膨大におこると、特定の場所や食品に濃縮がおこり、健康に害をもたらす」可能性が生まれる。』
この考え方を知っただけでもこの本を読む価値がある。発言抜粋が過半を占める構成で、専門用語が並んで理解しにくい部分も少なくない。たぶん正しく知るために必要だから掲載されているであろうデータも、正直(素人で流し読みをせんとする僕には)理解しにくい。こうした内容にも関わらずこの本が売れているのは、正しい情報が何か分からず、一次情報を求めている人が多いからなんだろうと思った。
Posted by ブクログ
YouTubeで話題となった「7・27衆議院厚生労働委員会・全発言」も収録された児玉龍彦の著作。《危険を危険だとはっきり言うのが専門家》という信念の元に、豊富な資料と実測データ、それに過去の実例に基づいて、専門家としての知見を提示する。
この著者が信頼に値する最大の点は、被害者面してないことかなあ。政府や東電に対して苛立ちはあっても、ただ非難するのではなく、あくまで具体的な現状からの改善案を示す。それと同時に、国民ひとりひとりに対しても、現状を説明して具体的な対策を講ずる。専門家としてのブレがない。