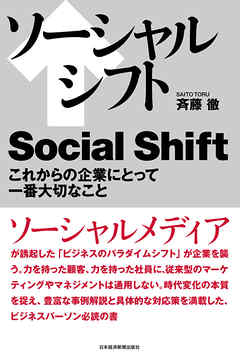あらすじ
ソーシャルメディアが誘起した「ビジネスのパラダイムシフト」が企業を襲う。力を持った顧客や社員に、従来型のマーケティングやマネージメントは通用しない。豊富な事例解説と具体的な対応策を満載した、ビジネスパーソン必読の書。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
お客様を私とあなたの関係ととらえ、こころ通わしファンになっていただくには、リアル以外にもコミュニケーション手段があるのだ、取り入れるべきだと感じた
会社の存在意義が見失われ、内向の経営になっている危機感を感じさせられたし、働く一人ひとりにどう経営理念を浸透させ、一人ひとりがお客様と向き合う仕事ができるか、その課題解決のヒントをいただいた
Posted by ブクログ
ちょっと前に参加した東京朝活読書会(エビカツ読書会)での「ツンドクブ」をきっかけとして、どこかで再読しようと思っていた『ソーシャルシフト』。その時は時間が足りずに(正味20-30分ほど)概要の概要を把握する位で終わったのですが、子どもが宿題を片付けているのを横目に、ふと思い立って手にとってみました。
せっかくなので、佐藤さんが『読書の技法』でおっしゃっていた「速読(30-60分)」にチャレンジしようと、30分1本勝負を目標にスタート。300ページを越えるボリュームのため、30分でとなると一言一句を追うわけにはいかず、見開きページ単位で俯瞰&気になった所にマーキングしながら追いかけてみました。
入り方は「ツンドクブ」の時と同じく「ソーシャルメディアを情報基盤として捉えた場合の、社会的、個人的な位置づけは?」との情報のキュレーターとしての視座から。そして問題意識は「ソーシャルメディアが広がった背景とこれからでてくるであろう社会的な問題」、「情報発信が双方向に行われるようになっていることと、その課題」、「今後のビジネス組織のあり様の変化」とこれも変わらずに。
副題の「これからの企業にとって一番大切なこと」というのが示すように、企業と社会、そしてそこに生きる人々の“パラダイムシフト”について、豊富な事例と共に丁寧にまとめられていました。
今までの企業は上から下への垂直な統制志向型が主流ですが、今後は立場上では対等で強者も弱者もない、お互いに足りないものを補完しあうように“シフト”していくだろうと。同じことができるメンバーを集めてれば(もしくは教育すれば)よかった時代は終わり、“共感しあった目的”に向かってそれぞれの強みを持ち寄るといったイメージでしょうか。
これは集合知とも言われる概念で、『ワーク・シフト』では“ポッセ”との言葉で表現されています。
今まで、権力を握るためのポイントとされていたのは「富」「暴力」「知識(情報)」で、これらは上層に行かないと手に入らないものでしたが、、これからは「共感」という心の深奥に響く要素が一番必要とされるようになり、それは組織の上層部でなくても手に入るようになってきた、と。そしてその世界を導き出したのは、個人同士の緩やかなつながりを推奨する“ソーシャルメディア”と位置付けています。
今後、この“ソーシャルメディア”で共感される企業になるための5つのポイントは、、
1.社会に対する自社の付加価値を見直すこと
2.顧客に対する貢献姿勢を明確にすること
3.信頼される企業になること
4.生活者と同じ目線で対話交流をすること
5.社会に対する貢献姿勢を明確にすること
としていて、企業を“ソーシャルシフト”させていく6つのステップは、以下としています。
step1.プロジェクトのコアをカタチづくる
step2.ブランドコンセプトを練り上げる
step3.すべての顧客接点を改善する
step4.オープンに対話できる場をつくる
step5.顧客の声を傾聴する仕組みを構築する
step6.社員の幸せと顧客の感動を尊ぶ社風を育む
文中で何度か出てきますが、これからは「透明性の時代」で、“社会性”を意識していかないと生き残っていくのは難しくなっていくのでしょう、企業も人も。人間は本来「社会」から切り離されては「人」としては生きていけない社会性の強い動物です。そういった意味では、原点回帰とも見てとる事ができましょうか。
もう一つ興味深かったのが、終盤で“日本の原点に戻り、日本人としての誇りを取り戻そう”と話されている点。これは戦後レジームの中で日本人が半ば強制的に忘れさせられてしまった「国のかたち(国体)」のことと思います。ちょうど並行して読んでいた『日本人はいつ日本が好きになったのか』とリンクして、不思議な縁を感じました。
出版されたのはちょっと前の2011年11月、ケーススタディとしてあげられている事例こそ古いものの、根っこに横たわる概念は今まさしくの時代を投影していると、思います。『ワーク・シフト』や『未来の働き方を考えよう』、『2022 - これから10年、活躍できる人の条件』あたりともシンクロして、興味深く拝読できました。今回の速読では事例は流し読みでしたので、折々で読み返してみようと思います。
また個人的な見解となりますが、戦後日本が変わったターニングポイントは「東日本大震災」であった、これを機に“戦後”が終わり、戦後レジームからの脱却がはかられたと、後世に言われるようになると感じています。
ん、企業が生き残っていくためのヒントだけではなく、日本人が「大きな物語」を取り戻していくには、なんてところまで考えさせてくれた、そんな一冊です。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディアの威力を教えてくれる。
ソーシャルメディアの良いところ、良い部分に(だけ)着目してどれだけの効果があるか魅力的に伝えてくれます。
「共感」によるブランディングや
AISASなどのマーケティングモデルによる分析などを豊富な事例を元に紹介していてソーシャルメディアの流行の理由なども察することができました。
対談なども載っていて、ボリュームもあるので買って損はしないのではないかと思いました。
Posted by ブクログ
大きく取り上げられているわけではないが、製品関与マップごとのメディア戦略の整理が自己の立ち位置のために参考になった。事例に豊富で、個人的なリサーチや行動の起点になる記述が多かった。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディア活用の基本を、まずブランド構築と置き、更にバリューチェーン上の様々な機能で、その力を活用している企業の具体的な事例が豊富に掲載されている。
後半では、その実現のため、組織のエンパワーメント、及び顧客とのコンタクトポイントにおける一貫した対応が重要であることが説明される。
これはそう簡単な話ではないと思うが、ブランド体系をしっかりと構築し、これを社内に徹底することで必要であると著者は言う。
現在の経営管理、組織のあり方を問い直す必要がありそうである。
Posted by ブクログ
友人の加藤くんが勤めるLooopsの代表、齋藤さんの著書だったので読んでみました。
新しい時代に確実に変わり始めている今、何が起きているのかを自分の実感だけでなく、同じ時代に同じような感性で時代の流れに乗っていると感じられる人の本を読むことは、自分自身や世の中をもう一度整理するためにとても大事なことだと思うし、さすがだなぁと思うこともたくさん書いてあってとっても勉強になった本でした。
TwitterやFacebookをある程度使ってる人であれば、とても考え方を加速させられる一冊だと思います。これから始めてみようかなと思ってる人にも、どんなことができるのかシンプルにわかりやすく事例が書いてあるのでとても参考になると思います。
Posted by ブクログ
ソーシャルネットワークが広がり、これからがどうなっていくのか。Facebook、Twitterを業務に取り入れ企業と顧客の結びつきを変えることができる。その必要性とパラダイムシフトを企業の実例を元に紹介した本。良書。
Posted by ブクログ
企業をソーシャルシフトするステップとして、
1.プロジェクトのコアをカタチづくる
2.ブランドコンセプトを練り上げる
3.すべての顧客接点を改善する
4.オープンに対話できる場をつくる
5.顧客の声を傾聴する仕組みを構築する
6.社員の幸せと顧客の感動を尊ぶ社風を育む
ソーシャルメディアで共感される会社になるためには、
1.社会に対する自社の付加価値を見直す
2.顧客に対する貢献姿勢を明確にする
3.信頼される企業になる
4.生活者と同じ目線で対話交流する
5.社会に対する貢献姿勢を明確にする
ブランドエッセンスである事実特徴と機能価値、ブランドパーソナリティである情緒価値と社会生活価値
Posted by ブクログ
副題の「これからの企業にとって大切なこと」というのが、よく表している通り、これまでとは異なる戦略・思考が必要となる、ソーシャルの世の中の成功例や成功例に導くための留意点をまとめた本である。
一言で言えば、「共感」というのがキーワードになり、そのために必要なソーシャルの道具として、twitterやfacebook等が必要になるだろうということになっている。
内容は、ソーシャル化している社会の現状、マスコミ等が制御できない力となっていることや、個々の企業の努力などの紹介をまとめている。全ては鵜呑みにはできないが、少なくても10数年前にはなかったビジネス・モデルができ始めていることには疑いない。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディアの発達により、企業が今まで以上に透過性を求められている。
そのことについて記された本。
東日本大震災以降、人々の感覚が変わり、あいまってfacebookなどのソーシャルメディアの発達が、企業のコミュニケーションを変える。
事例が豊富に乗っており、中には炎上対策まで記されている。
ソーシャル時代の潮流を知るには良い本だと思います。
Posted by ブクログ
本書の特徴は「ソーシャルメディアが人々の考え方をどう変えて、その結果として人々はどう振る舞うべき世の中になったのか」という観念的な面に比重を置いている点です。
例えば現場の店員の振る舞いが一瞬にして2000ツイートに結びつく。良い場合も悪い場合もある。口コミが強力なので有名なのはリッツカールトンだが、ソーシャルメディアの登場で、あらゆるブランドの口コミが強烈になってきている。
だから現場の人間が思想として正しいものを持っていないといけないし、管理本部は現場に権限を与えないといけない。
そんなアプローチで、「企業がどう変革していかないといけないか」を語っています。
よく見かける事例も色々と載っていますが、観念的な視点で紹介しているので、もともと知っていた事例でもちょっと面白い。
ソーシャルはビジネスになります。
でもそれは、そもそもソーシャルが可能性を持っているからです。
可能性のことを考えると熱くなります。
そんな忘れかけていたようなことを思い出させてくれる1冊でした。
Posted by ブクログ
★ソーシャルメディアは今のところ、ブランディングの道具のようだ。それが、企業のあり方を変えるところまで行くのか見ものだ。
★透明性の時代になって、原則が重要になってきた。社員によるソーシャルシフトは影響の輪に働きかける、ということだろう。7つの習慣はここにも応用可能だ。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディアの発展によってこれまでよりも企業活動の透明性が重視され、"Do the right thing"の精神が大切なのは納得。ソーシャルメディアを使ったマーケティングがどれほどの効果があるのかは、やや疑問もあり。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディアが誘起した「ビジネスのパラダイムシフト」が企業を襲う。この本はソーシャルメディア使用の第一人者が書いた、時代変化の本質を捉え、豊富な事例解説と具体的な対応策を満載したものであります。
この本はソーシャルメディアを専門とする会社の経営者が書く「ソーシャルメディアを使ったパラダイムシフト」について描かれた書籍でございます。豊富な実例を用いて「これからも企業はこうあるべきだ」ということが書いてあって、時代の変換を感じさせるものでありました。
具体的なことを申し上げますと、
「ソーシャルメディアが社会にもたらす本質的な変化」
「企業と生活者との新しいコミュニケーションのカタチ」
「すべての顧客接点で素晴らしいブランド体験を提供するための仕組み」
「それを実現するためのリーダーシップや組織のあり方」
「具体的に企業を変革するためのステップ」
こういうことがかかれております。運営している会社もツイッターやフェイスブックその他もろもろのソーシャルメディアを知恵を駆使して利用している場面、特にローソンや無印良品の使い方にはうならせるものがあって、とても参考になるかと思われます。
企業をソーシャルシフトさせる6つのステップとして以下のようなこともあげられていて、
ステップ1 プロジェクトのコアをカタチづくる
ステップ2 ブランドコンセプトを練り上げる
ステップ3 すべての顧客接点を改善する
ステップ4 オープンに対話できる場をつくる
ステップ5 顧客の声を傾聴する仕組みを構築する
ステップ6 社員の幸せと顧客の感動を尊ぶ社風を育む
こういうことができて、これからの「透明性の時代」に生き残っていこうという筆者の主張には、もはや抗うことのできない「時代の流れ」というものを痛切に感じました。早いうちから取り組んでいるところはそれでよし、なかなかそういうことを理解できない方にもこの本を一読いただくか、ここに書かれていることを要約してうまく説明できれば必ず変わっていくことを信じていこうと思っております。
Posted by ブクログ
ループスの斎藤氏による著作。ソーシャルメディアの存在を無視できなくなった時代に、企業はどのようにしてソーシャルメディアと向き合っていくべきなのかを書いている。事例を豊富で、読んでいて入ってきやすい。
文章が読みやすいため、ボリュームの割にスラスラ読める。
Posted by ブクログ
ソーシャルビジネスの第一人者が書いたと聞いて、読んでみた。
ビジネスにおいて、どのようにSNSが活用されているのかが豊富な事例を交えて詳しく書いてあり、大変勉強になった。
特に、良品計画(無印良品)の試みがすごい。まさに顧客と一体となって製品を開発できること示した好例。
ビジネスの在り方が激変することを予感させる1冊。
Posted by ブクログ
業務参考として。 引用が多いが、要素網羅/事例豊富。
もうソーシャルそのものの本は暫く良いかな。
ここから顧客心理など専門的な本に分岐して読んでいく必要性を感じた。
オープンリーダーシップ
Posted by ブクログ
■ソーシャルシフト
1.あやゆる情報を共有できるソーシャルメディアの登場は次のようなパラダイムシフトに直面する。
A.企業やブランドは、不誠実な言動がないか監視される。
B.顧客の感情に訴えるメッセージやサービスが重要となる。
C.信頼関係を築けた顧客は、企業を支えるパートナーとなる。
D.大企業において組織の硬直化等、負の側面が目立ってくる。
2.生活者が企業のバリューチェーンに参加する。
3.昔のマーケティングは「製品が中心」だった。良いものを作れば売れる時代、どの様に製品を販売するかに力点が置かれていた。だが、これからのマーケティングは「人間が中心」だ。
Posted by ブクログ
企業がどのようにソーシャルメディアとつきあっていくべきかを解説した書。豊富な事例解説が特徴となっている。
事例紹介の中で印象に残ったのはザッポス。
「最も有名な伝説は、母親を突然亡くしたため、プレゼント用に購入したシューズを返品したいと申し出た女性の話だ。電話を受けたコンタクトセンター社員は、悲しみにくれる彼女のもとに宅配業者(規約では顧客が集配所まで持っていく必要がある)を手配するとともに、翌日には手書きのメッセージカードを添えたお悔やみの花束を届けたのだ。感激のあまり号泣した彼女は、その感動をブログにつづり、それがネットを駆け巡ることになる。」
このような真摯な対応は心を打つが、実際問題として大きな企業になればなるほど、このような対応をするべきか判断が難しくなるところである。しかし、企業の価値はますますこのような真摯な対応で試されるように時代がシフトしているのを強く感じた。
Posted by ブクログ
出版された頃と現在ではソーシャルメディアを取り巻く環境も大きく変化している。
でも、特に企業がこれらを有効な武器にしていくために考えなければいけない基本は、そう変わっていないのかも知れない。
何年経っても出来ていないところは出来ていない。
Posted by ブクログ
ブランドのミッション、ビジョン、バリューの定義を行うだけでなくそれを社内に浸透させるインナーブランディングの大切さを再認識。自由度が高くカスタマーと近い接点で商品改良ができ世の中に新しい価値を提供しやすくなった反面、組織の末端まで浸透する価値観を醸成しなければマイナスの影響も計り知れない。
マイナス点は2点。1点は前述したマイナス面があまり記述されていなく、ソーシャルメディアハッピー!な内容になってしまっていた点。2点目はtwitterとfacebookに話が閉じていた点。生活者のSNS事情はめまぐるしい速さで進化を遂げており、それぞれにタグづけされた”表層的な顔”とカスタマーの本質をそれぞれ認識する必要があるのではないか。
Posted by ブクログ
新しいコミュニケーション方法を介して共感を得ることで市場を活性化することのようだ。いいね!という感情をシェアする。ひとつの企業を超えたコラボレーション。
待ち時間にQRコードの広告
信頼できるサービスの体験をリアルにする
説得(マスメディア)⇒共感(ソーシャルメディア)
人脈とは?リアルorネット
Do the Right thing
Posted by ブクログ
基本的に、BtoCビジネスをしている事業体(企業とは限らない)向けの内容。
大分、Twitter、Facebook活用万歳な内容になっているが、主流SNSがその2つだから仕方ないか。しかし、この本が2011年発行なので、それ以後盛り上がってきた、クローズドなSNSであるLINEにどう対応しようとしているかは見て見たいかも。LINEはある意味、仲間内外との接触拒否なツールなので、オープンなSNSにどんな影響を与えているのか?
どこまで行っても、事業体(企業とは限らない)側が情報強者で、クライアントのコントロールができる時代ではなくなった事だけは、仕事をする上で肝に命じる必要があるし、クライアント側もモンスター化したら退場させられる、イーブンかつフラットな世の中に近づいているのは確かだと感じる。
そんな世の中での価値あるものは、やはり情報ではなく「知恵」だな…。
Posted by ブクログ
時間かかったがザーッと読んでも頭に残らないタイプの本。実際にソーシャルメディアを活用したカスタマーコミュニケーションやブランディング、プロモーションの導入を考えてる企業のウェブ担当者や経営者が、組織やポリシーを新しいものにかえる際には神本になりそう。
Posted by ブクログ
facebookやtwitterをいかにビジネスに活用すべきかを、豊富な事例を紹介しつつ解説した一冊。
ソーシャルネットワークによって、発信するだけでなく相互に繋がることが可能になり、パワーを持った一般大衆は、企業の立場からみると、顧客であったり従業員に該当する。この時代に最悪なのは、旧来と同様に管理を強化し、体制を維持ようとすること。これはビジネスの世界だけでなく、中東における体制変動や米国などでの選挙といった政治における動きとも共通する。
柔軟性とスピード、そして本書にもあるように、なによりボトムへの権限委譲が重要になるが、これらはビジネスというより、歴史、社会学の観点をもって考えていく課題であるように思われる。
Posted by ブクログ
ソーシャールメディアによって企業をシフトする6つのステップが記述。
ソーシャルメディアが社会にもたらす本質的な変化、企業と生活者との新たなコミュニケーションのカタチ、「シェア」がもたらすもの、リーダーシップや組織のあり方や具体的な変革のステップなど。
個人的にはあまりスッとアタマに入って来なかった本。
Posted by ブクログ
企業は生活者とのあらゆる接点で、今までの考え方を大きく変革する必要がある。ソーシャルメディアが誘起したパラダイムシフトを「ソーシャルシフト」と読んでいるようです。
気になったことを何点か
①企業は創業時のDNA・企業理念を経済合理主義・行き過ぎた資本主義のもとうしなってきている。と書いてあるが。そんな企業は少数だと思う。
企業のマネージメントが透明性がないとかウンヌンカンヌン書いてありますが何か偏った見方のような気がします。
②企業やその組織のソーシャルシフトすべきであるということに関しては総論賛成でためになることもかかれてあると思います。ただ、こういうことを考えるときって。普通の人は自分の属する企業や組織を思い浮かべると思うのですが、どうしても顧客の組織や企業を思い浮かべてしまうのは、どうなんだろうと自分のことを思います。
③今の若者は、モノを浪費すし環境を破壊するビジネスに心の底から嫌悪感をもっていて、社会への貢献なしにお金儲けに走る人々をかわいそうな人たちと思っている。そうで。。。ボスが怠惰な週末を過ごしている間に、企業の枠を超えた仲間が集まり次々と時代のニーズを解決していくそうです。
うちの若い人たちもそうなのかなあと思いました。
怠惰にすごさざるを得ない我々は、本書に書かれてあるオープンリーダーシップを身につけるべきであるとは思います。
でももう一方でそういう若者の考え方や行動も、はやりを追っているだけ
ではないのかとも思います。