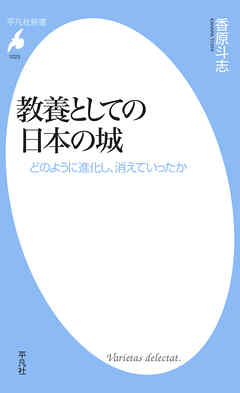あらすじ
姫路城、江戸城、熊本城……なぜ日本の城は豊かな発展を遂げ、消えたのか。16の城を世界史の中で読み解き、新たな視座でとらえ直す
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書は「各地の城址を訪ねる」ということの御案内に留まらず、判り易く目立つ形で残る建築、或いは存在が伝わる巨大な城ということを入口に「近世の文化の変遷」を説くような、なかなかに興味深い内容を展開していると思う。
「城」とでも言うと、色々な史跡が在って、その内容は様々である。が、「城」とでも言えば「大きな石垣の上に、大きな建物が建つ」というような様子を思い浮かべるというのが「公約数的な理解」になると思う。そういう「大きな石垣の上に、大きな建物が建つ」というような様子の「多分“元祖”」は、かの安土城と思われる。本書はその安土城に纏わる篇を冒頭に置き、以降は「近世の文化の変遷」の中で語るべき内容を持つ各地の城を取上げた篇を連ねている。
本書で取上げられている各地の城は、安土城、大坂城、小田原城、熊本城、姫路城、二条城、彦根城、名古屋城、江戸城、島原城、原城、丸亀城、宇和島城、高知城、松山城、松前城、五稜郭ということになる。これらの中、個人的には原城、宇和島城、松前城は近寄った、または遠望したということも無い。江戸城も「城址を訪ねて」というようなことはしていないかもしれないが、東京に在れば、その城址に相当する場所を動き廻った経過は在る。そういう具合ではあるが、とりあえず取上げられた場所の多くを訪ねた、または立寄った―「訪ねた」と言いたい程にゆっくりしたということでもないながら、近くに行ってみた、眺めてみた、辺りを歩き廻った記憶が在るという感じ―という経過が在る。本書の叙述で「そうだ…あそこは…」と色々と思い出す場面も非常に多かった。
安土城が登場したような頃の、それ以前の時代には余り知られなかった「遠い国の宣教師の見聞」というような外国の建築の様子の伝承、鉄砲の類のような新しい武器を多量に用いる戦術の導入と普及を踏まえて、新しい様式の城が登場した。やがて、「徳川方と豊臣方で全国の諸勢力を巻き込む戦い?」という中で城の建設が流行り、建築の技術等が著しく発展した時期が在る。その後は「火災等で損なわれたモノを“旧に復する”」ということが専らである時代が続く。やがて幕末期に新しい発想での築城も見受けられるが、戊辰戦争関係の戦闘で、それらの城が大きな存在感を示し得たとも思い悪い面も否めない。こうした変遷が、現在に伝わる城の建物等の様子の紹介も交えて、詳しく語られているのが本書だ。読み易く面白いので、頁を繰る手が停まらずにドンドン読み進めた。
更に本書では、「火災等で損なわれたモノを“旧に復する”」ということで、防火のための工夫等が加えられる、そうした意図で改められるということが無いままに何度も「建直し」が繰り返されたらしい経過、新しい工夫が入るでもないままに創建時の形での「建直し」が為されて現在に伝わっているという経過、他所の建物の旧い建材が大胆に再利用されていると見受けられる建物等、「諸外国の事情と比べると、少し驚く」という内容も取上げられている。
本書は、訪ねてみて興味深い各地の城址の豊富な話題を供しているが、それに留まらず「近世の日本?」を広く深く思う材料を供してくれているというようにも思う。非常に興味深いと思う。
Posted by ブクログ
日本の城がヨーロッパからの影響を受けたかどうかという観点から論じた本。例えば安土城がヨーロッパの影響を受けた証拠があるかというと、そういうものはないのだが、推論としては魅力がある。
いろいろな想像を掻き立てる本である。