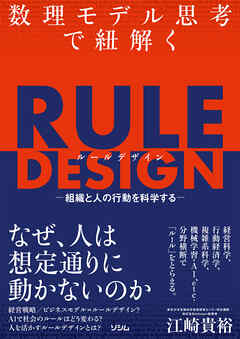あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
本書は、組織や社会の「ルールの法則性」に焦点を当て、「ルール作りの基礎教養」ともいうべき新しい概念(=ルールデザイン)を、独自の切り口(=数理モデル思考)から構築するための一冊です。
幼稚園のお迎えに遅刻した保護者に罰金を科したらどうなった?
道路の混雑状況をドライバーに知らせたら渋滞が逆に悪化した理由は?
野生のコブラを減らすため報奨金を出したら逆に増えた。なぜ?
発展途上国の小学校で教育水準を上げた意外な方法とは?
各家庭に毎月、近隣家庭の平均的な電気使用量を知らせたらどうなった?
一見すると予想不可能な "人の行動" 。
「RULE DESIGN」「数理モデル思考」という2つの視点で、そのメカニズムを解き明かします。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ゆるコンピュータラジオ繋がりで江崎先生を知り、その秀才ぶりに興味を惹かれる。そんな数理モデル分野最前線の方が著した本書は、一般向けのルールデザイン本である。
ルールが破綻するそれぞれの原因を4章に分け、豊富な実例にて平易な説明に落とし込んでくれてる。
ルールを破綻させないための著者の提言として、チェック機能の重要性を説く。具体的には「適応的制度設計」という手法。認知バイアスによって人は一度策定したルールは絶対のものであると勘違いしやすい。内的外的要因でルールは機能しなくなったり陳腐化するという事実を知っておくべきだ。
正しいデータの収集とルール策定までに至る論拠の蓋然性も見逃せない。一見関連ありそうなデータで感覚的な論拠によるルールはむしろ自己満足のみの、弊害になりかねない。
理論的な話はほぼなく、専門知識ゼロでも大変楽しく読むことができた。随所に現れる事例は、ちょっとした豆知識としてどこかで披露できるかも。
Posted by ブクログ
会社や社会をより良くするための重要なツールとしてのルールに関して、様々な事例をもとに体型的に述べられている。事例に関してはその他のビジネス書で見かけるようなものが多いが、ルールデザインという視点でよくまとまっている。
Posted by ブクログ
数理モデルに関する書籍で知っていた著者であることと、そうした数理的思考の社会への応用に関心があったため本書を手に取りました。
本書はルールを設計する際に考えるべき点や、あるいは人がルールに対してどういう行動をするかなどに関して読みやすい形式で概説した書籍です。「数理モデル『思考』で」とあるように、実際に数理モデルをもとに説明するのではなくて考え方のベースに添えるに留まっており、広い幅の読者を想定しうる本だと感じました。また、多くの部分で良く陥る失敗パターンをもとに良い考え方が導入されており、人間をそれなりに長い年数やっている方には理解しやすいと思います。
ルールの作り方に関し非常に読みやすい本ではありますが、「数理モデル」要素が若干薄いことと、設計に関する方法論があまり具体的ではない点はやや少し気になりました。
Posted by ブクログ
「人の行動」に関する様々な研究をもとにルールデザインのアンチパターンを多数教えてくれる。
解決策の章はシンプルだったが、アンチパターンをインプットしておくことで効果が最大化させることに繋がる。
人の行動に関する施策を検討する際には辞書のように活用したい本
Posted by ブクログ
読む:15分
話す:10分
書く:1分
なぜルールがうまく機能しないのか、原因は下記の4つであると示されている。
①ルール自体の欠陥
②個人
③集団
④環境
Posted by ブクログ
トピックとしては面白いし、ルールは間違いうるもの、改良していくべきもの、という視点はあらゆる人が理解しておいて損がない。数理モデルについてはあまり大きな題材でなかったように感じられた。どちらかというと心理学的な話題が多い。
Posted by ブクログ
ルールを作る側、守る側のどちらも理解しておきたい内容
何かあるたびに厳しいルールが作られても、実行されない、もともとの意図が忘れられて形骸化するなど耳が痛い内容だった
ネットフリックスの方針(あえて具体的なルールを細かく定めず、会社利益を各々が考えて行動する)といった事例も新鮮で参考になった
Posted by ブクログ
身近なところで言えば業務マニュアルとか就業規則などもルールにあたると思うが、ルールを取り巻く前提条件、技術、人、設備、etc...は変化する、ということを見越してルールをデザインしなければ、そもそも秩序を保つためのルールが逆に秩序を乱すことになるなだな、ということを再確認出来る本。
Posted by ブクログ
自社のマネージャー読書会の題材として読んだ。
まず、内容の良し悪しとは別に、この書籍は読書会の題材としてはあまり向かないな、という印象。
特に前半の章は「ふむふむ」「だよね」的な話が多く、皆でのディスカッションポイントとなりにくい感じだった。
内容としては決して悪くないのだけれど。
あと、最後まで「数理モデル思考」の成分がやや不明だった。
学びとして、最初からルールの変更を意識しておくという部分は素直に心がけたいと感じた由。
Posted by ブクログ
各組織に一冊ほしい。ルール設定は多くの場合業務ではなく「土台」みたいな位置づけになってしまうからか、見直しやフィードバックがされづらい、受け付けてもらえないような面がある。全員がこの本の前提に立つと、この本で述べられたことを依り代として全員でコミットする雰囲気も醸成できそう。
あと集合知の話は面白かった。相談しない、一人の権力者の判断に委ねないって大事なんだなと。
Posted by ブクログ
行動経済学や認知科学関連の書籍で読んだことがある事例や社会実験、実際あったことが豊富に記載されているので、そういったものを多く知りたい場合は役に立つと思う。
実際にどうすれば良いのかという点においては、やはり自分で考えルールをデザインをしないといけないので、こういった事例から学ぶことは良いことだと思う。
Posted by ブクログ
自分が知らなかった事例などが豊富に挙げられていて、サクサク読み進めることができた。どのようにルールをデザインしても、完璧に機能することはないことは様々な事例からもよくわかるようにありえない。失敗に対して対応策に動き出せるルール設定を必ずしておくことが大事であり、そのような姿勢が大事である。何事においてもそうであるが、慢心して立ち止まらないことが大事である。時代に合わせて、状況に合わせてを肝に銘じたい。
Posted by ブクログ
すぐに直接活用できるものではないが,「ルールは何故破綻するのか?」と言う疑問についてとてもよく答えてくれる一冊だった.
何より,理路整然として分かりやすい!
すぐにでも実践できそうな事も実はちらほらあって,途中から未来を想像してワクワクしてしまった.よし,がんばろう!
Posted by ブクログ
①ルールに明らかな欠陥がある
・正しいエビデンスや目的に基づいて設定する
・ルールに従う障害を取り除く
・内容や目的を誰でも理解できる
②
コブラ効果
心理的リアクタンス
やるなと言われたやりたくなる
やれと言われるとやりたくなくなる
希少性バイアス
制限されているものは希少で良いものだと感じてしまう
グッドハートの法則
指標が管理のために使われると、その指標自体が当てにならないものになること
ナッジを利用する
③
社会的ジレンマ
個人のレベルで見るとルールに従わない方がメリットが大きい人々がルールを破り、全体としての目標が達成できない状況
集合知効果
知らない人の選択は分散し、知っている人の選択が積み重なることで、正しい答えになる
売り手買い手の情報の非対称性をなくす
④時代の経過や、社会や環境の変化でルールは見直す必要がある。
リープフロッグ現象
技術の導入やインフラ整備が遅れたせいで、規制や既得権益グループがいない地域において一気に最新の技術が普及すること
⑤
緑の卵とハム
自由は逆に難しく制約があることで良くなること
考える問題に対して適度に近いトピックを与える(プライミング)と効率よくアイディアがでる
あえて突拍子もない制約が面白いアイディアになることも
ただ、環境に制約を与えると逆効果になる
サンクコスト(埋没費用)
人間はしばしば既に支払った金額を価値判断に含めて誤った決断をしがち=コンコルド効果
Posted by ブクログ
事前にルールを更新することも見越してルールを設計しておき、データに基づいて必要に応じて対策を打てるようにしておくことが、理想のルールデザインを意識していきたい。
Posted by ブクログ
世界はルールに溢れている。
憲法や法律だけでなく、ビジネスの戦略、制約条件などのルールと罰則、チーム働くうえでの決まりごと、家族内の暗黙のルール......
ルールに縛られ・助けられ、作り出しながら生きてるのでルール作りについて学ぶために読んだ。
以下学んだこと↓
・「何らかの目的を達成するために設定された、従わなければならない行動の制約を与えるもの」がルール
・ルールの4つの階層:ルールそのもの。個人。集団。環境。この全ての階層における事態を予測しないと失敗したルールになる。
・ルールが機能するための最低条件:目的が設定されている。効果のある介入方法になっている。ルールと目的達成までのロジックが成立している。ルールが持続的に運用、遵守されている。
・ルールは目的達成のための手段。ルールを守ることや作ることが目的になることはない。
・インセンティブも罰もどちらも逆効果や無視できない副次効果を生むことがある。
・ルールが目的になると数字に踊らされる。
・個人と集団は別物。personはpersonsではなくpeople.
・そもそもルールの前提や環境が外部環境の変化で変わることがある。
・ルールを遵守することにはコストが発生する。
・ルールがないことも、ありすぎることも目的達成を阻害する。
・絶対的に不変なルールは作ってはならぬ。フィードバックループが回り、ルール見直しが必ず入るようなルール設計をせよ。
Posted by ブクログ
ルール作りについて個人、組織、社会と階層分けしてデザインの指向と具体的な失敗事例を挙げている。ルール作りの失敗事例集として秀逸だと思う。
Posted by ブクログ
企業の管理部門経験が長く、小さな範囲ではあるが、ルールメーカー側であることが多いという自覚から購読。ルール設計失敗のあるあるをきちんと実験データで整理してくれており、分かりやすく、だよねーと思う点は多い。それなだけに新しい発見が少なかった印象。
Posted by ブクログ
人間の心理などによって想定していた結果とは異なったことがある。
それを減らすにはどうするか。
給付金の不正取得の変換はよいケース
ペナルティが強いと保守的になる など
Posted by ブクログ
うまくいかなかった規制やルールを集めて考察した本。
内容的には社会科学系の話が多く、たぶん、ほとんど再現性がない話だろうし考察も正しくないものが多いんじゃないかとは思うがたくさんの例を集めており、眺めるだけでも楽しかった。個人的にはコブラの話がよかった。
デザインが素晴らしく、挿絵の威力を思い知らされた一冊でもあった。流行のフラットイラストレーションですごく理解が進むような気になった。
・植民地時代のインドで、コブラによる被害を減らすためにコブラ駆除を目的としてコブラの死骸を買い取るようにしたところ、コブラを飼育して繁殖させる人が多くなった。飼育の途中で逃げ出すコブラも多く、かえってコブラが増えてしまった
Posted by ブクログ
数理最適化の本かと思いきや行動経済学の本だった
江崎さんのカラー本の切れ味とわかりやすさの同居と比べると本書はわかりやすいものの切れ味は今ひとつ