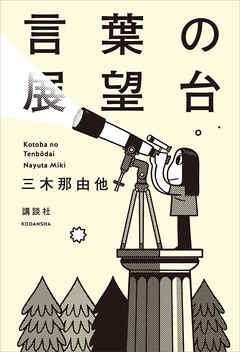あらすじ
いま、あなたとの会話で起きたことは、いったい何だろう?
マンスプレイニング、コミュニケーション的暴力、会話の引き出し、言語的なポリティクス、アイデンティティと一人称、人々をつなげる言葉、誠実な謝罪と不誠実な謝罪……。難しくて切実で面白い「言葉とコミュニケーション」を、「哲学」と「私」のあいだのリアルな言葉で綴るエッセイ。
【目次】
プロローグ コミュニケーション的暴力としての、意味の占有
そういうわけなので、呼ばなくても構いません
ちょっとした言葉に透けて見えるもの
張り紙の駆け引き、そしてマンスプレイニング
言葉の空白地帯
すだちかレモンか
哲学と私のあいだで
会話の引き出し
「私」のいない言葉
心にない言葉
大きな傘の下で会いましょう
謝罪の懐疑論
ブラックホールと扉
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
現代分析哲学・言語哲学が専門の方によるエッセイ集。トランスジェンダー当事者によるエッセイ集としても読めるし、その側面が際立つ「『私』のいない言葉」(pp94-102)は、私自身もトランスジェンダーであることもあり、いろいろな幼少期の嫌で悲しい記憶が蘇ってきながら当時抱いていたどろどろした感情の渦に巻き込まれそうになったのだが、しかし、著者は、あくまでも学者なのである。ある方の著書を読み、その本を楽しみながらも、しかし、著者自身が子どもの頃から抱き続けている謎はまだ解けない、と、上記の文章は閉じられ、私も、負の感情に落ち込み続ける危険にはいたらず、むしろ、これまでとこれからを見つめ直すいいきっかけになった。
Posted by ブクログ
エッセイから分析哲学への接続がきれいでとても読みやすい 筆者の個人的な話を交えながら、するりとコミュニケーション論について考えを巡らすことが出来てよい
Posted by ブクログ
三木那由多さんのエッセイ集。
購入してから大事に少しずつ大事に読み進めて、今日読み終わりました。
後書にもある通り書いている最中に当初は予定していなかったカムアウトのお話もあり、「実は歴史的な一冊なのではないのか!」とか勝手に興奮しながら読んでたりしてました笑
言葉に対する感性と言うか捉え方も矢張りプロ。一読しただけでは理解出来ず何度か戻って読み返したりネットで調べたり。
素の自分から出てくる様々な思い。考えながらいつの間にか哲学の話になっている。
きっと本当に好きでらっしゃるのですね。
最後に載っている文献も有り難い。
今後気になるもの…ポール・グライスさんの本とか読んでみたいと思います。
素敵な本をありがとうございます。
Posted by ブクログ
面白かった!
『会話を哲学する』では、漫画や小説から会話が引用されていて、それらの言葉は作品の読者に分からせようという意図が強く働いているから、面白い話ではあるけど自然な会話の例ではないじゃん……という違和感をもっていた。
でもこの本を読んで、三木さんは言語哲学が扱ってきた会話に潜む強さや揺らぎなさをとっくに自覚していたことを知った。なんだか安心した。というか、流石すぎる。
Posted by ブクログ
エッセイとしては難しい部分もあったが、とても興味深かった。コミュニケーションは本当に多様なもので、哲学ではカバーしきれない部分もあることがよくわかった。
そのカバーしきれない絡まった部分を、三木さんは丁寧に解きほぐして考えている。コミュニケーションにおいて、心的な関わりを占める割合は高い。なのに、コミュニケーションだけでは人の本心はわからないことが多い。少しでも考えてコミュニケーションをとっていこうと思う本だった。
また、自分もセクシャルマイノリティの当事者なので、気持ちの部分で語られる「哲学と私のあいだで」「『私』のいない言葉」はとても実感を感じながら読んだ。少しでも、(性に関することに限らず)多くのマイノリティが過ごしやすい社会になればと思う。
Posted by ブクログ
地球っこさんのレビューを見せていただき、是非読んでみたいと思った一冊。
すごい。。。
言葉、会話を分析・哲学するって。
こんな分野があるなんて、考えたこともなかった。
最初は頭をフル回転させながら、なんとか食いついていくかんじだったのが、カムアウトされたところぐらいから、すごく作者の意図することが理解出来るようになった。
そもそも一般向けに分りやすくエッセイと解説の間ぐらい というのがコンセプト。
しかし この人たちの頭の中はどうなっているのだろう。
会話を哲学するって・・・
次に読もうと思っている「会話を哲学する コミュニケーションとマニピュレーション 」は準備済み。
次も楽しみです。。
Posted by ブクログ
言語哲学に興味が湧いてくる本
コミュニケーションそのものを考えられる本
日々の何気ないコミュニケーションをする中で、コミュニケーションとはいったい何かというもの考えさせられる。コミュニケーションはただの記号の情報交換ではないということはなんとなく同意してきたが、おそらく私はそれが一体何なのかということについて理解していない。私は言語学(英語学)ついてはある程度学んできた自負はあるが、それは主にある言語の特有の表現方法に関わるものがほとんどであり、文字からどのように理解できるかがメインであった。そのため、この本で紹介されている話し手にとっての意味とは何か、聞き手にとっての意味とは何かといった、言葉として必ずしも現れないものについて深く考察しないと解決しない事象についてはさして考えてはこなかった。
身近な例から哲学の知見を援用して本質に迫っていく構成になっており、スリリングであった。ときに話の展開についていけなくなることもあるが、それもそれでおもしろいと思える本であった。
Posted by ブクログ
コミュニケーションや言語について、コンビニの貼り紙や、ヒーローアカデミアの1話など身の回りのテーマで書かれている。入りやすく、確かに言われてみればと思うことが多く、興味深く読めた。
Posted by ブクログ
コミュニケーションってなに、会話ってなに?難しすぎ~~~!無理~~~~!と日頃常々思っている。
不毛なのはわかっているけれど、自分の言葉や相手の言葉がちゃんと齟齬なく届いているか、受け取っているかって考えると、いや意思疎通そのものがかなり無理では?ハードでは?と思ってしまうんであった
「言葉の展望台」は言語やコミュニケーションを専門とする日本の哲学者でありトランスジェンダーでもある三木那由他氏のエッセイ集。『金田一37歳の事件簿』を例に出した哲学的には認められないが、そうはいってもこういうコミュニケーションが好き!というエピソードや『僕のヒーローアカデミア』に見る誠実な謝罪と不誠実な謝罪、いわゆるご不快構文にならないためにはどうすればいいのか、我々はどういう謝罪を誠実だと感じるかというエピソードなどがあり、漫画好きの三木さんらしい漫画を絡めたエピソードがあるのもおもしろかった。学問的な解釈と三木さん自身の価値観を混ぜ合わせたエッセイでコミュニケーションや言語とはどういうものかを考えるには取っ掛かりやすい本だった
言葉って会話ってコミュニケーションって何なの?と思ったことがある人のための1冊
Posted by ブクログ
言葉はいつだって新しい旅への呼びかけ。
文中の著者のこのひとことからもわかるように、人同士の会話の中で、ちょっとした1つの発言に意識を向けてみるだけで、その発言者の背後にある意図(発言者当人は無意識であることも多い)や、聞き手への期待などが、複雑に絡み合っていることがわかる。
著者の研究分野である、言語哲学では話し手の意図が聞き手に真っ直ぐ伝わると仮定することも多い。
しかし、実際のコミュニケーションにおいては、そう簡単にはいかないゆえ、面白い現象も起こる反面、時には立ち場の強い聞き手が恣意的に話し手の意図を歪め、言葉の暴力につながることもある。
著者の興味のあることに対して、日常の些細な現象にも深く分析を加えていく姿勢は、私も持っておきたいものだと思いました。
言語やコミュニケーションに限らず、そのような姿勢が、少し大げさに言えば人生の豊かさに繋がるのだと思います。
研究対象は日常生活の中に溢れている。
Posted by ブクログ
なにげない会話やコミュニケーションの中で言葉が持つ意味、その暴力性や危うさについて、言語哲学を専門とする著者があーでもないこーでもないずっとぐるぐる思考してる感じ。しかも日常のエピソードをもとに深掘りしていくからとても面白い。とくに気に入ったのはすだちかレモンかの話。ミルクボーイの『コンフレークやないか、ほなコンフレークとちゃうか』状態でとても面白かった。
Posted by ブクログ
謝罪は決して何かの終わりや決着ではない。謝って解決するのではない。むしろ、謝罪は新しい始まり。 自分が後悔しているということをはっきりと相手とのあいだの約束事とし、その約束事に身を委ねて生きることを、謝罪は告げている。
Posted by ブクログ
話し手の意図を伝えるとき、聞き手の意味へと改ざんされる。同じ言葉の地図を持っていない限り、会話は聞き手により変容する。
日常でよくあることで相手が勘違いしているのをわかっているが面白おかしくなっているので、誤解を解くことは少ない。
聞き手は会話を引き取るという責任を持つことで会話を言葉だけの意味ではなく、裏の意図も同時に受け取るのである
Posted by ブクログ
普段何気なく使用している言葉やコミュニケーションを哲学する。
これまで特に深い考えもなく会話していたつもりだった。
でも実はそこに、無意識の意図や自身の属するコミュニティが透けて見えてしまうことがある。
言葉は“その言葉以上のもの”を相手に伝えてしまう。
だからこんなにも奥深くて興味深い。
Posted by ブクログ
普段の言葉のやりとりは、単なるコミュニケーションの手段ではなく、人間関係を構築するための重要な土台。そしてそこには意識/無意識にかかわらず、さまざまな意味が込められている。その人が発した言葉から心理を推測するのは容易ではない。
Posted by ブクログ
著者の日常から、そこで起きた疑問や喜怒哀楽を言語哲学を通して"気持ち"の謎を解明していく。
哲学は難しそうと思いつつ理解のための道具(補助輪のイメージ)として使っていくエッセイ。
もう「ただの言葉」とは言えない。
「謝罪の懐疑論」が今の悩み(反省しているのかどうかわからない人を相手にする)を理解するのに役立った。
言語哲学を通して見た日常の中にある疑問、言葉は「言っただけ」ではなく発話したこと自体にも意味がある。
言霊(言うことにより願望として捉えられる)とかを連想するけれども、霊的なモノではなく哲学の視点で解説してくれて面白い。
著者の疑問、自身の気持ちについて解き明かそうとする。日々、思い出せないくらい流してしまっている疑問に対して向き合える気持ちになる。
参考となった本も読みたい、もうちょっと知りたくなる本。
Posted by ブクログ
昔、男社会の風潮がまだ残る会社で、会議中こんな話をされたことがある。
「これ専務に話通すのムズイなー。〇〇(昔うちの部署にいた女性)がプレゼンすると、専務のOK大体貰えたからな。〇〇(部署で唯一女の私)がいってみない?」
と、加わってもないプロジェクトの話をふられた。
彼らからしても勿論それは冗談で、本当にプレゼン頼まれた訳じゃなかった。
なんだけど、不愉快だったなあ。そういうことを言ってしまえる無神経さに、無神経でいることが許容されてる組織の鈍感さに、不愉快だったなあ。
その女性が専務に話を通せたのは、彼女が優秀だったからじゃないのか?"女だから"通ったと思ってるのなら、その女性にとても失礼だなと思ってムカついた。
そんなことを、この本を読みながら思い出していた。
ーーーーーーーーーーーーーーー
「セクシュアル・ハラスメント」という言葉がなく、それゆえ「その行為はセクシュアル・ハラスメントだからやめてほしい」とは語れないが、代わりに同じことを「その行為は不愉快だからやめてほしい」と語ることで伝えようとしたとしよう。このとき、「不愉快」という言葉を選んではいても、そのひとが本当に言いたいのは自身の心理に関することではなく、むしろ社会的な不正に関わる振る舞いが生じているということである。だがたとえそのひとがそうしたことを意図して発言をしていたとしても、この発言が単なる心情の表明と理解され、しかもその理解が発言のなされた場で共有され、そのひとは単に自分の心理に関する何事かを言っていたひととしてそれ以降扱われるということは、容易に起こりうる。そうした場でたとえ「単なる心情の問題ではない」と訴えたとしても、「ヒステリック」で「感情的」で「不合理」な者として片付けられるのが落ちだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーー
そういえば、そんなことを考えていたな。
この組織を変えるには、今の発言が無神経だということを皆が認識しなきゃいけない。その為には私が声をあげればいい。簡単なはずのこと。
でも、相手が無神経なだけじゃなく思慮もないのなら、声をあげたところで「フェミニスト」とか「面倒くさい女」とか思われてもっと生きにくくなるんじゃないかって思った。私は彼らのことを、どれくらいその点について感受性豊かか分からなかった。だから未だに言ってない。
ただ、言っていないから、それはその組織では未だ許容範囲のものとして許されてるんだ、と思う。
私は別の、そんな言動が許容されない、豊かな組織を知っているので、そんな井の中の蛙状態の人たちのことをどう思えばいいのか、未だ分からないでいる。
Posted by ブクログ
コミュニケーションである言葉や会話を哲学者が哲学の面から分析している書籍。哲学を用いた内容になると、言葉遊びのように思えてしまう。色々と分析、説明しているがそもそも用いられている単語もよくわからず、それを駆使して記されているので益々わからないといった感じ。