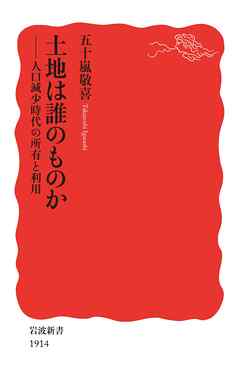あらすじ
「太平洋戦争の敗北より深刻」と司馬遼太郎が嘆いた地価高騰・バブルから一転,空き家・空き地の増大へ.生存と生活の基盤である土地はどうなるのか.近年続々と制改定された,土地基本法と相続など関連する個別法を解説するとともに,外国の土地政策も参照し,都市計画との関係や「現代総有」の考え方から解決策を探る.
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
表題の「土地は誰のものか?」という問いを今まで意識することなく暮らしてきた。「まぁ誰かのもの」くらい。本書を読み終わって街を歩いていると、街の風景の見方が変わった気がする。「土地」を意識して歩くようになった。
本書を通じて、明治時代に確立し現代にまで残る個人の「絶対的土地所有権」は、日本の歴史で見ても、海外と比較しても、主流とはいえないということがわかり、時代の要請に応じて変遷すべきものだと認識した。少子高齢化が猛スピードで進む中、東京一極集中により東京の地価は上がり続ける一方、地方の空き家空き地は増えていく現代において、筆者のいう「現代総有」は検討に値すると思う。
また、本書は「土地」にまつわる制度を、縦(歴史)にも横(他国)にも広げて説明してくれるため、大変勉強になった。
Posted by ブクログ
令和二年、30年ぶりに改正された「土地基本法」。これまで自由主義的な「不動産所有=権利」という発想のもと運用されてきた日本の土地政策が、不動産所有には権利のみならず「管理義務」が付随するとの概念構成のもとで転換点を迎える。
著者によれば、昨今の所有者不明土地や耕作放棄地などの土地に関する問題の根源は、高度成長期の「日本列島改造論」に象徴される生活・産業インフラの大規模な整備過程において、それまでの住宅・生産の基盤としての土地の性格が後退し、代わって公共事業の対象、換価可能な資産としての土地がクローズアップされたことにあるという。過度に市場原理が適用されてしまった結果、市場性の高い都市圏の土地に需要が集中する一方、そうでない土地は放置・放棄される傾向が正当化されてしまったというわけだ。東日本大震災後の土地利用について政府に提言した経験を持つ著者はこの傾向に歯止めをかけるべく、今回の基本法改正に伴い、行政のより積極的な規制、例えば建築「確認」制度に代わる「許可」制度の創設や、より実効性のある「都市計画マスタープラン」の運用などを提言する。
著者の思想の根底にあるのは、資本主義が極限まで押し進められた現在では個人的環境を包含する形でそれに強く影響を与える社会的環境の改善が強く求められており、それにはかつてみられたような、自発的にゆるやかに結合した自立したコミュニティが必要だという認識だ。そのコミュニティを制度的に確かなものにあらしめるのが「現代総有」という土地所有形態であり、そこではコミュニティ総体の公共的意思により個人の権利が制限され、「資源」としての土地活用が図られるという。
著者の構想がワークするか否かは日本でコミュニティの立ち上がりがいかに多く発生するかによるところが大きく、ややユートピア論に傾斜しているように思われる。かつての江戸時代の日本で見られたようなコミュニティは封建体制に対抗すべく自助の必要性が高い状況下で成立したのであり、そのような可視的な抑圧構造を欠いた現代において同様の共同体が再現する可能性は、個人的にはそう高くないように思えた。
Posted by ブクログ
首都圏の高層マンション群、狭小住宅、地方都市の駅近傍のマンションや建売住宅などが建て続けられ、その住人は人生の大半をかなりの額のローン返済の呪縛にとらわれることは必定だ。
著者よればマンションは巨大な廃墟(廃棄したくてもできない)と化す運命だという。直観はしていたがやはりそうか。30年先なのか40年先なのか、詳しくは語られていない。なんとも絶望的な雰囲気が漂う。
そして急速に増加しているのが空き家・空き地だ。日本の絶対的所有権に基づく日本の法のもとでは行政も手をこまねいている、というか策がない。
一方、東日本大震災では復興のための都市計画が立てられた。しかし、著者はその計画は耳障りのよいきれいな言葉で飾られているが、地域住民の声が反映されず、栄える街ではなく、無機質な風景がつくられているという。
本年2月24日にロシアがウクライナ東部に軍事侵攻をはじめた。我々日本人は自分が生まれ育った地域を破壊されている方々の嘆きが理解できるのだろうか。