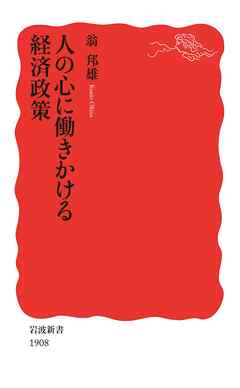あらすじ
感染抑止のために行動変容を促す国民の心への働きかけと,デフレ脱却を目的とした人々の期待への働きかけ.この二つの「働きかけ」は,背景とする人間観(と経済学)が違う.行動経済学の成果を主流派のマクロ経済学に取り入れた公共政策を,銀行取付,バブル,貿易摩擦,日銀の異次元緩和などを題材に考える.
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
メインストリームの経済学は、人間をコンピューターのように、現在、将来の利益と損失を正確に計算して行動するという仮定の基で作られているとのことです。
でも、実際はそんなことでは全然なくて、いろいろと人間らしい判断をして、間違った選択もいっぱいしています。
なので、経済政策では、そういう人間らしさを考慮した行動経済学の知見を活かすことが大切だとのことです。
物価の安定という中央銀行の第一の使命ですが、
これは2つの考え方があって、ひとつはインフレ率が2%などと一定の水準でいること、
もうひとつは昔のFRB議長のグリーンスパン氏が云う人々が物価について何も心配せずに暮らしていること、ということです。
私は、グリーンスパン氏の考え方のほうがあっていると思いました。
Posted by ブクログ
近年、行動経済学という分野がさまざまな文脈で活用されるようになったが、本来この分野が生かされるべき金融政策の文脈において成果を上げることができていない。その事についての課題観を、黒田日銀による異次元の量的・質的金融緩和の事例と共に見ていくことが本書の主な目的である。
筆者の指摘で賛同した箇所は、黒田日銀の政策に欠けていたものとして、異次元緩和によるインフレが一般の消費者にとって良い影響をもたらすというポジティブ・フレーミングの欠落を挙げていた点だ。デフレ脱却のためにも、日本国民の多くがインフレに対して抱いている忌避感を払拭するようなフレーミングを作ることが求められているように思う。
Posted by ブクログ
マクロ経済学をミクロ化=期待への働きかけ。応用ミクロ経済学となったマクロ経済学。
行動経済学の誕生と発展。
この2点がここ50年の大きな変化。
ドーンブッシュの法則=通貨危機の法則。テキーラ危機の時。通貨危機は永遠に来ないように思えるが、実際に来たら急速に進展する。正常化バイアスが続きそれが崩壊するとパニックになる。
現在バイアスの罠
現在バイアスが強いと、現在の満足を優先する度合いが強い。ダイエットが失敗する理由。
国民に現在バイアスが強いと長期的に好ましい政策が選ばれない。
サンクコストの罠=コンコルド効果。サンクコストを避けたいだけでなく、生み出した責任から逃れたいため。責任者の判断にバイアスがかかる。
人間の判断はストーリー性がある=ナラティブエコノミクス。AIにはない。AIは過去にとらわれず、最適手を選ぶ=AIはエコンと同じ。人間は流れを重視するがAIは一番の急所を突いてくる。
人間は社会規範が重要=罰金と補助金が中心ツールになる。保育園の遅刻の際の罰金は逆効果だった。社会規範と市場原理は綱引きをしている。
「ジョンブルは敗北に当たっても気高く振る舞う」プリンスオブウェールズのトーマスフィリップス提督が脱出せずに船とともに沈んだ逸話。実際は日本軍の創作=社会規範を形成した。
プロスペクト理論=価値関数は非対称。損失を重く見る。
表現の選択や選択肢の見せ方をフレーミング、この設計を選択アーキテクチャと表現した。ナッジのダークパターンも存在する。
行動経済学的な人間像
利益の喜びよりも損失の痛みを強く感じ、過去の出費が無駄になることをもったいないと感じ、判断の責任を取ることを避けるために傷口を広げる。現在の快適性を優先しがちで、ちょっとした異常は無視し、行動に当たっては社会規範という他人の目を意識する。選択肢がどう示されるかで判断は変わるため、企業や政府の意図的な誘導に従いやすい。
中国は日米貿易摩擦に学んで、対米貿易戦争で譲歩はしない。要求に従っても対米黒字は減少しなかった。
日本は自然減50万人で移民20万人、差し引き30万人の減少。定住外国人=移民のおかげで人口減少が緩和されている。外国人は日本と同化を望んでいると考えている。移民からの軋轢は少ない。現在バイアスに囚われていないか。特に外国人子女に対する教育が遅れている。
ウイルスの感染拡大とストーリーの拡大には類似性がある=ナラティブエコノミクス
自然利子率とは完全雇用が過不足なく実現できる需要を引き出す実質金利水準。
中央銀行が経済の先行きを決めるのではなく、構成員の期待が先行きを決める=期待への働きかけが必要な理由。インフレ目標の設定。しかし、一般人はそもそも金融政策に関心があるのか、という疑問。
インフレ目標を与えて中央銀行の政策の独立性を保つ、という形に収れんし、インフレが収まった。
インフレ率が目標より低い場合は金融緩和を強化、しかし金融緩和による金利の低下の本質は需要の前倒しに過ぎない。長い目で見れば中立的。補助金と同じ。成長戦略ではない。
政府の現在バイアスがインフレに結び付くことから、中央銀行に独立性を与えた。デフレが恒常化した状態では、政府の現在バイアスはインフレには現れない。中央銀行の独立性への疑問。
グリーンスパンの物価安定の定義
物価の安定は経済主体が経済的な意思決定における一般物価の予想される変化を考慮しなくなったときに得られるもの=2%などの数値ではなく、物価をきにしなくなっている状態を安定という。健康と同じ。健康について意識していないときが健康。
物価の安定について正常化バイアスが働いている国では、この定義は成立している。
物価の測定は、付加価値が計量化困難なものになり、技術革新や新製品の登場により、困難になっている。ヘドニック法、など。
消費者の個人の生計費の変動は、使い方により消費者物価指数とは異なる。若年層より高齢者のほうが上昇を感じやすい。
異次元緩和の出発点は2012年。金利誘導を長期金利まで広げる、マネタリーベースの供給量を増やす。=長期国債を購入することで両方の目的を果たす。
買いオペ=資金供給=金融緩和、売りオペ=資金吸収=金融引き締め
当座預金の付利は、資金余剰を当座預金に吸収するから売りオペと同じ。補完当座預金制度の仕組みでペナルティーが発生するから、マイナス金利で資金を貸すメリットが生まれる。現金に換えて保管することは事実上できない。
マネタリーベースの増加効果は、それ自体では効果はないが、期待に働きかける効果がある、と考えられた。
ブレイクイーブンインフレ率=物価連動国債の価格から市場の予想インフレ率を推測するもの。量的緩和のために低下した。=市場はこれ以上の手段がないことを見切った。家計も異次元緩和には興味がなかった=グリーンスパン的物価の安定状態。
正常化バイアスのために、2%程度の物価上昇では期待インフレ率は上がらない。
フレーミングとして、賃金の上昇と一体である説明が必要。しかし、実際は賃金は下落している。
2016年のマイナス金利導入は、サプライズの試みだった。市場はむしろ拒絶反応をおこした。銀行株の下落、ベア凍結、預金のマイナス金利への不安、など。
昭和の時代は、公定歩合の操作について嘘をついてもいい、という常識。近年では、サプライズは無用な市場の混乱を招く。丁寧な市場との対話がよいとされる。
物価上昇につながるフレーミングとナッジが必要だった。賃上げのアンケートを取る、など。選挙の前に選挙に行くか尋ねると、投票率が上がる。賃上げと物価上昇をセットにするフレーミング。
物価指数は真の物価動向に比べて高めになりやすいバイアスがある。
実効下限金利状態の長期化は不可能ではない。
2%のインフレ目標は、国際標準ではない。
市場が需給ギャップにあまり反応しなくなっている理由として、情報の処理能力には限界があるため、という合理的無関心の可能性がある。グリーンスパン的には物価の安定には望ましい状態。無理にそれを覆すのは本末転倒ではないか。
フェルドスタインの消費税の連続的引上げ(所得税を下げて税収的には中立にする)によってデフレを脱却する方法=現金給付と組み合わせればマイルドな物価上昇予測を持たせることができる。しかし消費税をデフレ脱却に使うことはできなかった。むしろデフレは日銀の問題としておいたほうが都合がいい。
金融政策は実効下限金利の壁があるが、財政政策ならインフレ率を挙げられるのではないか。MMTへの関心とともに中央銀行の財政ファイナンスに注目が集まっている。
シムズの物価の財政理論。債務に無関心だからこの手法による物価上昇は起きそうにない。人々の危機感を程よく煽ることはできない。正常化バイアスが崩れれば一気にパニックになる。
Posted by ブクログ
行動経済学についてなんだけど、後半は日本の金融政策。
メインストリームの経済学は主体は合理的であるという前提に基づき、予定調和的で経済変数は唯一の合理的な均衡に向かって動くとされている。その中でも起きうる予定調和的でない現象として自己実現的予言による複数均衡があり、実例としてトイレットペーパーパニック、銀行取付を挙げている。不安心理だけではなく高揚によって起こることもあり、それがバブル。その実例として17世紀オランダのチューリップバブル、18世紀イギリスの南海泡沫事件が挙げられている。
一方で人間は意外とパニックを起こしにくく、それは正常性バイアスによる。金融市場にも同バイアスは働き、メキシコ通貨危機を説明した経済学者にちなんでドーンブッシュの法則と呼ばれている。
他にも現在バイアス、サンクコストの罠、ファスト&スローの2つの認知システム、フレーミングとナッジ。
フレーミングとナッジについてはマクロ経済の実例もひいており、日米貿易摩擦時に日本を支配したフレーミングである国際協調、移民政策に対して定住外国人と呼ぶフレーミング、COVID-19に対する諸々の対策に利用されたナッジなどの話。
そして最後が著者が本業として携わってきた中央銀行についてで、期待に働きかけようとしてきた黒田日銀の政策等の話。
Posted by ブクログ
日銀黒田総裁の打ち出したバズーカ砲は、結局空砲だったに過ぎなかったと言う事。
アナウンス効果が無いと分かってからも、大規模緩和を続けその副作用に苦しむことになる。
一体何のための施策だったのか、新総裁に期待したい。
Posted by ブクログ
感染防止のための働きかけとデフレ脱却のための働きかけは、人間観、経済学が違っている。行動経済学の成果をマクロ経済学に加味した政策を行う必要があるが、国民が思うような行動を取るかはわからない。
Posted by ブクログ
終身雇用や年功序列といった日本的労働慣習はどうしたら打破できるかというところから最近、労働経済学に興味があり、タイトルが気になってジャケ買い。マクロ経済学の基礎がなっていないのか、金融政策のところはなかなかついていけなかった。。
そんな自分を肯定するようで恐縮ながら、多くの人はそんなもんなんだと思う。本書に出てくる、金融「緩和」と言われるとなんだかポジティブな気がするし、「マイナス」金利と言われたらなんか嫌だ…というのもそういうことだろう。そこに専門家の難しい理屈で経済政策を打ち出しても、そりゃ国民には刺さらず、空振りし続けているのが、いつまでも達成できないインフレ目標なんではなかろうか。
メインストリームたるマクロ経済学と、行動経済学にはまだまだ解離があるという話と理解。