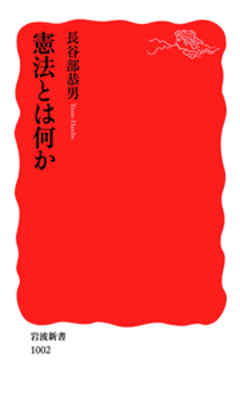あらすじ
憲法は何のためにあるのか。立憲主義とはどういう考えなのか。憲法はわれわれに明るい未来を保障するどころか、ときに人々の生活や生命をも左右する「危険」な存在になりうる。改憲論議が高まりつつある現在、憲法典に向けられた様々な幻想を戒め、その本質についての冷静な考察をうながす「憲法再入門」。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
憲法改正論議を理解する参考文献として読んだ。
憲法学者の重鎮ということで、この著者の本をとりあえず読まねばという義務感で選書。
全然期待してなかったけど、表題どおり、憲法とは何か を知るために良い教科書的な本で、読んで良かった。
「憲法とは」基本的なことを知ってから改正論議をしないとダメだとわかった。ダイジェストでこの内容を国民みんなに知らせないで改正の是非を投票させるのは、ものすごく問題があると思う。
憲法典とは原理を示すもので、そこに書いてあることは法令で定めないと実行されない。改正して書き込んだことが必ず実行されるものではない。
例:アメリカ南北戦争後、黒人の人権を認めることを憲法に書き込んだ。しかし、実際は公民権運動後に法令ができるまでしっかり実行されなかった。
また、憲法典に書いてあることは、現実に即しておかしいのであれば、実行されていないのが普通である。
例:イギリス議会はオーストラリアの憲法を無効にできる。→実際はどう考えてもできない
日本国憲法も多大なエネルギーを使って変えることのメリットは多くないだろう。憲法に書き込んでも法令を作らないと実行できない。逆に、書き込まなくても法令を作ればできることは、憲法改正してまで書き込む必要がない。
この著者をこき下ろす内容を含む本を先日読んだのだが、憲法9条を改正しなくても軍備に支障はないという点では、その著者とこの本の意見は同じということのようだ。
「解釈改憲」という用語があって、私はこれを「ズルをする」というか、ホンネと建前が違っていて歪なこと、などと思っていたが、解釈で憲法が変わるのは当然のことなのだと理解した。
○本書の内容について
・まず、憲法が絶対王制の権力に制限を加えるために作られたことなど、歴史的な話。
・現代の政治の形(民主主義・共産主義・ファシズム)は憲法の違いであり、それが国のあり方の違いである。
・現代の政治のあり方の違いを簡単に解説。大統領制の弊害など。
・憲法と法令の違い 憲法はおおまかな原理にすぎず、実行は法令による。
・執筆当時2005年における憲法改正問題について。憲法改正に多大なエネルギーを消費しなくても、必要な法令を作れば良い。憲法は解釈で変わる。解釈は社会の変化で変わる。
・裁判所は判決によって解釈の変化を定着させていくものだが、日本の最高裁は政治に対して弱腰?
前半は多分にロマンチックというか文学的な著者の嗜好が盛り込まれていて読みにくかった。さすが岩波の赤、教養本なのである。
しかし、基本的なことを押さえるには必要な本だった。
Posted by ブクログ
・近代立憲主義
立憲主義は国家の権力を制限しようとする古くからある考え方。近代立憲主義は多元的な近代を制御するために生まれた考え方で、公私を区別し、国家は私的な領域に踏み込まず、私的信条は公共に持ち込まれない体制。これは人間の自然的欲求に反する。人は自らの信じることが社会全体に行き渡って欲しいと思うものであり、また唯一の明確な正義に従っていたいと思うものだから。近代人は異なる価値観の選択に常に悩む宿命にある。近代立憲主義の前提として、異なる価値観の比較不可能性がある。価値観の比較不可能性を認める論者は、マキャヴェリ、バーリン、ロールズら。認めないのは、レオ・シュトラウス、カール・シュミット、マルクス。
・憲法改正を論じるに当たっては、その改正によって日本が国家の基盤としての思想的にどの陣営に属することになるのか、そしてそれが他国との関係にどういう影響を与えるかを熟慮すべきである。
・立憲主義的憲法は、多元主義を前提とするので、唯一の正しい生き方を国民に強制するものとはなり得ない。即ち、憲法の条文は、強制的なルールではなく誘導的なプリンシプルである。9条を文字通り読んで自衛隊の存在を全く認めないのは、憲法をルールと捉えるものであり誤りである。21条も文字通り読めば表現の制限を全く認めないように見えるが、わいせつ表現の制限は認められるではないか。
・共和制
世襲による君主制に対し,主権が複数者にある政治形態。国家元首や人民の代表者を間接・直接に選出し,主権が人民にある民主的共和制と,少数特権階級にのみ主権がある貴族的共和制・寡頭的共和制などがある。古代ギリシャでは、民主制はネガティブな言葉だったが、共和制はポジティブな言葉だった。
・プレコミットメント
憲法によって国家の権力を制限するのは権力者自身が望むことである。なぜなら権力の一部を自発的に他者に委ねた方が、自分のミスを防いだり、権力の信頼を高めたりするなど、権力の長期維持に資するからである。即ち、無制限の権力よりは制限された権力の方が強い権力である。という考え方。
・大統領制
行政の長である大統領と立法府である議会の議員の両方を選挙で選ぶ。
・議員内閣制
議会の議員のみを選挙で選び、行政の長は議会が選ぶ。
・二元的民主主義
利害調整の通常政治と、身近な利害を超えて国の基本的あり方を議論する憲法政治。憲法政治は必ずしも憲法典の改正のことではない。
・国境を決める明確な原理は存在しない。故に、現状の国境から後退した場合、踏みとどまるべきラインも決定できないので、国家は現状の国境の維持にこだわらざるを得ない。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
憲法は何のためにあるのか。
立憲主義とはどういう考えなのか。
憲法はわれわれに明るい未来を保障するどころか、ときに人々の生活や生命をも左右する「危険」な存在になりうる。
改憲論議が高まりつつある現在、憲法にまつわる様々な誤解や幻想を指摘しながら、その本質についての冷静な考察をうながす「憲法再入門」。
[ 目次 ]
第1章 立憲主義の成立
第2章 冷戦の終結とリベラル・デモクラシーの勝利
第3章 立憲主義と民主主義
第4章 新しい権力分立?
第5章 憲法典の変化と憲法の変化
第6章 憲法改正の手続
終章 国境はなぜあるのか
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]