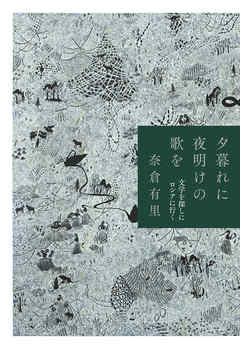あらすじ
「分断する」言葉ではなく、「つなぐ」言葉を求めて。
今、ロシアはどうなっているのか。高校卒業後、単身ロシアに渡り、日本人として初めてロシア国立ゴーリキー文学大学を卒業した筆者が、テロ・貧富・宗教により分断が進み、状況が激変していくロシアのリアルを活写する。
私は無力だった。(中略)目の前で起きていく犯罪や民族間の争いに対して、(中略)いま思い返してもなにもかもすべてに対して「なにもできなかった」という無念な思いに押しつぶされそうになる。(中略)けれども私が無力でなかった唯一の時間がある。彼らとともに歌をうたい詩を読み、小説の引用や文体模倣をして、笑ったり泣いたりしていたその瞬間──それは文学を学ぶことなしには得られなかった心の交流であり、魂の出会いだった。教科書に書かれるような大きな話題に対していかに無力でも、それぞれの瞬間に私たちをつなぐちいさな言葉はいつも文学のなかに溢れていた。(本文より)
【目次】
1 未知なる恍惚
2 バイオリン弾きの故郷
3 合言葉は「バイシュンフ!」
4 レーニン像とディスコ
5 お城の学校、言葉の魔法
6 殺人事件と神様
7 インガの大事な因果の話
8 サーカスの少年は星を掴みたい
9 見えるのに変えられない未来
10 法秩序を担えば法は犯せる
11 六十七歩の縮めかた
12 巨匠と……
13 マルガリータ
14 酔いどれ先生の文学研究入門
15 ひとときの平穏
16 豪邸のニャーニャ
17 種明かしと新たな謎
18 オーリャの探した真実
19 恋心の育ちかた
20 ギリャイおじさんのモスクワ
21 権威と抵抗と復活と……
22 愚かな心よ、高鳴るな
23 ゲルツェンの鐘が鳴る
24 文学大学恋愛事件
25 レナータか、ニーナか
26 生きよ、愛せよ
27 言葉と断絶
28 クリミアと創生主
29 灰色にもさまざまな色がある
30 大切な内緒話
関連地図
本書に登場する書籍一覧
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ロシア、という言葉の先入観から、大国らしい描写もあるのかと思いきや、等身大の感覚で読み進めることができました。肩肘はらず、またリラックスしすぎず。学生時代の話は、想像を沸き立たせる描写がとても新鮮でした。むしろ、今の社会情勢から振り返ると、周囲の人たちとのエピソードが優しくて泣けるような感覚も。私はあまり表現が得意な方ではないですが、多くの文化や人の感性に触れてその感じ方や対処を学ばれたのだな、と感じました。だから紛争中の今が悲しくなります。
素敵な人たちが描かれています。おそらくこの本を通じてしか出会えないです。他の人が描いても異なる描写になるでしょう。
Posted by ブクログ
若い頃に外国で暮らすことで出会う喜び、1人ではどうにもできない世界の複雑さとの直面、全てのかけがえのなさが痛いほど伝わりました。ニュースからは得られないロシアの姿が、やっと少しわかりました。
Posted by ブクログ
ああ、私は生まれ変わりたくて本を読んでいるんだと思った。この人生を生きることは決まっているから、せめて本を読んで、学んで、別のものに変わっていきたいんだと。そして文学はそれができる数少ないものなのだ。嬉しい。そんなものに無限に触れられるこれからの人生が嬉しい。
Posted by ブクログ
ロシア文学を勉強しにロシアに行き、文学大学に入学した日本人の学生の生活記録である。中にあるロシア文学の半分も翻訳されてはいない。ロシアの地理の棚にあったが、高等教育あるいはロシア語あるいはロシア文学の棚に置くべきものであった。黒田の日本でのロシア語の勉強についての本以上に面白く、ウクライナ情勢も書かれている。1年ちょっとで6刷も出版されているので、人気がある。あとは文庫本になるのを待つばかりである。
ロシア文学に興味がある学生、ロシア語を学習中の学生へぜひ読むことが薦められる。
Posted by ブクログ
ロシアの作家は名前や作品は知っているが、ほとんど通読したことがないことをあらためて痛感させられた。奈倉さんのロシア文学に対する膨大で愛に溢れた知識と、それを育んでくれた恩師の方々への尊敬の念が最後のページまで感じられた。
Posted by ブクログ
ロシア文学の知識があればより楽しめるかなと思いました。
もともとロシアには興味があったけど、この本を読んでからよりその気持ちが強くなりました。
奈倉さんの平和に対する強い気持ちがひしひしと伝わり、またそれが簡単には実現しないという事実に胸が痛くなります。
Posted by ブクログ
素敵な本でした。ロシア語にちょっと興味があるかなぁと考えいたこの今、この本に出会ったのは運命的かなと思いました。
ロシアは常にミステリアスで、一歩近づけたと思っても二歩遠ざかるような国。その懐に思い切り飛び込んで、著者は自ら道を切り拓いてきた、もちろんそんな自負はなく、大好きで、大好きだからこそ、諦めない気持ち、今となれば奇跡のような数々の出来事。
そして、それは過去では無く、今日を生きる私にまで繋がって、現在進行形であること。
バトンを渡された訳では無いけれど、本を通じて繋がって、私もちょっとだけ関わる事が出来た、
もうちょっと私も、私の向き合いたいものに真正面から向き合ってみようという気持ちにさせられた、素敵な本との出会いでした。
Posted by ブクログ
奈倉友里さんの紡ぐ言葉に、どうしようもなく惹かれています。好きすぎて、うまく言葉にできません。
これまで遠く感じてきたロシアのことが、本書を通して、少し身近に感じられるようになりました。
Posted by ブクログ
ロシア・ウクライナ周りの話やそこに住んでいる人々のことが窺い知れるだけではなく、文学を好きでいていいんだ、と思わせてくれる本。本当に読めてよかった。
Posted by ブクログ
物凄く好きな本。
ロシア語を学びにロシアへ赴いた20歳の女性の、文学に対する情熱、大学の先生や学生との葛藤、戦い、そしてロシアという国を前にして感じる無力感。
などが激しく伝わってきた。
文字に込められた感情が躍動していた。
P38
語学学習というと、心の底にあるドロドロした得体のしれないもの。それを掬って言葉にしていくことは、その言語で思考できるようになるための第1歩。
→自分も留学経験があるから分かる。
母語では言えるのに、、、!と何度も悔しさを噛み締めた瞬間。言いたいことがあるのに、その感情を伝えたいのに、言葉が分からないばっかりに地団駄を踏むしかなかった。
「言葉は人を繋ぐこともできるが、分断してしまうこともある。」というトルストイの詩。
「愚かな心よ、高鳴るな。」
と、希望を求め、生を愛していたにも関わらず夭逝してしまったエセーニンの詩。
各タイトルと共に記されている詩の一部分を読むのが楽しみだった。
やはり時代的に、心に響いてくるものばかりだ。
国家から制圧され、攻撃を受け、制限だらけの中で抵抗する民たち。
彼らの反骨精神が文字となり、血をまとったように響いてきた。
Posted by ブクログ
課題のために読み始めたが、美しい文章と遠いロシアの地で作者に起こった様々な出来事に魅了されてあっという間に読み終わってしまった。
特に文学大学での日々の回想録において、作者が講義や多様な文学作品に没頭する描写が印象的だった。そして、自分はこんなに文学研究にのめり込めないので羨ましくなった。
何かに夢中になることとロシア文学の素晴らしさを再認識させられると共に、混乱を極めるロシア周辺の情勢と、昨今の文学軽視の風潮に思いを馳せた。
Posted by ブクログ
珠玉。地を穿つような学びは人間の奥底に通じている。無力のようで、実は深く大きな力として。アントーノフ先生への思いは限りなく尊く、胸を打つが、これは現実なのだと思い直しすと、粛然とせざるを得ない。
Posted by ブクログ
3月に青木理「時代の叛逆者たち」で逢坂冬馬の姉だと知り、4月にネットの古本屋で見つけた「世界臨時増刊」でエカテリーナ・シュリマンのウクライナ戦争に関する講義を読んだ。奈倉有里の翻訳である。
そして本書。ロシア語、ロシア文学に興味を持ちロシアに渡って文学大学で学んだ日々を友人や教師との交流などを交えて教えてくれる。
学ぶ姿勢の深さにまず驚かされた。深いから到達点も高い。彼女がこの先もおおいに発信してくれることを願っている。楽しみな人だ。楽しみな姉弟だ。
Posted by ブクログ
最近全然聞かなくなってしまった、高橋源一郎の飛ぶラジオで紹介された作者。ゲストで出演もされていた。それを聞いて以来読みたいと思いつつ一年くらいがすぎてしまって、やっと読んだ一冊。
作者がロシアに留学し、語学学校を経て、ゴーリキー文学大学で過ごした日々を綴ったエッセイ集だ。
作者は私と同じ82年生まれ。こんなにも言語・文学を探究し、愛し、体感した作者に一種の感動を覚えた。
素晴らしい先生や友人たちとの出会いを、自身の文学的な力にすることができたのは、紛れもなく、作者のあくなき探究心と好奇心と努力だ。
作者が愛したロシア文学とそこに住むさまざまな国から来た友人や同級生たち。敬愛する先生との出会いと別れ。変わりゆくロシアと悪化していくウクライナとの関係。それらが、揺るぎない文学への信頼に基づきながら語られる。
作者が執筆したときよりも、さらに世界情勢は悪化してしまった。だからこそ、筆者が綴った言葉を胸に刻みたい。作者が通った大学のある教室に掲げられたレフ・トルストイの言葉。「言葉は意外だ。…人と人をつなぐことができれば、分断することもできるからだ。…人を分断するような言葉には注意しなさい。」それを引用して筆者は、「どうしたら人は分断する言葉ではなく、つなぐ言葉を選んでいけるのか。その判断はそれぞのいかなる文脈の中で用いられてきたのかを学ぶことなしには下すことはできない」と語っている。
文学者ほどうまく言葉を扱えないにしても、日常的に使うもの。だからこそ言葉を「つなぐもの」にするために、学び続けることが必要なのだと感じた。
ロシア文学を読んだことがないので、これを機に少しずつ触れてみたい。
Posted by ブクログ
"文字が記号のままでなく人の思考に近づくために、これまで世界中の人々がそれぞれに想像を絶するような困難をくぐり抜けて、いま文学作品と呼ばれている本の数々を生み出してきた。"
この一文がすごく沁みてくる本。
Posted by ブクログ
「同志少女よ、敵を撃て」→「文学キョーダイ!!」からたどり着いた。
ロシアの文学大学留学中をメインとした、エッセイ。当時の様々な背景を持つ人々との交流や文学への愛が大いに綴られている。
恋をする同級生や、ニーチェ本で卒倒する子。おかゆ文化、3人で教会へ行く話等もある。この大学は、日本人は奈倉先生1人。ロシア語で全てコミュニケーションを取り、ロシア語をフランス語に訳す授業もあったらしい。自分なら直ぐに帰国するので、純粋に凄いと思う。
ロシア内部の不穏な空気も描かれている。突然人が消えたり、警察が犯罪を平気で行ってたり。教授が「ロシア語よりウクライナ語より文学的で優れている」と言ったり。歴史で学ぶこととは異なり、現地の雰囲気が味わえた。
日本で行えば、即退場レベルなことが行われているが、居続けた奈倉先生は肝が据わっていると思う。
↓印象的だった言葉達
ある大教室の壁には、レフ・トルストイの言葉が掲げられていた―ー「言葉は偉大だ。なぜなら言葉は人と人をつなぐこともできれば、人と人を分断することもできるからだ。言葉は愛のためにも使え、敵意と憎しみのためにも使えるからだ。人と人を断するような言葉には注意しなさい」227ページ
「そうしてようやく、先生に出会ってからの「学び」がそれまでとどう違い、自分の身になにが起きたのかを知った。それは私にとって、少しずつ生まれ変わることだった。新しいことを知るたびに、それは単なる知識ではなく、細胞がひとつひとつ新しくなるような喜びだった。浮き輪につかまって海に入ったようなかつての心もとない学びではなく、いくらひとりでいても孤独ではない安心感があったーーだって、私はひとりではなかった。
そしてこの先もずっと、永久にひとりになることはない。いつのまにか、かつての自分といまの自分はまったくの別人というくらい、私の内面は変わっていた。私を変えた人はこれからもずっと、私を構成する最も重要な要素であり続けるだろう。」258ページ
エレーナ先生やアントーノフ先生との出会いが、奈倉先生の人生に大きく関わっていると思う。純粋に羨ましい。自分もそんな人達に出会えると良いな。
"”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
「19世紀の伝統的なロシア詩では耳で聞いてわかりやすい、二拍子なら二拍子、三拍子なら三拍子で統一されたリズムの詩が多く、なかでも一行のなかで弱強格を四回繰り返す四脚ャンプが好まれました。」129ページ
↑これを体感したいため、某動画サイトで詩を読んでいる人を探したが、見つからなかった。ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください!
Posted by ブクログ
こんなにも没頭して読書し、勉強した留学生活……。
ただただすごい。
……という視点で読んでいたのだけど、終盤、アントーノフ先生との顛末がえがかれるに至って、涙をこらえながら読むことに。
文学への、詩への情熱を媒介に、アントーノフ先生とユリの間には、たしかに愛情が流れていたように思うけれど、それはやはり文学への愛情だったんだろうな。そしてアントーノフ先生を追いつめ、アルコール依存症へと駆り立てたものは、文学者らしい鋭敏な感覚で嗅ぎ取った時代の転換だったのかもしれない。
そうか……クリミア併合は2014年だったのか。ソチ五輪という言葉が出てきてどきっとしたけれど、ウクライナ侵攻も北京五輪の直後だった。五輪というものは、悲しいかな極度に政治的な道具になりうるのだ(泣)
本書が書かれたのは2021年で、今回の本格的なウクライナ侵攻はまだ始まっていなかったけれど、そこへ至る道筋も描かれていて胸が痛くなる。
Posted by ブクログ
「文學界」の連載で好きになったロシア文学者の奈倉有里さんのエッセイ。モスクワの文学大学での留学中、ロシア文学や言葉の大切さについて真摯にそして熱中して勉強している様子がとても瑞々しく描かれています。悩むことやつらいこともあるけど、学ぶことは楽しいというのが伝わってきました。ロシア文学は今まで読んだことがなかったけど、奈倉さんのおかげで読んでみようと思えました。
Posted by ブクログ
『ことばの白地図を歩く』では著者がなぜ「ロシア語」に惹かれたのかをさらりと紹介していたが、本書は真逆。たったひとりの日本人留学生がどんな環境でどれほど熱心に学んできたか、友人達との交流や日々の生活やそんじょそこらの恋愛よりもよほど濃密な師弟関係に、最後に添えられた世界地図に、読み終えた今も経験したことのない感情で心が揺さぶられ続けている。
「文学が歩んできた道は人と人との文脈をつなぐための足跡であり、記号から思考へと続く光でもある」
世界にはその光を灯し続ける人々がいることを信じている。
Posted by ブクログ
その国で出会ったすべてがつながって。
ロシアに留学していた日々を綴ったエッセイ。渡航時の不安、出会った人々、文学大学の授業、日常と事件、そこから考えた自分、国、文学、言葉。どうして、と問う事態になっている今だからこそ、ロシアを見つめる。
途中まではふむふむと、米原万里を思い出したりしながら読んでいた。しかしアントーノフ先生の話を一通り終えて、これは壮大なラブレターだと思った。恩師への敬愛と感謝を込めた大きな意味でのラブレター。そう思ってから全体的に見て、やはりこれはラブレターだと思う。ロシアへの、文学への。
歴史には詳しくないけど帝国ロシア、ソ連、ロシア連邦と変わってきた中で、幾度ともなく変わる思想と政治と国境。変わってしまう人と、変わらないために戦う人と、どちらもがそれぞれ抱える痛み。著者が見つめるロシアの、一言では言い表せない姿。一言では伝えられないから散文となるのに、直接には表せないから詩になるのに、文字にすると現実とは異なる意味が加わり、ありのままの姿はそこにない。そんな文学の苦悩と価値。文学が語れる言葉は止めてはならない。ありのままじゃないからこそ、読む人がそれぞれ考えるからこそ、文学は時間も空間も超えて人と人を繋げる大きな力を持っている。
Posted by ブクログ
神戸のおしゃれな本屋さんで買った。背表紙やタイトルに惹きつけられた。なにか文学の特定のものを探しにいくフィクションかと思っていたが、そうではなかった。ロシアへ留学した日本人の女の人の留学日記だった。ちょっとした時間に読めるコラムのように小気味よく分けられていてた。見出しに詩や文学からの引用が2行ほどあり、その引用になぞらえて、話が展開する。
プロフィールを読むと、ぼくの一年先輩だった。
ここから書くのは、本の内容じゃなくて、この本を読んで思い出したことを書く。
大学で論理学という授業を採った。コンピュータが始まる前に人類が到達していた機械言語の本流のかけらに興味があったのだった。たしか土曜の午前中で比較的のんびりした時間だった。
50代くらいのふつうのおじさんにしか見えない教授は、当時のカセットテープが再生できる機械がビルトインされてた教卓におもむろにテープを入れ、音楽を再生した。
♪目薬さすとき無意識に口を開けてしまう
嗚呼 小市民
再生されたのは、牧歌的なフィドルの音とともに、ダミ声で関西弁の男の歌声だった。
教授、いくらなんでも間違いすぎじゃないか、恥ずかしい、論理学の授業に、嘉門達夫って。。しかもその時はもう2001年だったので、もう古い。
ずっこけそうになっていると、教授は、全くあわててない、いたって真面目なていである。
教授は言った。
「これがパラダイムシフトという。いまぼくは授業という枠組みをすり替えた。枠組みをかえてしまうことをパラダイムシフトという」
教授は最高にダサくて最高にかっこよかった。
話は、この本にもどりますが、
大学のころの、学問にもっとも近づいた気がした数年のことを記録した、とても良質な本でした。
Posted by ブクログ
淡々とした語り口とは裏腹に、そこには静かに燃える情熱を感じる。
後半のアントーノフ先生との関係は、切なくも美しく感じた。誰もが感じることの出来るものではない彼らの繋がりを、羨ましくさえ思った。
言葉を学んでいく過程の瑞々しい表現もとてもよかった。
Posted by ブクログ
なんと同士少女よ敵を撃ての著者のご姉弟。
ロシア文学部へ留学した作者の現地交流を交えて、ロシア文学を紹介してくれます。
この中から順次本を発注しております。
Posted by ブクログ
ただひたすら文学への愛と情熱を持って。
著者のロシア留学の思い出が語られている。
学生らしい友達との交流や生活のありようは微笑ましく、作者の勉強する姿に驚嘆したりしながら読んだ。
そして。最後の2章が素晴らしい。恩師への想いをことばにのせているんだけど、何とも言えない感動があった。作者の学問や文学、ことばそして、人に対する誠実さは私のような末端の本読みにも届く力があった。
Posted by ブクログ
読んでいて何となく堀江敏幸氏の本を思い出した。
なにも言えなかったのは、言うべきことがなかったからではない。ただ、どの言葉も心を表しはしなかったからだ。そして言葉が心を超えないことを証明してしまうような瞬間が人生のどこかにあるからこそ、人はどうしてその瞬間が生まれたのかを少しでも伝えるために、長い長い叙述を、本を、作り出してきたのだ。
Posted by ブクログ
翻訳家、奈倉有里さんのロシア留学中の話。
ロシア語で会話してることを忘れるくらいルームメイトや教授との会話がナチュラルで、奈倉さんが深くロシアの人と関わり合いながら生活していたのがよくわかる。
穏やかに進む物語のなかに、民族事情や社会情勢の変遷が描かれていて「へぇ、ロシアってこんな感じなのか」と好奇心をくすぐられる。
仕事でくさくさしている時に読んだのだけれど、心地よくフラットな描写に心が洗われた。
Posted by ブクログ
ロシア文学の知識がほぼ無い私には(ドストエフスキーとか有名どころの名前のみ知っている)少し難しかったけれど、普通にロシア留学エッセイとしても楽しめる部分が多く、読んで良かった。
今の情勢を目の当たりにしているからか、どこか切ない気持ちになる。