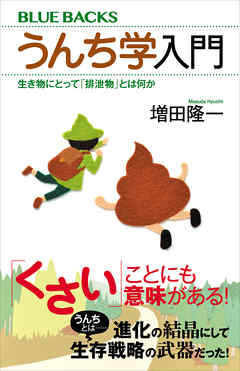あらすじ
うんちに秘められた生き物たちの「すごい生きざま」!
なぜするのか?
いつからしはじめたのか?
しない生き物はいるのか?
臭い理由は?
うんちに擬態する生物や、他人のうんちを食べる動物がいる!?
仲間やライバルの行動を支配する、うんちを使った情報戦略とは?
うんちとは……、進化の結晶にして生存戦略の武器だった!
思わず誰かに話したくる「うんちのうんちく」が満載!
〈もくじ〉
第1章 生物にとって「うんち」とは何か
第2章 個体にとっての「うんち」──なぜ「する」のか
第3章 集団にとっての「うんち」──果たして「役に立つ」のか
第4章 他の生物にとっての「うんち」──「うんち」を使った巧みな「生き残り」&「情報」戦略
第5章 環境にとっての「うんち」──地球規模で活躍する「うんち」
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
うんち君とミエルダによる「うんち学」のお話
第1章 生物にとって「うんち」とは何か
第2章 個体にとっての「うんち」──なぜ「する」のか
第3章 集団にとっての「うんち」──果たして「役に立つ」のか
第4章 他の生物にとっての「うんち」──「うんち」を使った巧みな「生き残り」&「情報」戦略
第5章 環境にとっての「うんち」──地球規模で活躍する「うんち」
序盤は生物の主に代謝についての知識
高校の生物で習う内容よりちょっと詳しい知識などもあったり
生理学、分子進化学、遺伝子分析等の視点で語られている部分は興味深い
食糞する動物は結構いる
本書でも語られているけど、親の腸内細菌を子に引き継ぐという意味もあるし
消化吸収しやすいという意味もあったりと、理由は様々
うんちの臭いの意義
同種のコミュニケーション手段になっていたり、自身の体調を反映するものだったり
胃腸免疫系の変化はうんちに反映されやすいのはそうでしょうね
ヒトが排便後に拭くようになった理由
直立二足歩行を始めたことにより肛門の位置が後ろから下になったのと
括約筋が衰えて排便の勢いがなくなったから
皇居の溜め糞の観察研究
当時の天皇陛下による論文だっけ?
確か溜め糞を長期間に渡って同一地域での例は希少というのを聞いたことがある
自然環境の調査でも溜め糞場なり、糞などのフィールドサインから種の同定やバイオマスの推測なんかもしますよね
生き物の排泄物が果たす役割と生態系での物質循環の役割
窒素でも何でもいいけど、生物にとって必要な元素の循環を見ると、よくできているなぁと感心する
自然に繰り返されるうちに安定化してった結果なんだろうけど
だからこそ種の保存は大事なんだよなと思える
「うんち」と「おしっこ」
同じ排泄物でも消化器系と循環器系の違いがある
なので、同じレベルで語られるのはちょっと違うんじゃないかとも思ったり
Posted by ブクログ
著者の言う「うんちの役割4箇条」とは,以下の通り。
1 生き物と進化の証である「うんち」
2 個体間のコミュニケーションを担う「うんち」
3 種間での情報戦略と種の存続に役立つ「うんち」
4 生態系での物質循環を担う「うんち」
いずれも,あまり説明が要らないのではないだろうか。言われてみれば,その通り。結論的には,あまり新しいものは無い。しかし,具体例を挙げながら説明して貰うと,理解が進むのも確かである。
進化の過程で生まれてきた消化管という仕組。考えてみれば,これは体の中の一部なのか,それとも体の外なのか。極端に言えば,ドーナツが長くなり,中の円形の空間がとても狭くなったと考えれば,私たちの体(ドーナツ)の外の部分とも言えなくもない。著者はこれを「内なる外部環境」という。
「内なる外部環境…。食物は外からやってきて,消化管という『内なる外部環境』を通るうちに『うんち』となり,ついには肛門から,ふたたび外部環境へ出ていくんだね。食物から消化・吸収された栄養素は,『いのち』という内部環境の形成と維持に利用され,内部環境で不要となったものは消化管から『うんち』となって放出される,そういうことなんだよね?」(本書,p.190)
現代ではすっかり忌み嫌われるうんち,なるべく見えないようにしようと近代化された人のうんち処理。でもでも,もう一度,動物がうんちをする意味を考えてみませんか,著者の呼びかけに,自分のうんちの存在の重さを感じるのである。