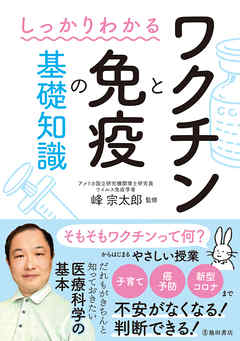あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で、切り札として登場したワクチンに注目が集まりました。しかしそのワクチンとはいったい何なのか、免疫とは何なのか、基本的な仕組みはあまり知られていません。本書は、「ウイルスとは?」「生ワクチンとは?」などテーマごと、見開きで、やさしく、しかし基礎知識はしっかり理解できるよう、イラスト図解つきで紹介するものです。また、国内で接種できるワクチンを、ロタウイルスワクチンからインフルエンザワクチンまで、主要14種類を紹介していますので、子育て中の方にも大変役立つ内容となっています。そして、新型コロナによってワクチン開発の世界はガラリと様相を変えました。そのまったく新しいワクチン「mRNAワクチン」とは何なのか、さらに開発が進む「レプリコンワクチン」とは? など、未来のワクチンについても、米国立研究機関のウイルス免疫学の第一人者である峰宗太郎氏の監修のもと紹介します。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
コロナワクチンについて、自分がまず最初に手に取った本の著者による、一般向けに書かれた本書。内容は当然、件の作品と同様で、それを分かりやすくまとめ直したという結構。ざっくり復習に。
Posted by ブクログ
ワクチン開発の歴史から基礎的な免疫の働き方、新型コロナウイルスのワクチン、ワクチンのこれからについて平易な言葉で簡潔に綴られた良書。通読向き。少なくとも専門家じゃない人はこの本を読み終えてから各論的な議論に参加すべきかと。
Posted by ブクログ
2021年10月になって急激にコロナ感染者数が減少してきて、普通の生活になりつつあります。やはりワクチンを2回接種した人が全国民の7割以上となったからでしょうか。
この本にはワクチンがなぜ作られてきたのかの歴史、今回のワクチンがなぜ短期間で開発できたのか、さらに将来のワクチンはどうなっていくのかついてまで解説されています。
今回のワクチンは治験期間が短期間で将来に身体の変化を及ぼしかねない等の情報が流れていますが、この本を読んで少し安心できた感じがしました。また、日本ではなぜワクチンが義務化できないのかについての解説もあり参考になりました。
以下は気になったポイントです。
・ウィルスや細菌を「生きた」まま摂取する生ワクチンは、その病気にかかった時のような症状が出ることがあるので、生きたままではなく「殺して」接種すれば良いという考えから生まれたのが「不活化ワクチン」、生ワクチンによる感染問題が生じないのが不活化ワクチンの良い点である。実際に感染が起こるわけではないので、免疫の反応が若干弱いという欠点があるので、免疫への刺激を強くするために「アジュバント」という補助剤が加えられている。激しい感染が起きていると体に勘違いさせるような働きをする、自然感染や生ワクチンを接種した場合に比べて、抗体価が上りにくいし、一旦上がった抗体価も容易に下がってしまうので追加接種が必要となる、インフルエンザワクチンのように(p30)
・コンポーネントワクチンは、病原体の一部だけをワクチンとして使うもの、免疫系の反応は弱いが副反応は比較的怒りにくいのが特徴である(p32)
・病気の治療薬には「副作用」が出ることがある、病気を治したり症状を抑えたりするのが主作用で、本来の目的以外の作用が副作用である。副作用と言わず「副反応」というのは、免疫をつけて感染を予防したり、重症化を防いだりするのがワクチン接種による「主反応」であり、そうした本来の目的以外の反応を「副反応」と読んでいる、ワクチンを投与した後に生じた好ましくない症状は「有害事象」と呼ぶ(p34)
・ワクチン開発の歴史は副反応克服の歴史であった、世界初の天然痘ワクチン(1976)に始まって、コレラ、炭疽菌、狂犬病、ペスト(1897)、百日咳、結核(1927)、黄熱病、発疹チフス、インフルエンザ(1945)、ポリオ、日本脳炎(1954)、麻疹、風疹(1970)、水痘(1974)、ロタウィルス(2006)である(p37)
・ワクチンの成分は、主成分(抗原)、緩衝材(PH保つ)、安定剤(抗原の損傷を防ぐ:グルタミン酸ナトリウムなど)、不活化剤(病原体を不活化:ホルマリン)、抗菌薬(不要な細菌などを防ぐ)、保存剤(長持ちさせる)である(p41)
・一度かかると二度かからない感染症があるという現象から、人類は感染症を克服するための2つの方法を考え出した、1)ワクチンによって感染症を予防する、2)感染症を治療するための血清療法である、北里柴三郎は抗体による免疫反応を発見(1890)した、破傷風菌が病気を起こすのは、感染した菌が毒素を出すためだが、その毒素を投与されても生き残った動物は、毒素に抵抗性を持つようになる、抵抗性を発揮する因子が血清中に存在することを発見した、この因子は「抗体」である。毒素を動物に投与して抗体を作らせ、動物の血液から血清を取り出し、それを患者に投与するという治療法である(p53)
・日本では1992年に種痘後脳炎の訴訟で国が敗訴、1993年には副反応の影響でMMRワクチンが接種中止となった、少なくとも800人に一人が脳炎を起こして死亡者も出てしまった、これがきっかけとなり、1994年に予防接種法が改正されて「集団接種・義務接種」から「個別接種・努力義務」へと大きく舵が切られた。こうして日本の予防接種は他国から大きな遅れをとることになった(p58)
・4種混合ワクチンは、ジフテリア(致死率:5-10%)・百日咳(10%)・破傷風(5-10%)・ポリオ(10-20%)に対応したワクチンである、生後3ヶ月から1歳までに4回接種する。(p73)
・1962-1979年生まれの男性は、風疹ワクチンの予防接種・集団接種の対象外であった、1962年までは自然感染多数であったので、接種はなかった。(p77)
・最近になって、水痘ワクチンは帯状疱疹の発症を抑えるのにも効果があることがわかってきたので、50歳以上の人も接種を受けることができる(p78)
・人に感染するコロナウィルスは6種類知られていて、今回7番目として新型コロナウィルス(SARS -CoV-2)が加わった(p105)
・今回のワクチン開発では、1)ウィルスベクターワクチン(害のないウィルスを運び屋=ベクターとして利用して、DNAを人の細胞内まで運んで、そこでタンパク質を作らせる)、2)拡酸ワクチン(DNAやRNAを直接送り込む)がある、特に早く開発できたのが、mRNAワクチン(ファイザー、モデルナ)と、ウィルスベクターワクチン(アストラゼネカ)であった(p108)
・新型コロナウィルスが認められたのは、2020年1月9日であるが、その翌日にはウィルスのゲノムが解読されて公表された、そこからワクチン開発のレースがスタートした、モデルナは2月7日には製造、同24日には第一相臨床試験を開始、ファイザーも4月22日に臨床試験を開始した(p110)
・ウィルスベクターワクチンを打った人は、運び屋に対する抗体ができてしまうので、ブースター接種はmRNAワクチンなどを接種することになりそうである(p114)
・遺伝情報を載せたmRNAは非常に不安定で壊れやすいので、そのまま投与できない、そこで脂質でカプセルのように包むことにした、こうして人の細胞まで届けられるようにした、これはアームストロング船長が月面に足跡を残したことと同じような快挙である、この開発によって将来の医薬品開発に大きな影響を及ぼすことになる(p120)
・インフルエンザのような呼吸器感染症では、ウィルスは鼻や喉の粘膜に付着することで感染し、全身をめぐる血流にはのらないまま、粘膜の細胞などで増殖してしまう。(p136)その対策として、点鼻薬で鼻の粘膜にワクチンを接種する「経鼻ワクチン」の研究が進められている(p136)
・現在の最先端のワクチン(mRNA)の先をいくのが、レプリコンワクチンである、自ら増殖するmRNAを使ったワクチンで、レプリコンワクチンの自ら増殖するmRNAが人の細胞に入ると、RNAを増やすタンパク質をまず作り、mRNAがどんどん増殖する(p138)
2021年11月23日作成
Posted by ブクログ
「新型コロナとワクチン 知らないと不都合な真実」に続き、今年2冊目の峰先生の著書。峰先生は、こびナビの先生方の1人でもあり、情報番組にも一時よく出演されていたので、ご存じの方も多いかもしれませんが、私の印象の一番は、分かりやすい言葉で明快に説明してくださる先生。そして、特徴的な高音ボイスで早口なのに、なぜか聞き取りやすい。偉い先生にこんなことを申すのもなんですが、Twitterのスペースなどを聞いていても、”おしゃべり上手”ですね。
「知らないと不都合な真実」の方も、こういった本には珍しく対談形式を取っていて、素人が分からないこと気になることに丁寧に答えていっていて、非常に読みやすく、かつ分かりやすかったのですが、
今回の著書は、更に、文字を詰め込み過ぎず、図解なども用いながら、見開き1ページに1つの内容を説明する形で、分かりやすい。タイトル通り、基礎的なことがきちんと確認できる、と言う感じ。
個人的には、前著も読んでいたし、こびナビのスペースもかなり聞いているし、厚労省のHPやこびナビのTwitter、Instagramなど、日々目を通してきたので、この1年くらいで得た知識の再確認、と言う意味合いが大きかったですが、この本で、難しいなあと思っていた情報が、より明確に分かった気がする。図解おそるべし。
これなら、中学生や小学生でも高学年なら、読めるのではないかな、と思うので、お子さんに正しい情報を伝えたいけど、ネットでは情報が氾濫しているし少し難しいし、と言う親御さんも、これを一緒に読むと良いのじゃないかな、と思った。
現在開発が進んでいるワクチンや、コロナ以外でも、未来のワクチンの展望なども少し知ることが出来て、楽しい。
インフルの経鼻ワクチンなど、出来るといいですよね。身近に、ワクチン打っているのに、毎年のようにインフルに罹る上司がいるんですよねぇ(重くはならず、それでも強制的にお休みになるので、行事のように満喫してる感があるのを、部下たちは知っている、、)
あと1つ。こういう時期に出す本として、いかにワクチンが感染症対策の切り札として大切かわかるように説明するだけではなく、過去のワクチンの副反応で、過去には事故死なども起こっていたりすることも、きちんと触れていることは誠実だなと思った。
Posted by ブクログ
ウイルス免疫学者の峰宗太郎さん監修による、ワクチンと免疫についての基礎知識がわかりやすく解説された一冊。これまでのワクチン(生ワクチン、不活化ワクチンほか)、これからのワクチン(mRNAワクチンなど)、未来のワクチン(レプリコンワクチンなど)の3世代分けて、ワクチンの詳細が語られる。がんに効くワクチンの開発経過など、あまり知らない事も多く面白かった。コロナワクチンで、初めて使用されれることとなった遺伝子ワクチンが他の病気を予防するためのワクチンとして使われる可能性があるというのも興味深い。