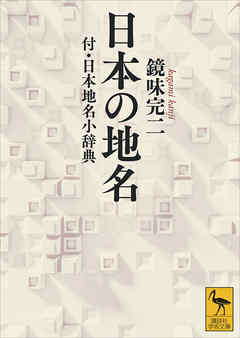あらすじ
地名には歴史的・文化的に貴重な価値が含まれています。日本の地名はバリエーションも多く、その起源についてもさまざまなものがあります。
地名の成り立ちや命名の仕方について研究する地名学は、柳田國男も取り組んでいた。もともとは地理学との関係が深いが、歴史学、民俗学、言語学などのアプローチが必要でもある。
いくつか具体的にみてみましょう。
大和語(ツル=水流=津留など)・アイヌ語(ホロ=大=美幌など)・朝鮮語(フル=火・村=布留など)・マライ語(アゴ=真珠の首飾り=英虞など)などを起源とするケース、もともとの地名が方言によって違っているケース(タロウ=太郎・田老=巨大または小平地など)、時代の流行によっているケース(開墾が盛んだった時代は、「田代」「新開」「新田」など)がなどです。
また、地名は発生した後に、その伝播のしかたにも特徴があります。もともとの地名が伝わっていくときに、扇状に伝わるということがあります(親不知付近では混在している「しとる」「してる」が、南では扇状にその範囲が広がる)。また、「空洞」と呼ばれる「地名のない部分」が発生したりします(たとえば中国・四国地方では、山の呼び名に「岳」を使用しないことが多い)。
地名を研究することで、隠された歴史の痕跡を読み取ることが可能なのです。
「文化化石」としての地名を研究する学問として、「地名学」を提唱した著者が、その集大成として刊行されたのが、本書です。
また、本書巻末には約1000項目の「日本地名小辞典」が付いております。
身近な地名の謎に迫るためにも好著ですし、歴史学・民俗学の補助としても役に立つ一冊です。
【原本】
『日本の地名 付・日本地名小辞典』(角川新書 1964年刊)
【目次】
はじめに
第一章 地名学とはどんな学問か
第二章 どうして研究したらよいか
第三章 むずしい地名の意味をどうして解くか
1 富士山のフジの意味
2 「名古屋」の意味
3 「船越」の意味
第四章 地名にはどんなタイプがあるか
1 語根型
2 民族型
3 時代型
第五章 地名はどんな形で分布するか
1 波紋形の分布
2 相似関係の分布
3 現状に境界線が集まる現象
4 「空洞」といわれる「地名のない部分」の現象
5 伝播する地名
6 双子地名
第六章 地名の発生年代は決められるか
第七章 地名の正しい書き方
第八章 郷土の地名の調べ方
第九章 地名研究の参考書
おわりに
付録 日本地名小辞典
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
地名への関心が民俗学系の専門家の間で高まってきた頃に皆が独自の論法に基づき行っていた調査や考察のしかたに問題があると気づき、科学的な地名の由来の解明を提唱した本。
自分の知っていることや自分の専門ばかりを見つめてそこから解決の糸口を導き出そうとするのでなく、もっと弘く物事を捉え検証を多層的に且つ深くすることで本当の由来を解明しようとする著者の意気込みの溢れる内容。
地名学を始めようと考える人向けに種々の助言や参照すべき文献を挙げるなど可也実践的なことが書かれている。
ただ惜しむらくは自分の専門でないことを参照するとやはりどうしても説得力をかいてしまうのか読んでいてウーンと思うところも少なくない。勿論そこにはこの書籍の出版された時代からまた可也時が経っているということもある。しかし検証の為に参照した情報がおかしなところもいくつか実際にある。
例えば、「九江」と「珠江」は共に北京語ではチューチャンで同音となる、という発言。北京語をカタカナ読みしたらという言い方ならまだわかるが、それにしたって九はjiu、珠はzhu、カタカナ読みならジウとズー、母音が二つと一つでは全然違う。しかもjiuについては本来はjiouなのでジォウ、つまり母音が三つ。これをジューと書いてしまうのは些か乱暴にすぎる。
著者はそれでも同時代に於いては恐らく慎重な方だったのだろうと思うし、地名を研究するには実際、自分の専門外のことでも避けて通る事ができない。そうなるとどうしても不確かな方言学の知識で地名を紐解かざるを得ず、怪しいところが増える。
これは言い換えれば地名学がそれだけ博い学問を必要とするということであり、垣根を踰えた学術交流が必要という事だと思う。
日本語古語や日本語方言だけならまだしも、中国語や朝鮮語からの影響も実際受けているのが日本の歴史なのでそこも避けられず、果てはマレー語も国や民族の形成に少なからぬ割合を占めているというから、マレー語の専門家による解明も必要となる。
大野晋がその方面に日本語古語の解明の糸口を求めて生前に熱心に取り組んだが、影響は限定的と思われているのか、マレー語など南アジアと結びつける話はあまり今でも頻繁には聞かない気がする。
本自体は薄いしある程度古語や方言に興味があって自学したことのある人には読みやすいと思うが、なんの下地もなしにいきなり地名学面白そうと思う人にはチンプンカンプンなところも多いと思う。そういう人は大野晋が岩波から出した新書(緑と黄)読めば大体わかる。絶版のため、在庫があればの話だが……
ところで附録の小辞典を読んでいて思うのは「湿地」と訳される地名の語幹の多いこと。湿地にどうしてそこまで沢山の言い方があるのかむしろそこが気になってくる。
地名学には興味あれど自分で研究するほどまでは手が出ないという向きには、この本にも挙がっていた柳田國男『地名の研究』(講談社学術文庫による再出版)の外に日本地名研究所『民俗地名語彙事典』というのが ちくま学芸文庫から出ている(これも三一書房が出版したものの再出版)。