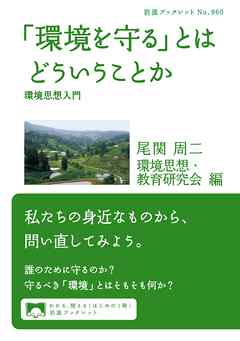あらすじ
環境問題に取り組むための学問として1980年代以降、環境学は発展し様々な分野に細分化されていった。こうしたなかで、そもそも「環境を守るとは?」という根本をまず考えるために、自動車、カブトムシ、イルカ、原発!?といった「身近な話題から哲学する」視点で、若手研究者がわかりやすく読み解く環境思想の入門書。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
60頁ほどのブックレットに尾関周二、上柿崇英、熊坂元大、関陽子、大倉茂、澤佳成、布施元ら7人の論者の論説があり、薄手の論文集といった趣になっている。
内容としては、明示はしていないもののディープ・エコロジーの自然中心主義(エコ・セントリック)的環境思想を批判し、人間中心主義的な方向から環境を考えるための論考で共通している印象を受けた。
“ しかし筆者は、本章で見てきたように、「環境」を考え上で重要なことは、まずもって「人間にとっての環境」の特性について理解すること、そして「自然環境」、「社会環境」、「人間」という三つの要素の関係性と、その歴史的な変遷過程を視野に、私たちが「環境危機」と呼んでいる事態の本質がどこにあるのかを見極めていくことであると考える。”
(上柿崇英「第1章「環境」とは何か――「自然環境」「社会環境」「人間」の関係性」、13頁より引用)
“したがって、環境を総体として捉えようとすれば、自然環境と社会環境にともに関係する人間の視点が鍵となる。環境を考えるうえで人間を考えることは避けられない。環境思想は“環境についての思想”でありながら“人間についての思想”でもある、ということである。”
(布施元「第6章私たちの「環境」について改めて考えてみる――持続可能な発展の視座をきっかけにして」、本書58頁より引用)
といった具合である。ただ、本書には、名指しこそされてはいないものの、批判の対象として考えられているのであろうディープ・エコロジーの開祖アルネ・ネスの名も、また、本書の執筆陣の発想と極めて近いソーシャル・エコロジーの開祖たる社会的アナキスト、マレイ・ブクチンの名も出てこない。他方で、6頁と52頁にはウォーラーステインの世界システム分析の話題が挙げられている。個人的には大倉茂氏の論説からエコ・マルクス主義的な発想を感じたので、岩波は環境思想ではマルクス主義で行こうという心づもりなのかもしれないと感じた。
それぞれの論説が短いので、体系的に何かを理解するには不十分だが、各論説の文献案内をブックガイド的に使うのならば役に立ちそうだとは感じた。