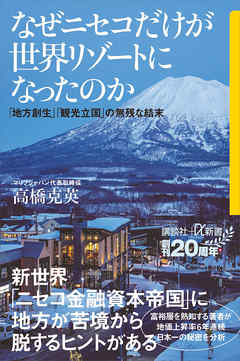あらすじ
地価上昇率6年連続日本一の秘密は何か。
新世界「ニセコ金融資本帝国」に観光消滅の苦境から脱するヒントがある。
富裕層を熟知する著者の知見「ヒトより、カネの動きを見よ!」
ローコスト団体旅行によるインバウンドの隆盛はただの幻想だった。かわりにお金を生むのは、国内に世界屈指のリゾートを作ることだ。平等主義に身も心もとらわれた日本人は、世界のおカネのがどこに向かっているのか、その現実にそろそろ目覚めるべきではないだろうか。
ニセコ歴20年、金融コンサルタントとして富裕層ビジネスを熟知した著者による、新しい地方創生・観光論。バブル崩壊以降、本当にリスクを取ったのは誰だったのか?
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
富裕層向けに資産運用アドバイザーをしている著者が、ニセコについて書いた本。ニセコの開発について歴史的に紐解きつつ現在に至る経緯を説明している。著者は、マーケッティングやポジショニングの知識も豊富で、トレードオフの重要性についても意見を述べている。その知識・経験から、ニセコは今までどおり外国人富裕層にターゲットを絞ったアプローチをすべきと主張している。著者の主張は、説得力があり同意できる。ニセコに特化した研究ではあるが、谷頭和希著『ニセコ化するニッポン』よりもはるかに考察は深く、勉強になった。
「ニセコには「外国人による外国人のための楽園」ができている。5つ星ホテルのパークハイアットは、日本には東京、京都、ニセコにしかない。他の5つ星ホテルではリッツ・カールトンが開業し、アマンの建設も進行中だ」p3
「ニセコは、他の国内リゾートとは違い、「海外観光客」ではなく、「海外富裕層の投資家」を強く惹きつけてきたため、コロナ禍でインバウンド需要がゼロになっても、活気を失っていないのだ」p5
「2020年路線価によると、全国32万地点の標準宅地における上昇率で6年連続全国1位となったのがニセコだ」p15
「当地コンビニであるセイコーマートのニセコひらふ店は、富裕層を中心とした外国人観光客を意識した店舗となっており、国際クレジットカード対応可能な銀行ATMに外貨両替機、TimTimなど豪州で人気のスナック菓子やイギリスパンなど食品類、そして種類豊富なワイン類が並んでいる。3万円近いドンペリニヨンなど高級シャンパンも棚に鎮座している。ここはコンビニなのにだ」p24
「中国のスキー場の多くはニセコのようなパウダースノーではなく、アイスバーンだらけの硬い雪質であったり、人工雪であったりする場合も多い。このため、パウダースノーを誇るニセコをはじめ日本国内のスキー場は、アジアの中では特に競争力があり、ニセコの知名度は中国を含めたアジア全体でも非常に高い」p32
「(東急不動産)2004年、東急不動産は、自ら開発してきたニセコ花園スキー場を、ニセコの魅力に魅了されたオーストラリア人を主とする投資家グループが出資して設立した「日本ハーモニー・リゾート」に売却した。東急不動産グループでは、手塩にかけて育てた花園地区を売却することで、ひらふ地区に経営資源を集中させたということができよう。いずれにせよ、ニセコグラン・ヒラフスキー場などは東急不動産が運営することとなり、一方で、花園は手放すこととなった」p47
「(西武グループ)グループ再編の一環として、不採算部門の売却が実施され、ニセコもその対象とされることになった」p54
「花園やグラン・ヒラフにおける東急不動産グループ、ニセコビレッジにおける西武グループだけでなく、日本航空グループもバブル崩壊とデフレ不況の中で業績不振に陥り、経営再建の一環としてホテルやスキー場、ゴルフ場を売却し、ニセコから撤退していたことになる。そして現在は、それら日本企業に代わって、シンガポールや香港、マレーシアなど、興隆するアジアの大企業が、ニセコを牽引しているのだ」p59
「バブル期に東急グループや西武グループなど日本企業によって作られたニセコの礎は、バブル崩壊後、豪州や米国資本の手を経て、今は香港、シンガポール、マレーシアなどアジアの財閥グループなどによって、更なる大規模開発が続くに至っている」p80
「ニセコエリアのコンドミニアムのオーナー比率は、香港の36%を筆頭に、シンガポール16%、マレーシア10%、中国9%、タイ8%、台湾5%とアジア勢が上位を独占している」p111
「2019年の住宅価格は、クーシュベル1850がトップ、アスペンが2位、ベイルが6位、サンモリッツが7位となっている。ニセコは、日本ではトップながら、世界では31位であり、トップのクーシュベルの半額以下の価格帯となっている」p114
「ニセコが狙うのは、今まで通りこうした世界水準のスキーリゾートを自国に持たない、豪州、アジアの顧客、そして日本国内の富裕層だ。そういう意味では、各々が上客や特徴を持ちながら、ベイル、クーシュベル、ニセコは、うまくグローバルに棲み分けができているのかもしれない」p117
「外国人富裕層向け高級コンドミニアムや飲食店などの場合、年間収益の8割前後をスキーシーズンに稼ぎ出しているという。スキーシーズンだけの営業で1年分稼げるリゾートであるべきではないのか」p127
「スキーリゾートなのに、夏も稼がないとやっていけないというのでは、この先も未来はないのではないか。ニセコは基本的には今まで通り、冬だけで稼ぐビジネスモデルを追求すべきだ」p128
「間違っても、幕の内弁当型のマーケッティングをしないことだ。中間所得層などあらゆる年代世代所得ステージの人々が訪れるのが理想ではある。しかし、それは富裕層の離反を招く施策だ。彼らは混雑を嫌い、誰でも行けるリゾートを好まない」p129
「海外富裕層は、多くのものをすでに手に入れており、モノよりも時間により価値を置く場合も多い。観光や旅行においても、何もしない贅沢、何もしない時間を求めている場合が多いという。そもそも滞在するホテルからあちこち出歩いたりはしない」p130
「ニセコは富裕層以外には敷居が高い観光地になってしまったかもしれない。しかし、それでいい。すべての顧客層が満足するスキーリゾートになるキャパシティーは、ニセコにはないのだ。「選択と集中」「売上より利益」というビジネス観点からも、今までの高級化路線を継続するのが得策だ。誰でも行けるニセコにするのか、特別な日に行くニセコなのか。前者になれば富裕層は逃げ、次のニセコを見つけようとするだろう」p131
「官主導、地元自治体主導の観光策やリゾート計画だと、卓上のこうあるべき論や、調査やアンケートやイメージなどから始まり、デメリットやリスクも考え、結局、総花的で「幕の内弁当」のような施策となり、肝心の需要が置き去りにされて、失敗するケースがほとんどだ」p167
「ターゲットとする顧客も、全方位的ではなく、富裕層、中間所得層、マスリテール、日本人、外国人のどこをメインにするのか。キラーコンテンツとターゲット顧客を定めるだけで満足してはいけない。本当に儲かるのか、ということが最も重要だ」p175
Posted by ブクログ
世界中から何故ニセコに集中的に投資が行われるのかを、その背景と共に分析した書籍。
2020年に書き上げている書籍のため、若干データにブランクはあるが、オリンピック中止や北海道新幹線延期を加味しても、ニセコに対する投資は決して衰えていない。それはニセコに対する投資が一時的なものでないことを示す証だろう。
それがサブタイトルの、「地方創生 観光立国の無残な結末」に集約されている。日本の投資と世界の投資、考え方の違いかもしれない。キラーコンテンツであるパウダースノーをベースに、逐次投資ではなく大規模投資を、短期スパンでなく長期スパンで行うことで、世界の富裕層・超富裕層を呼び込み、その客層が更なる投資を呼び込む好循環を生んでいる。それだけの大型投資は、日本企業では難しいのだろう。
倶知安町とニセコ町に分かれる行政の弊害や、温暖化によるリスク等はあるものの、まだしばらくこの状況は続きそうだ。出来ればこの投資効果をニセコだけに留まらせず、札幌や道東、知床など、北海道全体に波及させるプランを練るコーディネーターが欲しい。勿体ないし、そのポテンシャルを北海道は持ってると思う。
Posted by ブクログ
1.そういえばいつのまにかよく聞く名前「ニセコ」
なんで人気になったのだろう思ったので読みました。
2.富裕層に圧倒的な人気を誇っているニセコはなぜここまで人気になったのか、それは「選択と集中」を実践しているからです。日本人大好きな幕の内弁当作戦とは縁を切り、地域の資源はなんなのか?どうすれば収益に結びつくのか、だれに投資してもらいたいかを考えた結果、このような実績を残しています。このニセコがどのように発展していったのかその様子が書かれています。
3.外国の資本についてあまり良い印象を持っていませんが、日本人の金融リテラシーならば仕方ないことなのだと思います。「お金と結びつく行為」に集中することができず、前例主義を続けてしまう日本の悪い風潮で育った人たちはニセコの状況をきっと「外国に売りやがって」と怒ります。しかし、それは負け犬の遠吠えにすぎないと感じました。
ニセコはしっかり戦略を練った上で外資を呼び込んでいます。本書でも、自然環境への関心は外国人の方が高いとも述べています。
この本が出たのが2020年12月21日なので、まだまだ日本人の土地は海外勢に取られてしまうと思います。
Posted by ブクログ
庶民には無縁とも言えるニセコの、「今」と「これまで」を学ぶにはとても良い本でした。日本企業はバブルで一度敗北し、ニセコは外資の割合が多くなった。日本企業は観光業で盛り返せるのか。「幕の内弁当」的な展開ではなく、「選択と集中」が必要だというのは心の底から同意である。一方で、しかし世界の富裕層を集めるには、ワールドクラスのホテルやブランド店が必要というのもなるほどと。ハイクラスの観光業について、色々と考えさせられました。
Posted by ブクログ
ニセコが世界でも有数のスキー場であり、富裕層が流れ着くのかを解説。パウダースノーと言う自然のギフトを武器に、世界から有数のリゾートホテルが集まる。
すべての人に特化した幕の内弁当の様なやり方は日本でも通用しなくなる。中間層が消滅し、人口が減る日本では、全てに一律のやり方でなく差別化を図らないといけないのは、時代の流れとして仕方ないですね。
何よりもお金はある所こらしか取れない訳ですし。
小説の「海が見える家」の富裕層のお客さんの言葉を思い出しました。
Posted by ブクログ
オーディブルにて。
3年ほど前にニセコへ訪問した際、ホテルやレストランでまず英語で話しかけられる、なんならホテルマンも外国人で日本語がすんなり通じないところもあり驚いた。ここは日本の中にある海外だ…と感じ、まさにタイトルのとおりなぜニセコだけ?という疑問が生まれた。
パウダースノーという地の利を最大限に活かし、豪州やアジア、国内の富裕層に絞ったターゲティングが成功しているという説に納得した。幕の内弁当的にターゲットを広げないことが功を奏したとのこと。マーケティングの参考になった。
Posted by ブクログ
パウダースノー以外に、アジアには高級スキーリゾートがそもそも日本にしかないという地政学的な強みがあるということが分かってよかった。また、ベイルやクーシュベルという海外のスキーリゾートの存在も初めて知ったので調べてみたい。
Posted by ブクログ
先日読んだ本(観光系)では、同じニセコについて注目した際に、四季折々値段も様々で様々な種類の外国人観光客に対するターゲティングがうまくいっていると説明があった。
一方で本書では、一つの集中するべきコンテンツを選択、判断し、幕の内弁当のようにならないように一つのコンテンツを極めることが重要だと述べられていた。
共通していた部分は、ニセコは超富裕層をしっかりをターゲティングできているという点だ
さらに観光系の本を読んでいると、経済的な面から観光を捉え、観光を娯楽など楽しいものと考えるよりかは、経済を支える利益を生み出すものと考えていると感じた。