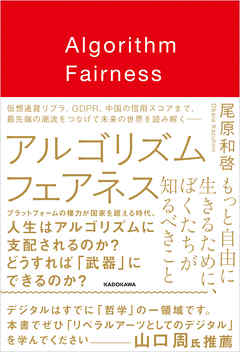あらすじ
「デジタルはすでに『哲学』の一領域です。本書でぜひ『リベラルアーツ』としてのデジタルを学んでください」
山口 周氏推薦!
本書は、「ぼくたちがもっと自由に生きるにはどうすべきか」を考え抜くために書かれました。
かつて自由とは、所属する国家との関係性によって得られるものでした。
しかし、GAFAの権力が社会保障からベーシックインカムまでを担うかという、前代未聞の時代が来ようとしています。
そこでぼくたちの人生は、アルゴリズムに支配されるのか? それをもっと自由に生きるための「武器」にできるのか?
人類が直面するこの難問の答えは、「アルゴリズム フェアネス」という言葉のなかにあります。
本書で尾原氏は、AIがもたらす圧倒的に自由な世界を描きつつ、仮想通貨リブラ、GDPR、信用スコアなど最先端の潮流、そして「分散」に向かうインターネットの本質も踏まえ、そこでぼくたちの自由を増やすにはどうするか? そのために何ができるか? ということを、「アルゴリズム フェアネス」という言葉を補助線に読み解いていきます。
iモード、リクルート、楽天執行役員として日本のブラットフォームを、グーグルで世界のアルゴリズムを知り尽くした人間だからこそ書けた、渾身の一作。
断片的な情報と情報とがつながり、読後には目の前の世界がまったく違って見えてくる、まさに「『リベラルアーツ』としてのデジタル」の誕生です。
【目次】
序章 「アルゴリズム フェアネス」とは何か
第1章 AIが生み出すワクワクする新世界
第2章 国家を超えるプラットフォームの権力
第3章 「国というアルゴリズム」が選べる時代
第4章 ブロックチェーンと究極のフェアネス
第5章 自由を増やす「ハンマー」を手にしよう
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
「アルゴリズム」
は優越を決めるもの
「フェアネス」
は公平・公正ということ
今は無意識にいろいろなものに誘導されます。
YouTubeの動画然りGoogleの検索然り。
そこに恣意的なフェイクが差し込まれたら…
アルゴリズムにフェアネスが欠かせないと言うことはよくわかると思います。
「信用スコア」
日本人は点数をつけて差別すると言う感覚になるかもしれません。
ただこれまでもありましたよね。
ブラックリストとか。
それをもう少し全体に広げてもう少し公平にした感じやと思います。
僕はフェアなスコア方法で評価してもらえるならその方が良いと考えます。
「自分の能力を最大限に発揮すること」
「主観的ながら世の中の役に立つこと」
能力のある人は生活に困らない収入を得ることができます。
マズローではないですが生命の安全安心と言った物質的欲求が満たされると精神的欲求に進みます。
自己実現したい、社会に認められたいという欲求に繋がると社会を良くしたいという良いサイクルが回ります。
これがノブレスオブリージュに繋がるんですね。
「ネットワーク外部経済性」
僕はよくデファクトスタンダードになってるという言葉をよく使うんですが「みんなが使うから当たり前になる」ってほんまに強いですよね。
特にコミュニケーションツールで言うとLINEは日本では最強やと思います。
家族間の連絡はほとんどLINEですもんね。
「オープンソース」
知識・情報は交換されるたびに新しい価値を生み出しどれだけ速く行なうか、回数をどれだけ増やすかによって、より高度に発展する可能性が高くなります。
それが可能になるのがLinuxのようなオープンソースとのことです。
集合知が概ね正しいのと近いかもしれません。
「一隅を照らす、これ則ち国宝なり」とは、比叡山を開いた伝教大師・最澄の言葉。
「一隅」とは、自分のいる場所を指します。
まずは自分が輝いて周りを照らす。
フェアネスを追求すると言うことはそう言うことなのかもしれません。
Posted by ブクログ
本を読むまで、恥ずかしながらこのタイトルの意味がピンと来ませんでした。サブタイトルは「もっと自由に生きるために、僕たちが知るべきこと」です。
AIの発展には三段階あって、分析(Analysis)、予測(Prediction)、処方(Prescription)という段階がある。渋滞しているという道路状況の分析から始まって、渋滞しそうだという予測ができるようになる。そして、その予測をベースに信号を制御すれば、渋滞を緩和することができる。そんなイメージだ。ただ、渋滞の緩和させ方がアルゴリズムであるなら、そこに恣意性を持たせることで、ある人にとって利益を、逆にある人にとっては不利益を被らせることも可能になる。例えば、Googleの検索結果で恣意的に上位に出すものと、絶対に出さないものがあるとしたら・・・それがアルゴリズムフェアネス。
では、フェアネスっていったい何なのだろうか?というのが改めての問い。立場によって、あるいはケースによって、人々が感じるフェアネスは変わってくる。従来はそれを国家が決めていたわけだけど、AIが進展するにしたがって、実は国家に代わるGAFAなどのプラットフォーマーがこれを決めている側面もある。あるいはむしろそういう側面が大きくなってきている。例えば有名な中国の芝麻信用は信用スコアが高いことで色々な優遇が受けられる。もし、知らぬところで(不可解なアルゴリズムで)信用スコアが悪くなったら、本人の努力ではどうしようも無くなってしまうかもしれない。便利に使えば便利なものだけど、恣意的に運用されると何とも言えない怖さがある。しかも、相手は一企業。どこまで企業のフェアネスを信じて良いのか?もちろん、プラットフォーマーは自ら厳しく自分たちのフェアネスをチェックしているが、アルゴリズムによって、思わぬことが起こっているのも事実。例えば、AirBandBの出現によってパリはホームレスと犯罪が増えたといわれている。パリでは需要が多いため、住宅として貸すよりもエアビーに出した方が儲かる現実から、パリの家賃相場は3割増、とりわけ移民が多く住むようなエリアでは家賃が2倍になりホームレスが増えた。そして、犯罪率も上がった。エアビーは何かを意図してマッチングをしているわけではないけど、結果としてパリのホームレスと犯罪率が増えた。誰にとっての何がフェアネスなのか。
結局、我々にできることは、こうしたプラットフォーマーの現実を知り、アンフェアであると思えばそれを指摘し、改善されないようなら、別のプラットフォーマーに依存する。プラットフォーマーの独占も監視し、常にオルタナティブを用意しておくこと。プラットフォーマーを選択できる環境を用意しておくことなのではないかというのが、この本のメッセージだったのではないかと思いました。
Posted by ブクログ
グローバルIT企業によって与えられる自由と、そのアルゴリズムによって与えられる機会によって作られた世界は、本当に全員にとって平等な世界なのかを考えさせられる本だった。事例が豊富で、個人的には第3章の中国、ヨーロッパ、アメリカ、そして最先端のIT立国 エストニアの対比が面白く、わかりやすかった。
・どこまで行っても「100%フェアネス」にはならない。フェアネスを求めるために、①プラットフォームによって奪われようとしている国家権力を国家によって規制・監視を行うこと。②ブロックチェーンを活用したフェアネスをめざすこと。③ユーザーが監視を続けること。アンフェアだと思えば声を上げること。
・人口オーナス期には、できるだけムダを減らし、生産した資産の回転数を上げ、遊休資産をゼロにしていくことが、国家としての重要な政策課題となる。シェリング・エコノミーへブロックチェーンの活用(遊休資産とそれを使いたい人のマッチングに有効)が期待される。
Posted by ブクログ
尾原さんへのインタビューや投稿を「ユーザーの自由の選択の幅」と「データ管理者に求められるフェアネス」にフォーカスさせたエッセイ的な一冊。広大かつ深遠なテーマだが、正直、浅い所をピョンピョン跳ねてる感否めない。編集者とライターに拍手を送りたいです。よくまとめたなぁと。
★★★★☆の高得点にしたのは、尾原さんの新たな視座として今後に期待してるから。「ITビジネスの原理」も同じ印象を受けた。広いが浅い。でもその後「The Platform」「アフターデジタル」「ディープテック(未読)」「ネットビジネス進化論」と視座として深められている。この本も「モチベーション革命」「どこでも誰とでも働ける」を経て行き着いた着想と思われる。「アルゴリズムを軸とした個人の自由と管理者のフェアネス」という視点もライフワークにして書き続けてもらいたいなぁと期待している。
自由やフェアネス(公平性、平等、道徳、善悪、人権など)に関する哲学用語のwiki的解説と実例をサクッとつなげる浅さから一歩踏み込んで、アフターデジタルやディープテックのようにひとつひとつについて読んでみたい。