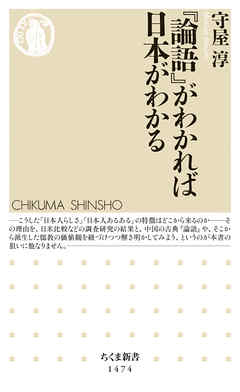あらすじ
理不尽な上下関係や努力信仰が幅をきかせ、抑圧的な組織の論理がまかり通る日本社会――。われわれの多くに刷り込まれたこのような常識や行動様式はどこから来るのでしょうか。江戸時代以降、中国の古典『論語』は、日本人の無意識の価値観のもととなってきました。本書では、『論語』や儒教のものの考え方を丁寧によみとき、さまざまな国際比較研究の知見と照らし合わせることで、わたしたち自身を無自覚のうちに縛るものの正体を解き明かします。己を知り、より自由に生きるための、現代人必須の教養書です。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
会社勤めしていると色々と理不尽だな〜と感じたり、ジェネレーションギャップを感じたりします。トレードオフの概念を素直に受け入れると色々とシンプルになるのにな〜と思うが、実際は難しいですね。
Posted by ブクログ
日本人の価値観の根っこには、孔子らの教えがある。『論語』や儒教のものの考え方と、「日本人らしさ」。そのつながりを考察した書籍。
『論語』で教えを説く孔子は、中国の春秋時代末期、戦乱の時代を生きた。それゆえ、「平和で安定した秩序をうち立てるには、どうしたらよいのか」が、彼の抱いた問題意識だった。そして「過去の良きものにこそ手本がある」と考えた。
日本の戦国時代、武将の立場は平等で、彼らの野望を押さえる権力や権威もなかった。その後、江戸時代に、世襲を基本とした序列、上の権威に下が服従する体制が作られた。この制度設計に正統性を与えるため、『論語』や儒教の教えが使われた。
江戸時代以降、『論語』や儒教の教えをもとに日本人の価値観が形成されていく。それは、次のようなもの。
①年齢や年次による上下や序列のある関係や組織を当たり前だと思う
②生まれつきの能力に差はない、努力やそれを支える精神力で差はつく
③性善説で人や物事を考える
④秩序やルールは自分たちで作るものというより、上から与えられるもの
⑤社長らしさ、課長らしさ、学生らしさなど与えられた役割に即した「らしさ」や「分」を果たすのが何よりいいこと
⑥ホンネとタテマエを使い分けるのを当たり前と思う
⑦理想の組織を「家族」との類推で考えやすい
⑧組織や集団内で、下の立場の「義務」や「努力」が強調されやすい
⑨教育の基本は「人格教育」
⑩男尊女卑
Posted by ブクログ
日本人が知らず知らずのうちに重んじてしまう習慣や考え方は論語の影響が大きい。
ホンネとタテマエ、生まれつきの差はない、男尊女卑、、、
アメリカと比べるといろんな差があるが、それらはすべて否定されるものではないと筆者は言う。
それらを理解することで、縛られた固定概念から自由になることができる。
Posted by ブクログ
日本人らしさの根源はどこにあるのか、それは徳川時代に取り入れられた論語だという。もちろん人それぞれに論語濃度は違うが。
論語に由来する日本人らしさとして、序列が当たり前、生まれより努力と精神力、性善説、ルールは上から、らしさや分が大事、組織を家族で類推、下の義務や努力の強調、教育の基本は人格教育、男尊女卑、集団重視、気持ちを考える人格教育。
これらが学校や会社などでどのように見られるのかとか、アメリカなど他国と比較してどうかと議論している。
金儲けは卑しいとする考えは根強かったようで、それをひっくり返したのも渋沢栄一の功績。
Posted by ブクログ
日本の学校風土と企業風土を、アメリカを中心に諸外国と比較する比較文化論で、日本の学校と企業に根付いた国民性を『論語』の教えに照らし合わせて説明しようとする。今現在、中国古典を読むことの意義は何なのかを考えたくて、ヒントになるかと思い読んだ。
現在進行形で学校教育に関わる人間としては、筆者や筆者のインタビューした学校関係者の持つ学校観や教育観には、やや古さを感じるものの、「年功序列」「努力・精神主義」「気持ち主義」などなど、およそ日本人が持つ学校あるあるとして共感できるものが多い。そうした日本人の心性が、『論語』の言葉と重ねて説明されるので、とても納得感のある本だった。
特に面白かったのは、最終章の渋沢栄一『論語と算盤』の解説で、筆者は、渋沢の考えをかなり高く評価している。渋沢栄一は、『論語』の道徳観と、算盤=資本主義の道徳観、それぞれの強みと弱みを分析し、お互いを補完することで、公益を達成しようとする「合本主義」という思想を説いていたとの説明だった。
存在は知っていたが、中身については知らなかったので、興味の湧く内容だった。
所々、日本人性のイメージとして古いのでは、と感じるところがあるなど、やや疑問に思うところもあったが、まだまだ、確かに今の職場にもあるな、と感じるものがある。
最後に筆者も述べている通り、自分たちを理解するために古典を読む。ただの趣味や教養ではなく、古典を読むことの意義を考えるヒントに、十分になる本だった。
Posted by ブクログ
◾️要点
「多くの日本人を無意識に縛っている常識や価値観とは何か」を論語の価値観を通じて理解するため、読みました。
印象に残ったのは、以下のフレーズです。
人生の述懐を裏から読むと面白い。
孔子でさえ、14歳までは学問に志さなかった。
29歳まで自立できなかった。
39歳まで迷いっぱなしだった。
49歳まで天命を知らなかった。
59歳まで他人から忠告を受けると、バカヤローと思っていた。
69歳まで欲望のままに振る舞うと、ハチャメチャやっていた。
◾️意見
そんな見方があるのか、と感心する部分が多かった。世代間差も、論語濃度の違いで説明できるかもしれない。9章までは論語のマイナス要素にフォーカスしている印象があるが、10章まで読み進めると納得がいく。自身も論語と算盤を人生の指針にしたいと実践しているが、それはあくまで手段であることを改めて肝に銘じたい。