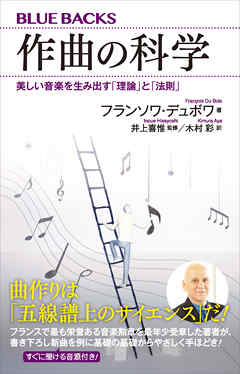あらすじ
美しいメロディを奏でる「論理」と「数理」とは? フランス音楽界で絶賛された作曲家・演奏家が語る「作曲のロジックとテクニック」
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
フランソワ・デュボワ(Francois Du Bois)
1962年、フランス生まれ。94年にレジオン・ヴィオレット金章音楽部門を史上最年少で受章するなど、世界的なマリンバソリスト、作曲家として活躍中。楽器史上初の完全教本『4本マレットのマリンバ』(全3巻/IMD出版)を刊行するなど、卓越した表現力で、作曲、執筆などを通じてマリンバソリストの地位を向上することに大きく貢献。慶應義塾大学で作曲法を指導しはじめたことをきっかけに在日21年目。本書読者のために新譜『Gunung Kawi』を特別公開(ハイレゾ対応)。
じつは、単に音符を書き込んだだけでは、その人の頭の中にある音楽を正確に再現して記したことにはなりません。その理由は、個々の音符が示しているものが、その音の 相対的な 高さと長さだけだからです。 相対的な音の高さと長さ──これが、音符が示しているものの本質です。
すでにお気づきのとおり、音楽は、規則に縛られた特殊な芸術です。 絵画や彫刻などの他の芸術分野に比べ、やたらに制約やルールが多く、その点からも、数学の一種といっていいものです。あるエンジニアの友人から、「数学者は音楽に数学を見出し、音楽家は数学に音楽を見出す」という面白い表現を耳にしたことがありますが、まさにそのとおりでしょう。 実際に、数学的素養をもつ理系人から音楽家になった人は少なくありません。私の先輩世代でいえば、ルーマニア生まれのギリシャ人でフランスで音楽活動をおこなったヤニス・クセナキスや、指揮者としても活躍したピエール・ブレーズら多くの作曲家たちが、建築学や数学を修めています。
さて、対位法を駆使した代表的な作曲家といえば、J・S・バッハでしょう。先に、平均律の名前の由来としても登場した、あのバッハです。 彼による徹底的な音の研究のおかげで、対位法の可能性は極められたといって過言ではありません。バッハの生涯の仕事の集大成として没後に出版された『フーガの技法』は、彼の偉大さを体現する究極の作品集ですが、この「フーガ」こそ、対位法のなかで最も優れた構造とされていました。 この作品の中から、「二声のインヴェンション第4番」を選んで、通常のスピードよりもはるかにゆっくりと演奏した音源を特設サイトに用意しましたので、ぜひ聴いてみてください。
美の基準に絶対的なものなどありそうにないのに、和音についてはなぜ、美しい/醜いと呼び分けるのか。ちょっとふしぎな感じがしませんか。
また、不協和音を駆使することで、独特のかっこよさやミステリアスさを創り出すことに成功している音楽家もいます。その代表格が、ジャズピアノの巨匠、セロニアス・モンクです。 彼の曲には、典型的な不協和音である「ド・ファ#・ラ♭・レ♭」などが登場します。 旋律に対する美醜の意識がさまざまに異なることは、世界各国の民族音楽を聴き比べると、さらに一目(一耳?)瞭然ですね。アフリカ、インド、タイ、インドネシア、日本、沖縄、アラブ諸国、世界各地のどの和音にも独特の存在感があり、それぞれの美しさを発揮しています。
「さくらさくら」「うさぎ」「うれしいひなまつり」などは、ほとんどの人が歌えるのではないかと思います。これらの曲には、日本ならではの音楽の伝統に基づいた「耳に残りやすい音の構成」がなされているのですが、ご存じでしょうか? それは、「ヨナ抜き短音階」という音階が用いられていることです。「ヨナ」というのは、明治時代に「ドレミファソラシ」のことを「ヒフミヨイムナ」と、1~7を意味する和名でよんでいたことに由来します。 じつは、現代のポップスにもヨナ抜き短音階を使っている楽曲があり、松任谷由実の「春よ、来い」がそうです。どこか懐かしい郷愁をそそるあのメロディには、日本人が幼少期から慣れ親しんでいる童謡と同じ響きが含まれているわけです。
作曲家の選択による最良の音(楽器)の組み合わせに、演奏家による精度の高い再現(演奏)が加われば、定量的な美しさを生み出しうる。音楽は科学的な芸術なのです。
繰り返し述べているとおり、作曲は数学です。 和音Aは和音Bとは相性が悪いけど、和音Cとは共通する響きがあって相性が良い、というような決まりごとがたくさんあることで、音楽の美しさは作られています。
倍音は、それこそ数学的な性質をもったもので、1636年に、メルセンヌ素数で有名なフランス人数学者、マラン・メルセンヌ(1588~1648)によって発見されました。前述のとおり、音の本質は空気の振動であり、音はそれぞれ高さを決定づける周波数をもっています。倍音は、この基音の周波数の整数倍の値の周波数をもつ音の成分で、倍音が豊かであるということは、その楽器の音色が豊かであることに直結するの
です。
作曲家として、あるいは演奏家として、楽器に対して私がつねづね考えていることを最後にご紹介しておきます。 それは、「良い楽器には、そもそも良い音が宿っている」ということです。数多くのマリンバを演奏してきた経験からもそれは確かで、たとえば、福井県に本社を構える世界的なメーカー・こおろぎ社のマリンバは、世界一の音を宿していると感じています。
Posted by ブクログ
入門者向けなので音楽や数学に素人でも楽しんで読める。
作曲の横軸と縦軸についての解説と、語彙としての音色、そして実際の作曲。音楽や記譜法の歴史、著者と各楽器との付き合いなど、読み物として純粋に面白い話もある。マリンバといえばグアテマラシティの国立劇場で聴いた演奏を思い出す。
Posted by ブクログ
「蜜蜂と遠雷」の小説を読んで、もっと音楽の知識があれば更に楽しめるんだろうなという思いを持っていたので、本書を手に取りました。
作曲は数学だと著者は繰り返し述べていましたが、確かに方程式を解くのに近い印象を持ちました。クイーンのギタリストのブライアン・メイのように数学などの理系学問を修めた人が音楽家になるケースも実際多いそうです。
様々な知識やテクニックを使って方程式を解くように、様々な音の規則性や楽器ごとの出せる音域・得意な音域などの知識やテクニックを駆使して複雑な曲を作り上げていくプロセスは、非常に興味深かったです。
著者は音楽専攻でない大学生向けに作曲の講義もしているそうですが、本書はト音記号の説明からしてくれるので、義務教育レベルの音楽知識しかなかった私にとっても読みやすい一冊でした。
ハ長調やA Minorなどについてもよく理解できてスッキリしました。また、音源つき(CDではなくウェブから聴けるというのが非常にいい)でA Minorがどんな音なのかなども確認しながら、読み進められる点も良かったです。
Posted by ブクログ
フランソワ・デュボワの『作曲の科学』読み終わったー。著者の作曲に至るまでの背景を見せつつ記譜法や音楽の理論の基礎を最小限導入してておもしろかった。最後の方は作曲実践入門的な感じで、電車だったので帰ってもっかい読みながら試そうと思う。いい本だなー。
DAW音作りはできはするが理論ぜんぜん知らないしめっちゃ怖いと思ってたけど、なんだか気軽にやってよさそうという気分にさせてくれる、よい本だったな。
Posted by ブクログ
いやー勉強になった!
モノフォニーカラーポリフォニーへそして和声楽へ 音楽の進化を知れた
音楽の足し算は時間軸=メロディ
音楽の掛け算は和音や楽器の重なり
この考え方も面白い
そして豆知識も手に入った
タイ=結ぶ〈伊〉
テンポ=時間〈伊
ブルーバックスは理系向けとのことで自分に読めるか不安だったけど興味ある分野はいける!
Posted by ブクログ
音楽理論のとっても初心者向けの解説になっている。作曲でもしてみたい、という人はもとより、クラシック等のスコアを読みたいという人や、バンドやっててコードの構成とか進行について興味ある、というような人にもすすめられる。手に取りやすいし、サイズも値段も手ごろなので、プレイヤーになってみたい人、音楽を理解してみたい人はぜひ!
Posted by ブクログ
作曲に対するハードルは、今やかなり低いらしい。
コンピュータの様々なアプリのおかげで。
そういう時代の作曲指南本なのだが、音楽史の話も、個人史もよりあわせつつ、やはりがっつり楽典、和声法。
とはいえ、読み物としては読みやすい。
特に作曲をしたいとは思わないけれど、自分が好きな音のつながり、和声を探ってみるのは楽しそうだ。
Posted by ブクログ
フランス人で日本在住の作曲家による、音楽の基礎と作曲に関する話。小学生の頃習った音楽の基礎をもう一度おさらいし、かなりの疑問点が解決できた。経歴や自分自らについてのよもやま話の部分が長すぎる。
「(演奏家)グループで演奏中、必ずどこかでソロとして弾くタイミングが回ってくる。そのソロパートを聴いて「彼には独りよがりな傾向があるな」とか「あの人は注意深く正確に、他人の音に耳を傾けているな」とか「この人は権力志向が強いな」「度胸があるな」といった、個々の奏者の才能や深層心理、性質や演奏傾向を読み取ります」p14
「作曲とは数学である」p39
「ピアノの場合は右手の担当領域がト音記号、左手のそれがヘ音記号」p67
「平均律という共通ルールを使うことで、複数の楽器による合奏が容易になりますが、一方で、各文化圏に特有の民族音楽系は演奏できなくなります。平均律は、近現代の西洋音楽に慣れた耳に向けて作った人工的な調律なので、当然のことと言えるでしょう」p70
「下から上に上がって弾くときは「ド♯」と書き、上から下に向かって弾いているときは「レ♭」と書きます。ある音符に♯や♭がついていたら、その小節内ではずっと記号をつけた状態で弾くのが原則です。記号をはずして弾いてほしい場合には「ナチュラル」という記号をつける決まりになっています」p70
「プロの歌手が「連日のコンサートで、今日は喉が疲れた」というときに、いつもより音域を下げて歌うことで喉を守るなど、同一人物が発声状態に応じて歌い分けられるのも、移調の効果の一つです」p74
「(作曲の科学)小節という箱の中で合計が合うように足し算する」p75
「(ヨナ抜き短音階)明治時代に「ドレミファソラシド」を「ヒフミヨイムナ」と和名で読んでいたことに由来し、ファとシを抜いた音階で作られた曲。童謡や「東京音頭」がそう。松任谷由実の「春よ、来い」もそうで、どこか懐かしい郷愁をそそるメロディには、日本人が幼少期から慣れ親しんでいる童謡と同じ響きが含まれているから」p93
「(オーボエ)世界で最も演奏が難しい楽器と言われている」p162
Posted by ブクログ
「作曲」をテーマにしているが、楽典の基本的部分、特に和声の基礎が分かりやすく書かれていて面白かった。後半では、実際の作曲を目指してコード進行の例がクラシックだけでなくロックや歌謡曲も引き合いに出して説明されている。残念ながら、知らない曲が多くてよく分からなかったが、フランス人でありながら日本滞在歴も長い著者が日本人に向けて書いた本書の意気込みを感じた。
音や音楽は、書物では表しきれない部分があるが、特設ウェブサイトで音のデータにアクセスして実際の音や響きを聴くことができ、本では伝わらない部分を補っているのがよい。
Posted by ブクログ
こんな本を手に取るなんて…というか,こんな本がブルーバックスの一冊になるなんて…というか…。
まったく場違いというわけではない。振動数と音の関係というのは科学だし,わたし自身,いろんな楽器を弾いてきたし,興味もあった。
しかし,こと,作曲なんてことは考えたこともなかったのだが,本書を読むと,わりと簡単に作曲できそうな気になる。
本書の凄いところは,まるで日本人が書いたような文章になっているところだ。著者のフランソワ・デュポアという人は,もちろん日本人じゃないのだが,この文章を読んでいると,ついつい「あれ,これって日本人が書いたんだったっけ」という錯覚に陥ってしまう。それくらい,読みやすい訳文なのだ。訳者は木村彩さんという,日仏英のトリリンガルとして活躍している人らしい。この人,たいしたものですね。
さて,内容だが,音楽をたし算とかけ算にたとえながら,説明していくあたりは,さすがだ。そして,本当に,本書の最後には,作曲もできそうな気がしてしまうから不思議。
ただ,最後の方は,ちょっとかけ足で説明されていて,もう少し順を追って説明してほしいなと言う部分はある。さすがに,まったく和音など知らない人はちょっととっつきにくいかも知れない。ただ,そんな人は,こういう本を手に取らないだろうから大丈夫だけど。
本書に紹介されている音階や和音は,スマホなどで簡単に聴くことができる。これもいいサービスだと思う。そばにピアノなどの楽器がなくてもいいからね。
Posted by ブクログ
フランス生まれのマリンバ奏者で、慶應で音楽専攻ではない学生に作曲法を教える著者が、音楽の初心者に向けて作曲に必要な初歩的な知識と技法を解説したもの。QRコードを読み取って、本書に載っている楽譜や実際に著者が作曲した音楽の音源にアクセスすることができる。
楽典の基本の基本、みたいなところが分かりやすく解説されていて、読みやすい。個人的には音程の長短・増減・完全○度みたいなやつが、やっと分かった気がする。というか分かってみると結構簡単で、なんでこんなの分からなかったんだろう、という気さえするくらい。たぶん、厳密な部分が省略されていてポイントだけ、初心者向けに解説されているからだろうと思う。例えば音律だったら平均律以外に純正律とかピタゴラス音律とかピタゴラスコンマがどうのこうの、という話は必ず出てきていっぱいいっぱいになってしまうけど、平均律の話しかないので、そういう負担がなくていい。でも和音のところはやっぱりちょっと難しいかも(と言ってもこれ以上の基本はないのだろうけど)。あと作曲は「旋法」を利用しよう、というユニークなアプローチで、誰でも気軽にできます、となっているけど、実践するには直接教えてもらいたい、というのが本音だった。
この本の特徴的なところは著者がマリンバ奏者だということで、打楽器奏者の苦労とかも含めて、マリンバ奏者の立場から他の楽器(ピアノ、バイオリン、クラシックギター、フルート)の「個性」、つまり音色について解説されているところ。同じ音楽家でも見方は様々、ということが改めて分かった。
作曲はしなくても楽典の基本を理解するのにちょうどよい本だった。(24/06/16)
Posted by ブクログ
「カセットテープミュージック」でスージー鈴木さんが紹介していたので、興味を持ちました。著者は慶應義塾大学で音楽(作曲)を教えているフランス人の世界的なマリンバ奏者であり作曲家。
「音楽は科学だ・数学だ」というコンセプトなので科学新書のブルーバックスなんですが、中身はと言えばやはり「譜面の読み方をある程度分かっている人」向きなのは否めません。加えて、著者自身の「自分語り」の部分も一定量を占めていて、肝心なところへなかなか行きつけないもどかしさがあります。大学教授の著書というだけあって、講義を聴いているような雰囲気でしょうか。それが「単刀直入に、シンプルに『音楽と科学の関係』について理論的に語られる」のを期待して読み始めた、譜面の読めない理系の夫にとっては期待外れだったらしく、冒頭で投げ出してしまいました。
私は子供のころピアノを習っていたし、今も趣味で続けているので、音楽の基本的なことはわかっているつもりです。ですが、作曲というはやってみたいと思いながらやったことはなく(ピアノ伴奏譜くらいは作ったことありますが)、特にコード、和声についてわかりやすい説明の本を何冊か買って読んではみたものの、どれも帯に短し襷に長しで、一長一短。本書は、これまで読んできた本に足りなかった部分を補ってくれる部分があったので、私にとっては価値がありました。
基本的には、ピアノ(キーボード)くらいは手元にあった方がよいかと思います。参考楽曲は特設サイトで登場順に聴くことができるので、その点はありがたいといえるでしょう。
敷居が高いと思いがちな「作曲」という創作活動の、ハードルをグッと下げてくれる良い導きの書、というのが最終的な印象です。五線譜に書くのがめんどくさければ、今はパソコンでDTMソフトを使って作曲ができる時代なので、工夫次第で新しい音楽が作れるかも、と思うと楽しみが広がりますね。
Posted by ブクログ
「作曲の科学」というタイトルだが、作曲の話も科学の話もあまり出てこない。
本書の半分は音律の基礎で、4分の1は楽器についての読み物で、残りの4分の1が作曲についてである。
作曲を勉強しようと思って読むと期待外れになるが、楽譜の読み方入門として読むのにはちょうど良い本だと思う。
Posted by ブクログ
・フランソワ・デュボワ「作曲の科学 美しい音楽を生み出す『理論』と『法則』」(講談社ブルーバックス)を読んだ。本書は「曲作りの『しくみ』と『原理』を、音楽の理論的な知識をまったくもたない人にも理解していただけるよう」(4頁)に書かれたといふ。実際、五線の各部の名称から始まる。これはヨーロッパの記譜法の歴史を終へたところで出てくる。第1章「作曲は『足し算』である」と名づけられた章である。 副題として「音楽の『横軸』を理解する」(21頁)とある。なぜここに記譜法や五線が出てくるのか。「音の組み合わせには『定理』があり、美しいメロディ を生み出すための“足し算”や“かけ算”があって、その『四則演算』を知らなければ、決して美しい楽曲を作ることはできないからです。(原文改行)そして、その四則演算を理解するために必要不可欠なのが、『音楽記号』です。」(39頁)何事も基礎を知らねばならぬ、音楽も同様だ、といふことであらう。それにしても、足し算やかけ算とは何かと思ふ。音楽が数学等と非常に密接に結びついてゐるのは知つてゐる。クセナキスやブレーズ(79頁)がその代表である。さういふのと関係があるのか。しかし、ここでの足し算は関係がなささうで、1拍が2つで2拍となり、2拍が2つで……のやうに考へるのが、ここでの意味であるらしい。全音符、全休符から32分音符、32分休符までの一覧表もある。これで1小節の中を埋める足し算をせよといふのであらう。これに対してかけ算とは何か。「単一の音では実現できない音の響きを、複数の音の組み合わせで可能にする」(同前)操作である。「音楽の縦軸は、ある同一時点において、 同時に組み合わさって鳴らされる音のセットを指」(同前)すから、かう言へるらしい。だから「クラシック音楽におけるオーソドックスな『かけ算』には2種類あります――『対位法』と『和声法』です。」結局、ここに至つても私にはかけ算の意味がよく分からないのだが、要するに音の重ね合はせ方をここではかけ算といふらしい。その説明のためにラモーの「和声論」あたりから始まつてクラシック、ポピュラー、そしてヨナ抜き音階からユーミンまで、実に幅広くの材料で説明してゐる。これは読み手に実際の音が思ひ浮かぶやうにといふ配慮からであらう。ただ、私はポピュラー系はほとんど分からないので、却つて複雑な、あるいは不明な響きになるだけにやうな気がする。これはしかたのないことだが、もしかしたらデュボワの頭には、本書の読み手として専らポピュラー音楽の聞き手があつたのかもしれない。これ以後も多くの歌が出てくるが、クラシックはほとんどない。私のやうな者が読むことがまちがつてゐるのかもしれない。最後の曲例も明らかにクラシック音楽ではない。巷でよく聞かれる曲である。コード進行も「あえて日本の王道コードを使って」(209頁)あるとか。出てゐるのと曲例のとを比べると、確かにさうなつてゐる。かういふのは見たことがあるやうな気はするが、その実際は私には分からない。そんなわけで、おもしろかつた反面、実際の曲作りや旋法等になるとあまりおもしろくなかつたと言へる。私とは考へることが違ふらしい。かういふ人が和声のテキストを作るとどうなるのかと思つてみたりもするのだが……。
・それにしても本書は「」、括弧が多い。大体は「」だが、ごく一部に“”もある。一種の強調表現であらうが、一々つけなくてもいいのにと思ふ。足し算はともかく、かけ算は所謂かけ算らしくないよなと思ふ。だからつけたのかもしれない。それにしてもである。引用するのに苦労したことではあつた。
Posted by ブクログ
世界最古の楽器
35000年前のハゲワシの骨のフルート、22cm、ドイツ
世界最古の楽譜
紀元前1400年シリア
中世イタリア1025年、修道士グイード作 音程も考案
記譜法の基礎1650から1750年に確立
ピアノ並みの音域を奏でられるのはチェンバロとハープ
Posted by ブクログ
全く作曲のことはわからないのですが 面白そうだなと思って読みました。
素人のわたしでもわかるような気になったのでとても良かったんじゃないかなと思います。
Posted by ブクログ
この本は4章構成になっていて、個人的には3・4章の「作曲のための語彙を増やす」「作曲の極意」目当てで読み始めた。目次を読む限り、3章では様々な楽器を取り上げ、それらの特徴やら曲での活かし方が記載されているのだと思っていた。確かにそれもあるが、著者と親交の深い奏者へのリスペクトのついで程度のようでもあり、そこは少し残念。同じ曲でも違う楽器で演奏すると雰囲気がかなり変わる旨の説明までしてくれたのだから、いっそほぼ全部の楽器を取り上げて作曲の際はこの楽器のこういう特徴を生かすと雰囲気が出る等のコツを網羅してくれればよかったのになぁ、と思った。
しかし説明がわかりやすいし、音源が結構入っていて、作曲や音楽理論を始めて勉強する人にとってはイメージしやすくてよい本だと思う。未公開音源もあって著者の力の入れようが感じられる(文中の例として日本の曲を取り上げていることからもサービス精神を感じる)。