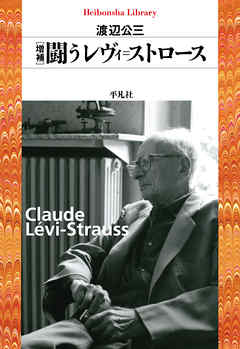あらすじ
レヴィ=ストロースの壮大な思想は図式的理解を拒むが、闘う知識人としての姿を追うことで難題に挑む。100年の生涯で彼は何と闘ったのか。第一人者による最良の入門書。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
なかなか歯が立たないレヴィ=ストロース。少しでも理解の足しにと手に取ったが、正直難しかった。
学生活動家だった頃から説き起こしている。
親族構造から神話研究に至る理由も。まあそんなものかと思う。「生のものと火にかけたもの」の意味するものも初めて知ることができた。
だけど、構造の何たるかは結局よく判らない。
第二章の最後に、家族は社会の条件であると同時にその否定であると記されている。
親族構造の最初が家族だよね。社会はまず、親族の基本構造から始まっているんじゃないの。どういうこと?
Posted by ブクログ
構造主義人類学を提唱したことで知られる人類学者レヴィ=ストロース(1908ー2009)の生涯と思想の概説。言語学者ソシュールが「一般記号学」を構想する中で到達した抽象的な「構造」の概念が、より具体的な人文諸科学の中でどのように展開されていったのか、そこからどのような政治的態度が導き出されるのか。
□
1942年、亡命先のニューヨークにて、レヴィ=ストロースはロシアの言語学者ロマン・ヤコブソンと出会い、その音韻論を通してソシュール記号学を知ることになる。ヤコブソンの音韻論の方法論を人類学へと拡張することによって、ソシュールにおける「構造」の概念を、自身の新しい人類学に取り入れていく。そこでは、諸シーニュの否定的な差異の体系によって言語の意味が生成されるとするソシュール記号学の議論と並行的に、インセスト・タブー(「近く」の女性との性関係を禁止する⇔「近く」の女性を「遠く」の男に提供することを命じる⇔「近く」の女性を「遠く」の女性と交換することを命じる)によって「近い」「遠い」の差異としての親族関係が生成し、以て諸人間がさまざまにカテゴリー化されそのカテゴリー間における交換(コミュニケーション)関係が生成するとされる。こうして生成される親族関係は、言語(ラング)と同様に恣意的価値体系=「構造」を具えたものであり、この「構造」によって人間諸集団間の関係性が規定されていく。ここに、自然から文化への移行が見出されることになる。
「固有の意味作用はもたないが、表意作用を形成する手段となる音素と同様、インセストの禁止は、別個のものと見なされる二つの領域のつなぎ目をなすとわたしには思われた。こうして、音と意味との分節に、他の平面で、自然と文化の分節が対応することになったのである。そして形式としての音素が、言語的コミュニケーションを打ち立てる普遍的手段として、あらゆる言語に与えられているのと同様、インセストの禁止は、その否定的表現だけに限るならば、普遍的に存在し、これもまたある空虚な形式を構成する。だが、空虚であってもこの形式は、生物集団の分節が可能になると同時に必須ともなって交換の網の目をつくりだし、これを通して集団相互のコミュニケーションが生じるためには不可欠なのである。そして最後に、音素の存在は、その音的個性のうちにあるのではなく、音素が互いに結ぶ対立的、消極的関連のうちにあるのと同様、婚姻規則の表意作用は、諸規則をばらばらに研究してもとらえられず、それらを互いに対立させない限り浮かびあがってこない」(p126ー127)。
音韻論は、さらに神話の分析においても参照されることになる。
「あらゆる神話の言説を、ある種のメタ言語として扱うことにした。このメタ言語の構成要素となるのは「主題」や「場所」〔シークエンス〕であるが、これらはそれ自体で意味作用をもつものではない。これは言語〔ラング〕における音素のようなもので、体系の中に関連づけられたときのみ意味を持ちうるものである」(p158)。
□
マルクス主義の学生活動家であった若かりし頃のレヴィ=ストロースは、雑誌『社会主義学生』にて、ポール・ニザン『アデン・アラビア』の書評を書いている。
「私はそこに、似たものの発見以上に異なったものの発見を、人間との出会い以上に世界との出会いを見るのである。ポール・ニザンの経験の価値は、アデンから帰還したことではなく、そこに行ったことにある」(p68)。
来るべき人間倫理は、「他者」と「自然」との出会いの上に拠って立つものでなくてはならない、という極めて具体的で政治的な態度を表明している。それは後年の「反‐自民族中心主義(反‐人種主義、反‐西欧中心主義、反-植民地主義、文化相対主義)」「反‐人間中心主義」「反-理性中心主義」へとつながっていく。
「初めてインディオと共に荒野で野営する外来者は、これほどすべてを奪われた人間の有様を前にして、苦悩と憐みに捉えられるのを感じる。[略]しかしこの惨めさにも、囁きや笑いが生気を与えている。夫婦は、過ぎて行った結合の思い出に浸るかのように、抱き締め合う。愛撫は、外来者が通りかかっても中断されはしない。彼らみんなのうちに、限りない優しさ、深い無頓着、素朴で愛らしい、満たされた生き物の心があるのを、人は感じ取る。そして、これら様々な感情を合わせてみる時、人間の優しさの、最も感動的で最も真実な表現である何かを、人はそこに感じ取るのである」(p110)。
「南北アメリカのどのインディアンに「神話とは何か」と聞いてみても誰からも次のような答えが返ってくるでしょう。それは動物と人間が実際には区別されず、人の姿と動物の姿のあいだでどのようにもまた変えられた時代に起こったことの物語なのです。私たちにとってほとんど悲劇的ともいうべき真実とは、[略]、それは私たちが私たちと同様に生きていながら、意思疎通できないものたちと間近に接して生きている、ということなのです。神話の時代とはまさにそれが可能だった時代なのです」(p194ー195)。