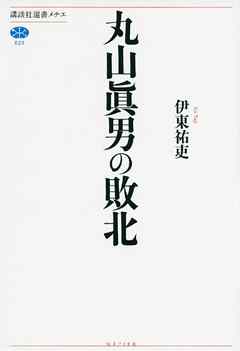あらすじ
丸山眞男(1914-96年)は、戦後日本を代表する知識人である。その政治的著作は敗戦直後から多大な影響力をもち、丸山は「戦後民主主義」の象徴となった。本書は、その全主要著作を通覧し、解説する絶好の概説書である。しかし、丸山を生涯にわたって貫く原理である「丸山眞男の哲学」を発見し、それを前提に著作を読んでいく中で、本書は驚愕の結論に到達する。──丸山眞男は、1960年にはすでに「敗北」していた。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
現代において戦後というものをどう考えていけばいいのだろうか?という疑問に突き動かされて本書と巡り合いました。
丸山眞男の思想の内容については良く知らない状態で読み始めましたが、本書は平易な文章でその概説をしているため非常に入り口として役立つものでした。
結論として丸山眞男の思想が枠に囚われた思想であり、現代において既に敗北しているという論述がなされており、その論旨も納得いくものです。
それを踏まえた上で、本書を入り口として丸山眞男の著作を今読むことにどのような意義が出てくるのか不明瞭になってしまい、「丸山眞男思想の入門書」として本書を読んだ人はその入り口で心を折られてしまいかねないとも感じられました。
Posted by ブクログ
戦後史のなかで、丸山眞男の政治思想および日本思想史における仕事がどのような意義を果たしてきたのかという問題を論じた本です。
著者は、丸山の福沢諭吉研究を手がかりにして、丸山が論じている福沢の思想的方法が、丸山自身の仕事にも見いだすことができると主張しています。その方法とは、状況認識にもとづいて社会という舞台での役割を演じるというものであり、著者はこの方法を「丸山の哲学」と呼びます。本書はまず、戦前の丸山が「近代の超克」の議論に対してどのように向きあっていたのかを明らかにし、つづいて戦後史の歩みのなかで丸山が、いわば逆風に向かって凧を上げるというしかたで、社会の動向や風潮に逆行してみずからの論考を提出してきたことを明らかにするとともに、政治の時代の終わりを迎え「無思想の時代」に入ったことで、そうした丸山の方法が通用しなくなっていったことを、「丸山眞男の敗北」というかたちでえがき出そうとしています。
著者は、丸山の戦争体験を参照しつつ、丸山の思想には自分たちが戦争で多くの死者を出したという「当事者意識」が欠けていたと批判しています。こうした著者の発想は、加藤典洋の『敗戦後論』(ちくま学芸文庫)の考えを引き継ぐもので、戦後の日本が繁栄のなかで「無思想」へと埋没していったことを、改めて思想の問題としてとりあげる必要があると主張しています。
時代のなかで丸山眞男の仕事の意義を論じたものとしては、水谷三公『丸山真男』(2004年、ちくま新書)や竹内洋『丸山眞男の時代―大学・知識人・ジャーナリズム』(2005年、中公新書)などがありますが、本書は丸山のいわゆる「本店」の仕事も含めて、丸山の仕事を時代状況のなかに位置づける試みといってよいのではないかと思います。