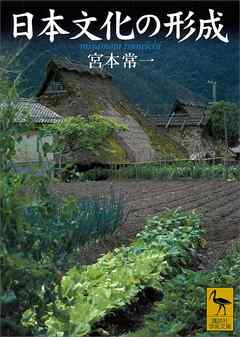あらすじ
日本列島を徹底踏査した民俗学の巨人が、『古事記』『日本書紀』『万葉集』『風土記』などの古代文献を読み返し、それらと格闘の末、生まれた日本文化論。稲作を伝えた人びと、倭人の源流、畑作の起源と発展、海洋民と床住居など、東アジア全体を視野に入れた興味深い持論を展開する。長年にわたって各地の民俗を調査した著者ならではの着想を含む遺稿。(講談社学術文庫)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書は、民俗学の巨人・宮本常一氏が生涯にわたる実地調査から得た着想を基に、日本文化の形成過程を探求した遺稿集です。
著者は、単に古典文献の解釈にとどまらず、東アジア全域を視野に入れながら、稲作や畑作の伝来、海洋民と床住居の関係など、日本文化の源流を徹底的に掘り下げています。『古事記』『日本書紀』はもちろん、『万葉集』『風土記』といった貴重な文献にも新たな光を当てています。
特に注目すべきは、長年各地の民俗を実地に調査してきた著者ならではの問題提起です。畑作の起源、床住居の由来など、従来の通説に一石を投じる鋭い指摘が随所に見られます。文献資料だけでは看過されがちな民俗実態から、日本文化の淵源を探ろうとする試みは斬新です。
一方、膨大な文献と実地調査から得た知見を一つの体系的理論に昇華しきれていない面もあり、断片的な印象は拭えません。しかし、民俗学の権威による日本文化形成論としては重要な価値を持つ好著と評価できるでしょう。
文化の形成過程に関心を持つ読者のみならず、民俗学を学ぶ者にとっても示唆に富む一冊といえます。
Posted by ブクログ
冒頭から話が面白い。引き込まれる。民俗学はから語りの面白さを奪ったらただの歴史くずれだ。
民俗学の探求心は語りべによって構成されているようにさえ思える。
Posted by ブクログ
81年の本をまとめ直して05年に出版。小さく読みやすい。
稲作は東南アジア・南方から伝わってきた。
日本に稲作が伝わってきた時代、朝鮮半島ではまだ行われていなかった。
「旧唐書」日本は倭国を併した→倭国と邪馬台国は別。
Posted by ブクログ
古代史・考古学関連本をずっと読み漁って来て、何となく壁に突き当たっていたが、民俗学の権威の先生の本を読んで、また違った視点で古代史を見ることができるようになった気がした。
一点どうしても以前から気になってたこと。朝鮮半島における倭人の拠点。古墳などの考古学遺物もあるし、中国、広開土王碑、日本書紀などの文献にも半島での倭人の活動が何度も書かれている。民俗学として見た場合にも列島との文化交流の掛け渡し役として、半島に植民地か居住地があったと見て良さそう。任那や百済が失われた時点で足掛かりをなくしたのだろう。
Posted by ブクログ
50近くで他界した叔父の毅彦も「宮本常一のように生きたい」と言っていたと聞いていて、常に気になる存在である宮本常一。『塩の道』や『忘れられた日本人』に感銘を受けるも、まだまだ叔父のような生き方には至らず。
この本を読んでみて、最近、南の島にも行ったりしてるので、海や半島からの文化(つまり人と生活様式)の流れが、読後には相当気になりはじめました。日本語の形成過程や地名などの由来、居住形態などの考察も含め、興味深く惹き付けられます。
さらに、宮本氏の師である渋沢敬三の言葉にやられました。
『(略)…渋沢先生のいう「物をして語らしめる」ということは物の中に含まれている意志を読みとる力がないと読みとれないものであって、それにはできるだけ多くの物を見ていかねばならないと思っている。』(p172)
「物をして語らしめる」うーむスゴい言葉です。
ものづくりの立場としても、含蓄が深いです。
Posted by ブクログ
日本書紀で神が出雲にやってきたときに、そこにいたとされるコトシロヌシ(事代主)を後世の人はエビス神としてまつった。古くから日本列島に住んでいた人々がエビスと呼ばれたと考える。
中国の夏は東南アジア系の人々の王朝で、祖先神として蛇身の水神(竜)をまつった(岡田英弘「倭国」)。越人は夏の王の後裔であると言い、体に入れ墨をして米と魚を常食とする海洋民族だった。倭人は越人の一派に属するとも考えられる。揚子江や西江では、船を家にし、鵜を利用して魚をとる人々がいる。
日本列島で国家を形成したのは、新たに海の彼方から強力な武器を持って渡来してきた人たちであり、東南アジアの海岸から北上してきた海洋民と考える。
周防に勢力を張り、中世末まで続いた大内氏は、百済の聖明王の子である琳聖太子の子孫と言われた。秦氏は秦の始皇帝の後裔と言われ、秦滅亡後に朝鮮南部に移動して日本へも多数渡来した。秦氏は畑耕作や機技術を伝えたと考える。雄略天皇の時代に秦酒公が秦の民を管理下におき、太秦の姓を与えられた。秦氏は欽明天皇の頃から朝廷と関係を持つようになる。
高床式家屋は稲作文化と深いかかわりがある。日本へ稲作を持ってきた人たちが高床式家屋に住んだ形跡は乏しいが、穀物を保存する高倉は設けた。貴族の家は古墳時代から、仏寺は鎌倉時代に高床になる。西日本では床のある家が多かったが、東日本では明治になってから。
Posted by ブクログ
宮本常一の未完の遺著である。柳田国男の『海上の道』とおなじくらい壮大な意図をもって書かれた書物と思われる。したがって柳田の同著と同様に、民俗学の通常のテリトリーを超え、むしろ歴史学に近づく。ただし宮本は柳田の仮説よりはもっと常識的な範疇で提言している。
この本で説かれている、たとえば稲作・畑作の伝来、エゾ=エビス文化のなりゆき等、読んでそれなりに面白くはあるが、やはり歴史学者の専門的な記述にかなうものではないと思う。
この本が未完で終わってしまったのは残念だが、もっと民俗学的なパースペクティヴが生かされた論述を期待していたので、やや不満足を感じてしまった。
Posted by ブクログ
なにかのきっかけで、この本であんなことが書いてあったな、
と思い出せるように頭の引出しの中に入れておけたらいいな。
古代の日本での、稲作の伝来ルートや、人の移動、農耕など、
人々の生活のありようがどうであったかを記した本です。
「秦氏」は侵略によって文化を運んできたのではなく、
必要とされることで文化を伝えた、
といったような記述が心に残っています。
宮本常一さんの、勤勉で実直な様子が文章から読み取れます。