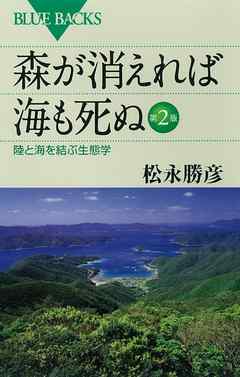あらすじ
森はいかにして海を豊かにするのか。昔から、魚介類を増やすには水辺の森林を守ることが大切とされ、こうした森は「魚つき林」と呼ばれた。森の栄養が海の生き物を育てているのだ。現在、漁師たちが山の木を育てる「漁民の森」運動が全国で進められている。その科学的根拠ともなった「陸と海を結ぶ生態系」を解き明かす。(ブルーバックス・2010年2月刊)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
日本の山は漁業のみならず、稲作、水の濾過、水を貯める役割等多岐にわたります。林業はもちろんです。
むやみやたらと山を切り開いて、太陽光パネルを並べることが、いかに愚策かよく分かる本です。
Posted by ブクログ
豊かな海は天然の森と川があってこそ!!
何が豊かな海をもたらしているのかを一般読者向けに一通りまとめてくれてるおススメの一冊。
本書に書いてある内容は一般知識として知っておくべき大切な事だと思う。一方、本書に書いてあるようなことを知る機会って普段生活してる中で殆ど無い気もして、小さい頃からごみを捨てるなと同じくらい教えてもいいんじゃないかなって思った。
Posted by ブクログ
なぜ森林は守られ、管理されなければならないのか。著者はそのことを化学的に説している。森林は川で海とつながっており、森が死ねば海も死ぬ。
化学物質の話が随所に出てくるので、高校の化学を理解していないとわからないことが多いが、結論としては明確であるのでわからなければ読み飛ばしても問題ないと思う。
巻末の方で植林の重要性を著者は説いていたが、何でもかんでも木を植えれば良いという問題ではない。その地域環境に最も適合する種を育てないと生態系を破壊してしまう恐れがある。
Posted by ブクログ
著者は長年、河川や海の生態系、特に陸との関係について研究してきた方。ウニなどの食害による海藻の減少を否定し、陸からの腐植物質の流入が減少したことが原因であると説明している。
鉄は細胞がとりこんだ硝酸塩を還元する硝酸還元酵素に関与しているため、光合成色素の生合成にも不可欠だが、腐植物質には鉄などの金属を結びつける機能があり、細胞に鉄を運ぶ役割をしている。腐植物質に乏しい海では、石灰藻が岩や岩石を覆って、昆布やワカメなどの海藻が育たなくなり、水産資源が減少してしまう。
昆布が有名な日高地方の海には数多くの河川が流入して栄養素が運ばれている。また、津軽海峡と北海道の日本海側には対馬暖流水が流れ込むが、多くの河川が流れ込む海峡側では昆布もウニも生育しているが、河川のない日本海側では石灰藻が拡大しているという実例を紹介している。
著者は海の生態系を復活させるために、植林や間伐を提唱している。間伐が有効なのは、下層まで日光が届いて下草が生え、腐食土が形成されるためである。
植物や植物プランクトンなどの光合成生物が生態系の基盤を支えているのは言うまでもないが、その生育には窒素やリンなどのタンパク質の原料だけでなく、鉄などの金属も重要な役割を果たしていることがよくわかった。窒素やリンの河川への流入が増えると、珪素を必要とする珪藻とそれを食べる魚より、珪素を必要としない鞭毛藻とそれを食べるクラゲが増えるというのも、陸と海がつながっている一面として興味深い。
なお、この本では、海への鉄散布については、大気中の二酸化炭素を削減する効果は得られていないとしている。
・世界人口の約25%がマングローブ周辺で暮らしており、家屋、家具、薬品の原料、燃料として利用されている。
・1000haの干潟で10万人程度の汚水を処理することができる。
・石灰藻が岩や岩盤を覆うと、ワカメ、コンブなどの海藻が生育できなくなる。半永久的な磯焼けの原因となり、水産資源が減少する。
・サンゴの天敵はオニヒトデで、オニヒトデの天敵はホラ貝。ホラ貝の乱獲によりオニヒトデが増加し、サンゴの死滅の原因となっている。
・熱帯や亜熱帯では、海藻の代わりにサンゴ礁が魚介類を増やす役割を果たしている。
・腐食土は高濃度のリンを吸着し、窒素化合物を窒素ガスにする脱窒素の機能を持つ。
・湿地の底土中の水には、光合成に不可欠なフルボ酸鉄が含まれている。この水が川に流れることによって、海の生物が育つ。
・鉄は、細胞がとりこんだ硝酸塩を還元する硝酸還元酵素に関与しており、光合成色素の生合成にも不可欠。
・鉄は沿岸海域には河川から流入し、外洋には偏西風によって運ばれる。赤道域、南大洋、アラスカ湾では鉄が不足している。
・陸上では、鉄との結合力が大きい有機物質シドロホアを分泌することにより、鉄イオンを取り込んでいる。
・腐植物質には鉄などの金属を結びつける機能がある。
・腐植物質があると炭酸カルシウムの結晶形成が阻害されるため、石灰藻は育たない。
・海の食物連鎖では、珪藻が魚に、鞭毛藻がクラゲにつながっている。窒素やリンの河川への流入が増えると、珪素を必要としない鞭毛藻が増えるため、クラゲが多くなる。
・鉄不足海域への鉄散布実験では、大気中の二酸化炭素を削減する効果は得られていない。
・間伐をすることにより、下層まで日光が届いて下草が生え、腐食土が形成される。
Posted by ブクログ
ちょっと「運動家」っぽいところがあって、筆が滑っていそうなところがちらほら。
そのせいで、「これ、ほんとに事実なのかなあ」と首をかしげちゃうところもちらほら。
ただ、総じて見れば誠実な書と言ってもいいんじゃないでしょうか。