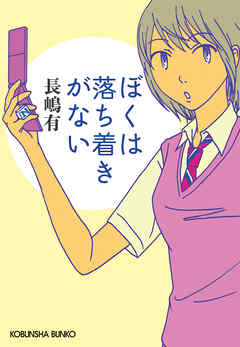あらすじ
両開きのドアを押して入るとカウンターがある。そこは西部劇の酒場……ではなく図書室だった。桜ケ丘高校の図書部員・望美は今日も朝一番に部室へ行く。そこには不機嫌な頼子、柔道部と掛け持ちの幸治など様々な面々が揃っている。決して事件は起こらない。でも、高校生だからこその悩み、友情、そして恋――すべてが詰まった伝説の不可思議“部室”小説が電子書籍化!
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
中学生の時に読んでめちゃくちゃ好きだった本。
入手してもう一度読み直す。
こういう人、いる。そして部内で流行もあり、頻繁に変わる。わかる。
望美の精神というかテンションというか、当時の私も今の私もなんだか彼女と波長があっている。だから余計に好き。
登場人物全員魅力的だけどナス先輩、部長、頼子はもう合戦モノ。
みんなこの3人の誰かしら好きでしょ。
私は片岡哲生も好き。樫尾もいいな〜!選べん!
Posted by ブクログ
本を読むということの(いろいろひっくるめてすごく簡単に要約すると)面白さが、ものすごくたくさん詰まっていて、書かれていて、読みながらずっと読んでいることにうれしくなる小説だった。
Posted by ブクログ
30ウン年生きてきて一番しんどかった時期に読み、クラスでは目立たない子達がなんとなく居場所を持って背伸びしないで生きていく姿にまったりと救われました。
特に「本はつまり、役に立つ!」の部分に電車の中で思わず号泣。
自分の芯を持って生きている人は強い。
Posted by ブクログ
本作の舞台である図書部部室。
図書室を削って作られた細長いその部屋では
繰り広げられる大騒動も事件も何もない。
何もない風に書かれているけれど、図書部員たちは未来に向かって進んでいる。
描かれていないところで影響を受ける些細な何かがそれぞれにあったことが伺える。
その何かがわからないから何も起こっていない風に感じるのだと思う。
何もないようでも部員たちは日々何かに出くわし何かを感じて、そして時には動き出す。
そんなささやかな日々を抱きしめて離したくないと私は思った。
Posted by ブクログ
さらっと読むと、なんか懐かしい的な感想しか出てこない。そこがこの作家のすごさだと思う。こまやかな仕掛けがたくさんあって、その気になって読み込むと、ものすごく深い。系統としては『ねたあとに』と同系だと思う。
Posted by ブクログ
子供には子供の、中学生には中学生の、高校生には高校生の、同世代の中で暮らしてる中での独立した世界がある。今の世代を描いてるようで実はそうでもなくて。扱われる素材が違うだけなんだろう。懐かしいでもなく、ただ淡々と頷けた。
文庫版解説が堺雅人さんです…いい解説です。
Posted by ブクログ
高校の「図書部」を舞台にした物語。何か事件が起こるわけでもなく、個性豊かな部員たちの日常が淡々と描かれる。こんなふうに書くと、よくある(本当によくある)ラノベ的学園世界を想起してしまうけど、この小説が書こうとしている世界は、たぶんそれとは違う。
図書部の面々は、ゆるゆるとした毎日を過ごしている。部室でお茶を飲みつつダベり、漫画の貸し借りをして、「本来の」活動である図書室の貸出業務もおこなう。かつて文科系高校生だったすべての男女が「いいなぁ」と嘆息する日常がいきいきと描かれ、心地良いノスタルジーへと誘う。そして同時に、彼らがそのノスタルジーの奥底に沈めたものを呼び覚まし、ときおりヒヤッとさせたりもする。
教室の皆に自分が仲間はずれにされているのではない、自分が皆を置き去りにして仲間はずれにしているんだー(中略)そういう逆転の見立てを、部員のうちの気弱そうな何人かは抱いているように見える。(p.97)
「休憩休憩!」部室ではない、図書室内のテーブルで作業をしていた部員全員がほっとした表情。影の薄い浦田は黙って部室に向かった。(p.121)
教室に居場所のなかった自分。
そして、安息の地であるはずの文科系コミュニティーの中でさえ、上手く馴染めていなかった自分。
「ラノベ的な」日常ではスルーされがちな、文科系高校生の「苦さ」を、この小説は見逃してはくれない。もちろんそれは、作者が冷淡だからではない。自分たちの「苦さ」を痛いほどに噛み締めて、その上で笑ったり泣いたり悩んだり怒ったりする彼らに向き合おうとしているからだ。そのためには、彼らの「苦さ」にも向き合わざるを得ない。
現実では劣等感に苛まれ、フィクションでもまっとうに描かれない文科系高校生を文字通り「直視」しようとする誠実なまなざし。この小説の真価はそこにある。
と、かつて文科系高校生だった自分は思う。
Posted by ブクログ
この主人公は他人と深く付き合うのが苦手なのかもしれない
なおかつそのことに、自覚が薄いタイプなのかもしれない
だからこんなタイトルをつけられてしまったのか?
Posted by ブクログ
どこにでもある、誰にでもあった高校生活をそのまま切り取った日常作品
特に、何があるでもなく、登場人物も常識レベルで変わった人達ばかり。
しかし、見事に切り取られた高校生活には本好きなら必ず共感できる世界。
一人の女子高生が主人公で、その子の考え方が垂れ流し状態のストーリー。さっき下を向いてたのに、もう前を見ている、そうやってコロコロ変わりながらも少しずつ、少しずつ前に進んでいく主人公の精神。
ともすれば、本当にヤマもオチもない物語ですが、読んでいる間に何かつかめる。そんな作品です。
Posted by ブクログ
ジャケ買い。でも失敗じゃなかった。
図書部の面々のなんでもないようでなんでもあるような日々を主人公の視点から描いている。
語りが独特で、自分には歌の歌詞の様に思えた。好きなフレーズも幾つかある。
ヤマもオチもないが、何でか楽しめたことが自分でも不思議だったが、堺雅人さんの解説でシックリきた。
Posted by ブクログ
表紙の絵がどうにも好みでないのと、うーん高校生の部活の話かーとか思ってたのとでちょっと敬遠していたんだけど、読んでみたら、まったく違和感なく、おもしろく読めた。長嶋有が描く高校生だからかなあ。べつに高校生じゃなくてもいいというか、身分にかかわらず、共感できる。主人公の、じっと観察してて、あれこれ考えちゃうところが、だからって実際なにかするわけじゃない、っていうような感じがすごーくよくわかる。だれもが生きにくさをかかえている、っていうのも、なんだかすごくよくわかる。こういうのって、思春期にかぎらず、感じる人はずっと感じつづけることなのかも。なにかが起きてがらっとなにかが変わったりしないところもリアルな感じがしてよかった。それにしても、ともかく、高校時代こんな図書部があったら入りたかった!!やっぱり長嶋有の作品って好きかも。
Posted by ブクログ
解説につられて、初・長嶋有。
図書室がホームとなっていた高三時代を思い出して、ちょっとなつかしかった。だらだらしたゆるい青春小説のようでいて、メッセージも意外としっかり感じられた。「本はつまり、役に立つ!」
Posted by ブクログ
「皆、誰かに期待なんかしないで、皆、勝手に生きててよ。」
高校の、図書部のおはなし。
タイトルの「ぼくは落ち着きがない」は、むかし図書部にいた先生が書く、次回作のタイトル。
おそらく、図書室につながる両開きのドア(西部劇なんかにあるやつ)を擬人化して「ぼく」としているのではないだろうか。
私は、作中の先生が書いた同タイトルの小説を読みたい、と思ったのだけど、これを読み終わることでその願いはかなってるのか、なんて厨二みたいなこと考えました。
青春小説特有のかる~い会話劇が私はもんのすごく苦手なんだけど
長嶋先生はやはりセンスがあります。
滑り知らずというわけではないけれど薄ら寒くもない、あーわかるわかる、があるから安心して読めるんだ。
雑多に登場人物が出てきて
思い思いしゃべって
ときどき気になる人もいて
事件もことごとく地味、なんだけど、それがいい。
高校生の自分をおもいださせてくれるのが、青春小説の醍醐味かも。
Posted by ブクログ
主人公の望美ちゃんがとても好きだ。ひょうひょうとしていて、自分のいる状況を受け止めるのが上手だなぁ、と。
それにしてもこの作品は帯に学園小説と書いてある割には、他の学園ものほど劇的な展開や刺激的な出来事も起こらない。が、それが高校生のリアルだと思う。そうドラマチックな出来事なんてなくて、日々は胸がざわつくような小さな出来事の積み重ねだよなぁ…。
Posted by ブクログ
【本の内容】
両開きのドアを押して入るとカウンターがある。
そこは西部劇の酒場…ではなく図書室だった。
桜ヶ丘高校の図書部員・望美は今日も朝一番に部室へ行く。
そこには不機嫌な頼子、柔道部と掛け持ちの幸治など様々な面々が揃っている。
決して事件は起こらない。
でも、高校生だからこその悩み、友情、そして恋―すべてが詰まった話題の不可資議学園小説が文庫化。
[ 目次 ]
[ POP ]
ベニヤの壁で仕切られた図書室の奥の小さな空間を舞台に、図書部員の高校生たちの日々をゆるやかにかつ生き生きと描く青春小説。
友達が不登校を宣言したり部長と顧問が噂になったりドラマになりそうな出来事もあるけれど、変なあだ名や部室で飲むお茶、何気ない昼休みの会話の積み重ねこそが彼らを変えていく。
ひねりの効いた文体が楽しい。
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
図書部員・望美の視点が描かれる高校生の日常。とはいえ、登場するのは図書部員だけなので、非常に狭い世界だ。
そうだよなあと思うのが156頁。
この世の中の人は、誰もがただ会話するだけでも芝居がかる。即興で「キャラを演じる」。役割の中でボケたり、ツッこんだりもする。
誰もがテレビや本や、あるいは先人たちのふるまいや、それぞれの心の中に降り積もった情報を参照して、言葉を外部に発しているんだ。
上手にふるまえない人は、しんどい。当意即妙に冗談がいえたり、余計なこといわなかったり。「空気よめない」のは生きにくい。
Posted by ブクログ
高校の図書部が舞台の青春ストーリー。
図書部のメンバーは何となくクラスメイトと上手くいかない人が多く、さわやかな青春とは違う屈折した雰囲気が漂う日常が描かれている。
最後まで大きな出来事がないのに飽きないところが本書の魅力だと思う。
Posted by ブクログ
生きにくさと居心地について、丁寧にちょっと不思議に。
長嶋有さんの作品は初めて読みました。偉そうな言い方をさせて頂ければ、この作家さんはセンスがある。この作品が自分にどんぴしゃというわけではないけども。雰囲気のある希少価値のある書き手だと思いました。
Posted by ブクログ
確かに悪い意味で不可思議かも。
長嶋さんは元々盛り上がりの乏しい描き方をする人なのです。しかし、この小説の主人公は女子高生。舞台は図書部の部室で、登場人物のほとんどが高校生。少しは跳ねるのかと思ったら、やっぱり盛り上がりが乏しいのです。ネタとしては色々仕込まれているのですがね。どうも描き方が。。。
何を描きたかったのか良く判らなかった話でした。
Posted by ブクログ
図書の貸出等を行う図書部に所属する高校生達の淡々とした日常を描いた青春小説。
なんとも不思議な雰囲気の小説で、評価が難しいが、冷めているようでいて真っ直ぐな主人公のキャラクター設定には好感。
堺雅人氏による巻末の解説も、見事な切り口による分析で印象的だった。