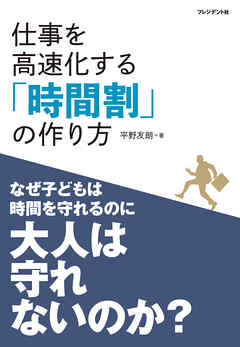あらすじ
なぜ子どもは時間を守れるのに、大人は守れないのか?
学校に通う子どもたちは、1日にさまざまな教科を時間通りにこなします。
開始時間になったら授業に参加し、終わったら次の予定に向かう。
それを可能にしているのが「時間割」。
大人にも時間割があれば、どんどん仕事が捗ります。
手帳、ノート、付箋、優先順位付け――、全部要りません。
本書の中でできそうなことを「自分ルール」として取り入れるだけで、あなたの明日が変わります。
【著者紹介】
平野友朗(ひらの・ともあき)
株式会社アイ・コミュニケーション 代表取締役
一般社団法人日本ビジネスメール協会 代表理事
ビジネス実践塾 主宰
筑波大学卒業後、広告代理店勤務を経て独立。メディア掲載1000回以上、著書26冊のビジネスメール教育の第一人者。
メールのマナー、営業力アップ、効率化を中心に官公庁や企業などでのコンサルティングや講演・研修は年間120回を超える。
ビジネス実践塾を主宰し、小規模事業者にマーケティングやブランディングのノウハウを提供している。
メールマガジン『平野友朗の思考・実践メルマガ【毎日0.1%の成長】』を発行。
【目次より】
◆プロローグ 「時間」と「お金」――どちらが大切ですか?
◆Chapter1 付箋を使うな
◆Chapter2 ノートを使うな
◆Chapter3 優先順位はつけるな
◆Chapter4 手帳を使うな
◆Chapter5 メールに時間をかけるな
◆エピローグ 0.1%の成長
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
プレジデントの年間契約をした際に、特典として本書が付いてきました。
たまたま手に入った本なので軽い気持ちで読み始めましたが、自分の仕事ぶりを見直すよいきっかけになりました!
仕事もプライベートもTODOリストを使うのが大好きなのですが、イマイチ効率が悪いのはTODOリストは備忘録であって時間の概念がないからだ、と当たり前のことに今更納得。
仕事に集中できる環境づくりと効率的な時間割の大切さを実感しているところです。
・仕事を予定通りに進めるために寄り道をしている暇はない。目の前の業務に集中する。パソコンに貼ったフセン、卓上カレンダーの主要スケジュール、デスクトップのファイル、デスクに置いた書類など、仕事にブレーキをかけるノイズ情報を撲滅しよう。
・他人の発言、カレンダー、メールなどから、あ!と思い出すことが多いということはすべきことを管理できていない証拠。思い出したタスクを実行するために他のタスクをずらすので効率が悪くなる。
・卓上カレンダーではスケジュールを一元管理できない。
・手順を決め、仕組みで回し、思い出す必要をなくし、考える対象を減らす。
・期限がないものは仕事ではない!時間管理のマトリックス(緊急度・重要度で優先順位を決める)は使わない、仕事はやるかやらないかだけ。優先順位もつけない、時間割に埋め込み、時間が来たらそれをこなすだけ。
・賞賛ラインで仕事をする。
・時間管理は投下時間を正確に見積もる、ピッタリの時間を把握する。すべての予定を書きだす。
些細な事を本書の言うとおり少しづつ素直に実行して現在10日程経ちますが、手応えを感じています。
よく考えたら家事だって、ルーティン作業は効率がいいし「洗濯機がまわっている間にコレを終わらせよう」と競争しながらやると早いもんね。
いつも忙しいのは自分のせいだな。
お仕事がんばろー!!
Posted by ブクログ
TODOリストとスケジュールアプリ(Googleカレンダー)との使い分け方は、参考になる。
現状、バレットジャーナルで、すべてのタスクをDAILY LOGに洗い出しているけれど、そこから実行に移さずに、また翌日に先送りしてしまうものが、毎日多数発生している。
習慣の時間割りを作って、実践し始めているが、まだまだ、仕事の前倒しにまでは至っていない。
継続していこう。
Posted by ブクログ
仕事の時間割をしっかりと作成したことがなく、自分の作業時間が曖昧であることに気がついた。早くやらなくてはという意識が強く、いつも時間や仕事に追われている感覚があるような気がする。
各業務の標準作業時間を把握するため、スケジュール策定、実際の作業時間の記録をつけるようにしたい。ただ、同一の仕事を続けられないため、メールチェック、声をかけてられた時の対応用に30%は空き時間を作るという意識も忘れないように。
Posted by ブクログ
★なぜこの本を手に取ったのか?
・残業カッコ悪いから。
・時間管理して自分の人生コントロールしている
実感を得たいから。
・漠然とした不安抱えながら仕事したくないから。
◯情報は一元管理する。
→Lifebearで全て管理するの試してみる。
◯同じメールは2回読まない。1回でいつやるか
判断する。
◯メール1通に15分以上かけてたらそれは仕事とは
呼べない。電話する。
◯時間を見積もるにはタスクを細分化する能力が
必要。
Posted by ブクログ
一つ一つのやることはそこまで難しくなく、取り組みやすい実践的な本だった。部署柄、突発的な仕事が入りやすく拘束時間も多いが、時間割を作って進めていきたい。
だらだら続く会議、不要な問いかけ、ひとまず長く働きますというスタイルの上司に読んで欲しいと思った。このままだと効率良く仕事して早く切り上げても、じゃあこの業務もお願いと業務量が増えていくだけ。
Posted by ブクログ
筆者の考えるタスク管理、時間管理の極意を紹介。
大まかにいえば時間、タスク管理は一元管理。徹底的な断捨離。できるものは極力マニュアル化。
ビジネスパーソンであればすでに実践している部分も少なからずあるし、筆者の職場環境目線なので、その違いにより実践できないものもあるが、それでも何かしらの参考になる部分はあると思う。
付箋やデスクトップのアイコンなどは備忘録のために使う人がいるが、実際は気が散って仕事の集中力を奪い、効率が起きる。携帯の着信音や振動も同じ。そのような「衝動的な反応」を回避する環境を整えるのが仕事の効率を上げる。
ウィルパワーとは何かを決定する時に消費する力。些細なことでもウィルパワーを使うので、マニュアル化できるものは徹底的にマニュアル化し、考えずに消化する。そうすることで重大な決断に要するウィルパワーを貯めておくことができる。
一例で靴下は一種類を複数持つことで左右を合わせる必要もなく、考える時間を削減できる。のような小さな事も徹底的にこだわっている。
Posted by ブクログ
忙しいのは時間の使い方が下手なだけだとし、
上手に使うための方法・心構えを綴った内容。
「称賛ラインで仕事をする」を意識してのタイムラインを設定すること、
「自分のアポを入れる」ことによるタイムマネジメントを徹底すること、
この2つをするだけでも、自分の仕事はかなり効率化され、生産性が高まる予感がする。
前半のツールの使い方は意見が分かれそうな内容ながらも、
後半のタイムマネジメントについては、全ビジネスパーソンにおすすめできる良い内容。
ワークライフバランスを気にしている方にも是非読んで欲しい1冊。
Posted by ブクログ
記憶ではなく、記録。頭の中ではなく、外に書いておく
①何をすべきか考えるから疲れる。あらかじめカレンダーにやることを入れ、隙間時間にやることを決めておく
・行動開始のハードルを下げるため、ルールを作ってルーチンで回せるようにする。
・悪習慣はやりはじめるまでのハードルを上げ、だらだらするなら、あらかじめ決めてだらだらする
・気の散るものは視界に入れない。距離をとる。使わないものは捨てる。
②相手を催促しないのは、自分の時も見逃してくださいと自分を甘やかしている証拠。
・期限を守らないと謝罪のための無駄な時間が発生する。前倒しの期限を決めて対応する。
・相手が求めているより、+5点の結果を出せば良い。過剰な品質を求める時間を他の仕事をする時間にまわす
・仕事の評価は期限と質で決まる。同じ提出するなら相手から称賛される期限に提出
・時間の決まっていない仕事はない
③余裕がないなら余裕を持てるようにスキルアップを図るべき。自分の容量を増やさないと歳を取る意味がない。
・給与の2倍稼いで会社の収支はトントン。3倍稼がないと貢献にならない。
・毎日の成長のために、昨日と今日を1%変えてみる
Posted by ブクログ
新たな気づきというよりも、今まで感覚的に心がけていたことを、整理整頓してもらった感じ。その意味で読んでよかった。
「賞賛ライン」は実際にやってはいるが、それをこうしてネーミングされることで、今後より意識的に実践することができる。
Posted by ブクログ
子供は時間を守れるのに、なぜ大人は守れないのか 帯に惹かれて購入。
時間割で決められていた子供時代は、
宿題等期限があれば前倒しして基本遅らせることのなかったよい子だった。
やる時間はこうと決めていたわけではないが、
タスクの量が少なかったので、それでも何とかなった。
社会人となり、タスク自体は質・量ともに増えたとも言い難いが、
教師にいつやって、ここまでの成果 という導きがなくなって、
子供の時よりインプット・アウトプットが減っていると実感した。
これではいけない。
少しでも掲載されている、工夫等を取り入れ、
少なくとも退化から現状維持にならなくては。
プライドにかけてでも
Posted by ブクログ
自分の仕事の能力(容量)はコップ。コップを大きくし、あふれる前に対処するためには、意識と行動を変える必要がある。どのように行動していくのがオススメか、筆者の経験談をたくさん紹介してくれているので、小さなことから真似しやすいと感じた。また、何のために時間管理の本を手に取ったのか、自分の気持ちと向きあうきっかけにもなった。
効率的に働き、自分のための時間を捻出し、有効活用して未来を変えよう。その為に0.1%でいいから行動を変えて、小さな成長を積み重ねていこう。
Posted by ブクログ
「グーグルカレンダーを活用しましょう」という本。時間割を作る=作業時間を見積もる、やろうやろうと思いつつできてなかったけど、やっぱりやらないとあかんな。あとなんでも期限を意識すること。「そのうちやる」では確かにできない。
Posted by ブクログ
著者の平野友郎氏は、広告代理店を経て独立された方。
感想。
自分にとっては新たな発見は少なかったが、若手に読ませたい。
備忘録。
・考える必要のないものは考えない、悩まない、行動に集中。
・例えば、ルールを決めてしまう。○○が起こったら××をする、と決めておく。メモは○○でとる、△△がなくなったら××を買う、とか。
・何かを考え、決断する時には、結構なパワーを消費する。
・仕事はデッドラインではなく、賞賛ラインで取り組む。
・期限を守らない人には、期限の前に進捗確認をする。
・Googleカレンダーを活用して、自分の行動計画を時間単位で作成する。
・行動計画には、投下時間を正確に見積もるのが重要。これは訓練。自分の行動を記録することで。
Posted by ブクログ
すでに実施していることが多いなと感じた。ビルドのちょっとしたすきま時間にメールを読むとか。社会人を何年もやっていると自然と効率化して時間を捻出しようという考えになるものなのかも。相手との関係(心理的な近さ)によってメールのチェック度合いを変えるべきという話では、そうか、履歴書や謝罪文なんかは距離が遠いから誤字脱字があっちゃいけないのだなと思った次第。
Posted by ブクログ
(期限設定は)賞賛ラインで仕事する、1.4倍で見積もる(という自分なりの基準)、1日30パーセントは(余裕として)空けておく、「緊急」「重要」のタスクをやるな!とのアドバイスが参考になった。
Posted by ブクログ
主題の「時間割」についての記載はそう多くない
それよりも、総じて時短や効率化を図る、筆者の仕事術の本
<実践したいこと>
・今日の時間割を完璧にしてから一日をスタートさせる
Posted by ブクログ
マルチタスクを実現する上で、1日を時間割にしてしまおうという考え方はシンプルながら、取り入れやすいと思った。
一つの活動の単位は1〜2時間程度で、それぞれ飽きる前に終えていく。そうすることでフレッシュな刺激をたくさん得られる気がした。
卓上をスッキリさせようというのも良かった。カレンダーやサンプル、デスクトップのアイコンを減らしたところ、頭と心がスッキリした感覚があった。