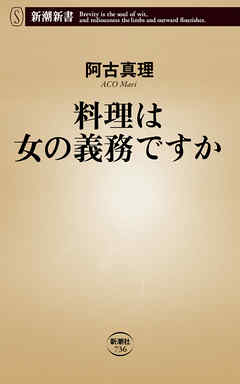あらすじ
「昔から苦手」「とにかく時間がない」……それでも家族のために気力を奮い立たせて、毎日台所に立つ女性たち。一体、どうすれば料理への苦手意識を克服できるのか? その歴史をひもとき、「スープの底力」「楽しい保存食」「便利な常備菜」といった先人の豊かな知恵に今こそ学ぼう。女性の社会進出と現代の台所事情、「一汁一菜」より大切なこと、料理がつなぐ人間関係など、好きな人も苦手な人もあらためて考える料理論。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
料理は女の義務ですか。阿古真理先生の著書。料理が女性の義務であった時代はとっくの昔に終わっています。女性の社会進出が進んでいる今の時代で女性が料理下手、料理苦手であっても恥じることはないし、非難される理由もありません。それに料理は男性も女性も義務感でするものでなく、料理をしたいと思う人が前向きな気持ちで楽しくすればいいもの。
Posted by ブクログ
書名に心のなかを見透かされたような気がして、ドキっとしながら手に取る。
本書は、作家であり生活史研究家である著者が、家庭料理を主に女性がどのように担ってきたか、歴史をふまえながら論じた本である。
史実やインタビュー、文献引用が非常に充実している。
冷静で淡々とした語り口も良い。
特定の価値観や主義主張を押しつけるようなことがほとんどないので、落ち着いて読め、一冊を閉じるころには、現代の食卓がいかに複雑な歴史と価値観が混在する結果になっているかが、自然と頭に入るようになっている。
読みながら、ふと今の私が生きる社会って、料理に対する「こうあるべき」や「こうしたら良い」という情報は溢れる一方で、残業をともなう仕事をもつ人間が現実的にどう料理することが「正解」なのか、実は答えが用意されていないんじゃないか、ということに思いいたる。
試しに私の中の漠然とした「良い料理」のイメージを、思いつくままに挙げると、
1.手作りである
2.手間をかけずに作っている
3.手間をかけて作っている
4.加工食品を上手に取り入れる
5.なるべく素の材料で料理するのが良い
6.農薬とかも気になる
7.食費は上手に節約するのが良い
8.やはり母の作っていた食卓が理想である
9.とはいえ、専業主婦の時代が長かった母と、仕事についている私とでは生活が違いすぎるから、それ相応になんとかしないと
etc.
って、矛盾だらけで、こんなの全て満たす正解なんてあるわけがない!(笑)
そもそも、長いあいだ実家暮らしをしてきた私の料理の腕が足りないし!
全く余談だけど、この本を読んでいたお正月休み、二人家族の夫と同時にインフルエンザをわずらい、家庭が閉鎖する目にあった。
少し体調が回復してきた日、とにかく水炊き鍋だけ作ろうと、白菜をざくざく切って湯気の上がる鍋に入れていたら、体は辛かったが料理できることがしみじみ嬉しかった。
料理は生きる権利である、と著者はいう。
うん、料理は女の義務ではなく、大人の権利だと思う。
そして、働く人誰しも、毎日簡単なご飯をつくって食べられる生活を送れるような社会を設計することが、大人の義務なんじゃないか。
少しずつでも、そんな社会になればいいのになと思った一冊でした。
Posted by ブクログ
期待はずれ。星2、にしようか迷ったけど、ま、三でいいや。
男が女とかではなく、そもそも人にとって社会に取って、食事とはどういう意味があってどれほどのインパクトかあったかを説く。いんじゃないか。
ま、読みたいのはそういう話でもなかったし、文章が下手で読み辛かったのはあるけども、なるほどの視点は感じた。
家庭における食事、料理、特に日本での展開なんかは面白かったな。エポックメイキングになる、どの本だとか、どの料理研究家のこのところってのは、新鮮な感じで良かった。
が、俺が男だからか、なんかやっぱりクソ感感じた。
最後、土井善晴の一汁一菜のススメの批判は、ゲロかったな。
ご自身が先に提案していたのに土井先生が有名だったから話題になった。提案自体には共感するけども、今更つけもんはないし、母の愛情を料理に乗せろっていうかと。
そんなこと言うてへんやん。
むしろ、立派な料理することができなくて悩んでいる人に、こんな程度でいいんですよ、こう言うことでも、もし、悩んでいるんなら、十分に愛情って伝わりますから。
そう言う本だったと思ったんだけど。
ユングじゃないけど、理に硬い女子ってのは、面倒臭くなるもんかね。
ま、そりゃ、恵まれた料理研究家と、毎日忙しくて、カップ麺用意するだけの家庭があることの違いもありますがね。
あの本読んで涙が止まらなかったって言う声は、女性からじゃないのかね。
あ、なんの本の評だっけ。
Posted by ブクログ
新書ならではのタイトル詐欺? いや、でも結果オーライの料理の歴史。
--------
料理は女の義務ですか。違うと思う。だがこのタイトルはもっと違うと思う。
目次からいくつか抜き出してみる。
スープの底力
味噌汁の誕生
世界の保存食
趣味化した料理
などなど。
オチを言ってしまうと、日本で性別役割分業による効率化の時代は終わった、とされているから、タイトルに対する答えもノー、であろう。
だが本書のほとんどは(まあ、歴史を知らずに未来を語れない、としても)、料理の歴史である。タイトルからすれば思わぬ誤算だが、僕自身はそっちのほうが好きであるから、これもまた思わぬ誤算なのだ。
僕んちではすでに料理は女の義務でなくなっているが、それを次代に継承できるかというと、必ずしもそうとも言い切れない。世の中、という姑は、やはり依然、古風な女であれ、というプレッシャーをかけてくるのだ。そういう姑は、悲しいかな僕の中にもいる。それに抗っているのが楽しいのだ。
料理は生きる権利でもある、としている。「健康で文化的な生活」には、それをする余裕を与えることも含まれるはずだ、と。そして、多忙故に料理をしない人を責めることもしない。ただ当人たちが「料理する権利を返せ」というべきだと。僕もそう思う。
いい加減、存在しない幻想を人に押し付けるのはやめて、楽しみたい人は楽しめばいいではないか。
ところで、女の義務、としていない世代として、切実でやむを得ず台所に立つシニア層と、家庭科教育を受け、自然に料理をする20〜30代、という人たちがいるようだ。僕はちょうどその中間層にいるのだけど、この世代の男は、単に厨房から遠ざけられていたから関心がないだけではないか、と。いったんハマると豊かな世界に目覚める、と。
あはは、そうかもね。目覚めた者談。こんなに面白いことを誰かに独占させてたまるか。