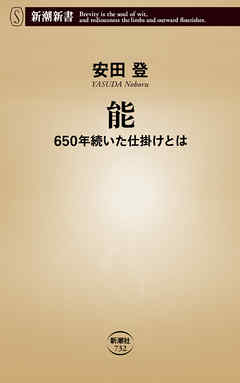あらすじ
なぜ650年も続いたのか――。足利義満、信長、秀吉、家康、歴代将軍、さらに、芭蕉に漱石までもが謡い、愛した能。世阿弥による「愛される」ための仕掛けの数々や、歴史上の偉人たちに「必要とされてきた」理由を、現役の能楽師が縦横に語る。「観るとすぐに眠くなる」という人にも、その凄さ、効能、存在意義が見えてくる一冊。【巻末に、「能をやってみたい」人への入門情報やお勧め本リスト付き】
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
能楽を初めて観たとき(最近の話です)、舞台の緊張感がすごく気持ちよくて、なんだかハマりそうな予感がしました。
主役(シテ)と脇役(ワキ)と各種囃子方はそれぞれ違う流儀の人で、演劇のような事前のリハーサルや練習はないと書いてあるのを読んで、ほんとうにびっくりしました。囃子方は伴奏ではないので、謡の間は聞こえるように音を小さくしたりもしない、というくだりもびっくり!
日本の古典芸能なのに(というのもへんですが)、忖度とか全然ないんですね!
あの潔いまでの緊張感の意味がわかった気がしました。
Posted by ブクログ
良書。
思ったより面白かった。
世阿弥の偉大さ、豊臣秀吉の影響。時のお金持ちが芸術を育てる。
能は見る人の想像力を要する。小説と同じだ。知識と人生経験がないと楽しめないのかも。
Posted by ブクログ
安田登(1956年~)氏は、大学卒業後、高校教員を務めていたときに偶々観た能の舞台に衝撃を受け、27歳で下掛宝生流ワキ方の鏑木岑男に入門。国内外の舞台で能を演じつつ、学生の創作能や能についてのワークショップ等、能楽の普及のための幅広い活動に参加している。能や能のメソッドを使った身体論等に関する著書多数。
本書は、能について、歴史、様式・形式、観阿弥と世阿弥、謡(うたい)、芭蕉や漱石への影響等、幅広い視点から解説したもので、目次は次の通り。
第一章:能はこうして生き残った、第二章:能はこんなに変わってきた、第三章:能はこんなふうに愛された、第四章:能にはこんな仕掛けが隠されていた、第五章:世阿弥はこんなにすごかった、第六章:能は漱石と芭蕉をこんなに変えた、第七章:能は妄想力をつくってきた、第八章:能を知るとこんなにいいことがある、<付録>「能を観たい、習ってみたい、知りたい」方へ。
私はアラ還の会社員で、これまで、演劇の類はオペラやミュージカルを観たことはあるものの、日本の古典芸能に接したことはなかったのだが、コロナ禍が明け、思い立って、能楽、歌舞伎、文楽(人形浄瑠璃)を立て続けに見てみた。結果として、いずれについても、今後も継続して観たいと思うほどの面白さは感じられなかったのだが、折角の機会なので、「能」のことをもう少し知りたいと思い、本書を手に取った。
読み終えて、舞台を一度見ただけでは到底想像のつかない、「能」という単独の芸能を超えた、様々な歴史や文化との繋がりを知ることができ、なかなか興味深かった。印象に残った点をいくつか挙げると以下である。
◆観阿弥・世阿弥が残した最も有名な言葉「初心忘るべからず」の真意は、「それを始めたときの初々しい気持ちを忘れてはいけない」ではなく、「折あるごとに古い自己を裁ち切り、新たな自己として生まれ変わらなければならない」ということであり、能が650年間も存続できたのは、時々に変化し、生まれ変わってきたからである。
◆能の典型的なパターンのひとつに、ワキ方の夢の中に死者の霊のようなシテ方が現れる「夢幻能」があるが、これは他の演劇にはない珍しいもので、敗者の無念を昇華させ、鎮魂するという意味があった。それは、勝者である江戸幕府が、能を庇護した理由のひとつでもあった。また、芭蕉も能の謡から影響を受けており、「おくのほそ道」の旅は、源義経の鎮魂と考えることもできる。
◆世阿弥が残した能の理想的な構造である「序破急」によれば、「破」の場面では、観客が半分目を開けながら寝るくらいにしておいて(観客の心の深いところに降りていく)、「急」の場面で目を覚まさせるくらいがよい。(これは驚き!確かに眠かった)
◆能は、舞台は極めて簡素であり、演者の動きも控えめで、話している内容もわからないことが多く、演劇としてリアルであるとは言い難い。しかし、それによって、観ている人は能動的にならざるを得ず、今見えていないもの(自分の脳内に蓄積されているもの)が見えてくることになる。謡も、それを媒介する効果がある。能を本気で味わうには、「能を観る」ではなく、「能と共に生きる」心構えが必要。
◆能のクライマックスは「舞」であるが、舞に「意味」はなので、そこから意味を汲み取ろうとしたり、ストーリーを感じようとすると、途端につまらなくなる。舞のゆっくりした時間の中に身を委ね、味わうのがよい。(これも驚き!)
(尚、能を観たり習ったりすることの直接的・現代的な効果(健康増進、集中力アップ、ストレス解消等)についての記述もあり、それらは新書の主たる読者層であるビジネスマンを意識したものであろうが、少々違和感が残った)
もう少し知識をつけた上で、再度鑑賞してみようという思いが湧いてきた。
(2024年2月了)
Posted by ブクログ
著者は、初めての能で「松風」を鑑賞中、水面に浮かぶ月の風景を幻視してから能にハマり、能楽師にまでなられた方。私も初めての能で、著者までではないが、鑑賞中時間を忘れてトリップした経験があり、能は従来のエンタメとは何か本質的に違うのでは、と思ったことがあったので、興味深く本書を読めた。
入門書に相応しく、能楽の歴史や、特徴や仕組み、効能などがカバーされていた。特に興味深かったのが、漱石や芭蕉、三島由紀夫や村上春樹などの現代の作家や漫画家の作品に見られる能からの影響。それら影響を受けた作品を改めて読んでみたくなった。
最も印象的だったのが、現代の映画などを私たちはお金を払って「消費」する感覚で鑑賞しているが、能は消費の対象ではないという事。映画などは鑑賞側の能動性が求められず、あくまでも受け身であるため「消費」となるらしい。逆に能は「観る」のではなく「能と共に生きる」心構えが必要で、そのために詞章(セリフ)を声を出して読んだり、謡や仕舞を稽古したり、聖地巡礼をすると妄想力が鍛えられ、能の見え方が変化するらしい。なかなかハードルが高いが、能は限られた要素を使って鑑賞者の妄想力を刺激し、幻視を発動させる装置とも言え、今のARやVRにも通じるものらしく大変興味が湧いた。
Posted by ブクログ
世阿弥の風姿花伝で能に触れた後、能のことをより勉強したいと思い購入。
面白いなと思ったのは世阿弥の「初心忘るべからず」という言葉の解釈である。本来は物事を始めたときの気持ちをずっと忘れるなととらえられがちだが、本来世阿弥が意味した意味というのは「折あるごとに古い自己を断ち切り、新たな自己として生まれ変わらなければならない」ということである。これは知らなかったため、「はぁ~」と勉強になった。実際、室町時代の能と幕府に保護され式楽となった江戸時代、明治時代以降、戦後と4つのフェーズで能は大きく変化しており、形を変えながら生き残ってきたのはまさにその「初心忘るべからず」を体現してるなと感じた。
また、江戸の武士の中で能は教養として身につけなければならないものであり、「候文」が武士間で使われていたのは、それが標準語となっていたからというのも面白かった。能を知っていることが前提で、方言同士では話し合えないため、候文が使われていたとか。
さらに、現代で通ずる話では、現在の2.5次元との相関性(能は妄想を映し出すスクリーンとなるとか)がある。
人気になる芸能は妄想を喚起させる力が強く、そこでは歌の力が強い。現代に通ずるなと納得。
また、聖地巡り(能で演じられた舞台を実際に旅するとか)も当時からあったと書いてあり、昔も今も人間の本質って変わっていないんだなと実感した。
温故知新ではないけど、過去の歴史のことも勉強して抽象化して、現代で起こりうることを予想することにもっと役立てたい、そう実感させてくれた。
Posted by ブクログ
著者自身がワキ方の能楽師でいらっしゃるため、「能というのはこういうものだよ」とレクチャーしてもらえる内容ですが、観劇を始めたばかりの現時点では「そうか、そういうものか」と知識として受け入れる状態です。
しかし、観劇の回数が増え、能の謡を習ってある程度年数が経った後にこの本をもう一度読めばより腹落ちするのではないかと思える、自分の能楽の経験値を測れる本のような気がしました。
内容として特に興味をそそられたのが、主人公の武士が修羅道や地獄に堕ちるストーリーの多い能を江戸幕府が庇護した主目的は「敗者の鎮魂」であった、そして幕府から与えられた鎮魂、それも「源義経の魂を鎮める」というミッションが芭蕉のおくのほそ道にはあった、というのは話 。
後半のミッションの話は著者の仮説ですが、読んでいるとあながち間違っていない気がしてかなり興味深い内容です。
芭蕉以外に能を習っていた文人は近代にも多くいたようです。特に漱石の作品には能の影響が色濃く出ているものがあり、中でも主人公が旅に出る『草枕』は「能を通して世の中を見る」という『おくのほそ道』と似通った設定(芭蕉は自身を能のシテ方と設定して旅をした)で物語が進みます。
かねてから太宰や漱石などの近代文学作品を読んでみたいと思いつつ、どうも食指が動かなかったんですが、これを機に『おくのほそ道』と合わせて『草枕』『夢十夜』から読んでみようと思います。そしてこの本同様、年を経て能の経験値が増えた時にもう一度読み返したいと思います。
Posted by ブクログ
「能」の魅力をふんだんに説かれて、すっかり興味を持ってしまった。チケットも買いました。鑑賞後、感動してもっと好きになるか、意味がわからず疎遠になるか、確かめてみます。
Posted by ブクログ
現役の能楽師である著者による「能」についての解説本。
650年間も日本で愛されてきた能の歴史、他の伝統芸能と比較した能の特徴、後世の文化や作品に与えた影響についての解説が主な内容。
あっさりとした文体で、読みやすかった。
能は、今から650年前の室町時代に、観阿弥・世阿弥父子が大成させてから現在に至るまで、一度の断絶もなく上演され続けてきた。
それは単にエンタメとして魅力があっただけではなく、長い歴史を必然とした能の仕組みがある。
「免状」「披き」「家元制度」などがこれにあたる。
特に「披き」という考え方が興味深かった。
自分の実力ではできそうもない演目を「やってみろ」と、師匠に命じられるのが「披き」である。
ピアノやバイオリンのように、技巧的に不可能ではないので、やれといわれてできないことはない。しかし、やるほどに自分にはできないと確信してしまう。
我武者羅に稽古する。そして、無我夢中で舞台を勤める。そうすることで、人は新たな自分(初心)を迎える。
これは現代でいうところの「タフ・アサインメント」であり、有能なコーチが使う技術だ。
能は意図的にこれを繰り返すことで、能の歴史を引き継ぐことができる優れた能楽師を育ててきたわけである。
また、世阿弥が完成させた「夢幻能」は、生きている人のみが登場する「現在能」に対して、主人公が謎の人物として現れ、一度消える。その後、本来の霊的な姿で再び現れるという能独特の構造であるが、これは後世の作品にも受け継がれているという。
三島由紀夫の『豊穣の海』、夏目漱石、夢野久作、村上春樹などがこれに当たる。
これまで能というものにまったく触れることがなかったが、本書を読んで理解を深めることができた。
長い間、日本人がトップマネジメントのための芸能として使ってきた能の優れた仕組みは、現代のビジネスにおいても有用な示唆を与えてくれる。
Posted by ブクログ
「100分de名著」で安田登氏が講師でらせん訳の源氏物語を9月現在やっているが、第一回目からとても面白かった。元は高校教師、代理で能を見に行って開眼し能役者になった、という経歴を知り読んでみた。安田氏が体得した能をかみ砕き説明してくれる。最近は能、謡、鼓にとても興味が湧いてきているのだ。
メモ
能の効能
1.「老舗企業」のような長続きする組織づくりのヒントになる ~「初心」と「伝統」である。世阿弥・観阿弥の言葉「初心忘るべからず」は、「初」=まっさらな生地に、はじめて刀(鋏)を入れることを示し、「折あるごとに古い自己を断ち切り、新たな自己として生まれ変わらなければならない、そのことを忘れるな、という意味
2.80代、90代でも舞台にたっているほどなので健康長寿の秘訣がある ~能の曲の詞章(曲の中の文句)を節をつけて謡う「謡」や、重心を落として歩く「摺り足」という独特の身体技法を使う。
3.不安を軽減し、心を穏やかにする効能がある ~信長は「信長公記」によれば、桶狭間の戦いの前に「敦盛」を舞った。それはストレスを行動エネルギーへと変換するための術だった。それを可能にするのは強い呼吸を伴う謡と、自分の陰陽を整える舞の動きだ。
4.将軍や武士、財閥トップが重用したように、政治統治やマネジメントに有効 ~江戸時代、武士のたしなみは能だった。「エリートによる、トップマネジメントのための芸能」だった。
5.夢幻能の構造はAI(人工知能)やAR(拡張現実)、VR(仮想現実)など先端技術にも活かせて、汎用性が高い ~能は「現在能」(生きている人のみが登場)と「夢幻能」(旅の僧などのワキが名所やいわれのある場所を訪れると、主人公であるシテが謎の人物として現れその土地に関連する話を始める)に二分される。AIなど最先端の技術を研究している人人はこの夢幻能の構造を含め、能に注目している。
・敗者のための能を守ったのは「勝者」 ~能の主役は敗者の立場の幽霊だというのが常。敗者の魂を鎮める意味が大きかった。
・現在演じられている能は、南北朝から室町時代にかけての、世阿弥の前後に作られたものがほとんど。江戸時代に式楽化されると新作はあまり作られなくなった。時事的な新作能を何度も上演する機会は少なく、室町までのものを繰り返し上演する過程で様式美を収斂させてきた。現行は二百数十の演目に落ち着いた。5つに分類される。
・「神」シン ~神をシテ。初番目物、脇能物。神様が登場して世の中を言祝いだり神社の演技を伝えたりして颯爽と舞う内容
・「男」ナン ~男性をシテ。二番目物、修羅物。主に『平家物語』に出てくる武将が、戦いで命を落として修羅場に堕ちた苦しみを描く。
・「女」ニョ ~女性をシテ。三番目物、蔓物。優雅で美しく、動きが少ないので、演者の力量が問われる。幽玄な至芸。
・「狂」キョウ ~四番目物、雑能。ほかの4つにはいらないもの。狂女がシテの能が多いので「狂」と呼ばれる。
・「鬼」キ ~五番目物、切能。番組の最後に演じられることが多い。鬼や妖怪、お酒の精、霊獣などがシテ。
※この五番に入らないのが『翁』。もとは「翁猿楽」と呼ばれ、エンターテインメントとしての能に対して、ストーリー展開もなく、天下泰平を祈る新生で儀式的な曲。秦河勝が作ったという猿楽のお家芸。
・正式な能の上演順序 『翁』を最初に置き、神から鬼の順に上演しながら、能と能の間に狂言を演じ、最後に縮減の短い能を演じる
・能面 能面はそれだけでは何も立ち上がってこない。優れた役者がかけたときに、本来の力を発揮する。
・能の目的は「変身」 ~能には神懸り的な要素があり、変身とはまさに神懸りであり、能面は憑依を可能にするための装置。
・世阿弥の功績 ~必ず継いでゆくという意志を、個人の責任に帰すのでなく、システムとして能の中に取り入れた。名人でなくても、誰しもがある程度のレベルを維持でき、次世代に能をつないでいける、それを「伝統」とした。家元制度もそのひとつ。実子とか血縁とか、そういうこと以前に、まずは「継ぐ」ことを最優先する。それを大切にしたからこそ現在の能がある。
・「稽古は強かれ、情識はなかれ」 ~「古」は「固」で歴史の波に現れてもまだ、ここに存在しているもの。能では世阿弥・観阿弥以来の謡や型。その型を自身の身体でも実現できるよう研究努力することが「稽古」。「情識」は争う心、慢心、迷い。
・世阿弥のすべては「花」にある ~世阿弥の功績は、現代にまで上演される能を数多く書いたことと、多角的な芸能論の執筆。「花と面白きと珍しさと、これ三つは同じ心なり」 花は何にもまして肝要。 面白きは目の前がパッと明るくなること。 珍しさは愛らしいこと。まったくふつうのことの中に「あわれ(ああ、という感嘆)」を感じさせる工夫。
・能舞台は「見えないものを見る」装置
安田登:1956千葉県銚子市生まれ。下掛流能楽師。ワキ方。
2017.9.20発行
Posted by ブクログ
観賞する機会があったので、お能について詳しく知りたくて、ストレートなタイトルのこの本を手にした。著者は言わずと知れた安田登先生。お能がなぜ650年もの間、途切れることなく続くことができたのか、その理由に迫っていく。お能の演目や観賞法、歴史など、いわゆる王道の入門書を期待した人にはおススメではないかも。
他の方も書いておられるが、私も印象に残ったのは「初心忘るべからず」の本当の意味。古い自分を裁ち切り、新たな自己に生まれ変わる。それを時々、老後と絶えず繰り返すということ。能楽師はもちろん、お能という芸能も、自分を顧みて、変化して、伝統になった。深い。