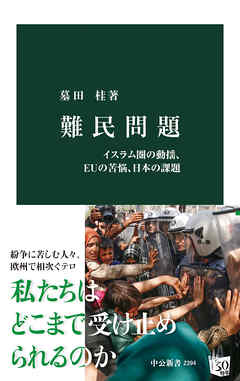あらすじ
シリアなどイスラム圏では紛争が続き、大量の難民が発生している。2015年9月、溺死した幼児の遺体写真をきっかけに、ドイツを中心に難民受け入れの輪が広がった。だが同年11月のパリ同時多発テロ事件をはじめ、欧州で難民・移民の関係した事件が続発。16年6月、EU離脱を決めたイギリス国民投票にも影響した。苦しむ難民を見過ごしてよいのか、だがこのままでは社会が壊れかねない。欧州の苦悩から日本は何を学ぶか。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
難民問題
イスラム圏の動揺、EUの苦悩、日本の課題
中公新書 2394
著:墓田 桂
紙版
本書は大きく3つに分かれる
1 難民とはなにか 古代アジア、古代の日本を含めて、難民そのものにものさしをあてる
2 2015年シリアを中心とするイスラム圏から欧州への難民の動き
3 難民政策を考える
気になったのは、以下です。
・難民の受け入れに積極的だった、メルケルは、シリア人からは、「慈悲深い母」と称えられていた
・世界各地の情勢が厳しさを増すなか、難民の流出はやむところをしらない
・自国の安全、社会の安寧、国家の財政を考えた時、「他者」に対して無制限に善意を示せる状態にはない
■難民とはなにか
・ユダヤ人は、離散の民として知られる
・大昔に世界に散らばった難民だが、民族が離散する際にも、国内で難民化を経験している
・昔のシリアでも難民は発生していた 636年ビサンツ帝国の支配下にあったシリアノダマスカスは新興のイスラム勢力に降伏した
・百済の同盟国であった日本に百済から難民がわたっていった。かれらが日本の国土防衛に貢献し、律令制度を伝えた
・フランス王国のプロテスタントであるユグノーは、ルイ14世の迫害を逃れるために国外に逃れていった
・イングランドからアメリカ大陸に渡った、ピルグリムファーザーズも、新教徒として迫害を受けた、難民といえる
・ロシア革命の避難民も日本に来ている
・杉原千畝のユダヤ難民へのビザ発行
・朝鮮戦争以前の43事件での韓国からの密航者の受け入れ
・ベトナム難民の11,319人の受け入れ 1,407人が日本に帰化
・現在の難民保護の枠組みは、第2次世界大戦後に作られた。国際連合の難民高等弁務官事務所(UNHCR)である
・難民申請者を保護しようとしても、UNHCRは保護の基盤となる領土をもたない。
ある国が別の国から逃れてきた難民申請者を保護することができるのは、領土をもっているからである
これを領域的保護という
・難民条約 1951年に難民の地位に関する条約が調印された
・UNHCRと難民条約が現在の難民支援の国際的枠組である
・難民条約に加入している国家はどのように難民を保護するのだろうか
申請者が難民か否かを決めるのが一般的だ。難民条約に加入している日本も同様である。
この手続きを、難民認定という
・条約難民の地位を認めない場合でも、申請者になんらかの保護を与え、在留を認める場合がある
これは、一般的に補完的保護という
・難民条約では、難民の生命や自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境に追放したり、送還したりすることは禁じられている
・人道危機とは、人々の普通の生活が失われ、無辜の人命が失われる状態をいう
■イスラム圏
・タリバン 学生たちを意味する 元々はパキスタンにいたアフガニスタン難民から生まれた組織
・アルカイダ 基地を意味する サウジアラビア出身のウサマ・ビン・ラディンがアフガニスタンを拠点につくったテロ組織
・EUへの非正規移動については、シリア、アフガニスタン、イラクの出身者が上位を占めている
難民化の現象はこれらの国にとどまらず、ソマリア、イエメンといったイスラム圏でも発生している
・2015年アフガニスタンの国内難民は、1,174,000人、2015だけでも 330,000が新たに難民化した
・2015年国外にいるイラク難民は、261,107人、加えてイラク人の難民申請者は、237,166人である
・イラクの国内避難民の数は難民の数をはるかに上回っている
2015年時点で国内避難民は、3,290,000人
イラクの国内避難民が発生した背景は、①サダム・フセイン時代、②イラク戦争後の混乱、③ISの台頭である
・シリアでは2016年2月までに内戦の犠牲者は270,000人、国内避難民は6,600,000人と推測されるが、実数の把握は困難を極める
・シリア難民の在留先の内訳は、トルコ2,503,549人、レバノン1,062,690人、ヨルダン 628,223人、イラク 244,642人、エジプト 117,635人 欧州にもおり、ドイツ 115,604人、スエーデン52,707人 (2015年末)である
・トルコは難民の最大の受け入れ国
シリア難民 2,503,549人、イラク難民 24,135人、アフガニスタン 3,846人
・ヨルダン パレスチナ難民 2,110,000人、イラク難民 400,000人、628,223人のシリア難民を受け入れている
・元来、イスラム世界には自由喜捨(サダカ)や、アラビア的な概念である連体意識(アサビーヤ)など人道行動を促す理念や義務がある
・サウジアラビア、クウェート、UAE、カタール、バーレーン、オーマンなど、湾岸産油国は積極的に受け入れ態勢を示していない。
■EU
・2015年EUに流入した非正規移動は 1,000,000人を超えた
・1990年代初頭、ユーゴの解体に伴って発生した武力紛争で、クロアチア、セルビア、ボスニア・ファルツェコヴィナにおいて難民が発生し、600,000~800,000は欧州諸国に逃れた
・EUへのルート
①東境界ルート(ウクライナ⇒スロバキアルート)
②バルカンルート(陸路)
③東地中海ルート(海路・トルコ⇒ギリシャへの最短ルート)
④ブッリア・カラブリア・ルート
⑤中央地中海ルート
⑥西地中海ルート
⑦西アフリカ・ルート
・ドイツ 非正規移動者の理想の目的地
EU域内では経済が好調
ナチスドイツ時代からの反省で難民政策が手厚い
・ハンガリー バルカンルートに位置する
フェンスによりブロック
・オーストリア バルカンルートに位置する
国境管理方針に転換、フェンスによりブロック
・スロバキア オスマン帝国侵攻に苦しんだ過去からイスラムを拒絶
・EU域内の移動 ダブリン規則、シェンゲン協定により、シェンゲンビザがあれば原則自由
EUの制度には、独自の法体系があり アキ・コミュノテールと呼ばれる
EU加盟国は、これを遵守する義務がある
・EU成立への制度史
1957 ローマ条約 欧州経済共同体設立条約
1967 ECへ編入
1992 マーストリヒト条約 欧州連合条約
1993 12加盟国でEUが発足
1997 アムステルダム条約
2007 リスボン条約
・EUが抱えている難民問題
①難民申請
②難民不認定の場合の強制送還
③難民不認定者で刑事案件の対象となった者への対応
④160,000人の非正規移動者の移転計画の実施
⑤EU内の国境封鎖に伴う前線国の扱い
⑥EU域外からの難民の再定住
⑦難民認定された人々の社会統合
⑧難民の家族の呼び寄せ
⑨EU域内に新たに流入した非正規移動者への対応
⑩ダブリン規則の改定
⑪FORNTEXの改組
⑫トルコとの合意の履行
⑬海上での非正規移動者への対応
⑭加盟国内の市民感情とEU内での合意形成
⑮中東・アフリカ諸国での難民と国内避難民に対する支援
■日本
・筆者の難民審査 2年で100人、偽装した難民申請者が大半
・難民認定率の低さへの反論あるも、難民性のない場合受け入れはできない
・難民受け入れは政治問題にも発展しかねる 中国、トルコからの移民
・日本は財政赤字、難民を受けいれる余裕はない、国内問題を後回ししてでも対外政策を行うことは正当化できない
・危機のシナリオ、中国、北朝鮮で難民が発生し、流入する可能性がある
中国の人口の0.1%でも、1,370,000。ごく一部の中国人が流出するだけでも大きな影響がある
北朝鮮に有事ありの場合、周辺国では入国管理が厳格化する可能性が高い
■漂流する世界~解決の限界
・国家が内外から挑戦を受けている と市民が感じているからに他ならない
共同体意識の表れであり、自己防衛の反応である
外部からの脅威から自国を守ろうと、国境線を堅固にし、出入力管理を厳格にするのは世界的な傾向である
・根本原因を解決することが難民流出に対する解決策であるが
⇒政治的解決が困難だからこそ、人々は武力を用いて物事の決着をつけようとする
目次
はしがき
第1章 難民とは何か
第2章 揺れ動くイスラム圏
第3章 苦悩するEU
第4章 慎重な日本
第5章 漂流する世界
終章 解決の限界
あとがき
主要参考文献
ISBN:9784121023940
出版社:中央公論新社
判型:新書
ページ数:272ページ
定価:860円(本体)
発売日:2016年09月25日発行
Posted by ブクログ
難民問題に関して冷静な見地からまとめられていて、ヨーロッパの苦悩や慎重な日本から、理想論ではなく現実味を踏まえてどのような策をとるべきか考えている。
難民認定が政治的で他国の内政を評価するものであること、日本から難民申請する者がいること、理想のもとやり過ぎたボロが出てるヨーロッパ、日本は難民条約からの脱退も含めた現実的な難民政策を講じるべしといった意見は初めて知って勉強になった。
Posted by ブクログ
国家の限界や安定、という視点から難民問題を考えたことがなかった。
たしかに無制限に受け入れると、国民の間で軋轢が生まれる可能性や国の破綻の可能性がある。
ただ、とはいえ難民をすべての国が放っておいたらどうなるのか、と考えてしまう…
Posted by ブクログ
難民・密航業・人道支援の構造上の問題とか日本の難民認定数が少ない本当の理由が興味深かった。作者は結構リアリストで読んでで偽善を感じなかったので、偽善者社会学者大嫌いな人にもおすすめです。
Posted by ブクログ
難民を受け入れることは人道的側面から見れば素晴らしいことかもしれないが、現実的に起こり得る諸問題、実際に起こっている問題、そして各国の政策と困惑が見えてくる。
Posted by ブクログ
墓田桂(1970年~)氏は、フランス国立ナンシー第二大学博士課程修了、外務省勤務、アテネオ・デ・マニラ大学客員研究員、オックスフォード大学客員研究員、法務省難民審査参与員等を経て、成蹊大学教授。
難民問題は、過去数年に亘り、国際社会やその受入国となってきた先進各国の国内政治を動かす主要なファクターとして、米国のトランプ前大統領の誕生や、欧州各国でのポピュリズム政党の大躍進の背景のひとつとなっているが、私は基本的には、世界中が内向き・排他的な思想に傾斜していく流れに強く懸念を抱くひとりである。
一方、著者は、「この本は葛藤の産物である」と語っているように、理想主義と現実主義の双方の視点を踏まえつつも、近年の国際環境の変化を考慮すると、人道主義の限界を冷静に見つめるべきであり、難民支援は夢想主義に陥ることなく、多様な観点で、かつ冷静に議論される必要があるとの慎重論の立場をとっている。
本書ではまず、「難民とは何か」について、その歴史とUNHCR等の保護制度を振り返ったあと、現在難民の多くを生み出している「揺れ動くイスラム圏」と、その難民の大移動に遭遇して屋台骨が揺らぎつつある「苦悩するEU」の実情を明らかにしている。
そして、難民の受入れを判断するに当たっては、以下のような点にも留意する必要があると指摘する。
◆「ある国の難民申請者を難民と認定する場合、外交にもたらす影響は小さくない。本質的に難民認定は当該国の内政を部外者が評価することである。その点では優れて政治的な行為なのである」
◆「国家間の「大きな平和」のために個人の「小さな平和」が犠牲になる側面は否めない。そもそもすべての平和を追求することは難しく、結局のところ、国家がおこなう難民政策は恣意的にならざるをえない」
◆「安全とリスクの管理は、国民の命を預かる政治家の責務である。やみくもに積極的な国際協力をおこなえば良いというものではない」
そして、現代の世界は、1648年のウェストファリア条約によって定着化した「主権国家体制」が崩れ、それ以前の世界が再現している「新しい中世」なのだとし、「主権国家」の体をなさなくなった国の国民は、「難民」として国境を越えた移動をすることにより身を守ろうとしているのであり、難民問題は、そのような世界の枠組みの根本的な変化を踏まえて考えなければならないと結んでいる。
難民問題については様々な角度からの議論が必要だが、現実的な視座を提供してくれる一冊といえる。
(2016年10月了)
Posted by ブクログ
日本で難民認定をした経験もある著者が語る、世界の、日本の、難民認定制度の現状と問題。日本は難民認定の数は少ないと印象が強いが、その裏には様々な理由があり、世界情勢の中の今の日本の立ち位置としては、決して少なくない数と主張。