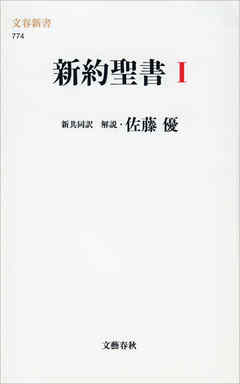あらすじ
宗教に特別な関心をもっていない標準的な日本人に読んでもらうために本書を書いた。
(「はじめての新約聖書-序文にかえて」より)
巻1にはイエス・キリストの生涯について記した福音書を収録。各福音書の前には佐藤優氏による案内も。「書物の中の書物」の読み方を伝授する。
【目次】
・はじめての新約聖書-序文にかえて
・イエスは常識を覆す-「マタイによる福音書」案内
○マタイによる福音書
・「神の国」はどこにある-「マルコによる福音書」案内
○マルコによる福音書
・「復活」とは死人の甦り-「ルカによる福音書」案内
○ルカによる福音書
・「永遠の命」を得るには-「ヨハネによる福音書」案内
○ヨハネによる福音書
・非キリスト教徒にとっての聖書-私の聖書論1
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
世界で一番読まれている書物の中の書物らしい。
1巻は4つの福音書と佐藤氏の解説が収められている。
聖書を読むのは初めてなのだけど、
お釈迦様との比較という罰当たりなことをしてしまうと、
お釈迦様の彼岸は現実を認めるところから始まり、
イエス様の神の国は理想に生きるところから始まっている。
お釈迦様のお説きになった事は頑張ればまだ出来るが、
イエス様のお説きになったことをやるのはとても難しい。
なるほど、お釈迦様は真に目覚めた人で、イエス様は神の子だ。
そして神の子の言うことを聞くことが出来ない我々は罪深い。
しかし、入り口は反対側だが、仏教徒もキリスト教徒も同じく、
自分の持ち物を捨てて、人のために生きろというのは共通している。
お釈迦様の彼岸もイエス様の神の国も同じ場所なのかも知れない。
Posted by ブクログ
佐藤優氏監修の新書版新約聖書。イエスのカエサルのモノはカエサルにとかのエピソードも今までは気にもしなかった。しかし佐藤優氏の解説でYESNOどちらでも駄目な答えをぶち壊す一流の解答という事が分かった。
この本に限った事では無いが弟子の裏切りが心に残る。ユダではなく鶏が3回鳴くまでに貴方は私の事を知らないと言うというエピソード。絶対に裏切らないと言っている奴ほど信用できないという事か。むしろ裏切りを指摘されて売り飛ばしたユダに漢気を感じなくも無い。
Posted by ブクログ
「その日の苦労は、その日だけで十分である。」
古典をより楽しく読みたいという思いが、聖書を手に取ったきっかけである。マタイ、マルタ、ルカ、ヨハネによる福音書が掲載されている。読みやすい。私が感じたのは、マタイが王道であり、マルタが簡易マタイであり、ルカはマタイ+-の情報であり、ヨハネは特殊である、ということである。特に、ヨハネは、ほかの3つと違い説明されている事柄も多く、また、他3つが同じような記載であっても、ヨハネだけは大きく違うこともあった。たとえば、「裏切りの予告」。
ぜひ次の巻も読みたいと思う。
Posted by ブクログ
生まれて初めて通読した聖書は、佐藤優氏による新書となりました。
現代語訳で書かれる、ここまでわかりやすくなるのか、と驚きます。
また、これまで忌避していたのは、その内容以上に
「版が古すぎて文字が小さ過ぎる」とか、
「かなの遣いが自分の感覚にしっくりこない」というような副次的な要因だったかもしれません。
何より、読む理由がなかった。
今回は参加する読書会のテーマ本ということで手にしましたが、そうでなければ手に取ることも無かったでしょう。周りでも、読まずに一生を終える人も多いに違いありません。
読んでみてどうだったのか、と問われたら。
一番は、「宗教を信じるか、信じないか」という究極的な対決を始めるのではなく、彼の言い回し、人間への洞察が鋭い点にうなりました。
宗教書としてではなく、ビジネス書としての観点です。私がいま仕事をしているという理由もあるでしょう。
例えば、福音書の中に、「なぜあなた(イエス)は、人に話す時に例え話ばかり使うのか?」と聞かれる一節があります。
彼はこたえて、
「神(私は「真理」と書き換えたほうがしっくりきます)に近い人間は、それを言葉通り理解できるが、神(真理)に遠い人間にはそのまま話してもちっともわからない。自分たちが普段触れているモノを用いた例え話でなければ伝わらないのだ。」と弟子たちを諭す。
自分が葡萄やパンや、らくだを真理を伝えるための道具として使っていることを認めるのです。
その中でも、私の中では「時が経った葡萄酒が全て酸っぱくなるわけではない。」というセリフが心に残りました。自分に「酸っぱい」中年としての自覚があるからでしょうか。
相手の理解のために例え話を使う。宗教を抜きにして、コミュニケーションに必要不可欠な要素です。
概して宗教意識が低い私や身の回りの人間からすると、宗教書を眉唾なフィクションとして軽視してしまいがちです。しかし、そういう観点ではない見方がありました。
一人の人間は「人の生き方はかくあるべき」と万人伝える時。自らインフルエンサーを名乗る時の思想や手練手管は、東西問わず、学ぶことがあるのです。
そして、もう1つ。私の誤解として読んでいただきたいのですが、
新約聖書は、
「いい生活を送るための100の小さな哲学」
(ナザレ出身のイエス著・●婦の友社刊)と受け取っています。
すでに述べたとおり、聖書は、一般の人にもわかるように、例え話や、誇張したエピソードをふんだんに盛り込んでいます。
ただ、そのフィクションがあまり秀逸で、人の心に刺激的であったため、虚構が、実際の話と同等の価値をもってしまった。
結果、「実用書コーナー」に並ぶはずだった本が、「宗教書」に格上げされてしまったのではないか、と受け止めました。
余談ですが、「クトゥルフ神話」という概念は、ラブクラフトという人が基礎を組み立てた近代フィクションなのですが、本屋によっては、「神話・宗教」カテゴリーに関連本が陳列されている時があります。あれは冗談のつもりなのか、本気なのか・・・気になります。
さて、アドラー心理学本のベストセラー、嫌われる勇気の著者、岸見 一郎さんがこんな言葉を使っています。
「宗教が、ある1つの真理を見極めたら、そこから先には進まない。先の見えない橋を降りるような生き方だとしたら、哲学は少し違う。哲学は、先が見えない橋から降りず、ずっと歩き続けることである。」
聖書の言葉にも同じ感覚を覚えました。
新約聖書にテキストとして残っていることは、イエスが哲学をする上で用いたレトリック(手段)の切り抜きであって、それが宗教化している。実はその先にもっともっと深いなにかがあるのではないかと思うのです。
そして、もっともっと先の「何か」最後まで突き詰めようとするのが、「哲学」。逆に人にはわかりようが無いものとして受け入れるのが「神」という考え方。
こう自分の中で注釈をつけながら読んでいくと、初めて手にした聖書が少し飲み下せる何かに変わっていく気がしました。
この初めての1冊を通じて、「神」「真理」といった、知っているけれど、使いこなせていない語彙の意味が深まった気がします。よい1冊でした。
ちなみに続刊は、友人からは「難解だからあまりすすめない」と言われています。
どうなんでしょうか・・・気になります。
Posted by ブクログ
個人的に尊敬している方に、「初めて聖書を読むならどれがいいですか?」とお尋ねしてこちらを購入しました。
「ヨハネによる福音書がいちばんおもしろかったです。
Posted by ブクログ
新書の聖書で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書と、佐藤優氏の解説が載っています。各福音書はイエスの生涯を描いていますが、同じストーリーを4回読むことになります。聖書は初めてですが、結構読むのに時間がかかってしまいました。
Posted by ブクログ
新共同訳での新約聖書のうち4つの福音書を収録し、
それぞれに佐藤優氏の解説が添えられている。
通常、聖書と触れ合う機会というのは教会での説教で断片的にーというのが多いため
通読を前提とした(その結果、新書という体裁をとった)本書は新鮮だった。
ゴルゴダの丘でのセリフひとつとってみても、悲嘆にくれながら絶命するマタイ/マルコの福音書と聖人然とした態度を貫くルカの福音書で全く印象が異なる。
ルカ、ヨハネによる福音書が物語としての肉付けもされており、初読者にはとっつきやすいと感じた。
Posted by ブクログ
まず佐藤優氏の解説を読み、それから聖書本文は軽く拾い読みするだけでも、重要なポイントはつかめると思う。本書に続く「2巻」とあわせて、全体の構成と成立過程、各文書どうしの関係など、非常によくわかった。佐藤氏の「深読み」が教理からみてどうかという判断はできないが、個人的には十分納得がいった。新書というスタイルも良い。
Posted by ブクログ
新共同訳の聖書を新書に収録し、佐藤優による解説を付している本です。第1巻には、四福音書が収められています。
巻末に収録されている「非キリスト教徒にとっての聖書」で佐藤は、「私は功利主義者だ。役に立たない読書は基本的にしない」とみずからの立場を明言したうえで、現代の世界が直面しているさまざまな問題をより深く理解するために聖書が役に立つということを、「非キリスト教徒」の読者に向けて語っています。
ここで佐藤は、佐藤は、菅直人が掲げた「最小不幸社会」という国家像に対して、「政治に夢や理想、あるいはユートピアを託すことを初めから諦めている」という問題点を指摘し、いっさいの政治的判断が情勢論にもとづいておこなわれることになると批判しています。他方で、柄谷行人の『世界史の構造』を参照し、国家と貨幣が密接に結びついて人びとに対する支配を強化している現状から自由になるために、柄谷の議論を「21世紀の宗教論」として読むことができると主張します。そのうえで、「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい」というイエスのことばに、国家と貨幣に対する警戒感が示されていることに注目し、その現代的な意義を論じています。
Posted by ブクログ
はじめてキリスト教を知ろうと手に取った。
100分で名著の新約聖書と合わせ、挑んだが、やはり難解。わかるようで、わかったふりをしたくなるが、やはりよくわからない言葉が続く。
また時間を置いて、開いてみよう。
Posted by ブクログ
佐藤優氏が「新約聖書を宗教に特別な関心をもっていない標準的な日本人に読んでもらうために書いた」という、全2巻の第1巻。
第1巻では、イエス・キリストの生涯について記した4つの福音書が収められている。
キリスト教の理解では、イエスが出現し、人間の罪をあがない、十字架上で死んだことによって、人間の救済はすでに始まっており、そのメッセージ(福音)を伝える核になるのが4つの福音書であるという。そしてそれは、大きく、「神の国」をイエスの中心的な福音であると考え、互いに近い関係にある「マタイによる福音書」、「マルコによる福音書」、「ルカによる福音書」と、「永遠の命」をイエスの中心的な福音と考え、言葉(ロゴス)が神であるという独自の神学に基づいて書かれている「ヨハネによる福音書」の二つのカテゴリーに分類されるという。
そして、著者は各福音書について以下のように述べている。
「マタイによる福音書」・・・キリスト教の思想としてよく引用される箇所が多い。「(主の祈り)天におられるわたしたちの父よ、御名が崇められますように。・・・」は、現在も、カトリック教会、正教会、プロテスタント教会のすべてで唱えられる。
「マルコによる福音書」・・・4福音書の中で最古のもの。「神の国」の到来を中心的な福音と考え、「人間により理想的な社会や国家はできない。神の支配がもうすぐ実現するのだから、人間は悔い改め、その支配を受け入れる準備をせよ」と説く。
「ルカによる福音書」・・・「マルコによる福音書」を下敷きに、知識人が書いたと考えられ、その著者は「使徒言行録」も執筆している。キリスト教における、「この世の終わりは、歴史の目的であり、終焉であり、完成である」という考え方が色濃く反映されている。目的に向かって突き進んでいくという、欧米文明に刷り込まれたキリスト教的発想、目的論がわかる。
「ヨハネによる福音書」・・・他の福音書と全く異なる。ロシアのキリスト教はこの福音書の影響を強く受けており、ロシア人の気質が欧米人とかなり異なるのはそのせいと考えられる。「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」ことが強調され、抽象的概念の世界で真理を追求することに意味を認めず、その真理が具体的にどのような意味を持つかについて常に関心を持つという、キリスト教徒に刷り込まれた価値観を表している。また、イエスの出現によって、人間に神に従うか神を拒否するかの二者択一を迫っており、物事を突き詰め、決断を迫るというキリスト教文化圏に埋め込まれた文化のもとを示している。
各福音書の本文訳のみではなく、ビジネス関連の著書も多い著者が、聖書が欧米のキリスト教文化圏の発想・価値観にどのような影響を与えているのかという観点からの解説も加えており、有益な書である。
(2010年11月了)