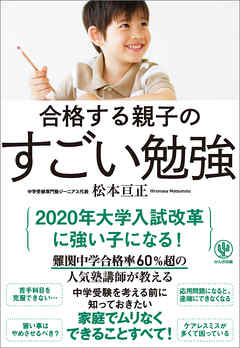あらすじ
「早いうちから本物の学力を身につけさせたい」
「勉強もそれ以外のこともできる子どもになってほしい」
「まずは中学受験で結果を残せたら……」
――多くの親御さんの思いではないだろうか。
「10歳の壁」と呼ばれるものがある。10歳ごろになると、学力面で個人差が大きくなってきて、差が目立つようになる。学校の勉強についていけなくなる子が出始めるのもこの時期だ。
だからこそ、10歳になるまでに覚えたほうがいいことは親が教え込んでいく。そして10歳以降は自分の頭で考える力、物事をつなげて考える力を伸ばしていく。
本書には、そのために知っておきたい子どもへの関わり方、応用がきく子にするための方法、子どもを伸ばす言葉がけ、中学受験への取り組み方など、受験を考えているご家庭でも、そうでないご家庭でも、今日からすぐに家でできる内容が詰まっている。
「叱らない」「よくほめるといい」など抽象的な解説ではなく、親の「こんなときどうしたらいい?」にズバリ応える、使える教育本。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
読み始めるのが少し早かった。小学校に入るタイミングで読むのが良い。再読必須。
中学受験に向かっていくこどもへの関わり方を中学受験塾の先生が書いた本
Posted by ブクログ
子供はまだ幼児だけど、すごく参考になった。
結局のところ、日々の生活で親が知っていることを根気強く楽しく伝えていくこと。
難関校に行ければいいけど、行けなくたってそれはその子の糧になる。
以下メモ。
高すぎるハードルは不正を招く
結果が出てから叱っても逆効果
このやり方だと成果が出ないからこういう風にやろうと伝えること
いい結果が出た時の因果関係を伝えてあげる
宿題が終わったらゲーム ✖️
1.終わったら親のチェック 雑でなければ終了
2.時間を区切って、終わっても見直しや復習をさせる(時間の設定だけでなく、ここまで終わらせるなど目安も示す)
低学年のうちは好きな教科が一つあれば十分、存分に深めよう
高学年になったらもう一教科がんばってみるか
会話の中で今いったことを繰り返してごらんと言って正しく理解しているか確かめる
→正しく理解する力を養う
自分の実力以上の応用問題集に取り組むより、簡単な問題の解き方を複数考える方が応用力がつく
塾は3年生後半くらいからがベスト
中だるみもしないし、間に合う
部活の頻度、親の関わり具合、進路
1月に2校、2月に2-4校くらいを受験
Posted by ブクログ
供の学力を伸ばしたい小学生(全学年)を持つ親御さん向け本でした。
読者のターゲットは広く
中学受験塾代表の方が著者ですが、受験情報オンリーではありません。
学年も全学年向けで、特に
親が叩き込む時期(~10才)から
子供自身で伸ばす時期(10才~)
を意識されており、この内容は10歳以前、この内容は10歳以降でと意識して書かれていました。
あと、子供の学力状態に即したオススメ本もいくつか紹介されているので、そうした本を探している方にとっても、いい参考情報になると思います。
Posted by ブクログ
冒頭「12歳までなら、伸びない子はひとりもいない!」と記されており、勇気が持てました。6歳までに、10歳までに、と色々いわれている中、うちは結局あんまり力を付けてあげられずにここまで来てしまったなと思ってたけど、まずはこの言葉に励まされました。
著者は中学受験専門塾ジーニアスの運営代表ということで、長年の経験があるからか何かと説得力がありました。(納得できることが多かった。)
また、項目の中には「10歳まで」「10歳から」に分かれているものがあり、これも良かった。年齢によって接し方やアプローチが同じで良いはずはないというのと、単純に当てはまるところだけ読めば良いので読者としては時短になる。私はインプット偏重傾向にあり、インプット時間を短縮しアウトプットに時間を割かないといけないと感じているのでこれはかなり有難いと感じた。
具体的におすすめの書籍や参考書を記載してくれているのも嬉しい。すぐに実践に移せそうな気がする。
とりあえず今日は息子と大きめの本屋さんに行き、息子自身に問題集を選んでもらった。思ってた以上にモチベーションが上がったようでこの本を読んで良かったなと思えた。(これから結果がどう転ぶかはさておき。)
以下、読書メモ
・10歳になるまでは、覚えたほうが良いことは親が教えていく。10歳以降は、自分の頭で考える力、自分で答えを導き出す力、物事をつなげて考える力を伸ばしていく。
・親が論理的であれば、子どもは大人の言うことに耳を傾けられる
・本を与えるときは、文字が多ければテーマは何でもOK、図や絵が多いものなら勉強に関するもの、とルールを決めるとやりやすい
・コツコツ真面目に努力できるタイプが中学、高校入学後も伸びる(努力・過程を褒める、努力することを習慣化する)
・子どもに細部にまでこだわっている姿を見せる
・情報と情報を結びつけて答えを出させていくと、AだからBなんだという物事の因果関係を考えられるようになる
与えられた情報と知識を組み合わせて推論を出せるようにする
ニュースを見たり、出かけたりしたときに、なぜそうなるのかを会話する
・習い事や塾の授業の日程は自分で調べさせると自主性が育つ
・簡単な問題を短時間で解かせることを習慣化していくと、10歳以降でも地頭をよくしていける
・10歳以前なら、好きな科目を伸ばせば良い。10歳以降は一番好きな科目は2番目に勉強時間を割くようにする
・「勉強は楽しい」と思わせるためにはエンターテイメント性を意識する(子ども自身が気に入った問題集を選ぶ、テレビや音声など、遊びながら学べる教材を使う、クイズ形式で正解数に応じてポイントをつけ、一定数たまったらごほうびと交換できるようにする)
・語彙を身に着けさせるには会話が重要(親はもちろん、塾や習い事のコミュニティも重要)
・好きなジャンルの本を読ませて、意味がわからない言葉にだけ線を引かせる(後日意味を調べる)
・中学受験に出題される論説文や説明文だけ読ませてみる
・親が探究心を持ち、調べるクセをつける
・問題が起こったとき、正直に具体的に報告させる(事実を曲げて話すということは、客観視できないということ)
・自分の常識・知識を結びつけて推論する力は生涯活きる(これからは、資料を読み取る力+自分の常識・知識を結びつけつなげる力が大切)
・指示を一度で聞けない子は伸びにくい、勉強量より聞く力をつけることを心がける
・この人の話なら素直に聴く、という第三者を探しておく
・簡単なメモをとる習慣をつけさせる
(メモをとる作業は、大人になってからも活きる)
・宿題に制限時間を設ける
・子どものやる気がわかないときは自宅ではやらせない
・良いことがあった場合には無理矢理でも因果関係を作って褒める(努力の過程)
・テストの点数が下がっても怒らず一緒に悩む
・勉強に気持ちが向いていないときは「何か悩んでたりする?」と聞く
・小説対策
話のあらすじをおさえる、登場人物たちの人間関係のなかで生まれる心情、どんな行動や発言がどのような心情と結びつくかを知る。共感力は映画を活用事例するのも良い。(感想をあとで話し合う)
・嫌いな科目はレベルを2段階落とした問題が解ければ◎(最難関に受かる子もオールマイティではない)
・試験の問題は欲張らない(苦手科目なら正答率60%以上の問題だけ見直せば十分、それができたら正答率40%以上の問題に取り掛かる)
・問題文の聞かれているものに線を引くようにするとミス紡糸につながる
・国語は少なくとも6割以上は正解できそうな問題集を選ぶ(記述問題は親子喧嘩のもとなので避ける)
・希望する学校の大学合格実績(上位20%)、校風や部活の頻度もチェック
・受験校の数は3〜5校が望ましい(対策が十分にできる範囲)
Posted by ブクログ
10歳以前と以降の指導方法の違いが書かれているのは良かったが、全体的にあまりグッとこなかった。
可もなく不可もなく。
その中でも納得・共感できる事があり、
「宿題をやったらゲームをやってもいい」
と言う事をやめてみた。
確かにいい加減に早く終わらせるのを優先させて雑な取り組み方が習慣化してしまうだろう。
「後でちゃんと勉強するならゲームやってもいい」に変えてみた。それだと「もうゲームやったし勉強もやらなきゃ!」とか「これで約束通り勉強をやらなかったら明日以降ゲームさせてもらえないかも」という気持ちが働いている様子。
しばらくこの方法を試してみようと思う。
あと、「中高で突然勉強する習慣がつくケースはほとんどない」にも激しく共感。
全くない!とは言えないけど、ほとんどないと思う。少しずつでも勉強する習慣を付けられるといいな。