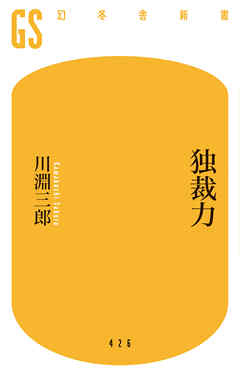あらすじ
国際試合禁止の処分を受けるほど末期的な状態だった日本バスケットボール界を、わずか半年で問題解決に導き、新リーグを設立、一躍救世主となった著者。なぜ門外漢にもかかわらず、短期間で未曽有の改革を成し遂げることができたのか。嫌われることを恐れずに、しがらみを断ち切り、トップダウンで独裁的に決断を下す。ただし、私利私欲があってはいけない。著者はそれが優れたリーダーの条件だという。今年80歳になる“キャプテン”が、その稀有なるリーダーシップと果てなきバイタリティーの源を明かす、すべてのビジネスマン必読の書。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
第1章から第3章までは、Bリーグ立ち上げまでの経験談である。題名の「独裁力」にジャストフィットするのは、第4章である。実のところ、第3章までは、題名から期待した内容ではなかったため、裏切られたような感想を持ちながら、読み進めた。第4章では川淵さんのリーダー論が十分に書かれているので、飽きずに読み進めて欲しい。書かれていることは、「リーダーのための自己啓発本」にも載っている内容と言ってしまえば、おしまいだが、川淵さんを想像しながら読むと、説得力があり、頭にもすんなり入ってくる。「リマインド」も含めて、読むことをお勧めしたい。
前の上司に似ているな、と思った。ある時、彼の意見に反対するものが10名いたが、完璧な理論武装で、一人一人論破していった爽快な光景が思い出された。また、ある時は、自分のクビをかけて、経営層に「間違っている」と意見した。まさに「私利私欲のない人」である。さらに、川淵さんが言っている「観察力」も持ち合わせており、まだ数回しか会っていないにもかかわらず「君は疑り深い、人と関係を築くのにちょっと時間がかかるね」と優しく言い当てられたことがある。こういう人に私もなりたい。
*リーダーには理論武装が必要
川淵さんは「怒りんぼ」のイメージがあったが、そのベースには事前調査・勉強に基づいた理論武装がある。
*インパクトのある言葉で「発信力」を持たせる
・言葉に発信力を持たせるには、まず訴えるべきことをインパクトのある言葉で示し、具体的な説明はその後にする。すると、その言葉で全容が思い出されるようになる。漠然とした長い説明だと時が経つにつれて印象が薄れていくもので、短い言葉で印象づけることで、その言葉が多くのひとの脳裏に刻まれ、継続した思考や努力につながっていく。
・マスコミは良くも悪くも僕の言葉に期待感を持って取材を求めてくるが、実は前もって「こう言おう」と準備したことはほとんどない。我ながら、「よくこんな言葉が出てきたな」と思うことがよくあるが、それは、常にいろんなことを考え、見聞きしているから、ここぞという時に象徴的な言葉が出てくるのだと思う。
・リーダーというのは何があっても「負けてもいいから」とは決して言ってはならない。最初から最後まで一貫して「絶対できる」と言い続けることが重要だ。常に成功を確信していること、また、是々非々をはっきりさせることもリーダーの務めだと思う。
*与えられた人材を生かすためにどうすべきか
誰でも新入社員の時に「怠けて働こう」なんて考えていた人はいないのではないか。「一生懸命会社のために働こう」と思って入ってきている。それが、いろいろな荒波に揉まれやる気を無くしてしまっているのではないか。私は普段、「この人使えないわね」と思うことがあるが、もっと包容力を持って接しなければならないと反省した。
・サッカーでもビジネスでも高い能力を持った人間だけを揃えることは難しい。それに、自分が使いやすい人ばかり集めたとしても、機能するとは限らない。リーダーはそれぞれ個々のレベルの差を乗り越え、多様な人間を一つの組織として束ねなければならない。それにはある種の包容力が必要だろう。選り好みをせず、与えられた人材を最大限に生かして成果をあげることがトップに課せられた責任でもあり、醍醐味でもある。
*「観察力」を養う近道
・組織のコミュニケーションを円滑にするのに、不可欠な要素は何か。僕は、一番大事なのは「観察力」だと思っている。観察力を養う近道は、毎日、部下の動静を具に見ることだ。普段の態度を見ていれば小さな変化も自ずとわかるようになってくるし、組織の異変を察知する能力も磨かれる。部下の表情や態度に変化があるときは必ず声掛けをする。それができていれば困難に陥った時に解決策を見出せるものだ。部下の変化を簡単に見過ごしてしまうような上司では信頼も得られないし、リーダーは務まらない。
・また優れたリーダーは部下の心の機微や好調な時のイメージを覚えておかなければならない。それがあれば、ここぞという時に「あの時できたのだから今度も大丈夫だ」と伝えることができるからだ。具体的な例を出して励まさられれば、部下は「見てくれていたんだ」と安心できるし、やる気も湧いてくるだろう。そう言った些細なやりとりが上司と部下の関係を良好に保つ。何気ない一言で部下が業務に励むようになれば、組織にも活力が出てくる。
・ただし、これもやりすぎたら逆効果になってしまう。ましてや「観察」が「監視」担ったら、元も子もない。見ていないようで、見ている、近いようで遠い、遠いようで近い、絶妙な距離で把握していることが重要だ。
*常に最悪の事態を想定する
・リーダーは常に部下とは異なる目線を持っておくべきだ。物事がうまく進んでいる時には部下にはひたすら前進させる。部下に自信を持たせて良いムードを作るのもリーダーの役目と言えるだろう。しかし、その好調はいつまでもつづくものではない。常に最悪の事態に備えておけば、万が一の時も冷静にそして速やかに事態の収束を図ることができる。
リーダーは人に好かれなくて良い
*私利私欲がない独裁者であれ
・誰の応援もない窮地に追い込まれた時こそ、その人の真価が問われるものだ。「責任を問われてしまう」とか「これをやったら孤立してしまうんじゃないか」なんて考えるようではリーダー失格。保身を捨て、使命を果たすためにどうしたらいいか、それを判断し、下の者を導いていくことがトップの責務だ。
・何でも多数決で決まるのなら誰がトップになっても構わない。しかし、それでは強い組織は作れないし、仕事のスピードも鈍ってしまう。だからある意味「独裁的なトップ」が必要だ。ただし、条件がある。私利私欲がなく、組織をそして社会を良くしようという志と信念を持った「独裁者」であること。もちろん、人間だから誰でも欲はある者だが、リーダーはできるだけ損得を忘れる努力をし、「社会に役立つ」という理念のもとに行動する。理念を持って初めて儲けを出すことを考えるのだ。
*部下をイエスマンにするな
・組織を動かしていく中でトップが判断を誤ることもある。そういうときは往々にしてイエスマンばかり従えていることが多い。これには、トップがいうことを聞く部下をあえて集めているケースとトップが部下を結果的にイエスマンにしてしまっているケースがある。トップが部下の意見や疑問に耳を貸さなくなると部下はいつしか諦めモードになり、次第に発言しなくなっていく。そしてその様子を見ている周囲の人間にもそれが伝わり、「うちのトップに言っても無駄だ」となって誰も意見を言わなくなり、徐々に組織は停滞していく。
・問題意識が高く、自分なりの意見や疑問をぶつけてくる部下というのは人とは違った視点を持っている者だ。たとえ採用する見込みがないアイディアばかりだとしても部下の意見に耳を傾け、その中に可能性のある意見があれば取り上げる。その際の判断軸は目標に向かうために考えられるべきで、うまくいかなかったら修正すればよい。
・自分の意見を聞いてくれる上司であれば、様々な意見が出るようになり、ボトムアップの風土が醸成されていく。そこで得をするのは上司であり、組織なのだ。もちろん、リーダーたるものは自分で決めたことはもちろん、部下の失敗に対しても矢面に立って責任を取るのは言わずもがなだ。そうした姿勢がなければ、現場はついてこないし、彼らもまた意欲を持って働くことはできない。
*真のリーダーに必要な胆識
・胆識とは何かを成し遂げるための決断力や実行力を伴った「見識」のことで、その見識を身につけるには、知識を増やし、様々なことに挑戦して研鑽を積むことが不可欠だ。
*ビジョンとハードワークの両立
川淵さんも明確なビジョンを持ったのは51歳時だったそうだ。私も遅くはないな。