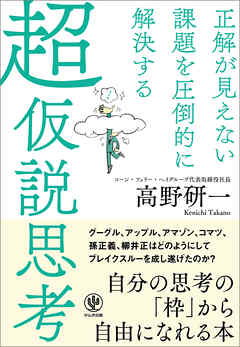あらすじ
本書は、「新しい付加価値を生む商品を開発する」「同業他社が考えつかない新規事業に打って出る」「部署間で利害が対立する問題に対して、みなが納得する答えを出す」など、私たちの目の前にそびえ立つ一筋縄ではいかない課題を解決するために役立ちます。
こうした課題の解決によく使われるのが、「フレームワーク」や「ネット検索」。ただし、前者は、フレームワークという「枠」に当てはめようとして思考が現実とかい離し、的外れな解決策しか出ないケースが多々あります。後者は手軽にできる反面、独自性のない金太郎飴のような結論になりがちです。
そこで本書では、アップルやグーグルなどのグローバル企業、孫正義、柳井正氏ら名経営者の事例を読み解きながら、自由自在に最適解をたぐり寄せる頭の使い方をお伝えします。
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
"
自分自身、型にはまった考え方をしがちで、新しい発想が苦手なので
今までにない仮説を立てる工夫の仕方が学べた。
まだまだ追いつかないことが多く、改めて少し寝かせた後に読んだら変わるのかもしれないが、
現時点でも読んでよかったと思う。
ーーーーーーー
◆フレームワークは""なんでも正解を出してくれる優れもの!""ではなく、
""型にはめて、定義して、答えを導いているもの""
良い方向にも悪い方向にも転ぶ可能性はある。
問題に対する視野を限定することで、唯一の解を導いている。
◆答えとは、問いを出している相手が誰かによって変わるもの
→唯一の正解など無く、それは幻想である
(※最初に思いついたもの、ひらめいたものに、飛びつきがち)
【フレームワークを使って正解に辿り着く発想法は、危険な面もはらんでいる】
◆モノの見方を柔軟に変えられる能力
→新しい記憶が蓄積されて、繋がっていく。記憶のライブラリーを豊かにすること
経営とは、知識で学べば点が取れる学問のようなものではなく、
<基本を繰り返し実践しないと体得できないスポーツや武道>に近い。
◆「自分の見えない世界」の中から、答えを探る
飛躍的に売上を伸ばす答えは自分の頭の中にはない(あれば、やっている筈)
新規事業のアイディアを考えるに当たって、社内でブレストをやるが、これも注意が必要
社内にいる人の頭の中のアイディアをポッと取り出してきて新規事業が生まれるのであれば、
新しい事業は次々と出てきていても良いはずではないか?
ーーーーーーーーーーーーー
◆売れている芸人はアイディアをネタを10個考えて、それを捨てる
まず思いついたネタは、ほかの芸人も考えていること
11個目移行のネタを捻り出すのは容易ではないが、町を歩いたり、刺激を受けながらなんとか出す
これを繰り返すことで、ベテランの芸人は""11個目のアイディア""がいきなり思い浮かぶようになる
「考えてみれば当たり前だが、誰も思いつかなかったアイディア」を引き寄せるイマジネーションを
◇キーエンスの営業職は、顧客と工場のラインに入り込んで、
「ここにセンサーを設置すれば、これぐらいの省人化とコストダウンが可能になります」と話す
普通は「センサーを使えば、自動化が可能になります」
他社が見えないところに入り込んで仮説を立てる訓練をしている
→提案の具体性や、インパクトがぜんぜん違う
◇アイリスオーヤマは、毎週新商品のアイディアを出す「プレゼン会議」を社長自らやっている
<ユーザーのライフスタイルを変えるストーリー性のある提案になっているかどうか>を徹底検証
・クリア収納
日本には四季があり、夏物冬物を入れ替えて使う
→どこにしまったか思い出せず夫婦喧嘩をした大山社長の実体験から、見えるケース
・米の小分けパック
精米したばかりの米を必要な分だけ買って、食べる
単身世帯でも米を食べたいというニーズを埋めている
ーーーーーーーーーーーーー
◆FacebookやGoogleの価値=喜怒哀楽を生み出す""場所""を提供すること
モノでニーズが埋まる時代は情報革命によって終焉した
従来:ニーズ→解決策→製品・サービス
現在:ライフスタイルを探る→喜怒哀楽から、価値ある情報が浮かび上がる
◆価値を生む方法が見えたら、すること
「そのために、どう人を生かすか」
自分ですべてをコントロールして他人との連携がうまくいかない人が多い
エコシステム(企業の枠を超えたオープンな文化)の中で生きていく上では、
【自分の知らない領域に強いパートナーを""どう生かすか""】がポイントになる
ーーーーーーーーーーーーー
「これまでは道がまっすぐだったが、この先は曲がっているかもしれない」
この考えで運転できる人こそが、環境の変化を先取りして、環境自体を変えられる人
最初から仮説が当たるという事は期待出来ない。
最初は必ず外れる。
しかし、実験や調査がうまくいかなかった後から、本当の仮説の設定と検証が始まる
・仮説が間違っている可能性
・仮説はあっているが、自分が気付いていないボトルネックがあり、成果を妨げている可能性
◆マテ茶の話
""太陽のマテ茶""以前に、他のメーカーが販売したことがある
売り出し初日に「これはダメだ」と判るくらいの、散々な結果だった
【ボトルネック】
お茶の色が濃くて、陳列されている他のお茶と比べて手に取ろうと思えなかった
しかし、このお茶は飲んでみると美味しい。肉料理にも合う。
【コカ・コーラ社の戦略】
・ボトルを派手にラッピングして、見えなくした
・CMでラテン系のお姉さんを登場させ、""日本のお茶とはまったくの別物""というイメージを創り上げた
結果、ロングセラーに!!
ボトルネックの検証→仮説立てが成功した事例。
売れたか売れなかっただけを判断基準にすると、この成功は無かった。
ーーーーーーーーーーーーー
【最後に】
自分の仮説をGoogleで検索してみて、
同じようなアイディアが簡単に引っかかってきたら、その仮説を捨てていく
→これが""正しいGoogleの使いかた"""
Posted by ブクログ
正解が見えない課題を圧倒的に解決する 超仮説思考
高野研一
コーン・フェリー・ヘイグループ株式会社社長
1987年神戸大学経済学部卒業。大手銀行勤務、ウィリアム・マーサーを経て、
2006年ヘイコンサルティンググループにディレクターとし て入社。07年より現職。
1991年ロンドン・スクールズ・オブ・エコノミクス(MSc)修了、
92年シカゴ大学ビジネススクール(MBA)修了。
第1章 学歴エリートが40歳を過ぎてつまずくワケ
第2章 「超仮説」をたぐり寄せる力がキャリアアップを可能にする
第3章 フレームワークでなくトレーニングが重要
第4章 見えない世界にイマジネーションを広げる
第5章 非連続な変化の先を考える
第6章 視点を自分の外に移してみる
第7章 人の心の中に入り込む
第8章 オープンなエコシステムに参加する
第9章 前提条件を疑う
第10章 超仮説を立てて検証する
最終章 実践こそがすべて
『フレームワークと合わせて読むべき本』
検討を進めていた案件が会議の場で、前提の誤りをしてきされて、再検討になった。
その時に「いかに仮説のセンスを学ぶかが大事」といわれて購入した本。
フレームワークを使う前に、実際に現場の声をきいたり、前提を確認したり、いろいろな立場の人の声を聴くことが
大事ということがわかる本。また仮説はワークを通して培われるとかかれていて、事例ととワークがセットで用意されている。
□ こんな人に読んでほしい
・フレームワークを極めた人
・いいソリューションを考えついてももう一押し足りない人
・仮説を立てるのが苦手な人
□ どんな内容か
・フレームワークは定義して、答えを導いているもの(定義は変わる)
・答えとは、問いを出している相手が誰かによって変わるもの
・「自分の見えない世界」の中から、答えを探る
以下 ほかの人の感想の引用
◆フレームワークは""なんでも正解を出してくれる優れもの!""ではなく、
""型にはめて、定義して、答えを導いているもの""
良い方向にも悪い方向にも転ぶ可能性はある。
問題に対する視野を限定することで、唯一の解を導いている。
◆答えとは、問いを出している相手が誰かによって変わるもの
→唯一の正解など無く、それは幻想である
(※最初に思いついたもの、ひらめいたものに、飛びつきがち)
【フレームワークを使って正解に辿り着く発想法は、危険な面もはらんでいる】
◆モノの見方を柔軟に変えられる能力
→新しい記憶が蓄積されて、繋がっていく。記憶のライブラリーを豊かにすること
経営とは、知識で学べば点が取れる学問のようなものではなく、
<基本を繰り返し実践しないと体得できないスポーツや武道>に近い。
◆「自分の見えない世界」の中から、答えを探る
飛躍的に売上を伸ばす答えは自分の頭の中にはない(あれば、やっている筈)
新規事業のアイディアを考えるに当たって、社内でブレストをやるが、これも注意が必要
社内にいる人の頭の中のアイディアをポッと取り出してきて新規事業が生まれるのであれば、
新しい事業は次々と出てきていても良いはずではないか?
ーーーーーーーーーーーーー
◆売れている芸人はアイディアをネタを10個考えて、それを捨てる
まず思いついたネタは、ほかの芸人も考えていること
11個目移行のネタを捻り出すのは容易ではないが、町を歩いたり、刺激を受けながらなんとか出す
これを繰り返すことで、ベテランの芸人は""11個目のアイディア""がいきなり思い浮かぶようになる
「考えてみれば当たり前だが、誰も思いつかなかったアイディア」を引き寄せるイマジネーションを
◇キーエンスの営業職は、顧客と工場のラインに入り込んで、
「ここにセンサーを設置すれば、これぐらいの省人化とコストダウンが可能になります」と話す
普通は「センサーを使えば、自動化が可能になります」
他社が見えないところに入り込んで仮説を立てる訓練をしている
→提案の具体性や、インパクトがぜんぜん違う
◇アイリスオーヤマは、毎週新商品のアイディアを出す「プレゼン会議」を社長自らやっている
<ユーザーのライフスタイルを変えるストーリー性のある提案になっているかどうか>を徹底検証
・クリア収納
日本には四季があり、夏物冬物を入れ替えて使う
→どこにしまったか思い出せず夫婦喧嘩をした大山社長の実体験から、見えるケース
・米の小分けパック
精米したばかりの米を必要な分だけ買って、食べる
単身世帯でも米を食べたいというニーズを埋めている
ーーーーーーーーーーーーー
◆FacebookやGoogleの価値=喜怒哀楽を生み出す""場所""を提供すること
モノでニーズが埋まる時代は情報革命によって終焉した
従来:ニーズ→解決策→製品・サービス
現在:ライフスタイルを探る→喜怒哀楽から、価値ある情報が浮かび上がる
◆価値を生む方法が見えたら、すること
「そのために、どう人を生かすか」
自分ですべてをコントロールして他人との連携がうまくいかない人が多い
エコシステム(企業の枠を超えたオープンな文化)の中で生きていく上では、
【自分の知らない領域に強いパートナーを""どう生かすか""】がポイントになる
ーーーーーーーーーーーーー
「これまでは道がまっすぐだったが、この先は曲がっているかもしれない」
この考えで運転できる人こそが、環境の変化を先取りして、環境自体を変えられる人
最初から仮説が当たるという事は期待出来ない。
最初は必ず外れる。
しかし、実験や調査がうまくいかなかった後から、本当の仮説の設定と検証が始まる
・仮説が間違っている可能性
・仮説はあっているが、自分が気付いていないボトルネックがあり、成果を妨げている可能性
◆マテ茶の話
""太陽のマテ茶""以前に、他のメーカーが販売したことがある
売り出し初日に「これはダメだ」と判るくらいの、散々な結果だった
【ボトルネック】
お茶の色が濃くて、陳列されている他のお茶と比べて手に取ろうと思えなかった
しかし、このお茶は飲んでみると美味しい。肉料理にも合う。
【コカ・コーラ社の戦略】
・ボトルを派手にラッピングして、見えなくした
・CMでラテン系のお姉さんを登場させ、""日本のお茶とはまったくの別物""というイメージを創り上げた
結果、ロングセラーに!!
ボトルネックの検証→仮説立てが成功した事例。
売れたか売れなかっただけを判断基準にすると、この成功は無かった。