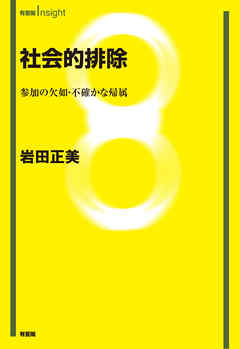あらすじ
ホームレスやネットカフェ難民、長期失業の若者や日雇い派遣など、現代の貧困を考えるうえで欠かせないキーワード「社会的排除」。グローバリゼーションとポスト工業社会において、福祉国家の制度では対応できない、深まるばかりの社会分裂にどう対応すべきかを明らかにする。経済や労働のみならず、家族や教育、文化や住居、社会関係なども含めた総合的な視点からアプローチし、現代社会を照射する。新しい「社会的包摂」のあり方を考えるために。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
ホームレスやワーキングプア、ネットカフェ難民、日雇い派遣、孤独死や自殺など、福祉国家の制度からこぼれ落ち、呻吟する人々。
彼らはなぜ、どのようにその拠り所を失ったのか。
グローバリゼーションとポスト工業社会において、深まるばかりの社会分裂を、どのように分析するか。
曖昧に使われてきた「社会的排除」概念を、社会参加と帰属に焦点を当てて、理論的にクリアに示し、データとフィールドワークを駆使して、日本の今のリアリティに迫る。
[ 目次 ]
序章 社会に参加するということ
第1章 「社会的排除」とは何か
第2章 社会的排除vs.貧困
第3章 社会からの「引きはがし」と「中途半端な接合」―路上ホームレスから見た二つの経路
第4章 若者と社会への「中途半端な接合」―ネットカフェ・ホームレスの場合
第5章 周縁―地域空間と社会的排除
第6章 セーフティネットからの脱落―福祉国家と社会的排除
終章 社会的包摂のあり方
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
タイトルのみで一読。最初は大きな社会というコミュニティの中から排除される人に関する本かと思ったが、排除される人の社会的位置づけに関する本といったほうが近い。社会論は全くの素人だが、こういう見方もできるのかという新たな見地を知ることができ面白く読むことができた。こういう話は物理学と一緒で、理論としては面白いのだが、現象の対応という現場論では難しい問題がいろいろあるのだと思う。ただ、社会や経済における構造を変えていくことで社会的弱者を減らしていくことはいつの時代でも変わらぬ課題だし、研究していかなくてはならない分野だ。
Posted by ブクログ
社会的排除という概念、それを使ってホームレス、ネットカフェホームレスを分析していく。
学びの多い本です。
ただ、社会的排除と貧困を社会学的に分析することの差異や
がしっくり来ませんでした。
申し訳ありません。
Posted by ブクログ
【読書】著者は、生活保護やホームレス問題に詳しい日本女子大学教授の岩田正美氏。貧困問題は、生活保護のケースワーカーの経験を通じ、興味をもっているテーマ。著者が描く、社会からの「引きはがし」と「中途半端な接合」とは、自分が生活保護の現場でみた現実世界。
社会からの「引きはがし」とは、これまで、失業や倒産、また、倒産と同時に生じた離婚や借金など様々な理由により、一般企業などに勤めているなど、社会のメインストリームにしっかり組み込まれていたのが、一気に転落するケース。本書で言う、ホームレスに至る3つの類型のうち、㈰転落型、㈪労働住宅型。㈪の労働住宅型については、リーマンショック後の派遣切り等で住居を失った労働者が一気に生活保護へと流れた。自身の怪我などで仕事ができなくなった瞬間に一気に仕事だけではなく、住居も失う状況。それも、仕事を通じて生活をしており、仕事を離れた瞬間、自分自身の生活が社会の中でしっかり築かれていないことに気づく。そのときには地域社会からも孤立してしまう。
もう一つの類型である㈫長期排除型は、引きはがされる社会のメインストリームへの参加を経験していない。途切れ途切れの不安定な就労のみのケースなど。福祉につながってもいない世帯もそうだろう。著者は、社会の参加が中途半端という意味で、「中途半端な接合」と呼ぶ。
本書の後半部、現在の生活保護の現場において、目先の就労を急ぎ、ともかく仕事があればよいというような就労支援は「中途半端な接合」を再生産する結果のみという、著者の指摘。自分自身の就労支援はどうだったのだろうと、今問い直す。
Posted by ブクログ
ホームレスやネットカフェ難民などを取り上げ、従来の貧困という考え方とは違う切り口で、社会的に排除されている人々を考察している。考え方の重要性はわかるのだが、排除(exclusion)の反対語である包摂(inclusion)の概念が曖昧で、統合(integration)との区別があまりなされていないようだったのが残念だった。
ある意味、発展途上国への開発問題のほうが議論として進んでいるような印象すら受けた。
Posted by ブクログ
・世界はまるでショッピングモールのように、あらゆる人々に開かれ、簡単に交換する場となりつつあるのに、
肝心な場面で、特定の人々を「関係者以外立ち入り禁止」の札によって拒み、彼らを社会関係の外に追いやろうとしている
構造が存在している
・貧困が、生活に必要なモノやサービスなどの「資源」の不足をその概念のコアとして把握するのに対して、
社会的排除は「関係」の不足に着目して把握している
・社会的排除は、しばしば特定の場所から排除し、その結果排除される人々が特定の場所に集められる(空間的排除)
・タウンゼントは、人々が社会で共有し参加することを当然とされる諸慣習や諸活動の体系を意味する生活様式に着目した。
普通、人々はこの生活様式の下で生活を営んでいるが、場合によって、この生活様式から大幅に脱落した状況に陥ることがある。
この状況を、社会的剥奪と呼んだ。そして貧困を、この当然とされる生活様式を保つために必要な生活資源を欠いている状態であると、
規定した。
・日雇いの場合は6割以上が社会保険に無加入であり、健康保険と雇用保険をカバーする日雇い保険にも18%しか加入していない
・もともと公的扶助は標準的なリスクへの標準的な給付に枠付けられた、社会保険の限界を保管するものとして位置している
これは、雇用保険に対する雇用扶助のような、個々の社会保険制度を補完する制度ではない。他制度・対施策を適用してみて、
それでも最低生活に満たない「最後」の手段として位置づけられてきた。
・路上ホームレスが経験した生活保護利用は、入院を基調にしている。つまり主に病気やけが、障害があったときにだけ
生活保護を利用している。稼働年齢期の人々の利用にかなり慎重。本人の労働力(または世帯員)の労働力を十分活用してもなお貧困であることを条件としている
・宮本太郎は、労働参加の強調を2つのアプローチに区分している。ワークフェアとアクティベーションである。
前者は就労義務を所得保障の条件としていくような政策、後者は就労促進のための社会サービスを所得保障と並列して行っていくような政策。
労働を強調するのではなく、労働と切り離した所得保障の進化系としてベーシックインカムアプローチを位置づけている。
・社会的包摂は、必ずしも労働市場への参加や復帰だけで達成されるものではない。社会的排除の究極の形態は、市民の権利義務の基礎としての存在証明の喪失であった。
・貯蓄などの資産は長期の人生設計にかかわり、貧困者が長期の見通しを持って行動したり、その中でライフチャンスを現実的に掴み取ることを可能にする。