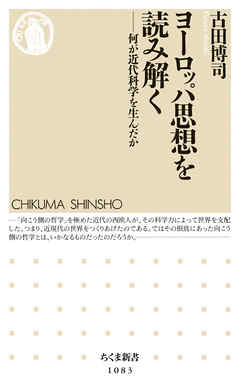あらすじ
なぜヨーロッパにのみ、近代科学を生み出す思想が発達したのだろうか。それは「この世」の向こう側を探る哲学的思考が、ヨーロッパにのみ発展したからなのだ。人間の感覚器官で接することのできる事物の背後(=向こう側)に、西洋人は何を見出してきたのだろうか。バークリ、カント、フッサール、ハイデガー、ニーチェ、デリダらが繰り広げてきた知的格闘をめぐって、生徒との10の問答でその論点を明らかにし、解説を加える。独自の視点と思索による、思想史再構築の試み。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書における向こう側とこちら側の厳密な語彙の定義と使い方は置いといて、こちら側で生活する者にとって「向こう側感」を持つことは往々にしてあるのだろう。
その「向こう側感」であるが、伝統的に西洋哲学ではイデア論を源流としてキリスト教にも受け継がれ、見えざる神からあふれ出る真理に迫ろうとしてきたことが本書で述べられる。向こう側との結節点である超越や直感の哲学的探検は、おそらく正しい認識への希求と表裏が一体で、何が近代科学を生んだかという副題のひとつの結論となるのだと思う。
著者が大陸系のアプローチをあえてこき下ろし、英米型の分析哲学やプラグマティズム的な思考法を健全と捉えるのは日本の現状を憂いてのことだ。主観であるが本来の日本人の向こう側というのは、日常の中でこんなところに向こう側がありそうだという驚きの内にあったように思う。輪廻に象徴される繰り返しの思想からは、時に垣間見える向こう側を様々な印象で語る機微があったように思う。しかし西洋から文物が伝わると、向こう側はいずれたどり着くものに変わり、今それが行き詰まり息詰まるとニヒリズムに陥る。
そこで本書は訴える。そうじゃないと。向こう側はこちらから迫り続ける存在であると。大陸系哲学ではないと。英米型の哲学が正解だと。実は啓蒙の書だったのだ。
あとがきにもあるように紆余曲折を経て新書として書籍化されたようで、途中サラリーマンに訴えかける描写があったり、なんだかちぐはぐな感は否めないが常日頃から「向こう側感」を抱く人とニヒリズムから一歩を踏み出したい人は読むべき。
Posted by ブクログ
著者は筑波大教授。ヨーロッパ思想として、ニーチェやサルトル、デリダ等の哲学を紹介する。キーワードは「向こう側」か。この「向こう側」を探る哲学的思考がヨーロッパ特有とのこと。対話形式で読みやすい。「向こう側」をキーワードとして、アリストテレスやプラトン、ニーチェ、サルトル、デリダらの「向こう側」に対する立ち位置の違いにより思想の違いを説明。明快です。
そういえば、昔よく読んでいた木田 元さんが、哲学というのはヨーロッパ特有の思想だ、というのをよく強調されていたことを思い出した。哲学と言うのはわかりにくいものだが、そもそもの問題意識が日本人にないものだから一層わからない。本書でも同様のことをいっている。数学とか物理学と言うのは普遍的なものだから日本人でも普通に勉強すれば理解できるが、哲学を同じように捉えると駄目なのでしょう。本書のタイトルになっているような、ヨーロッパ人の思想を学ぶ、という意識でいるほうが理解できるのだと思います。本書では、日本人にはそもそも「向こう側」の認知がないのだから日本に哲学が生まれるわけがない、とのことです。