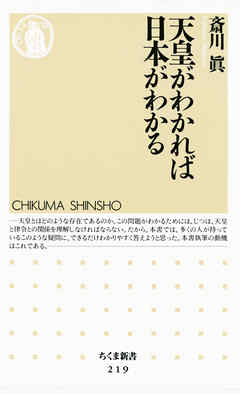あらすじ
天皇の称号はいつ成立したのか。天皇はなぜ続いてきたのか。この疑問にただちに答えられる人は多くはないだろう。天皇を長とする古代律令国家は、経済変動のために崩壊し、公家政治から武家政治へと時代は移ったが、それにもかかわらず、天皇と律令システムの正統性は失われなかった。明治の日本は律令国家の直系の子孫であり、じつは今の日本もれっきとしたその跡継ぎなのだ。ウルトラ混合政体にいたる日本国家の本質とその由来の謎をはじめてわかりやすく解き明かす新・日本学入門。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
天皇の称号はいつ成立したのか。
天皇はなぜ続いてきたのか。
この疑問にただちに答えられる人は多くはないだろう。
天皇を長とする古代律令国家は、経済変動のために崩壊し、公家政治から武家政治へと時代は移ったが、それにもかかわらず、天皇と律令システムの正統性は失われなかった。
明治の日本は律令国家の直系の子孫であり、じつは今の日本もれっきとしたその跡継ぎなのだ。
ウルトラ混合政体にいたる日本国家の本質とその由来の謎をはじめてわかりやすく解き明かす新・日本学入門。
[ 目次 ]
第1部 天皇という称号(「天皇」とは、そもそも法律用語である。;「天皇」とは、「北極星」のことである;君主の称号とは、臣下が献上するものである;日本の天皇号は、臣下が献上した;天皇は、「倭の五王」の子孫である;天皇の統治は、高天原の神の委任である;天皇の「姓」は、宮号である)
第2部 中国と日本(「冊封体制」とは何か;冊封体制とは、中華帝国の世界秩序のことである;天命思想とは、王朝交替の思想である;日本は、中華帝国に朝貢して、世界史に登場した;遣隋使・遣唐使は、中華帝国の官職・爵号はいらないと伝えた;日本という国名は、律令体制に伴ってあらわれる)
第3部 日本律令国家(日本は、中華帝国のような国家になりたかった;日本は、律令を作るために、中国から律令の写本を運んできた;日本の血統原理の正当性は王朝交替思想を排除して成立した;律令国家は、行政指導・官僚統制型の国家である;結論 そして、国家の枠だけが残った)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
たまたま読みました。
律令制があんまりわかってないからすんなりは読めませんでしたが、中国の真似をして小中華を作ろうとした結果+易姓革命の考えは除外した結果であるということはわかりました
Posted by ブクログ
――――――――――――――――――――――――――――――
倭国は、国内体制の整備をしなければならなかった。それは、前述したように、朝鮮半島から追い落とされてしまったためである。
その結果、日本国内に立て篭もらざるをえなくなり、国内政治システムの整備が、重要な政治課題になった。同時に、「日本とな何か」という国家としての自意識の確認や高まり、つまりアイデンティティをはっきりさせるという動きが出てきた。これが、王権の歴史の確認になる。官僚制度の整備と、新しい君主号の採用が、ここで結びつく。74
――――――――――――――――――――――――――――――
『日本書紀』推古天皇十六年(六〇八)九月五日条に、隋の皇帝・煬帝に宛てた国書が載っている。十五年の遣隋使が、四月に隋の使節を伴って帰国し、九月に隋使が帰る時に託した、煬帝宛ての国書である。
国書の書き出しは、「東の天皇、敬んで西の皇帝に白す」となっている。ここでは、もはや「天子」でも「皇帝」でもない。ましてや「倭王」ではない。ここでは、はっきりと「天皇」号が使われている。75
――――――――――――――――――――――――――――――
倭国には多くの国があったことがわかる。そして、「大倭王」は、「邪馬台国」に都を置いていた。つまり、倭国は連合王国だったのだ。しかも、それらの国はすべて世襲王権であったことが、明らかとなった。
そうか、わかった。倭国(日本)は、もとから世襲の国だったのだ。146
――――――――――――――――――――――――――――――
大和王権がめざしたのは、天皇を国家の長とする律令体制である。律令体制は、中華帝国が行っているような政治に基づいたシステムである。
中華帝国風の律令体制を採用すると、制度上、国家の形は、自分の国が、宗主国・覇権国になる。つまり、中華帝国と同じような体制になる。これが小中華帝国である。とにかく、小といっても、中華は中華である。152
――――――――――――――――――――――――――――――
当時の倭国が決心したことは、「私たちは、日本列島に立て籠もって、日本という中華帝国によく似た国家を形成するぞ」なのである。だから、日本は、中華帝国の冊封体制に入らないだけでなく、中華帝国の勅諭も聞かなかったのである。162
――――――――――――――――――――――――――――――
「日本」という国号をいつ決めたのかという史料はないけれども、大宝律令と養老令から、「日本」が律令体制とともに現れることだけは確実にわかる。
「日本」という国名は、大宝律令以来、ずっと使われてきている。165
――――――――――――――――――――――――――――――
日本は、中華帝国のような国家になりたかった。これが、日本の強い望みであった。
この中華帝国によく似た国家が、天皇を国家の長とする日本律令国家である。170
――――――――――――――――――――――――――――――
王朝から王朝に替わる時期というのは、戦争です。その覇権争奪戦に勝たないといけないわけですが、このときに、「徳」によって「天命」を受けたという主張が必要なのです。
政治的人間たちは、統治される人々を説得しないといけないのですが、それに先立って、まず自分を説得、つまり自分で思いこまなければならないのです。
政治思想というのは、最終的には、支配の事実をどう合理化するか(もっともらしい理屈をつけること)ということなのです。191
――――――――――――――――――――――――――――――
中華帝国の「徳・天命・王朝交替」が、セットになった政治思想が、日本に入って来ると、まずいことがわかる。
日本には、思想が希薄だから、あまり心配ないと思っても、万が一ということがある。だから、本家本元の中国の律令にある、王朝交替の思想に基づく条文を、日本律令は自覚的に削除している。192
いまここで大事なのは、「議賓」である。193
――――――――――――――――――――――――――――――
律令国家は、行政指導・官僚統制型の国家であった。律令国家は、国民に行政指導をおこない、国民と経済を国家の統制のもとに置こうとした国家である。198
律令政府とその後の政府が、なぜ国民に行政指導をしたのか。それは、一言でいえば、現在の企業のようなものがなかったからである。199
行政指導は、せいぜい明治政府の行政、あるいは戦時統制経済くらいのところにあると考えているであろう。しかし、この行政指導は、律令国家以来の一千年の伝統があって、現在につながっているのである。200
行政指導・官僚統制型の国家にならざるをえなかったのは、中国の律令を導入したためである。ということは、行政指導と官僚統制が、東アジアの伝統だということである。202
――――――――――――――――――――――――――――――
なぜ、政治家よりも官僚のほうが、エライとおもえるのだろうか。それは、日本では、政治家というのは、部族制の昔からずっと、王の臣下である官僚たちのことだったからだ。長らく日本では、国会議員などではなくて、官僚そのものが、政治家だったのである。226
簡単に言うと、官僚と政党政治家は、それぞれ所属する部族が違うのだ。227
――――――――――――――――――――――――――――――
明治から昭和の敗戦までを見ても、文官官僚であれ軍事官僚であれ、官僚上がりで、政治家になった者たちが、出身母体であった官僚たちから疎まれて、協力して貰えないことがよくあった。
その原因は、もとの部族をはなれると、部族外の人間になってしまうからである。
「陸軍あって、国家なし」「省益あって、国益なし」「局あって、省なし」、あるいは「課あって、局なし」などと言われたことはすべて、サブ・システムに実権が移っているということを言い表しているのである。227
――――――――――――――――――――――――――――――
拡大部族制+律令制+イギリス+プロシャ型政体+アメリカ型政体225
日本が、拡大部族制をベースにした混合政体であることを理解すれば、日本のことは、わかるのである。228
――――――――――――――――――――――――――――――