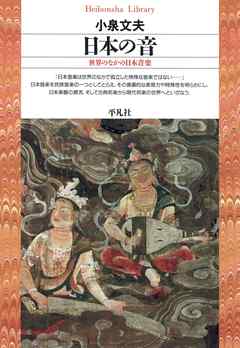あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
「日本音楽は世界のなかで孤立した特殊な音楽ではない…」日本音楽を民族音楽の一つとしてとらえ、その普遍的な表現力や特殊性を明らかにし、日本楽器の源流、そして古典邦楽から現代邦楽の世界へといざなう。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
読み返すたびに、
あゝ このことだったのか、
を再発見させてもらえる
極上の一冊です。
その時には スルーしていたところが
おっ これっ!
と読み取れた時の快感はたまりません。
それにしても
私たち(日本人)は特殊な音楽環境に
置かれてしまっているのだ
をちゃんと心得ていることは
ほんとうに大切だと思います
ご逝去されて
来年で生誕百年になるとのこと
小泉文夫さんがおっしゃっておられた
音楽への教えはますます現実味を
帯びて来たように思えます
Posted by ブクログ
日本語を母国語に持ち、日本列島に生まれ育った自分が、音楽について考えるにあたって、限りなく視野を広げてくれた一冊。食生活や生活環境、その土地の風土、言葉など、人が生きるにあたって身の回りにあるものが音楽にどれほどの影響を、具体的に与えているのかということを示してくれる。
音楽家の伊福部昭が「民族の特殊性というものを通過して、共通の人間性に到達しなければならない」という信念を持ち、「真のインターナショナルはローカルを通してでないと到達できない」と語っていたように、人間本来の根源的な何かに触れるものをとらえようとするなら、この国の民俗性について注意深く目を向けなければならないわけで、この本はそのために必要なさまざまな知見と示唆を与えてくれる。
ポピュラー音楽を見つめるにあたって、何度でもここに立ち返らなければならないように思う。音楽について考えたいのであれば、中村とうよう『ポピュラー音楽の世紀』と並んで必読。
Posted by ブクログ
日本文化を「音楽」の視点から取り上げ、日本音楽を民族音楽の一つとして捉え、その普遍性と特徴、世界の音楽との関係など、様々な観点から世界の中での位置付けを探るもの。
Posted by ブクログ
改めて、日本の音楽教育は片手落ちだと思わされる。明治維新、戦後と伝統文化軽視の風潮のなかで疎かにされたもの。こないだテレビで見た唐招提寺の番組とも重なるが、音楽には建築と異なる点もある。また、日本の音楽や楽器の伝統を踏まえながら、現在の状況と展望について語る内容は、70年代の空気を差し引く必要はあるかもしれないが、ほぼ現代に通じる。自分の周りの音楽を見渡し、その特徴や他の音楽との関わりなどを考えるきっかけになる、視野を拡げてくれる一冊。
Posted by ブクログ
老若男女問わず、いろんな人に読んでもらいたい1冊。
ホントに1970年代の本? と思わずにはいられないほど、現代の感覚を持った小泉文夫さんの本です。
この本と出逢って、また違う世界が開けました。
Posted by ブクログ
学生時代の坂本龍一が最もインパクトを受けた講義が小泉氏のものだったという。そして彼が音楽に向き合う態度を決定付けたと言われる小泉音楽論の決定版
Posted by ブクログ
・・・・・書きかけ・・・・・
存命なら83歳、三國連太郎よりも4歳も若い小泉文夫は、1927年3月29日に東京で生まれた民族音楽学者ですが、残念ながら27年前の1983年にわずか56歳で亡くなりました。
私たちは、映画では小津安二郎や黒澤明や大島渚や宮崎駿を、世界に誇れる存在だと知っていても、音楽について武満徹や高橋悠治や小泉文夫がそれに値することをあまり認識していないのではないでしょうか。
中でも音楽の直接の創作者でも演奏家でもない小泉文夫がなぜ重要なのか?
『おたまじゃくし無用論』(1973年)や『歌謡曲の構造』(1984年)など通俗に向けた論考もユニークきわまりないのですが、
Posted by ブクログ
日本文化論。明治からの音楽政策、文化政策を批判的な立場で論じ、西洋一編主義であった政府の、恐らく国是として進めていた、日本文化に対する危機感があった。
Posted by ブクログ
小泉文夫 「 日本の音 」民族音楽学の本。内容は「西洋模倣により 自己喪失した 日本音楽の原因と提言」このような分野の学問があることを知らなかったが、第一人者の話は引きこまれる。わらべうたなど 日本音楽の表現特徴、音楽教育の問題点、仏教音楽、能の話は 面白い
わらべうたなど 日本音楽の特徴
*西洋音楽のリズムは強弱→日本のリズムは前後
*日本音楽のリズムの強弱は 音楽の表現技法
*再創造=時代や好みによって形を変える
日本音楽の西洋化の原因と提言
*日本人が親しむ西洋音楽は その花の部分〜その元となった茎や根まで 感覚の領域は 至っていない
*日本人が日本音楽に疎遠になった理由は学校教育〜西洋音楽一辺倒の教育→日本の楽器、音階、リズム形式を放棄して 西洋音楽に変換してしまった
*朝鮮、インド、西アジアから学ぶべき
*日本語に結びついた表現(わらべうたを出発点とする音楽教育) からの教育が必要