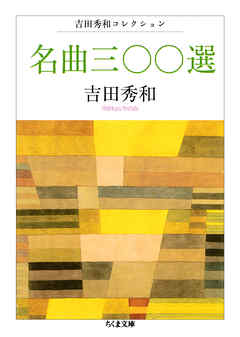あらすじ
グレゴリウス聖歌やルネサンスの音楽から、ブーレーズ、シュトックハウゼンらの現代音楽まで―音楽史の流れをたどりながら、きくものに忘れがたい感動をあたえる傑作300曲を選び、文化や芸術への深い洞察に満ちた解説を加える。音楽の限りない魅力と喜びにあふれる「名曲の歴史」。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
『名曲300選』と銘打っているが、所謂「クラシック名曲ガイド」とは一線を画しており、吉田独自の視点がかなり入っている。例えば定番のドヴォルザークの「新世界」は300選に入っていない。
したがって、“入門”を期待して読むと肩透かしを喰らうだろう。だが、文章自体は格調高く読みやすい。
「グレゴリオ聖歌」から始まるため(グレゴリオ聖歌は音楽の授業で習った記憶はあるが)、正直なところモンテヴェルディが出てくるまでさっぱり分からなかった。それだけ聴いてきた音楽の幅が狭いということだろう。
もちろん、「狭い=悪い」ということでは決してない。
Posted by ブクログ
吉田秀和せんせいの視点から、クラシックの名曲(・名盤)を300曲集めようという趣向です。
もとは、その曲の名演レコードを集めるという趣向だったようですが、文庫化にあたってその部分は削除したとのこと。
クラシックの名曲・・・と言えば、何と言ってもヴィヴァルディやバッハ辺りから始まるのかな、と考えるわけですが、そこは吉田せんせい。第1曲目はいわゆる「宇宙の音楽」、歴史に残るの残らないのどころではない、遙か原初の音たちに捧げる、というのですからスケールが違う。
続くグレゴリウス聖歌は納得なのですが、その後は宗教から世俗へ、宮廷から民衆へ、モノフォニーからポリフォニーへ、ルネサンスを経てバロックへ、というような悠久の変遷をたんねんに追い、バッハが出てくるのはようやく144ページ目(340ページの本の)だったりして、ご本人は「音楽史じゃない」とは言うものの、すぐれた音楽通史の本として読むことができます。
バッハは「今さら言うまでも・・・」という筆致ですが、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン(に至っては一人に一章を割いている)については綿密に描き出し、さらにロマン派に入ってヴァーグナーが一つの頂点をなしているところがこの本のポイントかとも思えます。
一方、その後の周辺諸国、すなわちフランス・イタリア・ロシアや北欧の中後期ロマン派の作曲家については、ほとんどスルーに近い書き飛ばしっぷり。マーラー辺りまではまだ軸足が乗っているかなとも見えますが、チャイコフスキーやシベリウスなどは一応触れたからもういいでしょ、という感じです。
ドビュッシーに至って最後の感嘆の声が挙がりますが、そのあとは二十世紀の音楽としてほとんど十把一からげ。
この辺は、魅力的な楽曲を書いたか否かではなく、音楽にいかなる革新的価値をもたらしたか、という視点が冷徹に貫かれているからかも知れません。
また、日本人はいつ出てくるかな(どきどき)と読んでいると、終わりから三行目、加筆の部分にようやく武満徹が「今、この本を書いたなら当然挙げただろう」ということで登場。本が最初に書かれたのが1960年代ですから、無理もないというところか。
このように時代背景(本が書かれた時分の評価や流行など)や著者のスタンスを若干割り引く必要はありつつ、前述の通りクラシック音楽の壮大な通史として非常に勉強になる本でした。