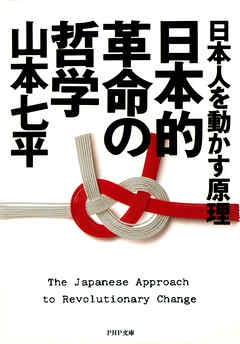あらすじ
本書は、「日本的革命家」北条泰時の思想と、その手になる『貞永式目』を、日本人の相続原則・刑罰思想・日本的実力主義など、様々な側面から克明に考察。そこから「道理のおすところ」たる日本人の行動原理を浮き彫りにする。日本における『貞永式目』の意味を初めて明らかにした画期的な名著である。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
鎌倉幕府、三代執権北条泰時を中心とした、日本的革命論
公家から武家への階級闘争は、鎌倉幕府の成立ではなく、承久の乱の過程で生じたと論ずる。
東国を支配していた鎌倉幕府は、それまで、西国については、支配することはできていない。天皇および上皇・院が西国を支配していたからだ。
しかし、乱以降は、京都に六波羅探題を置き、以後明治に至るまで、武家が全国統一して日本を支配することになるのである。
北条泰時の偉業は以下のとおりである。
・ゆるやかな武士の連合である、鎌倉幕府が、京都の天皇連合軍を破り、源頼朝でさえ成し遂げられなかった武家の全国統一を成し遂げた。
・三上皇を地方に流して、鎌倉幕府に都合のよい天皇に変更、貞永式目をつくって、公家を制御した。以後、日本は、象徴天皇制に移行、現在に至る。
・貞永式目とは、これまでの律令(中国からの輸入)から、はじめて、日本古来の固有法を制定した。しかも、律令制では、立法権をもっていないかった北条泰時であり、その後全国にこの制度を定着させた。この制度は、承久の乱にて混乱した世を収める上で、必要な明文法でもあった。
・北条泰時の政治とは、暴力を極力嫌う、徳の政治であり、承久の乱で敵となった多くのものを救った。
・承久の乱で敵となったものを、かくまった明恵上人を許したどころか、貞永式目制定にあたっては大いに、参考にした。
鎌倉時代の特長として驚いたものは以下です
・女性も相続権を有していた。北条政子を含めて女性が強かったのは、相続権を含めて女性の発言力が大きかったため。
・鎌倉幕府とは、統制が厳しい組織ではなく、緩やかな豪族の連合としてなりたっていたこと。執権とは支配者ではなく、あくまでも調整者であった。
・天皇家にはむかってはならないという不問律が存在していて、ぐずぐずしていては、天皇家に味方する豪族が寝がえりかねなかったこと。
・承久の乱までは、日本は、東国は鎌倉幕府、西国は、天皇家と分かれていて、別の国のように統治されていたこと。
乱を収め、争いをまとめるために、大変な貧乏だった、北条泰時の治世は、後世徳政とうたわれるのであった。穏やかで、人を殺したり、争うことが嫌いであった執権が、一代で成し遂げたのが、日本的革命であった。
目次
序文
第1章 日本に革命思想はなかったか
第2章 聖書型革命と孟子型革命
第3章 北条泰時の論理
第4章 「承久の乱」の戦後処理
第5章 明恵上人の役割
第6章 明恵上人と北条泰時
第7章 明恵の裏返し革命思想
第8章 「貞永式目」の根本思想
第9章 調整型経営者・泰時
第10章 象徴天皇制の創出とその政策
第11章 「貞永式目」の制定過程
第12章 日本人の相続原則
第13章 「泰時の平和」のジレンマ
第14章 鎌倉時代の宗教の自由
第15章 「式目」の刑罰思想
第16章 日本に奴隷制はあったか
第17章 統治する側の職務と権限
第18章 日本的実力主義の論理
ISBN:9784569564630
出版社:PHP研究所
判型:文庫
ページ数:362ページ
定価:621円(本体)
発売日:1992年04月15日 第1版第1刷