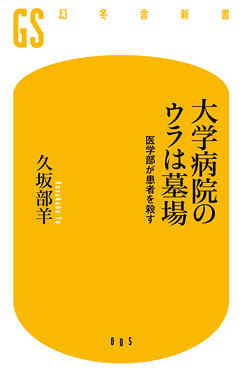あらすじ
心臓外科医が患者を四人連続死なせたがそれを「トレーニング」とうそぶいた(東京医大)、未熟な医師がマニュアルを見ながらの内視鏡手術で死なせた(慈恵医大青戸)、人工心肺の操作ミスで死なせたあとカルテを改竄(東京女子医大)……なぜ医療の最高峰ともいうべき大学病院は事故を繰り返し、患者の期待に応えられないのか。その驚くべき実態と医師たちのホンネに迫り、医者と患者の間に立ちはだかる本質的な壁を浮き彫りにした。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
大学病院の現実と世間の意識のギャップを的確に著していると思う。
世間の認識を変えることが必要であるという主張にも説得力がある。
医局が崩壊していること、医療がいまや崖っぷちの状況であること。
ジャーナリズムとして客観的によく書き切ったと思う。
オレは理学部出身だけど医学部の一部の連中とは特に気が合ったんで、3年4年の頃には毎週のようにスキーや飲みに行ったもんだ。
しかし、自分が病気にかかったら、彼らだけには診て欲しくないと思ったものだった。
どこも実態は似たようなもんなんだろうけどね。
オレが付き合ってた連中(10人くらいか)が特にバカ揃いだったこともあるけど…
(2008/5/6)
Posted by ブクログ
タイトルだけ見るとどんなとんでも本かと思うのだけど、中身は素晴らしかった。確実に確かな医療が受けられると信じて疑わない現在の私たち。患者、医師両サイドの意識改革の必要性を警鐘している。医療崩壊と言われて久しい日本であるが、この書籍を読むと内実がよく理解できる。
<今後の医療発展のために必要だと感じたこと>
・医療ミスを糾弾するのではなく、補償制度を充実させることで対処。
・研究、臨床の分離。研究分野で先進医療を受けるものは治験を受け入れ、その代わり医療費を免除。
・医師の将来の保証。その分若い頃に技術修練などに頑張れる。
Posted by ブクログ
同じ自由が認められながら、なぜ今までは日本の医療はまがりなりにもやってこられたのか。それは端的に言えば、医師と時代そのものにモラルがあったからであろう。自由に任せていても、医学生は自分の能力に応じた科を選び、必要とされる場所で勤務し、節度をもって開業していた。医学部がそれほど多くなく、優秀なものが医師になり、世間から尊敬される分、それに見合う責務を果たしていた。
時代のモラルが低下したことも大きい。ルールさえ守れば何をしてもいいという風潮、少しでも自分が得をすることが要領のよい生き方とされ、若者はそのための情報収集に奔走している。
診療にすぐれた医師を優遇せよ
良い医療が優遇されれば、医師は水が低きに流れるごとく良い医療に向かう。しかし今、良い医療を行おうとすれば、医師の私生活が破壊されかねない状況になっている。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
心臓外科医が患者を四人連続死なせたがそれを「トレーニング」とうそぶいた(東京医大)、未熟な医師がマニュアルを見ながらの内視鏡手術で死なせた(慈恵医大青戸)、人工心肺の操作ミスで死なせたあとカルテを改竄(東京女子医大)…なぜ医療の最高峰ともいうべき大学病院は事故を繰り返し、患者の期待に応えられないのか。
その驚くべき実態と医師たちのホンネに迫り、医者と患者の間に立ちはだかる本質的な壁を浮き彫りにした。
[ 目次 ]
第1章 「大学病院だから安心」ではない
第2章 大学病院の言い分
第3章 大学病院は人体実験をするところか
第4章 必要悪「医局」を崩壊させたのはだれか
第5章 先祖がえりした新臨床研修制度
第6章 産科医、小児科医につづき、外科医もいなくなる
第7章 大学病院の初期化が必要
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
センセーショナルなタイトルとはちょっと違う内容で
現在の日本の医療界の問題を淡々と述べていました。
著者さん、実は面白い人なんじゃないかと思います。
マスコミは理想論ばっかり言うんじゃないよー!
というお叱りの本ですが、
この本も結構理想論だと思いました。
ワタクシは、現実を見て理想を述べられるのは好きなので、
この本も結構好きです。
日本のお医者さん、頑張って欲しい。
最近話題の医師不足に興味のある人にはおススメ。
Posted by ブクログ
立場的に患者と医療者の中間…のような位置にいる私には、賛同する部分と複雑な気分にさせられる部分とがありましたが、筆者の主張は共感する部分が多いように感じました。
研修医の教育システム然り、マスコミの助長による過度な医療不信然り。
医師不足の危機を招いているのは、世間が異常なまでに正義を振りかざし、現実離れした理想論を追い求めた結果かもしれない。
普通の企業に就職しても、新入社員は失敗してそこから学んで成長していくものだと思います。ベテランだって、人間がやる仕事である以上ミスが0なんてことはあり得ない。
医療者だって同じです。命を預かる以上、「ミスしました、はいそうですか」では済まない事は事実ですが、新人のうちは患者に協力してもらって練習させてもらうしか技術を向上させていく道はないんです。
新治療法も、誰かが実験的に始めてくれない限り、発展することはないんです。
「患者も賢くならなければならない」とはよく言われますが、自分の主張を通す賢さだけでなく、こういった側面もあるということに対しても賢くなってもらわなければ、本当に日本の医療は崩壊します。。
Posted by ブクログ
書名を見ると週刊誌的に大学病院の内部を告発する内容かと思うが、実質はその反対に近い。
大学病院が一般の病院と違うのは、教育・研究という部門が治療部門とは別についていて、そのため未熟な若い医師のオン・ザ・ジョブ・トレーニングの場になっていることだ。それは次の世代の医療を供給するのに必須なのだが、当然一定のリスクを伴う。
それで事故が起こるとマスコミは袋たたきにするが、常にベテランが治療に当たるのは物理的に不可能だし、実践を積まないでベテランにはなれない。
筆者ははっきりと、必要もないのにいつもベテランの最高度の医療を求めるのは患者のエゴであり、マスコミの無責任なあおりのつけは必ず将来の医療や地方やマイナーな医科などにしわ寄せがいくと批判し、リスクがまったく伴わない医療はありえず、必要なのはリスクをゼロにしようとする不可能な努力ではなく患者と納得した形で合意できる保障制度だとする。
ここでの批判の対象は、むしろできもしないことを要求するマスコミと患者のエゴの方だ。そしてこの議論にはかなり説得力がある。
Posted by ブクログ
大学病院とその他の病院。同じ「病院」と名がついていながら前者は医学の研究に重きを置いていて後者は診療に重きを置いている。大学病院が診るのは未来の患者、その他の病院が診るのは現在病気を抱えた患者。誰かが研究をしていかないことには医療分野は発展しない―。
現在の日本の病院が抱える問題点(主に大学病院の構造とその問題点)についてまとめてある本。病院選びで泣かないように、診療を受ける立場である私たちが読んでおくと面白い。
Posted by ブクログ
日本の医療の現状とその問題点、その問題点の背後の歴史や事情。
それをよく知るマスコミの必要以上の煽動とただ自分たちの利益のための世論誘導。
そしてそのマスコミに煽られる市民。
その市民たちの反発を恐れ、必要以上の(悪ともいえる)制度を作ってしまう役所。
その制度に翻弄される病院と医師。そして押し寄せてくるプレッシャーと世論の反発に耐えられなく辞めていく医者。
そして医療問題がますます深刻になる。
病院、医師の視点、役所の視点、そして患者と一般市民の視点とそれぞれの本音をちゃんと書いている。
作者は医師で作家である。だからこそかけたこの一冊だと思う。
ただし、逆に医者だから見解が偏ってしまっている部分もある。
自分のために読んでおくべき本だと思う。
Posted by ブクログ
医療現場の問題点を洗い出し、批判と改善案の提案を行なっているが、当事者としての問題提起というより、外部からの無責任な批判のようにも読める。
何が医療の根本原因なのかを考える必要がある。
Posted by ブクログ
センセーショナルなタイトルからすると、大学病院は無理な人体実験を繰り返したり、研修医や医学部の学生の練習の場であり、それを告発する内容かと思いきや、全く逆で、大学病院は信頼に足り、また事件や事故のたびに、マスコミの批判や理想論に対応したこれまでの改革が、旧制度の医局を喪失したりして、それらが日本の医療の崩壊に向かっているという憂国(憂医療?)の書である。
医局の件については特に力点を置いている。
(注)医局とは医師・歯科医師の執務室、控室のことを指す。ここから転じて、大学医学部・歯学部の附属病院での診療科ごとの、教授を頂点とした人事組織のことを医局と呼ぶ。
「旧弊な医局制度が破綻し、医師は自由を得た代わりに、安定と将来の保障を失った。世間は不透明な寄付や名義借りをしなくてすむようになった代わりに、地域医療と産科医・小児科医を失った・・・(略)・・・訴訟のリスクの高い科の医師を失いつつある」と。
具体的には、従来は医局の教授が、一般病院はおろか過疎地域の病院まで目くばせして医師を配置してきたが、それが無くなった現在は、若手医師は激務の大学病院を逃げ出し、また地方や過疎地を避け、都会の開業医を目指している。
一方、時間の予定が立たない産科医や、子供相手の面倒な小児科、そして訴訟リスクの高い外科医を失いつつあると言う。
そして著者は言う。「そもそも大学病院とは人体実験を行ったり、新人の教育をするところなのだ。それを認めない事には、話が前に進まない」
大学病院は医師の数も多く、その分監視の目が多いということであり、間違った治療はチェックされ、また情報も多く集まるので、大学病院の医療は信頼に足ると。
著者は、現場の医師の声を代表して、現在の過酷な医師の実態と、将来の医療制度を理想論ではなく、現実的な目から見てくれと叫んでいる。
少し別な観点からみると、大学病院は研究・治療・教育と幾重もの役割を負わされているのがよく分かった。
そして良き研究者は良き治療医ではないと言うことも。
Posted by ブクログ
タイトルからはもっと軽いタッチの作品かと思ってたけど、いたって真面目な内容。ちょうど同時期に読んだ“医療の限界”と似てるな~、って思ってたら、やっぱり本作者も少なからず共感されてました。でも日常業務の忙しさのあまり、声を上げて医療の現状の打破を試みる人がほとんどいないから、こういう主張をどんどんしていくべきだとは思います。
Posted by ブクログ
この本のタイトルと内容には相当開きがあります。
医学部、大学病院、医局から観た医療制度改革の問題点について医師から見た意見であり、それを正しいと思うか?おかしいと思うかは読み手次第でしょう。
Posted by ブクログ
理想主義が日本の医療全体を破綻に向かわせた
制度が崩壊し問題点もわかってきたのだから、そろそろ、それらを織り込んだ次の制度が出てきてもよいのでは。
Posted by ブクログ
入院したときに隣りのベッドにいた患者さんが家族との会話の中で「大丈夫、先生に心付け渡しておいたから」と言っているのを聞いてすごく嫌な気持ちになったんだけれど、これを読み終わってみると、あれはあながち賄賂でもなくて、国家公務員一種職の天下り退職金みたいなものなのかな…と思った。私は大学病院に過剰な期待はしていない。あんなに大きくて患者が多いのだからベルトコンベアになっても仕方ないと思う。あとは先生との相性。
Posted by ブクログ
大学病院は人体実験をするところである、とはっきり言ってくれてスッキリです。患者側が医療に対する過度な期待を持ちすぎているとの現実認識も非常に的確だと思います。勉強になりました。
Posted by ブクログ
なぜ医療の最高峰ともいうべき大学病院は事故を繰り返し、患者の期待に応え
られないのか。その驚くべき実態と医師たちのホンネに迫り、医者と患者の間
に立ちはだかる本質的な壁を浮き彫りにする。