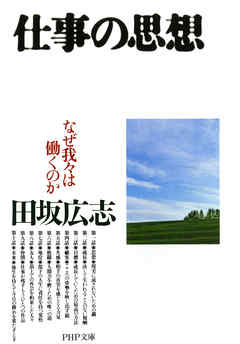あらすじ
なぜ、我々は働くのか。この深い問いに対しては、あくまでも、私たち自身が、その人生と思索を通じて、答えを見つけていかなければなりません。本書は、その思索を深めるために、仕事の真の報酬とは何か、を始めとする様々なテーマについて、著者の体験的なエピソードを交え、語っていきます。仕事を通じていかに成長していくか。成長のために夢や目標はいかなる意味を持つのか。なぜ顧客は成長の鏡となるのか。顧客との共感ということの本当の意味は何か。人間学を学び、人間力を身につけていくための唯一の方法は何か。なぜ、人間との格闘が大切なのか。働く人間にとって地位とは何か。生涯、会うことのない友人が、なぜ、我々の支えとなるのか。仕事の本当の作品とは何か。職場の仲間とは何か。仕事において、未来とは何か。そして、なぜ、仕事に思想が求められるのか。それらのテーマを深く考えることを通じ、読者一人ひとりに、生き方と働き方を問う本です。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
尊敬できるような人物が職場に少なく、ためになる仕事の心得を聴くこともないので、何か勉強になればと思い本書を購入した。
成長のためには自分の「夢」を本気で語り、そのための「目標」を定めることというポイントが最も勉強になった。
「夢」があるから人は大変な状況下でも力を振り絞ることができるとの説明にはとても納得した。
今現在、自分には本気で語れるような夢がない。あるとしてもそれとして認識していない。
「自分の夢の見つけ方」を次の自分の問いとして頭に抱えつつ、自分が人生をかけて成し遂げたいことは何か考えながら過ごしたい。
Posted by ブクログ
その問いを、深く問い続けていただくために、 思想 / 現実に流されないための錨 成長 / 決して失われることのない報酬 目標 / 成長していくための最高の方法 顧客 / こころの姿勢を映し出す鏡 共感 / 相手の真実を感じとる力量
格闘 / 人間力を磨くための唯一の道 地位 / 部下の人生に責任を持つ覚悟 友人 / 頂上での再会を約束した人々 仲間 / 仕事が残すもうひとつの作品 未来 / 後生を待ちて今日の務めを果たすとき というキーワードをとりあげ、全一〇回のシリーズとしてお話ししました。
「君も、あの高校の悪い評判は聞いているだろう。 それなのに、なぜ君は、あの学校を選んだのかい」 そのときの彼の答えが、いまも忘れられません。 彼は、決して気負うことのない静かな口調で、こう答えたのです。 「たしかにあの学校は、非行や校内暴力が問題になっている高校だよ……。 だけど、そうした学校にこそ、本当の教育が必要なのではないだろうか……」
そして、私は、仕事において困難に直面したとき、 いつも、彼のあの言葉に励まされてきました。 私は、仕事において困難に直面したとき、彼の言葉を思い出します。 そして、思うのです。 それなりの大学を出て、希望すれば好きな学校を選べる立場にあった彼が、 あえて、誰も選びたがらない困難な道を選んだことの意味を。 そして、その彼の後ろ姿が、「なぜ我々は働くのか」という問いを、 私に思い出させてくれるのです。
「最近になって、ようやく仕事が見えてくるようになったよ。 振り返れば、昔は、見えていなかったことがたくさんあったんだな……。 いまは、仕事の裏の動きや、仕事の先の展開が、 いやになるほどよく見えるんだよ……」 「いまは、仕事をどう仕掛ければよいかが、よくわかるようになったよ。
だから、ようやく、やりたい仕事がやれるようになってきたんだ……」 そうした彼の発言を聞いて、私は、 彼が、ひとりのビジネスマンとして、 その能力を急速に開花させていることを感じました。
そして、さらに五年の月日を重ねたころのことです。 また、彼と会う機会がありました。 私自身も、ビジネスマンとしての道を八年も歩んだころのことです。 かつて彼が言っていた「仕事の裏の動きが見えてくる」 「仕事の先の展開が見えてくる」「仕事の仕掛けかたが見えてくる」 ということの意味がわかってきたころでもありました。
「仕事というものは、こころを込めてやれば、何でも面白いよ……」
彼は、その商事会社で、 商社マンという仕事が「天職」であるかのように活躍しています。 仕事においては上司や顧客から信頼され、 職場においては同僚や部下から頼りにされ、 ひとりの熟練のマネジャーとして活躍しています。 その彼の活躍は、いろいろなところから伝わってきますが、 たとえば、あるとき、私は彼の職場の同僚とふとした縁で知りあい、 酒の席で、その同僚から次のような評価を聞いたことがあります。
「あいつは、夢のある奴だよ。そして、あいつは志を持っている。 うちの会社には、いなくてはならない奴だよ……」
「仕事の報酬は、給料である」という世界を超えて、 その向こうに、何かが見えるようになってくるのです。 給料という報酬を超えて それが、おそらく、「仕事の報酬は、能力である」という世界です。 そして、それは、仕事をおぼえることが面白くなってきたときに 見えてくる世界なのです。 仕事の能力を磨くことが楽しくなってきたときに見えてくる世界な
そもそも、「できなかったことが、できるようになる」という体験は、 人間にとって本源的な面白さであり、楽しさなのでしょう。 だから、それが、だんだんと面白くなってくるのです。 とくに、企画力や営業力などの高度なスキルやノウハウが求められる仕事は、 それができるようになるのは大変ですが、ひとたびその能力を身につけると、 大きな喜びを味わうことができます。 新しいスキルやノウハウを身につけることの面白さが味わえるのです。 たとえば、企画力が求められる仕事には、 そもそも、新しいビジョンや戦略を創造するという面白さがあります。
また、営業力が求められる仕事には、 そもそも、生身の人間を相手に商品を納得してもらうことの喜びがあります。 そして、商品を納得してもらうためには、何よりも、 その商品を売ろうとしている人間を納得してもらわなければならない ということに気がついたとき、その喜びがさらに深まっていくのです。
そして、こうして仕事のスキルやノウハウを身につけていくと、 当然のことながら、自分の能力を周囲から認めてもらえるようになってきます。 社内のいろいろなプロジェクトに メンバーとして参加することを求められるようになります。 そして、それはそのまま、 「自分の能力が社内でどれほど必要とされたか」という形での
業績になっていくのです。 もちろん、勤めている会社が典型的な年功序列型の賃金体系であったり、 皆さんが入社したばかりの若手社員である場合には、 そうした業績が、そのまま給料に反映されるわけではありませんが、 自分のプロフェッショナルとしての能力が確実に高まっていくことに対して、 実感と満足感を持てるということはきわめて大切です。
最近、給料の高さだけに目を奪われて企業を選ぶ若い人々が増えていますが、 こういう人々を見ていて心配になるときがあります。 なぜならば、多くの場合、高い給料を与えてくれる企業は、 あまりスキルやノウハウを磨かせてくれないからです。 給料が高いだけ、即戦力的なものを求めるからです。 したがって、いきおい人材育成という視点は弱くなります。 しかし、逆に、給料は低くとも、人材育成という視点を大切にして、 若手社員にじっくりとスキルやノウハウを磨かせてくれる企業があります。
たとえば、自分でやってみたいプロジェクトの企画があったとします。 もし魅力的な企画をつくる能力も、 それを上司や顧客に売り込む能力もなかったならば、 そうしたプロジェクトの企画を実現することは決してできません。 逆に、仕事のスキルやノウハウを磨いていくと、 自分のやってみたい仕事ができるようになっていきます。 自分の企画し、提案したプロジェクトに社内の関係部局が賛同してくれる。 そして、顧客が採用してくれる。 そうしたことを通じて、自分のやりたい仕事をやれるようになってくるのです。 私の友人が語った、
しかし、企画力や営業力などのビジネスマンとしての能力を磨いていくと、 自分にとってだけでなく、会社にとっても、顧客にとっても、 さらには、社会にとっても、有意義な仕事を企画できるようになり、 自分にとって「やりたい仕事」と「やりがいのある仕事」が ひとつになっていくのです。 そして、こうした段階まで能力を磨いていくと見えてくるのが、
「仕事の報酬は、成長である」 すなわち、仕事を一生懸命にやっていると、 仕事のスキルやノウハウが身につき、仕事の能力が磨かれ、 ひとりの職業人として成長していくことは当然ですが、実は、それだけでなく、 ひとりの人間として成長していくことができるのです。 そして、その成長を実感し、その成長の喜びを味わうことができるのです。 では、この「人間としての成長」とは何でしょうか。 それは、「こころの世界が見えるようになってくる」ということです。
なぜならば、「働く」とは、「傍」を「楽」にさせることだからです。 そばにいる顧客や仲間を楽にさせてあげることだからです。 たとえば、顧客に提出する企画書ひとつでも、顧客の要求や希望だけでなく、 顧客が社内で置かれている立場や気持ちがわかっていると、 いわゆる「痒いところに手がとどく」ような企画書が書けるのです。 そして、そのことによって、顧客を楽にしてあげられるのです。
また、職場の仲間と協働して進めるプロジェクトにおいても、 単に仲間の能力や適性だけでなく、仲間の性格や気持ちがわかっていると、 プロジェクトを文字どおり「円滑」に進めていくことができるのです。 そして、そのことによって、仲間を楽にしてあげられるのです。 そして、こうして、顧客や仲間を楽にしてあげられると、 顧客や仲間の喜ぶ顔を見ることができます。 そして、その喜ぶ顔を見ることによって、私たちは、 自分の成長を実感し、成長の喜びを味わうことができるのです。
たとえば、自分でやってみたいプロジェクトの企画があったとします。 もし魅力的な企画をつくる能力も、 それを上司や顧客に売り込む能力もなかったならば、 そうしたプロジェクトの企画を実現することは決してできません。 逆に、仕事のスキルやノウハウを磨いていくと、 自分のやってみたい仕事ができるようになっていきます。 自分の企画し、提案したプロジェクトに社内の関係部局が賛同してくれる。 そして、顧客が採用してくれる。 そうしたことを通じて、自分のやりたい仕事をやれるようになってくるのです。 私の友人が語った、
生活のために毎日自分の労働力を切り売りしているという感覚
これからは、会社で働く俺が、 ジャズを愛するもうひとりの俺を食わせていくんだ……」
「この人は、かならず成長していくだろう」と感じます。 しかし、面白いことに、こうした「成長の方法」というものは、 無意識に身につけていることが多いのですが……。 では、こうした人々を分ける「成長の方法」とは何でしょうか。 実は、「成長の方法」ということには、いくつかの基本的な原則があります。 それをすべて語ると、それだけで一冊の本が書けるほどですが、 ここでは「仕事の思想」という文脈において 最も大切な「成長の方法」を述べたいと思います。 それは、何でしょうか。
それは、「夢」を語り、「目標」を定めることです。 夢を語り、目標を定めることが、 人間が成長していくための最も大切な方法であり、最高の方法なのです。
ハンバーガーをかじりながら話を始めます。 すると、話はすぐにどこまでも広がっていくのです。 スタートしたばかりのこのシンクタンクを、日本一のシンクタンクにしたい、 いや、日本一では目標が低すぎる、めざすならば世界一のシンクタンクだ、
などと、横で聞いている人がいれば 誇大妄想に思われるような話をしていたのです。 しかし、それは、最高に楽しいひとときでした。 ついさきほど肩を落として客先から出てきたことなど、すぐに忘れてしまい、 これから自分たちが創りあげていくシンクタンクの将来の「夢」を 語り続けたのです。
やはり、「夢を語る」ということが、 私たちに生き生きとした目標を与えたのであり、 その生き生きとした目標が、 それに向かって精一杯に力を尽くすエネルギーを生み出したのでしょう。 だから、そうした意味において、 「夢を語る」ということは、最も大切な「成長の方法」なのだと思います。 生き生きと夢を語ることが、 成長していくための最も優れた方法なのだと思います。
仮に、棒高跳びの練習において、目標となるバーを置かずに 「とにかく、飛べるだけ高く飛んでみろ」とやっても、決して記録は伸びません。 これは、走り高跳びでも、何でもそうです。 人間というのは、目の前に明確な目標があるから、 それに向かって力を振り絞れるのであり、 力を振り絞るから、力が伸びていくわけです。成長していくわけです。
「はい、次は、何メートルの高さ。さあ、飛んでみなさい!」 と言われただけでは、本当の力は出ません。 彼が、本当に力を出しきって跳躍するためには、やはり、 その具体的な「目標」であるバーの向こうに「夢」がなければならないのです。 彼は、その跳躍のとき、バーの向こうに「夢」を見ているのです。 それは、ときに「県大会での優勝」であったり、 「歴史に残る記録」であったり、それぞれではありますが、 そこに、たしかな「夢」を見ているのです。 そして、その「夢」があるからこそ、人間は力を振り絞ることができるのです。
だから、このように、人間の成長にとっての 「夢」と「目標」の役割の違いを理解しておくことが大切です。 それらは、どちらも、人間の成長にとって必要不可欠なものです。 しかし、それぞれの持つ意味と役割が違うことを 理解しておかなければなりません。
したがって、もし、誰かが本当にポジティブ・シンキングを行いたいのであれば、 その人に求められるのは、実は、「念の強さ」ではありません。 求められるのは、「無邪気さ」や「純粋さ」なのです。 自分の描く夢の実現を無邪気に信じることのできる力や、 その実現をただひたすら純粋に祈ることのできる力こそが求められるのです。 そして、そうした力は、ときに、「天が与える」とでも呼ぶべき 稀有な能力であることも、またひとつの事実なのです。
すなわち、「理想家」と呼ばれる人物は、 夢を実現するために変えるべき最も重要な現実が 「自分」であることを知っています。 目の前の企業や市場や社会という現実を変えていくために、 真っ先に変えるべきは「自分自身」であることを知っています。 ですから、「理想家」と呼ばれる人物は、 自分を変え、成長させていくための努力を惜しみません。
このことは、逆にも言えます。 すなわち、人前で堂々と夢を語るということは、 おのずとその発言に対する責任を負うことになるため、 自分自身を追いつめていくための優れた方法になるのです。 そして、人間が最も成長するときとは、 自分にとって達成できるかどうかわからないほど難しい課題に、 あえて挑戦し、退路を断って悪戦苦闘するときなのです。
ビジネスマンが若き日に描いた「夢」とは、「初心」にほかなりません。 そして、その「初心」とは、山登りにたとえれば、 「登るべき山を定める」ということです。 生涯かけて登っていく山を見上げ、深く見据え、胸に刻む。 そういうことです。 そして、そのようにして胸に刻まれた「初心」は、 そのビジネスマン人生を通じて、 決して変わらぬものとしてこころの深くにあり続けていくものです。
私の好きな世阿弥の言葉に、あります。 初心、忘るべからず。 ときどきの初心、忘るべからず。 老後の初心、忘るべからず。 この言葉が教えているものも、 「初心」を胸に刻み、生涯抱き続けて歩むことの大切さです。 そして、そのような「夢」や「初心」を胸に刻んで道を歩み始めた人間と、 そのような「夢」や「初心」を持たずに歩み始めた人間とでは、 それからの一〇年を超える歳月を費やして長い道のりを歩んだとき、大きな差がでる
「顧客」です。 仕事における「顧客」が、私たちにとっての「成長の鏡」なのです。 「顧客」こそが、私たちの姿を映し出す「鏡」なのです。
「企画というものは、 顧客に納得してもらって、はじめて『良い企画』と言える」 「企画が顧客に受け入れられないとき、 それを顧客の能力の責任にしてはならない」 この体験を通じて、私は、そのことを学びました。
だから、私たちビジネスマンは、深く理解しておいたほうがよいでしょう。 「厳しい顧客」こそが「優しい顧客」である。 そのことを、理解しておかなければなりません。
「黙って去る顧客」も、こころを澄ませ、注意深く見ていると、 かならずその文句や不満を「無言のメッセージ」として発しています。 たとえば、企画書の説明であれば、説明の最中の表情、頷き方、首の傾げ方、 目の配り方、こちらと目を合わせたときの視線、何気ない質問のニュアンス、 やりとりの呼吸、こちらからの問いかけに対する答え方の雰囲気、 会議全体の空気、最後に別れるときの余韻。 そうした、細やかなものに気を配っていると、 顧客の「無言のメッセージ」は、かならず理解できます。 問題は、私たちに、それを気づく力量があるかどうかです。
なぜならば、そうした「無言のメッセージ」を聞くためには、何よりも、 細やかな気配りや繊細な感受性、さらには鋭い直観力や深い洞察力など、 人間としての高度な能力が求められるからです。 そして、そうした高度な能力を身につけるためには、 たとえば、一回一回の顧客への営業において、 その場に全身全霊で参入するという修練が求められます。
そこで、残念な思いのなかで、私はH課長に対して、 「それでは、明日までに、プロジェクトの企画書を書き直して持ってきます」 と伝え、机の上の資料をかたづけ、その会議を終わろうとしました。 しかし、そのとき、私のこころのなかで、声が聞こえたのです。 「自分は、本当に、顧客に対してベストを尽くしただろうか」 という声です。 そして、その声に続いて、 「いや、まだ、言い残していることがある」 という声が聞こえたのです。
「このプロジェクト企画に関する修正の指示については、了解しました。 明日までに、かならず修正した企画書を持ってまいります。 したがって、このプロジェクト企画についての議論は終わったと理解しています。 ただ、最後に、もう一度だけ、このプロジェクトの社会的意義について 説明させてください。それを説明させていただければ、 それだけで、私は結構です。最後にあと数分だけ、お時間をください」
「以上が、私どもが、このプロジェクト企画を御社に提案した理由です。 そして、結果としては、このプロジェクト企画は委員会のご理解をいただけず、 不採用になりましたが、私どもの信念は変わりません。 このプロジェクトを実施することができるのは、御社だけであり、 また、このプロジェクトを実施することが、御社の将来にとって
かならず有益な結果をもたらすと、いまも信じています。 ただ、私どもは、お客様から仕事をいただく立場の企業です。 最終的には、お客様のご判断に従います。そして、そのご判断もいただきました。 ただ、お客様に対してベストの提案と説明を申し上げるのが、私どもの責任と 思いましたので、最後に、もう一度だけ、そのことを説明させていただきました。 話を聞いていただいて、ありがとうございました。 お約束どおり、明日までに、プロジェクト企画の修正案を持ってまいります」
実は、その理由は、「操作主義」にあります。 営業担当者が「操作主義」に染まってしまっているからです。 営業担当者のこころのなかに、顧客を説得して自由に操作しようという 無意識の「操作主義」があるからです。 営業担当者のこころのなかに、顧客を意のままに動かしたいという 無意識があるからです。
そうした営業担当者のこころのなかにある無意識の「操作主義」は、 顧客も無意識に感じてしまいます。敏感に感じてしまいます。 そして、その結果、顧客はその営業担当者に無意識に反発します。 だから、営業担当者が、こちらの立場で「顧客を説得してやろう」 「顧客を動かしてやろう」と考えているうちは、 顧客は説得されることもなければ、動いてくれることもありません。 ましてや、共感を得ることなど、決してありません。
しかし、不思議なことに、私自身が「万策尽きた」と観念し、 このプロジェクトの実現を諦めたとき、私自身の口をついて出た言葉は、 「こちらの立場」での言葉ではなく、「顧客の立場」での言葉だったのです。
「顧客と共感する」ということは、まず何よりも 「顧客に共感する」ということなのです。 こちらが、顧客の気持ちに共感するという行為が最初にあるべきなのです。 それにもかかわらず、私たちは、しばしば無意識に、 「いかにして顧客からの共感を得るか」 「どうすれば顧客からの共感を引き出すことができるか」 ということを考えてしまいます。
なぜならば、「共感」とは、相手の真実を感じとることだからです。 自分の価値観や世間の常識にとらわれず、 ただ虚心に「相手にとっての真実」を深く感じとることだからです。 しかし、そうした意味で「顧客に共感する」ということができたとき、私たちは、 またひとつ、「こころの成長」の階段を登っていくことができるのでしょう。 そうして顧客に共感することを通じて、 私たちのこころは成長していくのでしょう。
その意味を正しく理解するならば、「人間力」とは、そもそも、 日々の生活の場や仕事の場の「現実」を離れて身につくものではなく、 また、「人間力」の前提となる「人間学」についても、 日常の生活の場や仕事の場での「体験」を抜きにして、 決して学ぶことはできないものであることを、腹に入れておく必要があります。 しかし、それにもかかわらず、最近では、 「人間学」や「人間力」ということまでも、 書物で勉強しようという風潮が強いようです。
二人で酒を飲んでいると、その課長の問わず語りの愚痴話から、 その課長の抱えている「つらさ」が伝わってきたのです。 それは、会社における自分の処遇に対する不満や、 家庭における家族との軋轢の苦しさなどがないまぜになった「つらさ」でした。 この課長のこうした話を聞かされながら、しみじみと感じたことは、 「あのときの女性社員だけでなく、 この課長も、誰もが、つらさを抱えて生きている……」 という切なさでした。
この課長には、この課長の「苦しみ」があることを知りました。 そして、そのとき、この課長のことを「無神経な人間」というひとつの見方で 決めつけて見つめている自分の「浅さ」を感じたのです。 要するに、「裁いて」しまっているのでした。 さまざまな姿を持った人間の「こころ」というものを、単純な見方で決めつけ、 「あの人は、ああいう人」「この人は、こういう人」という決めつけをして、 自分のこころの深くで、人間というものを「裁いて」しまっていたのです。 不思議なほどの豊かさを持った人間の「こころ」というものを、 単純な決めつけで分類してしまっていたのです。
別な表現をすれば、「反面教師」とは「内面教師」なのです。 ほかの誰かの姿に、自分自身の「こころ」の姿が映し出されているのです。 そのことに気がついたとき、私は、「人間学」というものにおいて 最も大切なものが何であるか、すこしわかったような気がしました。 それが、さきほどの言葉です。 「人間」というものを深く見つめること。 そして、この言葉が真に意味しているものは、 決して他人の「人間観察」ではなく、 何よりも自分自身の「内面省察」にほかならないのです。
「人間」というもののそうした裏も表も見えるのが、若手社員の時代なのです。
だから、いま振り返ってみると、私自身、 新入社員の時代や若手社員の時代こそが、 最も豊かな「人間学」の学びの時代であったことを感じます。 逆に、残念なことに、会社においてある程度以上の地位についてしまうと、 ほとんどの人が「良い部分」しか見せてはくれません。 あごでこき使われることもなければ、怒鳴り飛ばされることもない。 そして、人間としての「悪い部分」を見せつけられることも、あまりなくなってしまう
それが人間の世界であるかぎり、エゴとエゴの衝突があります。 そして、そのエゴとエゴのぶつかりあいの結果、私たちは、ときに、 文字どおり「荒砥石」の上で砥がれるような思いにかられることもあります。 また、ときに、それが「切磋磨」という言葉にふさわしい 良き関係を生み出すこともあります。 しかし、いずれにしても、 そうした「荒砥石」の苦しみや「切磋磨」の苦労から逃げることなく、 相手の「こころ」に正対するという修練をしていかないかぎり、 私たちは、本当の「人間力」と呼ぶものを身につけていくことはできないのです。
しかし、人間と正対し、人間と格闘することを抜きにして、 私たちが「人間力」というものを身につけていくことはできないのです。 ひとりの人間として成長していくことはできないのです。 だから、私たちは、この言葉を胸に刻んでおくべきなのでしょう。 人間との格闘こそが、人間力を磨くための唯一の道である。
「たしかに、そうだな……。みんな、愚痴をこぼしているようで、 その責任の重さが、結構、働き甲斐になっているんじゃないのかな……」 この発言で、その場にいた仲間は、それぞれに、何かを感じたようです。
すなわち、これらの社会のエリートたちは、いざとなれば命をするまでに 自分たちの義務と責任に対して強い自覚を持っていたわけです。 しかし、実は、この「ノブリス・オブリージュ」という精神の伝統の 最も優れているところは、単に義務感や責任感が強かったということでは ありません。 その最も優れているところは、もうすこし深いところにあります。 それは、彼らが、その義務や責任を「喜び」としていたということです。
この「ノブリス・オブリージュ」の世界であると思っているからです。 すなわち、企業や組織においてマネジャーという「地位」を得るということは、 やはり義務と責任を負うことであり、そして、何よりも、 そうした義務や責任を負うことを、自分自身の「喜び」とする
しかし、本来、マネジャーを志望するということは、決して、 出世への階段を求めてでもなければ、給料が上がることを期待してでもない。 ましてや、大勢の部下を持って権力を誇示したいからでもないと思うのです。 マネジャーになるということは、 義務と責任を求めてなるものであると思うのです。
もう一つは、義務と責任が、人間を成長させてくれるからです。 マネジャーは、義務と責任を負うことによって、 ひとりの人間として大きく成長できるのです。 しかし、その意味は、さらに二つあります。 一つの意味は、「仕事のリスク」に責任を持つことによって成長できるというもの
ビジネスにおける仕事というものは、かならず何がしかの「リスク」があります。 それは生きた現実の世界であるかぎり、 決して「ゼロ」にすることはできないものです。 そして、決して「ゼロ」にすることのできない「リスク」に対して、 自分自身が最終責任を持つという立場に立つことは、 人間の精神を鍛え、成長させてくれます。 逆に言えば、過去にやってきた仕事において、 まったく「リスク」を取ることなく歩んできたビジネスマンは、 精神的な「甘さ」の抜けない「スポイル」された人材となってしまいます。
マネジャーが「部下の人生」に責任を持つということは、具体的には、 部下としてあずかる人々の、職業人としての成長や人間としての成長を 支えるということです
そのことに尽きると思っています。 マネジャーが、ひとりの職業人として、ひとりの人間として、 どこまでも成長し続けていくこと。 そのことが最も大切なことであると思っています。 そして、もしマネジャーが、どこまでも成長していきたいと願い、 どこまでも成長していくことができるならば、 部下は、黙っていてもその姿から何かを学んでくれるでしょう。
そうした発想の逆転をしたのです。 すなわち、マネジャーの地位につくとは、 逃げようもなく、部下の成長を支える立場に立つことであり、 部下の成長を支えるためには、誰よりも自分自身が、 職業人としての力量や人間としての力量を磨いていかなければなりません。 だからこそ、マネジャーの地位につくことによって、私たちは、 みずから大きく成長していくことができるのです。
地位とは、部下の人生に責任を持つ覚悟にほかならないのです。
「ノブリス・オブリージュ」の精神とは、 かつての「高貴な人の義務」という意味ではなくなっていくでしょう。 そうではありません。 それは、「高貴な人が覚悟する義務」という古い意味ではなく、 その逆の「義務を覚悟する人の高貴さ」という新しい意味を 獲得していくのでしょう。
たしかに、これまでも、 職場のマネジャーが部下の成長に責任を持つと覚悟を定め、 互いに切磋磨し、部下の成長を支えている姿には、 マネジャーが醸し出す「高貴さ」とでも呼ぶべき香りや雰囲気がありました。
マネジャーになるとは、 「責任が重いおかげで、報われる苦労ができる立場」に立つことを 意味しているのです。 それが、私の実感です。
部下の成長を支えることを通じて、 何よりも、自分自身が大きく成長していけるからであり、 それは、誰よりも、自分自身のためなのです。 他人の人生に責任を持つ者が、最も成長できる。 この言葉は、人生の「理」ではないでしょうか。
「いつもながら、不思議なやつだな……。 こんなときに、見透かしたように、ちゃんと現れる……」
「君たちの無期限バリケード・ストライキという主張には賛成できない。 しかし、それは、無期限バリケード・ストライキが難しいからではない。 それが、あまりにも簡単なことだからだ。 大した警備体制も持っていない大学職員の抵抗を押し切って、 教室の机を壊し、遊びごとのようなバリケードを築き、 無期限と称するストライキを打つことなど、実に簡単なことだからだ。 しかし、我々にとって、本当に苦しい戦いがあるとするならば、
それは『バリケード・ストライキ』でも、『国家権力との戦い』でもない。 いま我々が語りあっている『この社会をより良きものにしよう』という思いを、 大学を出たあとも長くこころに抱き続け、その思いを実現するために、 いかなる困難があっても歩み続けることではないのだろうか」 そうした発言でした。そして、彼は、その発言の最後を、こう締めくくりました。 「もし、バリケードを築くのならば、大学のキャンパスにではなく、 自分のこころのなかに築くべきではないだろうか。 もし、君たちが、本当に『この社会をより良きものにしよう』と 考えているのならば、聞きたい。
これから三〇年たったときにも、君たちは、 いまと変わることなく、その思いを持ち続けているだろうか」
顔を合わせることのない友人 これが、「友人」ということです。 何十年もの長き歳月を別々の道を歩み、 そして互いに顔を合わせることがなくとも、 互いに言葉を交わすことがなくとも、 無言の励ましを送りあうことのできる友人。 それが、私にとっての、「友人」ということの意味です。
しかし、私は、こうした「友人」の消息を知っても、 決して連絡をとったり、旧交を温めたりすることはありません。 それは、必要ないのです。 彼らも、また、歩み続けている。 そのことを知っただけで十分なのです。 なぜならば、まだ、私たちは、道半ばだからです。
全一〇回のこのシリーズ・トークも、いよいよ最後に近づいてきました。 第二話では、「仕事の報酬とは何か」について皆さんと一緒に考えてみました。 そして、「仕事の報酬は人間としての成長である」という 私の考えをお話ししました。 私たちが一生懸命に仕事をしたときに与えられる真の「報酬」は、 何よりも「人間としての成長」であるという思想をお話ししました。
「たしかに、君の言うとおりだと思う。 もし、逆に、自分が辞令一枚で鉱山に行かされたならば、 きっと、しばらくは落ち込むだろうと思う。 しかし、もし、それが受け入れなければならない現実であるならば、 自分は、落ち込んだままではいないと思う。 それが鉱山であろうとも、どこであろうとも、 かならず人間がいる。そして、職場の仲間がいる。 人間がいて、仲間がいるかぎり、きっとそこには夢がある。かならず夢がある。 だから、自分は、もし鉱山に行かされたとしても、 そこで夢を語りはじめると思う。その夢を花咲かせようとすると思う。 そして、もし、その鉱山からまた別のところへ行かされたら、
おそらく、そこでも同じことをすると思う。 飛ばされたところで花を咲かせようとするだろう。 我々は、タンポポだ。 どこかに飛ばされたら、そこでまた、大きな花を咲かせればよい。 自分は、そう思う」
「自分は、本当に、そんな生き方ができるのだろうか。 ある日、まったく違った世界に飛んでいって、 そこでまた、タンポポのように花を咲かせることができるのだろうか。 本当に、そんな生き方ができるのだろうか」
ひとつの夢を実現すると、新たな夢が見えてくるのです。 それが、「日本に、まったく新しいタイプのシンクタンクを創ってみたい」 という夢でした。
顧客が満足する商品やサービス。 それは、たしかに、仕事を通じて私たちが創りあげていくべき 大切な作品だと思います。 しかし、同時に、 もうひとつの作品を忘れてはならないでしょう。 夢と共感にあふれた職場の仲間。
かつて、深い縁に導かれ、あるひとつの職場に人々が集まったこと。 それらの人々が、こころをあわせて大きな夢を描いたこと。 その夢を実現するために、力をあわせて困難な仕事に取り組んだこと。 そうした仕事を通じて、それらの人々が、 互いに理解しあい、共感しあう「仲間」になっていったこと。 そして、その職場において、一人ひとりが仕事の喜びを見出し、 職業人として、人間として、大きく成長していったこと……。
かつて、深い縁に導かれ、あるひとつの職場に人々が集まったこと。 それらの人々が、こころをあわせて大きな夢を描いたこと。 その夢を実現するために、力をあわせて困難な仕事に取り組んだこと。 そうした仕事を通じて、それらの人々が、 互いに理解しあい、共感しあう「仲間」になっていったこと。 そして、その職場において、一人ひとりが仕事の喜びを見出し、 職業人として、人間として、大きく成長していったこと……。
そうしたことなど、いつの日か、 誰も思い出すことのないときがやってくるのです。 そして、すべては、忘却の彼方に消え去っていくのです。 すべては、忘れ去られていく……。 しかし、私は、思います。 だから、素晴らしいのではないでしょうか。 だからこそ、この「夢と共感にあふれた職場の仲間」という作品が、 かけがえのない素晴らしい作品なのではないでしょうか。
「いつもながら、不思議なやつだな……。 こんなときに、見透かしたように、ちゃんと現れる……」
顔を合わせることのない友人 これが、「友人」ということです。 何十年もの長き歳月を別々の道を歩み、 そして互いに顔を合わせることがなくとも、 互いに言葉を交わすことがなくとも、 無言の励ましを送りあうことのできる友人。 それが、私にとっての、「友人」ということの意味です。
我々は、タンポポだ。 どこかに飛ばされたら、そこでまた、大きな花を咲かせればよい。 自分は、そう思う」
「自分は、本当に、そんな生き方ができるのだろうか。 ある日、まったく違った世界に飛んでいって、 そこでまた、タンポポのように花を咲かせることができるのだろうか。 本当に、そんな生き方ができるのだろうか」
だから、私たちは、仕事に取り組むとき、 もうひとつの作品を忘れてはならないのです。 私たちの歩みが残す「職場の仲間」という作品を 決して忘れてはならないのです。
いつか誰かが、その夢を実現する。 そのことを、素朴に信じられるようになったからです。 この映画は、私に、そのことを教えてくれました。 たしかに、主人公のマックは 「自由」という夢を実現することなく死んでいきました。 しかし、その夢を受け継いだチーフが、 マックが成し得なかったことを成し遂げ、マックの夢を実現したのです。 そのマックとチーフの姿を通じて、 この映画は、ひとつの大切なメッセージを、私たちに伝えてくれます。
だから、もし、夢を描く私たちが恐れるべきものがあるとするならば、それは、 「夢が破れる」ということではありません。 そうではありません。 私たちが恐れるべきは、 「力を尽くさぬ」ということなのです。
私たちに問われるものは、 「その夢を実現するために、力を尽くして歩んだか」ということなのです。 問われていることは、そのことだけなのです。 だから、私たちは、夢が破れることを恐れる必要はない。 それを恐れることなく、大きな夢を描けばよい。 その夢の実現を、こころの底から信じればよい。 そして、力を尽くして歩めばよい。
そして、力を尽くして歩んだあと、 私たちがなすべきことは、ただひとつ。 未来に思いを馳せることです。 我々が去った後、いかなる夢が花開くのか。 その問いを胸に、未来に思いを馳せることです。
Posted by ブクログ
ゆっくりと沁み渡る言葉。
仕事に向き合う姿勢を改める。
・仕事の報酬は、
給料である
能力である
仕事である
人間としての成長である
・本気の夢を持ち、実現に向けた目標を持つ
・人間は類型化できない。反面教師として裁いていないか。一面ではなく深く人間を見つめる
・責任と義務を持つことで成長できる
・顔を合わせることがなくても、歩みを止めていない友人
・夢を砕かれることを恐れない。仲間と未来につながる
Posted by ブクログ
なぜ我々は働くのか、仕事というものに向き合うための「仕事の思想」書です。
これをよめば、ビジネスマンにとって「仕事」とはどういうものかが理解できる。
<なぜ我々は働くのか>
・働くのは、それは、生活を糧を得るためだけでも、生き残るためだけでもなく、素晴らしい「何か」のために働く
<仕事の報酬とは何か>
・仕事というものは、こころを込めてやれば、何でもおもしろい
・仕事の報酬とは能力、仕事の報酬とは仕事、やりたい仕事、やりがいのある仕事こそが仕事の報酬である、そして仕事の報酬とは成長である
<どうしたら仕事を通じて成長ができるのか>
・夢を語り、目標をもつこと、それに向かって精一杯に力を尽くすこと、「抽象的な夢」から「具体的な目標」をもつこと、そして自分が達成できるかどうかわからない難しい課題にあえて挑戦し、退路を断って、悪戦苦闘すること
<成長のためのもう1つの方法:自分を映し出す鏡を見ること>
・ビジネスマンの鑑とは「顧客」、厳しい言葉を云ってくれる顧客こそが優しい顧客、逆に厳しい顧客とは、黙って去る顧客。
・細やかな気配りや繊細な感受性、鋭い直観力や深い洞察力をもって、「顧客の無言のメッセージ」を全身全霊で観察するという修練を行わなければならない
<どうすれば顧客と共感が得られるのか>
・自分は本当に、顧客にベストをつくしたのだろうか?
・顧客を操作する、動かしてやろうとするのではない。顧客の立場にたって、無条件に顧客に深く共感すること
<人間として成長するにはどうすればいいのか>
・日常の生活や仕事の場にこそ、最高の学びがあり、最高の修練がある、人間を深く観察する
・人と人と真摯に向き合うこと、エゴとエゴとのぶつかり合い、切磋琢磨をする。人間との格闘こそが、人間力を磨くための唯一の方法である。
<部下をどう育成するか>
・ノブリス・オブリージュ。義務や責任を負うことを自分自身の喜びとする。自分自身が成長すること、成長し続けること
・他人の人生に責任を持つものが、最も成長できる。
<友人とどう接するか>
・顔合わせることもなく、言葉を交わすこともない「友人」が、私たちを支えてくれる
・一人ひとり、登っていく道は違っても、めざす頂きはひとつ。いつかその頂上で友人と再会する
<不本意な異動の辞令を受けたら>
・われわれは、タンポポだ。どこかに飛ばされたら、そこでまた、大きな花を咲かせればよい
・若手の夢というが忘れないでもらいたい。ロートルにも夢があるんだ。若手だけが夢をもっているわけはない。
<夢がやぶれたらどうするか>
・たとえ自分が、その夢を実現できなくとも、いつか誰かが、その夢を実現する。
・大事なことは、夢がかなえられなったということではない。我々が恐れるべきは、「その夢を実現するために力を尽くしたかどうか」だ。
目次
はじめに なぜ我々は働くのか
第1話 思想 現実に流されないための錨
第2話 成長 決して失われることのない報酬
第3話 目標 成長していくための最高の方法
第4話 顧客 こころの姿勢を映し出す鏡
第5話 共感 相手の真実を感じとる力量
第6話 格闘 人間力を磨くための唯一の道
第7話 地位 部下の人生に責任を持つ覚悟
第8話 友人 頂上での再会を約束した人々
第9話 仲間 仕事が残すもうひとつの作品
第10話 未来 後生を待ちて今日の務めを果たすとき
謝辞
ISBN:9784569660158
出版社:PHP研究所
判型:文庫
ページ数:272ページ
定価:533円(本体)
発行年月日:2013年04月15日第16刷
Posted by ブクログ
浅田すぐるさんが良書として紹介していた。副題にある、「なぜ我々は働くのか」という本質的な問いへの考察が気になり、読んでみました。
結論から言うと、今後も傍において、何度も読み返したい本。自分の子供にも必ず推薦する。
・仕事の報酬は成長である。
・夢を描き、本気で夢を語ることで成長することが大切。
・夢想家ではなく、理想家になる。そのためには、一生懸命に夢を実現しようと、自分自身を変えていく。成長させていく。
・成長するために、自分自身の内面省察により、人間学を学ぶ。
・相手のこころと正対することにより、人間力を身につける。
Posted by ブクログ
ゆるゆる働きながら30歳を目前にした今、
仕事との向き合い方を見直したくなりました。
何度も読み返したい本になりました。
特に第二話。反省したいことばかり思い浮かびます。
以下各話からの個人的な気づき。
1.わたしは、錨(=思想)なく働いてきてしまいました。
だから、流されるんだ。
2.成長が仕事で得られるものだったとは、気付いていませんでした。この章は何度でも読み返したい。
3.目標は会社のためだと思ってました。でも自身の成長のためのものでもあることに気づかされました。
4.顧客は、私自身の鏡であることに気づかされました。
5.顧客に共感してもらうのではない、私が顧客に共感することが相手を動かすのだと気づかされました。
6.反面教師は内面教師。『そうはならない』ではなく、すでになっているんだと気づかされまた。近づきすぎず、安全を取りすぎず、適切な距離をとることが人間と格闘すること。
7.地位や役職は私には無いけれど、『責任が重いおかげで、報われる苦労ができる』と思える人になるつもりでいたいと思いました。
8.顔を合わせなくても言葉を交わさなくても心の中で支えてくれる友人は、幸いわたしにもたくさんいます。
(支え合える、じゃないところがまた良い。自分だけがそう思ってていいですものね)
9.職場の仲間は仕事を通して得られたかけがえのない作品、本当に苦しい時期を一緒に乗り越えて、次のステップに進んだ元仲間たちは、まさにその通り。
10.引用:私たちが恐るべきものがあるとするなるば、それは『夢が破れる』ということではありません。
『力を尽くさぬ』ということなのです。
Posted by ブクログ
深い。とにかく深い。一度読んだだけでは筆者が伝えたかったことを全て読みとれたとは思えない。また読みたい。ボリュームがあるわけでもなく、濃い内容がギュッと凝縮されてあるから、手元に置いて読み返したくなる。
Posted by ブクログ
「こころ」を深く見つめることが大切
分類や裁いてしまってはいけない。
生きた現実や生身の人間には想像を超えるほどの不思議が潜んでいる。
大人だなって思った。オレはガキだね
もっと成長していきたい。
思想:現実に流されてないための錨
成長:決して失われることのない報酬
目標:成長していくための最高の方法
顧客:こころの姿勢を映し出す鏡
共感:相手の市につを感じ取る力量
格闘:人間力を磨くための唯一の方法
地位:部下の人生に責任を持つ覚悟
友人:帳上での再会を約束した人々
仲間:仕事が残すもう一つの作品
未来:後生を待ち手今日の務めを果たすとき
Posted by ブクログ
仕事の思想、なぜ働くのか…
それは自己実現、自身の成長のため。
いままで比較的ポジティブに仕事をしてきた。
漠然とだが「何か自分の成長に繋がれば」と。
辛いときも腐らずに頑張ってきたことが、間違ってないよと著者に言ってもらえた気がした。
今後も辛くなったときは読み返し、立ち返りたい。
本書のキーワードやポイントをおさらいしつつ、部下にも伝えられるようにしたい。
Posted by ブクログ
・仕事の報酬は「人間としての成長」であるという世界を見失わない事が大事
・仕事の報酬にはいくつもの世界がある。
ステップとしては①給与・地位②能力③仕事そのもの、があるが、④人間としての成長だけは決して失われない報酬である。
・成長とは「こころの世界が見えるようになる」こと
・夢や目標を語ることを恐れない
・顧客に対して無意識の操作主義ではなく、相手に共感すること
・人間力を身につけるには、相手の心と正対すること
・夢を実現させる事よりも、力を尽くしたかが重要
Posted by ブクログ
日本総研を立ち上げた田坂さんの本。
「給料で自分の人生を売り渡した」とならないように「我々はなぜ働くのか」を問い続けることが大事と説いた本。
以下の観点から語ってくれる。
・思想:現実に流されないための錨
・成長:決して失われることのない報酬
・目標:成長していくための最高の方法
・顧客:心を写し出す鏡
・共感:相手の真実を感じ取る力量
・格闘:人間力を磨くための唯一の道
・地位:部下の人生に責任を持つ覚悟
・友人:頂上での再開を約束きた人々
・仲間:仕事が残すもう一つの作品
・未来:後生を待ちて今日の勤めを果たす時
Posted by ブクログ
なぜ、働くのか?
問いが立つのは、ただ食べるためだけではない「何か」があるからだ。
では、「何か」とは?
それを見出すために「仕事の思想」が求められる。
現実に流されないための錨となる「仕事の思想」。
それは本気で「夢」を語り「目標」を定め本気で取り組むことで生まれていく。
大事なのは結果じゃない。本気で考えて本気でやりきることなんだ。
Posted by ブクログ
特に印象的だったのは、
「顧客と共感する」ということを「顧客からの共感を得る」ということと勘違いしている人が多い。「顧客と共感する」といことは、まず何よりも「顧客」に共感するということ。
仕事を進めてくなかで、無意識にお客さんや相手を「納得させたい」って思うことが多かったから、まずは相手の立場や考えを理解することから始めようって思った。
Posted by ブクログ
■なぜ働くのか
A.思想 ―― 我々が仕事をするのは、生活の糧を得るためではなく、もっと素晴らしい「何か」のためである。その何かを見いだすためには、深みある「仕事の思想」が求められる。
B.成長 ―― 仕事の報酬には、給料、能力、仕事、成長など、いくつもの“世界”がある。その最も高みにある世界が「成長」であり、それを見誤らないことが大切である。
C.目標 ―― 人間が成長する上で「夢」を語り、「目標」を定めることは大切だが、その際に注意すべきことがある。それは、「理想家」と「夢想家」を混同しないことである。
D.顧客 ――「 顧客」は、自身の姿を映し出す「成長の鏡」である。成長するためには、顧客が心の中で抱く「無言のメッセージ」に耳を傾けることが欠かせない。
E.共感 ―― 自分の価値観にとらわれず、「顧客の気持ちに共感する」ことで、心の成長を遂げることができる。
F.格闘 ―― 人間力を身につけるためには、人間と「格闘」し、相手の心に正対することが必要である。
G.地位 ――「 地位」とは、部下の人生に責任を持つ覚悟に他ならない。他人の人生に責任を持つ者が最も成長できる。
H.仲間 ―― 仕事をした時に残る「作品」として、商品やサービス以外に、もう1 つかけがえのないものがある。それは、夢と共感にあふれた「職場の仲間」である。
I.未来 ―― 力を尽くして歩んだ後、我々がなすべきことは、ただ1 つ。我々が去った後、いかなる夢が花開くのか。その問いを胸に、「未来」に思いを馳せることである。
Posted by ブクログ
『夢が破れることを恐れる必要はない。私たちが恐れるべきは、力を尽くさぬということ。』
仕事と共に生きるということに正面から向き合う時に読み返したい一冊。
Posted by ブクログ
"なぜ我々は働くのか"というサブタイトルとがついているとおり、
「働く」ということに関して真正面から向き合える一冊です。
田坂さんはアメリカのシンクタンクに勤めた後に、
日本のシンクタンクである日本総合研究所の設立に携わった方。
現在では社会起業家としての生き方や働き方を提唱されています。
この本は思想、成長、目標、顧客、共感、格闘、地位、友人、仲間、未来という
10のキーワードを通じて働くことの意味を問いかけていますが、
エピソードを交えながらの内容には深くうなづけるものがあります。
例えば「地位」という章ではマネージャーとしての働き方、考え方が書かれていますが、
「部下の人生に責任を持つ」という言葉にはハッとさせられますし、
「そのためには自分自身が成長すること」という内容には考えさせられるものがあります。
また、「仲間」という章では会社で希望する仕事に就けるかどうかの話があり、
「どんな職場に行こうがそこには人間がいて職場の仲間がいる。
人間がいて、職場の仲間がいる限り、そこには夢がある」
という言葉にも考えさせられるものがありました。
ビジネス本の中には読み終わっても内容が頭に残らない本もありますが、
この本はインパクトのある言葉が残り、
何回でも読み返したいなと思える内容ばかりでした。
「働くということはどういうことだろう」というのは永遠のテーマだと思いますが、
その答えの一端がこの本の中にはあると思います。
Posted by ブクログ
仕事に対する姿勢や考え方の本。仕事を始める前に読んで良かったと思う。実際、アルバイトでも応用できるし、将来、仕事をする上での心構えとなる。短編だが、読みやすい良書。
Posted by ブクログ
深く心に刻んでおきたいと思うエッセンスが詰まった本だと思う。
いくつかのステップを上がる時に、必要な思考の仕方のヒントになると思う。
そういったものは、ノウハウを教えられるものではなく、自分で自分なりのメソッドを見つけ、身につけることが大切なので、まさに思想という意味合いで示唆に富む本というのが大切なのではないか。
Posted by ブクログ
くどくどとだらだら文書が書いてあるが
さいごのI couldn’t but I tried はすごく良い言葉だと思った。
その本はgen Zには刺さらないだろうな。
ただ夢を語ることと挑戦すること。これは死ぬまで続けたい。
Posted by ブクログ
仕事の報酬は仕事。
私が新卒のときに、大好きな役員がこの本を元に、私たちに仕事の報酬は何だと思う?と聞いたのが懐かしい。
その次からくる仕事を、できる人にだけ寄る仕事を辛いものとしか考えられなくて辞めてしまったけど、この言葉は正しいと今でも感じてる。
Posted by ブクログ
上司推薦、20代で読むべき本。実際、読んでみて、各年代で読むことで価値観の変わる本。
なぜ私たちは働くのか?
①思想:現実に流されないための錨(食べるためではない、ワクワクするため)
②成長:決して失われることのない報酬(給料→能力→仕事。究極的に成長のため)
③目標:成長していくための最高の方法(夢を本気で語り、目標を本気で定める。)
④顧客:こころの姿勢を映し出す鏡
⑤共感:相手の真実を感じ取る力量(まず顧客に共感することで、共感される)
⑥格闘:人間力を磨くための唯一の道
⑦地位:部下の人生に責任をもつ覚悟
⑧友人:頂上での再会を約束した人々
⑨仲間:仕事が残すもう一つの作品
⑩未来:後生を持ちて今日の務めを果たすとき(私がやらねば誰がやる?私がやれずとも誰かが引き継いでくれる)
キーワード:私は何のために働くのだろうか?
Posted by ブクログ
仕事は「修練」だと言われているようで、ちょっと辛い。
いろんな事例をあげながら一つ一つ教えてくれているのでわかりやすい。
ただ、本質がいい加減な場合、田坂さんのいう修練に気持ちを持って行くのはハードル高いなぁ。
読みこなせていないだけかもしれませんが。
課題図書、重し。
Posted by ブクログ
仕事の報酬は人間としての成長。給料も能力もなくなっていくが、成長は失われない。田坂さんにとっての成長の定義はよく分からなかった。
夢を語り、目標を定めよ。目標だけでは「力を振り絞ること」ができない。夢だけでは具体的な行動におとしこめない。
無意識の操作主義に注意。顧客に弊社のファンになってもらう、ではなく自分が顧客のファンになる。
Posted by ブクログ
友人が薦めてくれた本。
就活が終わったらもう一回よみたい!
熱く語れる夢はまだ探し中だけど、働くなら夢を持って働きたい。
沢山の人と夢を語り合いたい。
時間を空けて定期的に読みたい本かも。