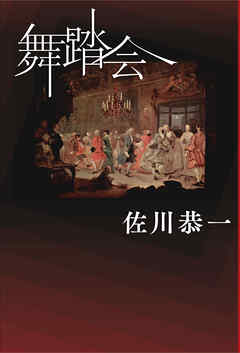あらすじ
5編の妄想と諧謔によって綴られる佐川恭一ワールド全開の一冊。
妻と娘との三人家族のわたしは、職場でも家庭でも孤立していき、限られた小遣いの中でわずかな喜びを見出す日々。強靭な精神を持つ妻に太刀打ちできないわたしは家出することで抵抗するが ・・・「愛の様式」 この世界はしらふで生きていられる場所じゃない。勝者しか存在を許されない会場で、ぼくたちは倒れるまで下手なダンスを踊り続けるしかない ・・・「舞踏会」など、「ことばと」掲載の表題作を含む5編を収録。
【目次】
愛の様式
冷たい丘
舞踏会
ひだまりの森
友情(浜大津アーカスにて)
【著者】
佐川恭一
滋賀県生まれ。京都大学文学部卒業。『踊る阿呆』で第二回阿波しらさぎ文学賞受賞。著書(電子書籍含む)に『サークルクラッシャー麻紀』『受賞第一作』『無能男』『ダムヤーク』などがある。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
現代に現れた太宰治。
拗らせた自意識。
出口のない煩悶。
人に言えぬ苦しみ。
今どき流行らない、かと言って、いつかの時代ならポピュラーであったということもない、ひた隠しに隠したい思いを、思うさまぶちまける。
素晴らしい。
「この舞踏会から逃げ出すことはできない。出口はない。ダンスの優れた者だけが評価され、評価された者が次の世代を評価する。評価されなかった者に存在価値はない。価値はなくともダンスはやめられない。誰も認めることのないダンスを倒れるまで踊らなければならない。あなたは倒れる。向いてもいないダンスを嘲笑われ、馬鹿にされ、いいことなど一つもなかった舞踏会場の端で、血と汗にまみれて倒れこみながら、あなたはこう言うのだ。「それでも、あいつよりはましだった」そうして誰も見ていない片隅の小競り合いで、やっとささやかな勝利を一つ上げて死んでいく。これはもっとも醜い形式の死だ。」
Posted by ブクログ
どれだけ、ネガティブな感情を吐き出しても辟易しないのが不思議です。
これは根っこの部分での作者への信用の成せる技でしょう。可愛い女性からの承認はこの世界を生き抜く為の最強の鎧であるのですね笑
Posted by ブクログ
『愛の様式』は家事にも育児にも協力的な夫であるわたしのちょっとした反乱の話です。
わたしは妻と二歳の娘の三人暮らしです。人並み以上に家事をやっているつもりなのに、妻にはやり方が悪いと罵倒され、ひどい時にはやり直しをさせられます。
妻の暴言は日常茶飯事でそれについては特に何も思わないが、家事をやるたびにやらなかった場合より厳しく当たられるのはかなりこたえるというわたし。
そんなわたしは友人の島田が彼女である里奈ちゃんと結婚すると知り心配します。島田には愛人がいるからです。しかも島田はそれを悪いと思っていないし、里奈のことも束縛しないと言います。わたしは島田が席を外した時に里奈ちゃんにそのことを言おうとしますが、里奈ちゃんは「全部知っているから」と言うのです。
その日の夜、十時までには帰るという妻との約束を破り、島田達と別れた後、風俗に行くわたし。
でもお目当ての子が居なかったので結局自宅に帰りますが、ドアにU字ロックがかけられ中に入れません。妻に閉め出されてしまったのです。
実家に電話をしても母親から「お前が全て悪い」と言われ、行くところがないわたしは妻への反発もあり、ネットカフェでしばらく暮らすことにしたのでした。
一人称で語られているので、しばらく読んでいるとこの読み方で合っているのか不安になりました。もしかしたらわたしの妄想?
わたしの評価はわたしの主観からしか読み手には分かりませんが、家を買い、妻が仕事を減らすことが出来るのだから、まるっきり仕事ができない人ということはないだろうと思いました。
印象に残ったのは、家族の在り様に悩んだわたしが同じように家族を養ってきた自分の父親に電話をし、聞いた父親の本音の一部です。
❝ おれはな、人生というのは一つでも、一瞬でも幸福を体験できればそれで成功だと思っている、一瞬の幸福以外のすべてが苦痛と不幸に塗りつぶされたような人生だったとしても、たった一つの幸福でその人生はあったほうがよかったものになると考えているんだ。❞
わたしは家族の元へ帰ることができるのでしょうか。
〖冷たい丘〗は少々ゾッとする話でした。
主人公のぼくは「永遠」という言葉を聞くとおそろしくて身震いしてしまいます。
クラスメイトの伊藤くんは異常なほど死を怖がります。
ぼくのクラスでは「帰りの会」で善いことをした生徒を発表する決まりになっていて、名前を言われた生徒は赤いシールをもらえ、それがたまると賞状やトロフィーがもらえることになっていました。
ある時、帰りの会で不本意な形で名前をよばれたぼくは日頃思っていたことを言ってしまうのでした…。
ぼくと伊藤くんの関係、「帰りの会」での善行発表の是非、そしてぼくが選んだ結末、と考えたいことが盛り沢山の短編でした。
表題作の『舞踏会』はエッセイのように感じられました。
公園を一周する『ひだまりの森』、よくある好みの女性をめぐっての『友情』等、著者のユーモアが効いた話も読んでいて楽しいと思いました。
最初に本をパラパラと捲った時に改行が少なくて読み難いのではと危惧したのですが、思いの外、引き込まれました。著者の術中にはまってしまったのかもしれません。