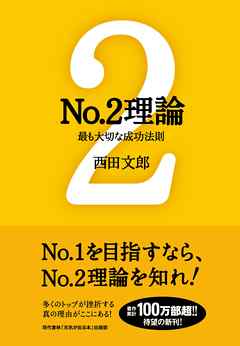あらすじ
すべてのエグゼクティブ必読の一冊!
「伸びる会社」「伸びない会社」の違いはココにある!
著作累計100万部超!
“能力開発の魔術師”西田文郎氏が明かす
「伸び続けるための組織論」
30年以上にわたる活動から導き出された組織運営の重大な経験則=No2理論、を詳らかにした意欲作。
何が組織の盛衰を決めるのか……
社長が優秀なのに、潰れる会社がゴマンとあるのはなぜでしょうか。
しかし実は、優秀なNo2がいるのに潰れた会社はほとんどないのです。
逆にいえば、優秀なNo2のいる会社は必ず伸びています。
No2がダメな会社に未来はありません。
特に発展途上の企業の場合はNo2で組織の盛衰が決まってしまう部分が非常に多いのです。
会社経営ではNo2が成功のカギを握っているのです。――それが「No2理論」です。
★No2が優秀だとなぜ会社は伸びるのか?
★優秀なNo2がいない会社はどうして発展しないのか?
本書では組織におけるNo2がマネジメントの最重要課題であること=「No2理論」を詳らかにします。
さらに、
★どういうNo2が本当に優秀なのか?
★No2の役割とは何か?
★どんな人間をNo2にしたらよいのか?
「No2理論」を実践導入していく上での必要な知識を伝授します。
ピラミッド型の会社組織からよりフラットな組織形態へと会社の形も徐々に変わりつつあります。
トップとボトムの距離が縮まりよりフラットな組織になっていくとすれば、
No2の役割はより一層大きくなります。
時代が優秀なNo2を求めているのです。
ぜひ、No2理論を実践して繁栄する会社、伸びる組織になってください。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ナンバーツーがダメな会社に未来は無い。
ナンバーツーと言うのは具体的にどういった人たちなのか、それはポジション的にナンバーワンの次と連想する人がほとんどですが、トップの後継者、及びトップが自分の次に信頼している人もナンバーツーの意味です。CEO、いわゆる最高経営責任者は船長であり、船の進路を決定し、進むべき方向を指し示しますが、ナンバーツー、いわゆる最高業務執行責任者は指示を受けて、乗り組み委員を統率しナンバーワンが差しめす方向へ実際に船を進める実動舞台のリーダーです。
ナンバーツーは組織の要を成します。ボスの下にナンバーツーがいると、ただの群れが組織に変化するのです。扇の要と言われるのがこのナンバーツーです。
ワンマン社長はいつか限界に直面する日が来ます。ごく小さな集団はナンバーツーがなくても機能しますが、組織が大きくなるほど、右腕が必要になります。しかし、大組織になり、あぐらをかいてしまうと、ナンバーツーの存在意義が薄くなってしまうのです。
組織として成功するかどうかは、優秀な側近を探すところから始まります。
Posted by ブクログ
伸びる会社には必ず優秀なナンバー2がいる。
自分が優秀になる確実な方法は今いる場所のナンバー2になること!
⚫︎役割の違い
ナンバー1は船長であり、船の進路を指し示す。
ナンバー2はクルーを統率し、ナンバー1の指し示す方向へ実際に船を進める。
ナンバー1が意思決定に専任できる体制が組織の命運を決める。
⚫︎ナンバー2の事例
脳→神経→筋肉 と
トップ→ミドル→ボトム の例えが最もハマった。
監督(トップ)→ヘッドコーチ(ナンバー2)右手コーチ(管理職)→選手(現場)を確立したのはV9時代の巨人軍 川上哲治監督。
Posted by ブクログ
よき。
本がめちゃくちゃ良いというよりは、ナンバー2という生き方を貫いてきた自分にとっての自信になる本だった。
全員が当てはまるわけじゃないだろうけど、個人的には0→1よりも1→10を得意とするタイプなのでやっぱり0→1を得意とするナンバー1は尊敬する
Posted by ブクログ
なるほどこういう視点からの成功法則もあるのね~と思った。これはどの組織にも言えるし,別に社長とNo.2の関係でなくても,どこでも当てはまる考えだ。
自分の場合は,学年主任と自分というふうにとらえなおすことができる。その立場立場で何度も繰り返し読みたい本である。面白い。
Posted by ブクログ
珍しいテーマについて書かれているな、と思い読んでみたのだが、新しい視点を与えてくれた良書だったと思う。
No.2というと誤解を生んでしまうとは筆者も言っていたが、要するに参謀であったり女房役として、組織を支える役割の重要性、その資質、心構えなどを解説してくれる一冊。
ビジネスにおいてだけでなく、部活動や家族などにおいても活用できる内容で新鮮だった。
自己啓発書とは違った、新しい価値観を見つけるための一冊、という印象だった。
Posted by ブクログ
会社のナンバー2は最高業務執行責任者(COO)
会社を伸ばすのはナンバー2であり、会社を潰すのはナンバー1である
ナンバー2はあくまで黒子
自分の美学を捨ててるか、自己犠牲できるか
部下のことを心配し、いつも気にかける
部下以上に情熱的に仕事に取り組む
世の中には常に3種類の人間がいる「いい加減な人間」「一生懸命な人間」「本気になれる人間」
Posted by ブクログ
No.2を目指してみようかな。
と、最終章の最終項で急に目覚めた。
読んだきっかけ
忘れたけど、何かのオススメだった気がする。
本のテーマ
優秀なNo.2が組織を成長させ、未来をつくる。
No.1とNo.2.では役割も求められる能力も全く違う。
ハイライト
“夢をかなえる第一歩は、自分が今いるところで頑張る以外にないからです。
仕事であれば、「職場のナンバー2を目指す」が正しい頑張り方なのです。
(ナンバー2として)誰かのために自分を捨てたり、自分を犠牲にするような訓練をしてこなかった。だからここぞという最後の最後に、自分の欲望や好き嫌いが出て判断を狂わせてしまう。失敗した企業家たちを見ていると、そんなパターンが非常に多いのです。 そういう挫折運を避けたいなら、二つの方法しかありません。・優秀なナンバー2になり、自己犠牲能力を高める・超優秀なナンバー2をつかまえる”
僕がナンバー2を目指してみようと思ったのはこの部分。
1〜5章までは、ナンバー2の必要性、ナンバー2の役割と心得、ナンバー2の適正などについて書かれている。
正直、読みながら「自分はナンバー2タイプではない」と感じていた。
しかし6章に入り、上の文章を読んだ時、「そうか!超優秀なナンバー2に出会うのを待つより、まずは自分が優秀なナンバー2になることを目指し、地力をつけたほうがいい」と、不意に平手打ちを喰らったような衝撃を受けた。
ナンバー2にとって重要な素養として「自己犠牲力」という言葉が何度も登場する。
意味はよくわかる。ただ、“犠牲”という言葉について引っかかりを覚えた。
犠牲は、自分をおし殺して誰かのために尽くすという意味から、「自分を粗末に扱う」「自分なんてどうでもいい」という印象を感覚的に持ったからだ。
この世に生まれてきた人間で、どうでもいい人間なんていないはずだ。自分を粗末に扱う生き方が、しあわせなわけがないと僕は考える。
本書では、ホンダの創業者本田宗一郎にとってのナンバー2藤沢武夫が何度も登場する。
彼はきっと自分を粗末に扱ったり、不要な人間だとは思っていなかったはずだ。むしろ自分を大切に思うからこそ、「ナンバー2としての生き方」を自ら選んだのではないか。
自分で自分を大切にできる人間だからこそ、自己犠牲を厭わず、他者に尽くすことができるのだ。ナンバー2にはそれだけ自立した人間性も求められるということだろう。
この本をどう生かすか
自分がナンバー2を目指すという視点で、もう一度本書を振り返った。
第5章に出てくる「ナンバー2実績考課表」は、優秀なナンバー2であるための姿勢がしっかり網羅されており、大変役立つツールだ。
ここだけでも時折見返して、自分のナンバー2としてのあり方を見直したい。
誰に薦めたいか
組織で活動するすべての人に薦めたい。
今の組織ではナンバー1の人も、もっと大きな単位でみたらナンバー2だし、新入社員であっても、ナンバー2的な働き方を身につけることで、成長できるからだ。
Posted by ブクログ
「トップが指示する方向へ進むようにメンバーをまとめ、組織していく」
というナンバー2の役割を果たすには、
どうしても使わなければならない能力が一つあります。
それがコミュニケーション能力なのです。
藤沢武夫
経営に終わりはない
「いちばん仕事のしやすい方法を私が講じましょう。あなたは社長なんですから、あなたのいうことは守ります。」
人は理論や理屈に従うのではなく、人物に従います。
ミドルマネジメント
①リーダーシップ
②コミュニケーション能力・誘導能力
③プレゼンテーション能力
④調整能力
⑤交渉力
「番頭としての立場に徹し、常に会社なり社長を第一において、自分というものを律しつつ、社業の発展に誠心誠意を尽す」
トップの考え方を徹底的に理解せよ。
ナンバー2の美学
ナンバー1を補佐し、
ナンバー1を成功させることで自分も成功できる。
人を大きく生かすための努力が、
自分を生かすことにもなる。
量的な拡大に、質的な“成長”がともなわなければ、破綻を生じる。
部下に惚れらるには
部下のことを心配し、いつも気にかける
部下以上に情熱的に仕事に取り組む
戦略が会社を動かすのではありません。
戦略や戦術は「どう動くべきか」を教えるだけです。
会社を動かし、成長させ、発展させるのは、
一人ひとりの社員の思いです。
部下にとって上司の一番の魅力
思いを語ってくれる
(理念の共有による連帯)
信頼してくれる
(権限の委譲による責任感と使命感の喚起)
情熱的に働いている
(感動と共感)
自分のことを気にかけてくれる
(承認欲求と自己重要感の充足)
組織力を強化すること
目標にむけてみんなの気持ちを一つにし、
またシステムや仕組みを工夫し、
効率や生産性を絶えず高める努力をし続けることで、
トップマネジメントを支える。
うちにはうちの良さもあり、
それを活かしながら戦略をたてる。
Posted by ブクログ
組織ナンバー2がどれだけ大事かの本。
セミナーの内容を詰め込んだ様な内容なのでひたすら濃く、自分の中で内容が全然整理できてない。
また読み返そう。
Posted by ブクログ
・No. 1には、"集団に方向性を与える役割"
・No.2には、"その方向へ進むようにメンバーをまとめ、組織していく役割"
・ボスの下にNo.2がいると、ただの群れが組織に変化する
・組織とは、"ある目的を達成するために、分化した役割を持つ、個人や下位集団から構成される集団" つまり、大事なのは"ある目的を達成するために"というところです
・リーダーには、二つの仕事役割がある、①目的目標を定め、それを実現する戦略を決める意思決定の役割。②目的目標を実現するためにメンバーをまとめわ引っ張っていく業務執行の役割。
・No.1には①をNo.2には②を求められる
・優秀でないNo.2は、意識的か無意識的か分かりませんが、トップと現場に立ちふさがって上から見通しが利かない組織にしてしまう。
・仲良きことは美しきかな。とはプライベートの範疇であり、仕事においては仲良きこと以上に大事なことがある。
・トップマネジメント コンセプチュアルスキル
・ミドルマネジメント ヒューマンスキル
・ロアーマネジメント テクニカルスキル
・コンセプチュアル ①概念化能力②洞察力③問題発見能力、解決能力
・ヒューマンスキル ①リーダーシップ②コミュニケーション能力・誘導能力③プレゼンテーション能力④調整能力⑤交渉力
・テクニカルスキル ①高度な処理能力②ファシリテーション(説明能力)③部下に技術・ノウハウを伝えるコーチング
・No.2の仕事は言うまでもなくミドルマネジメントでありヒューマンスキル
・トップダウンとボトムアップの両面をこなせるかどうか
★自分のための行動には、他人の評価が必要です。ところが、誰かのために行動するときは他人に評価される必要がないのです。
・自分の美学ではなく、男の美学をもつ
・真剣に相談しても腹ではなにを考えているかわからぬ奴はNo.2には置けぬ
・No.2の心得として、愚直であれ、とことん愚直であれ
・脳のは働きは主に二つのパターンがある、①流動的型:論理的思考に代表される、持続的働き方②結晶型:アイデアやひらめき、気づきのような直感的で、瞬間的な働き方
・No. 1はNo.2へ信用して権限を委譲せよ
・部下に惚れられるのに必要なたった二つの大切なこと①部下のことを心配し、いつも気にかける②部下以上に情熱的に仕事に取り組む
・部下にとって上司の一番の魅力とはここの四つである、①思いを語ってくれる(理念共有による連帯)②信頼してくれる(権限委譲による、責任感と使命感の喚起)③情熱的に働いてくれる(感動と共感)④自分のことを気にかけてくれる(承認欲求と自己重要感の充足)
---
こんな人はNo.2には選んではいけない
・利口ぶる人
素直でなく、自分の意見を心の中で通す
相手への尊厳や尽力ベースでなく自分のためだけに動く人
・自分を大きく見せようとする人
自分をデカく見せようとする
・要領の良すぎる人
・自分勝手なベテラン
・コンプラ精神に欠ける人
----
こんな人は向いてる
・No. 1と2で得意分野が異なること
・几帳面な人
・ヒューマンスキルが高い人
----
No.2の優秀度を調べる
①保有能力があり、自己犠牲能力もある
②保有能力はないが、自己犠牲能力がある
③自己犠牲能力はないが、保有能力がある
④自己犠牲能力も、保有能力もない
もちろん①が一番理想
②はあとから伸ばせる
③は一番やっかい
④はそもそもエントリーされない
----
世の中には3種類の人間がいる
①いい加減な人
どれだけ手をかけても無駄
②一生懸命な人
チャンスあり
③本気になれる人
飛躍しろ
----
・消費者ニーズの多様化で、大量生産の規格品でも満たせた必要性から、高付加価値の商品が与える満足感へのニーズの根本が一変します。
-自己解釈
・必要性に基づくバリューと必要性を超えた満足への訴求のバリューで大きく違う、時代の変化で物が溢れ後者の割合が多くなった。とはいえ、前者となる偉大なる何かは産業全体を見ればまだあるのではないか?これも時代の変化で堂々巡りするのではないか?
(例)介護問題、情報過多の整理、物が溢れるリユースリサイクル、人工知能、働き方の変化で起こる余暇時間への新産業
Posted by ブクログ
No.2が会社の成長の鍵を握っている
多くのカリスマは優秀なNo.2を持たず失敗してきた、数少ないカリスマは優秀なNo.2を得て大成功を収めてきた
優秀なNo.2に必要なスキルはなにか?
それを教えてれる本、言っていることはとても簡単
実践していつの日か適当な人間から本気になれる人間になって支えたい
Posted by ブクログ
No.1理論で有名な西田さんの本なので、No.2理論というのは相反するのでは?と思ったが、No.1を否定する訳ではなく会社の繁栄のためには縁の下の力持ちのNo.2こそが重要。
優秀なナンバー2になろうと努力することは、仕事のプロとして成長することでもある、という話。
本を呼んでいるけれども講演のような話口調で読みやすい。会社を動かし、成長させ、発展させるのは一人ひとりの社員の思い→素敵だな、と感じた。
Posted by ブクログ
フォロワーシップの大切さを説く良書。網羅的ではなく一つの類型が、著者が理想とする姿として提示されている。「組織を発展させるのはNo.2」との言葉は浸みる。