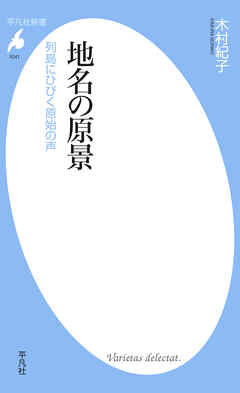あらすじ
野・山・川など、地名に使われる普通の言葉のもとの意味を探るなかから、文字以前の時代の列島の風景と人の暮らしを再構成する。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
地名は地図の記号ではない。人が大地と向き合い名づけることで結ばれた記憶の糸である。その糸を一つひとつ手繰り寄せる本だ。
山、川、浜、原。素朴な音の奥に狩りや祈り、恐れや恵みが折り重なる。その音に後から漢字を当てはめたとき意味は整えられ原景は覆い隠されてしまう。
便利さの陰で私たちは土地の声を聞き逃してきたのではないか。地名に耳を澄ますことから見えてくる足元の歴史を今一度見つめなおす必要があろう。
Posted by ブクログ
古代ことは、やはりわからないことが多すぎる。
研究者も、わずかな資料をもとに推定する。
ときに、かなり大胆な想定まですることがある。
そうした古代を論ずる面白さと、難しさが本書により改めて感じられる。
川(かは)は、古代の発音では「かぱ」。
あの川の精霊河童に通ずる。
たしかに!
原は「パラっと広がったところ」。
言葉としても「山」や「海」などと結び付けて扱うのではなく、独立して使われる傾向がある。
国の生産性を担う場所でもあり、人体の中でパラっと広がる平坦な場所に通じる。
こういう話、とても面白いが、どこまで信頼できるのか素人の自分にはわからない。
地名が政治的な判断で書き換えられることの問題は、地理方面の人も批判していたのを読んだことがある。
平成の大合併のあたりのころだった。
本書では、8世紀ごろからの好字への改名のことが話題になる。
滋賀県の「が」って何か?
たしかにわからない。
これは「ありか」「すみか」の「か」。
つまり、場所、在り所を表すものだとのこと。
好字として「賀」があてられたことで、意味がわからなくなってしまったものだとか。
今も昔も、政治上の効率により、こういうことが起こってしまうのだな、と思った。
多種類であることを示す「いろいろ・くさぐさ・とりどり・さまざま」。
「いろ」は古代語では「魚」。
魚のうろこの色がさまざまであることから「いろいろ」という用法ができたのでは、と著者は推測する。
「くさぐさ」は同様に「草」から。
「とりどり」も「鳥々」。
さまざまについては言及はない。
魚の呼称には「な」というものもあり、「難波」も「な・には」、魚の多いところという意味だったのではという。
本当かなあ、とも思うけれど、ちょっとおもしろい。
なお、論の進め方は、割と自由な感じ。
大御所の本らしい構成と言ったらいいのか。
テーマから話が少し離れた議論が入ってきたりする。
結論が知りたくてしょうがない気分の人には向かないかもしれない。