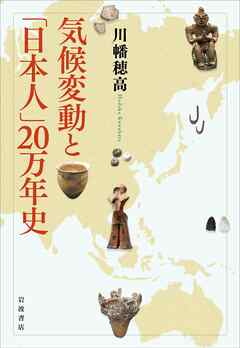あらすじ
ホモ・サピエンスの誕生から20万年.寒冷化なくして世界各地への拡散と社会形成はなかった!? アフリカ東部から東アジアまで,過去の気温を0.3度の誤差で復元した著者が,分子人類学や考古学の研究成果を元に大胆考察.過去2万年,寒冷期に日本列島では何が起こった? 古気候学や古環境学から「日本人」のルーツの定説が覆る!?
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
最新科学をもとに日本史に大きな影響を与えてきた気候変動を振り返る良書。土壌に含まれる花粉やプランクトンなどの解析を通じ、過去の寒冷化などの極端な気候変動が社会の大きな変動を促すことを示している。
以前読んだ「感染症の世界史」で、ピロリ菌の痕跡を調べることで人類がどのように広がっていったかを推測する「ウィルス人類学」という研究があることを知ったが、様々な科学分野の知見を持ち寄って人類の移動の足跡を追い込んでいくところにロマンを感じる。
Posted by ブクログ
気候の変化は人間に様々な影響をもたらす。これは今だけでなく、昔もそうだ。
今回の本は、古気候学、古環境学、分子人類がく、考古学などの研究成果を駆使して出来上がった。
人類が発達する上で欠かせないのが脳の容量の増大。ホモ・サピエンスにまで進化すると、脳の要領が増えて言葉を使っていった。
飛躍を遂げた理由の1つは「美食」にあると著者は指摘している。美食と言っても豪華な食事を味わうではなく、肉を食べるようになった。
葉物の野菜ばかりだと、すぐに充電切れになってしまう。カロリーの高い食事で充電して脳の活動を支えることができる。
人類の発祥の地と言われるアフリカを出て、世界各地に分散していった。それとともに病原菌も移動した。
例えば、結核菌のゲノム解析によると、約7万年前にホモ・サピエンスとともにアフリカからユーラシア大陸に拡散したそうだ。
稲作は弥生時代から始まったと教科書で習ったが、水稲に限って正しいと指摘している。
米作は、全国の30の縄文遺跡で確認されている。ただし陸稲(りくとう)という、畑地環境に合うイネで、水田で栽培される水稲とは違う。
読み進めていくと思いもしなかったことに言及していた。それは、奈良時代の都だった平城京で鉛汚染だ。
著者は調査して、飛鳥時代の土壌ではわずか十数ppmだったのに、奈良時代後期の土壌には、1200ppm以上の高い鉛濃度を示す試料があった。
当時、建物や仏像に使われていた塗装の原料に鉛丹(四酸化三鉛)や鉄酸化物などを使っていた。
そして奈良時代の一大国家プロジェクトとも言える奈良東大寺大仏建立で、水銀汚染が発生した。
飛鳥時代以前の土壌中に含まれ水銀の量を比べると、大仏作成後の奈良時代後期になると、土壌に含まれる水銀の値は7倍にもなった。
環境から日本史を見ると文献では分からないことが見えてきて興味深い。