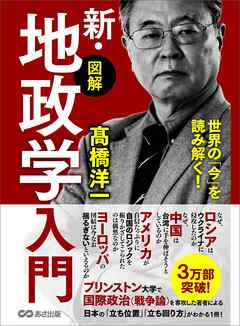あらすじ
●世界の「今」を読み解く!
・なぜ、ロシアはウクライナに侵攻したのか
・なぜ、中国は台湾に手を伸ばそうとしているのか
・アメリカが自信たっぷりに自国のロジックを振りかざしてこられたのは偶然なのか
・ヨーロッパの団結は今なお揺るがないといえるのか
プリンストン大学で国際政治(戦争論)を先行した著者による
日本の「立ち位置」「立ち回り方」がわかる1冊!
「地政学」とは、
【地理的な条件】が一国の政治や軍事、経済に与える影響を考えることである。
これをひと言で定義するならば、
「世界で起こってきた戦争の歴史を知る」になる。
地理的な条件とは、領土やその周辺地域のこと。
領土といえば国同士が争い奪い合ってきたもの、つまり戦争がつきものだ。
だから、地政学とは戦争の歴史を学ぶことといえる。
その国は地球上のどんな位置にあり、どんな地理的危機にさらされ、
あるいは地理的好機に恵まれながら発展してきたか。
地理的条件によって、
一国の危機意識も戦略思考も何から何まで変わる。
その国の性格、俗に「国民性」「お国柄」などと呼ばれるものの根幹にも、
地理的条件が大きく関わっているといっても過言ではない。
これら危機意識や戦略思考が目に見える形で現れるのが、戦争だ。
置かれた地理的条件によって、それぞれの国の生き残りや発展をかけた野心が生まれ、
そこから、さまざまな戦争が起こってきた。
すべての戦争には、地理的条件による各国なりの「切実な事情」が絡んでいる。
そうした戦争の歴史を知ることが地政学であり、
この視点をもって世界を見つめてみることが、
世界の深層をとらえる頭につながるのである。
本書は、国際関係が目まぐるしく動いているなかでの執筆となった。
なるべく最新の情報を盛り込むべく、校了のギリギリまで原稿に手を入れたが、
校了から刊行までには多少、時間がかかる。
おそらく、その間にさらに事態は動いているだろう。
本書で追いきれなかった点はご容赦いただきつつ、
ぜひとも自分で考えてみてほしい。
井の中の蛙を脱し、真にグローバルな視点から、
まっすぐに、鋭く、今、自分が生きている世界のありようをとらえる。
本書が、そのきっかけとなれば幸いである。
■著者 髙橋洋一(たかはし・よういち)
東京大学理学部数学科・経済学部経済学科卒業。博士(政策研究)。
1980年に大蔵省(現・財務省)入省。
大蔵省理財局資金企画室長、プリンストン大学客員研究員、内閣府参事官(経済財政諮問会議特命室)、
総務大臣補佐官、内閣参事官(総理補佐官補)等を歴任。
小泉内閣・第一次安倍内閣ではブレーンとして活躍し、
「霞が関埋蔵金」の公表や「ふるさと納税」「ねんきん定期便」など数々の政策提案・実現をしてきた。
また、戦後の日本における経済の最重要問題といわれる、バブル崩壊後の「不良債権処理」の陣頭指揮をとり、
不良債権償却の「大魔王」のあだ名を頂戴した。2008年退官。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
地政学と名の付く本を初めて読んだ。地理的要因を考慮した政治・歴史学。一文ごとにちゃんと文脈的つながりや理由があり、ストーリーとして納得感が高く分かりやすかった。面白い、が、基本的に戦争の歴史なので、世界の緊張状態が伝わってきて、気が滅入る部分もあった。。
Posted by ブクログ
日本の置かれている状況や危機的状況がよくわかる。国を守るために何をすべきか、話が通じない国にきっとわかってもらえるだろうというのは危険。ウクライナのように攻め込まれる可能性もある。日本はウクライナのように頑張れるのか。そうならないようにするには。
、、、、、、、
戦争は大義名分はともあれ、土地の奪い合い。
地政学というより海政学。海洋国家に覇権。
民主主義国家同士は戦争無し。
中国は広い海に出たい。
ロシアは肥沃な土地と不凍港。
オスマントルコ、ナポレオン、ポーランド、イラン、アフガン、クリミア、トルコ、日本、ウクライナ、南下を進めたいロシア。ずっと繰り返して、戦争をし、騙し、領土を拡張しようとしている。
ヨーロッパ、火薬庫バルカン半島(ボスニア、ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、ブルガリア、ギリシア、オスマントルコ、マケドニア、ルーマニア)、ロシアの壁のために小さな国を作る。
イギリスの三昧舌。
利害のためにみんないろんなところとくっつき、明日は、敵に味方に。
インドは二股対応。
アメリカも海洋国家。
スペインに勝利しグアムなどを取得。
引いたら押される。
戦争抑止のための正当な防衛費は必要。
個別的自衛権よりも集団的自衛権の方が戦争になる確率は低い。
Posted by ブクログ
地政学を「戦争の歴史」と定義し、具体的な事例を挙げながら各地域のこれまでとこれからを論じています。
やや筆者の立場への偏りはありますが、官僚として外交の最前線を見てきた方の言葉には説得力を感じました。
Posted by ブクログ
学校の授業で取り上げたら良いのにと思います。
どうしても日本国内にいると、視野が狭くなってしまう。マスのゴミがしょーもない報道しかしないし、、、(だからゴミ)
それぞれ国々の立場があって当然なのに、どうしても善or悪で物事を考えてしまいがちです。
『一般教養』としての地政学、とても勉強になりました
Posted by ブクログ
歴史に照らして、地政学を学ぶことができる本でした。
国々は生き残るため、不安を打ち消すため他国に侵略し、戦争を繰り返してきた。平和を目指すのは当然なのだが、生存が脅かされたら、座して死を待つことはできないのでしょう。
戦争に巻き込まれる確率をゼロにすることはできないが、その確率を減らすことはできる。
戦争確率を減らすためには、同盟国との連携を高め、他国との軍事バランスが崩れないようにすべき。
特に日本の周囲には非民主国で軍事力を持つ国々がある。
平和を維持するため、同盟と軍事バランスの強化が必要なのですね。
これらのことが数字や歴史をもとに分かりやすく書かれ、読みやすい本でした。
Posted by ブクログ
地政学の入門本。川を上れ、海を渡れ(過去を遡って考え、海外の事例を参照する)という著者の大蔵省時代に教わった言葉を挙げ、戦争をこれに当てはめたものが地政学であるとし、戦争の歴史、地政学の概念を簡単に解説した上で、中、ロ、欧、米の歴史を地政学で振り返った上で日本へのインプリケーションを示す。
途中の各国の解説はやや歴史の流れを追うような退屈さがあったが、最初(地政学)と最後(日本)の章は本書の珠玉であった。特に集団的自衛権や防衛費をめぐる議論は明快かつ斬新な部分もあって面白かった。
Posted by ブクログ
読みやすい本であった。改めて日本は経済もさることながら、国防にも力を入れないと行けないことになっている。このままだと将来日本は本当にどうなるのか憂いてしまう。
Posted by ブクログ
令和6年(2024)のGWの大掃除で発掘された本で、記録によれば2年前の年末に読み終わった本です。この本の著者である高橋氏には今までも多くの著作を読ませてもらってきていますが、私の興味のある「地政学」に絞って本を書いてくれたので、当時本屋で見つけて嬉しくなってすぐに買って読んだのを覚えています。
その後に時間が取れずにレビューを書くのが今になってしまいましたが。今年の誕生日で社会人生活も一区切りをつけて、少し時間を確保できるようになりました。読み放しだった本の要点を振り返って、このように纏めて、さらには興味のある分野についてさらに読書やできれば講座に参加してみたいと思っています。
以下は気になったポイントです。
・地政学=地理の政治学とは、地理的な条件が一国の政治や軍事、経済に与える影響を考えることである。一言で定義するなら、世界で起こってきた戦争の歴史を知ること、である(p18)
・人工換算後の戦争による死者の絶対数は、一位が中国唐(8世紀)に起きた「安子の乱」で、実際の死者数3600万人が、換算後には「4億2900万人」となる。絶対数の一位は、第二次世界大戦(5500万人)(p34)
・イギリスは、清の人々をアヘン中毒にすることで、清に流出していた銀を、インドを介して「回収」しようとした。アヘンの輸入により、清からインドへアヘンの代金(銀)が渡り、インドがイギリスから綿製品を買うことで、イギリスに銀が渡るようにした(p54)
・アヘン戦争の後、フランスは清の属国・ベトナムへ野心を露わにする。18世紀後半の、カルナータカ戦争でイギリスに敗れ、フランス領インドから撤退することになったので、インドシナに向けた(p58)
・日清戦争の後、フランス・ドイツ・ロシアが、日清間で結ばれた下関条約に介入し、遼東半島を清に変換するように日本へ要求した、返還されたはずの遼東半島の旅順・大連は、結局ロシアが咀嚼することになる(p65)加えて、三国干渉に参加した、ドイツ・フランス、さらにはイギリスまでもが、航海周辺および清の各地を租借した(p66)
・国際法上は、満潮時に水に潜ってしまう岩礁は「島」ではない。そこを埋め立てて「島」のようにしても国際法上は領土にならない。(p88)
・中国に工場を持っていた企業が撤退する、レアメタルに代表される重要物資の中国依存を下げるなど、民主主義国家の間で政策的に中国離れが進められつつある。その典型例は、IPEF(インド太平洋経済枠組み)QUAD(日米豪印戦略対話)の経済版である(p95)
・モンゴル人のキエフ公国の制服とともに、黒海・カスピ海の沿岸を含む広大な土地に、モンゴル帝国の国家(ハンクにの一つ、キプチャク・ハン国が築かれた、のちにモスクワ大公国が独立するまでの2世紀半、東スラブ人はキプチャク・ハン国の支配を受ける、これを「タタールのくびき」という(p160)17世紀末、ロシアは東方ではシベリア経営を進める一方で、オスマン帝国の勢力圏だったアゾフへの遠征により、黒海へ繋がるアゾフ海の制海権を獲得、1700年に始まる北方戦争でロシアは負けて、アゾフをいったんオスマン帝国に返却するが、その後にスウェーデンに調理して、バルト海を制する、スウェーデンに代わりロシアが北方の覇者となった(p107)
・第一次世界大戦にて、ソビエト政権は単独でドイツと、ブレスト=リトフスク条約でこうわし、第一次世界大戦から離脱。フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ウクライナほか、オスマン帝国との国境に接する地域の権利も放棄した(p141)ドイツの敗戦により、この条約は破棄されることになるが、ポーランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、フィンランド、ウクライナの独立の承認は継続された(p141)
・ウクライナはかつて核保有国だったが、日本の非核三原則のように核を廃棄した、その結果、ロシアから侵攻を受けたのも事実である。もしウクライナが核を保有していれば、ロシアもそう簡単に侵攻できなかっただろう。この意味で、日本の非核三原則や憲法9条があれば国の安全が保たれるという日本の平和主義は、リアルな国際社会では全く無力であることがわかってしまった(p168)
・第一次世界大戦当時、ロシアはバルカン半島で、バン・ゲルマン主義を掲げる、オーストリア=ハンガリー帝国、それを支援するドイツと対立していた。一方、ドイツ陣営には、同じゲルマン民族である、オーストリア=ハンガリー帝国、第二次バルカン戦争でセルビアやギリシアに敗北した、ブルガリアがついた。こうして、イギリス・フランス・ロシアを主とした連合国と、ドイツ。オーストリア=ハンガリー帝国を主とした同盟国が形成された(p131)
・ウクライナがロシアに蹂躙されるのを目の当たりにして、フィンランドもスウェーデンも、NATO加盟こそが最強の祖国防衛策であることに気づいてしまった。NATOは集団的自衛権の塊である、そこに両国が入ったのは、「戦争をしたくないから」に他ならない、集団的自衛権を認めた方が、戦争確率がさがる(p204)
・戦争リスクを下げるには、1)独立国としてふさわしい軍備をして牽制効果を高める、2)同盟関係を結ぶ、3)民主主義国同士で自由貿易を行う関係を築く、4)国連に加盟する(p270)
2022年12月22日読破
2024年6月7日作成
Posted by ブクログ
戦争を分析すると国の思惑が見える。視野を広げて日本を見なければいけない。国の性質、地理的関係性を理解しなければ、議論を始めることができない。論点は逸れるが、日本人の国に対する帰属意識は低下しているように感じることがある。これからの日本がどうすればいいのか国政の議論を深めるためにも国の大切さをもう一度見つめ直すところから始めようと思った。
Posted by ブクログ
近世以降の、主要各国の紛争や戦争の歴史を説明した本であり一般的な地政学とはやや異なる。社会主義や独裁国家は戦争をする事が多く、民主主義国家同士の戦争は稀である。と言う部分はピンカーも言っているが、感覚的に合っていると思う。戦力の均衡が戦争抑止効果を持つとなると世界各国の軍事費の増大は避けられないのではなかろうか。
Posted by ブクログ
中国、ロシア、ヨーロッパ、アメリカの4つの地域に焦点を当て、地理的な要因に触れつつ、戦争の近現代史について流れを解説した本。
世界史を通史で学んだことない私には学びが多かった。特に、民主主義国家どうしでは戦争をする可能性が低いという「民主的平和論」は初めて知ったので印象に残った。また、近隣国との防衛費の差が大きいほど戦争が起こりやすくなるというのも、国際政治学では当たり前の話とのこと。中国やロシア、北朝鮮など、隣国には民主度の低い国が多く存在するため、日本は戦争抑止に関心を持って注意する必要があるという。